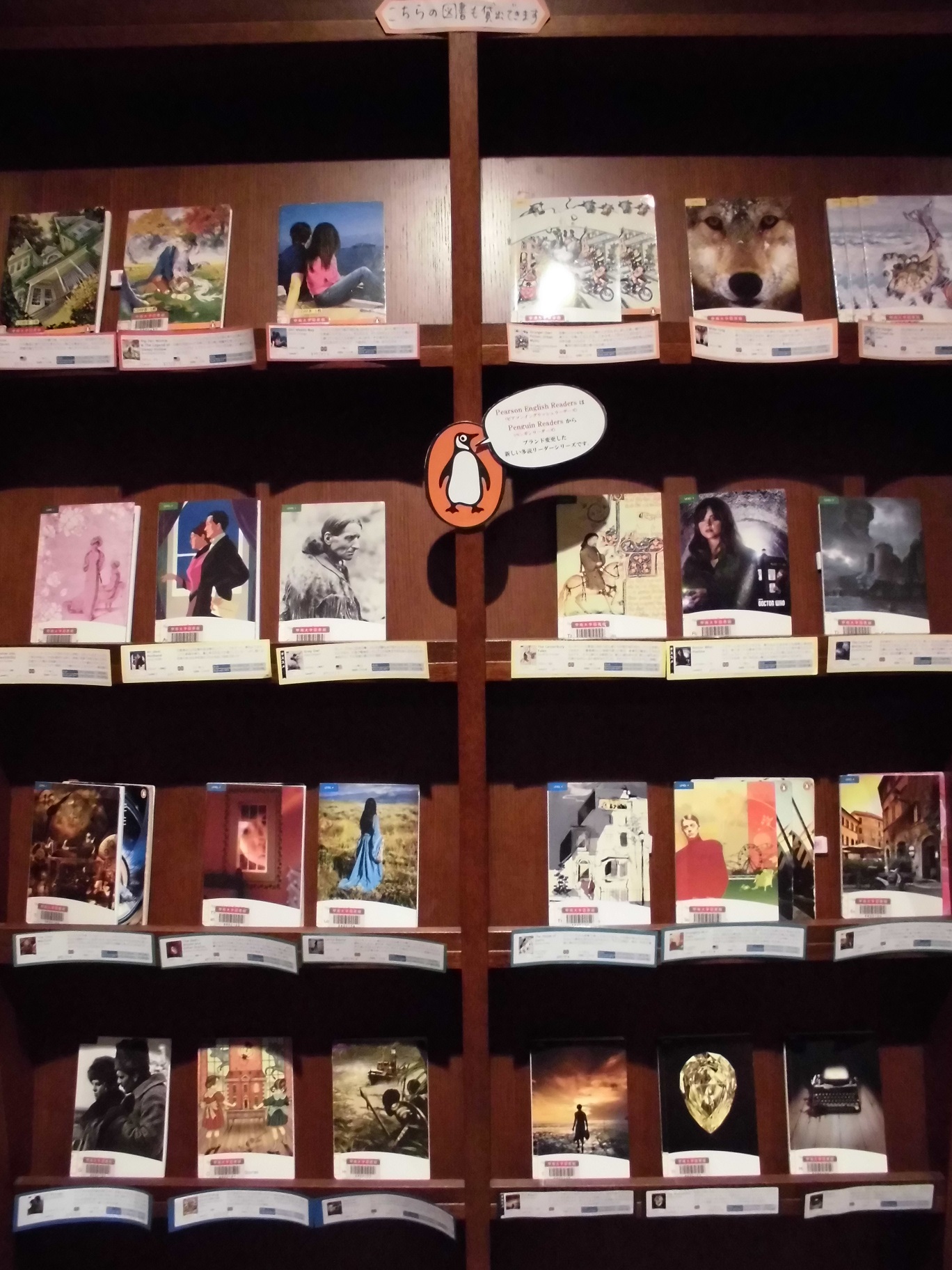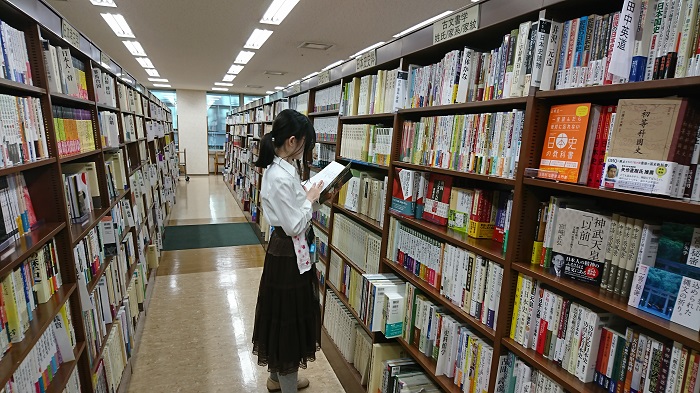図書館報『藤棚ONLINE』
北居 明 先生(経営学部) 推薦
「我々が『マネジメント』と呼んでいるものは、その大半が人々を働きにくくさせる要素で成り立っている」と述べたのは、近代経営学の父と呼ばれるピーター・ドラッカーです。たしかに、権限命令関係をはっきりさせるための階層は、人々の自主性を阻害することも多いです。計画どおり活動を進めるためのPDCAサイクルは、そのサイクルを回すこと自体が目的化し、仕事を増やす結果になることもしばしばです。「だって多くの会社が実際にそうやってるじゃないか」とか、「教科書にはそう書いてあるじゃないか」という声が聞こえてきそうですが、メンバーが自主性と創造性を最大限発揮し、互いがもっと協働できる経営のかたちは、他にもあるかもしれません。
今回ご紹介する「ティール組織」は、これまでの経営の在り方を覆すような、様々な具体例が示されています。著者のフレデリック・ラルーは、コンサルティング会社勤務後、2年半にわたって新しい組織モデルの調査を行い、先進的な経営を行っている12社を抽出し、それらの経営の在り方を「進化型(ティール)組織」と名付けました。ティール組織では、管理職はいませんし、公式の組織図もありません。勤務時間を管理するためのタイムカードもない会社もあります。ティール組織の特徴は、徹底した自主管理、全体性、そして存在目的です。それぞれについてごく簡単に説明すると、自主管理は、プロジェクト型の組織で進められ、新たな人の採用も、人事部ではなく、このプロジェクト組織の裁量で決定します。もっと言えば、給料や転勤も自主申告で決めることができます(ただし、助言システムを通す必要があります)。全体性は、人々が職場でもっと「自分らしさ」を発揮することです。存在目的は、エゴにとらわれず、「何のための人生なのか」、「組織や仕事の本当の意味は何なのか」を常に考え続けることです。したがって、ティール組織では、普通の企業が重視する利益、成長、ライバルに対する勝利は目的ではなく、副産物であると明確に位置づけられています。そのため、経営戦略論でしばしば教えられているSWOT(自社の強みと弱み、環境の機会と脅威)分析なども行われないと言われています。このような組織で働くことができれば、私たちはもっと自分らしく、仕事に生きがいをもって打ち込むことができるかもしれません(現在の『働き方改革』は、仕事は労苦であると暗黙の裡に仮定しているようなところがあるように思います)。
ティール組織は、世界中の組織の中ではほんのごく一部なので、学生の皆さんが将来働く組織は、ティール組織ではない可能性の方が大きいでしょう。ただし、それを当たり前にせず、自分たちが直面している現実は多くの可能性の一部であることを意識できる一冊と思います。