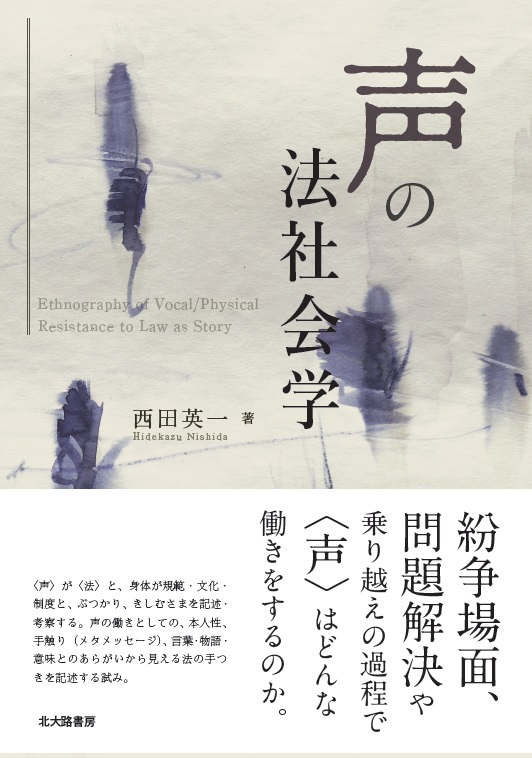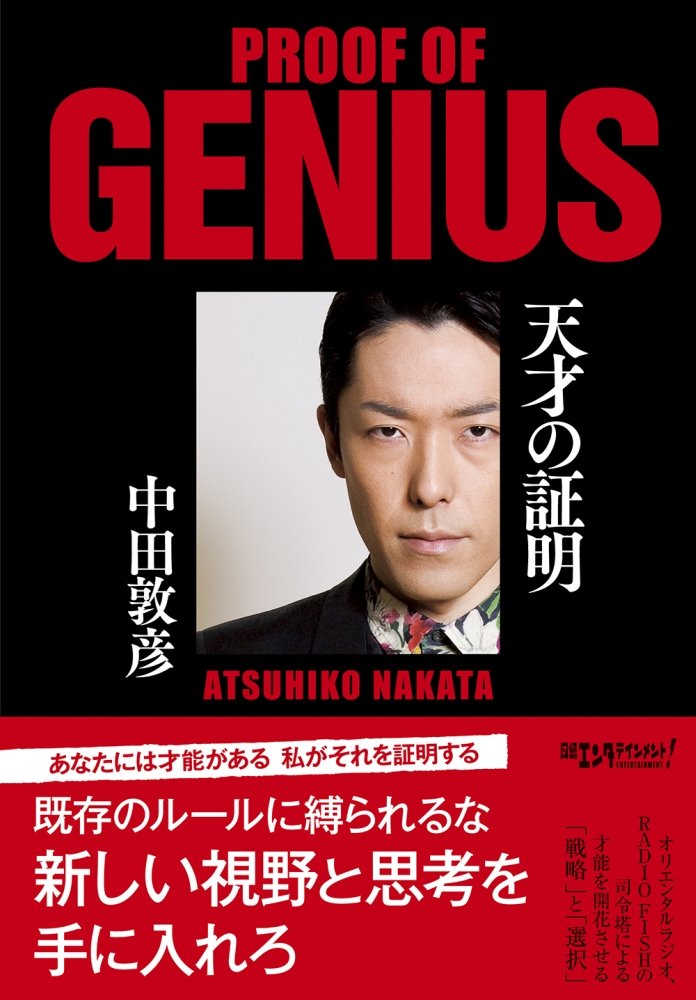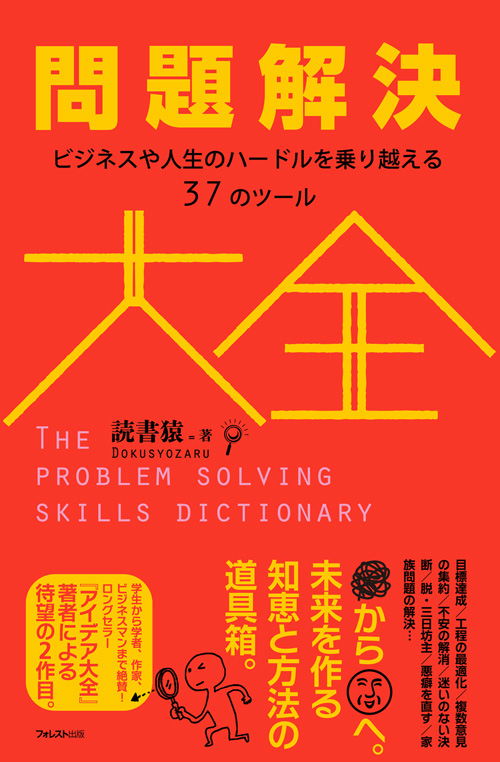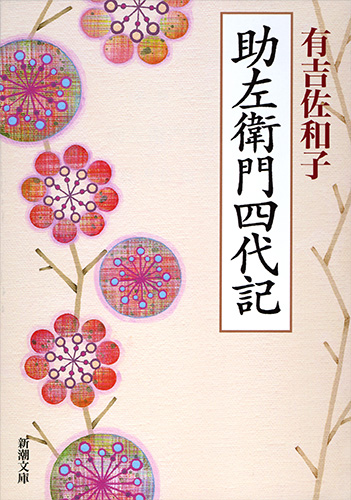知能情報学部 3年生 藤澤 舞さんが、マネジメント創造学部の広渡 潔先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
・本はよく読みますか。月に何冊程度ですか。
月に10冊程度です。
私の読み方は「見回す」感じです。Introduction とConclusionを眺めて、Contentsを見て 興味があるChapterをさらっと読みます。Introductionには著者の問題意識、議論の展開が書いてあり、Conclusionには展開した議論の要約と結論が書いてあります。ハーバード大学が学部生用にCritical readingという案内を出しています。そこでは、まず本をReadするのではなくLook “around″the text before you start readingとアドバイスしています。本を「見回し」ながら要約を掴み、本の印象を予備的に固めていくということです。万巻の書物を精読するには人生は短すぎます。
・どのジャンルの本を読みますか。
歴史関係が多いですね。人間には物事を理屈で割り切るタイプと歴史に還元して考えるタイプがいるかと思います。私は後者です。イタリアに5年、英国に7年いたこともあり、ヨーロッパの歴史、特に英国史が好きですね。英国という小さな島国が約400年をかけて世界に冠たる大英帝国を作り上げ、衰退していく歴史は味わい深いものがあります。
・人生を変えた本はありますか。
人生を変えた本はありません。ただ英国の名宰相チャーチルに関する本は好きですね。チャーチルは第二次世界大戦でナチスの脅威から世界を守った自由の守護者と言われています。同時に、インドなど植民地の独立を決して快く思っていなかった最後の帝国主義者でもありました。彼は19世紀の帝国主義を引きづっていたが故に社会主義やガンディーの独立運動を嫌いながら、それ以上に20世紀のヒトラーやファシズムの台頭に強烈な違和感を抱き、最後まで戦い抜きました。しかしその勝利の後に残ったのは大英帝国の衰亡でした。老境を迎え大英帝国に育てられ、その帝国の最後を看取っていきながら ‘all been for nothing…The Empire I believed in has gone.’と嘆くチャーチルに偉大な人間であるが故の悲劇を感じますね。「徒然草」に「死は前よりしも来たらず、かねて後ろに迫れり」とありますが、チャーチルの成功の裏に潜む挫折と悲嘆に、何がしかの死を抱いて生きる人生というものを如実に感じます。
・今の一般の大学生におすすめしたい本はなんですか。
「論語」「万葉集」やプラトンの「国家」などの幾世代もかけて読み継がれた古典のうちひとつを座右の書としてみてはいかがでしょうか。
・所感
今回、別のキャンパスに訪れたことを新鮮に感じました。また、広渡先生の専門(経済史:歴史的な史料を用いて経済社会を深く理解することを目指す学問分野)や歴史についてお話を聞いたことは自分の中で財産になったと思います。
(インタビュアー:知能情報学部 3年生 藤澤 舞)