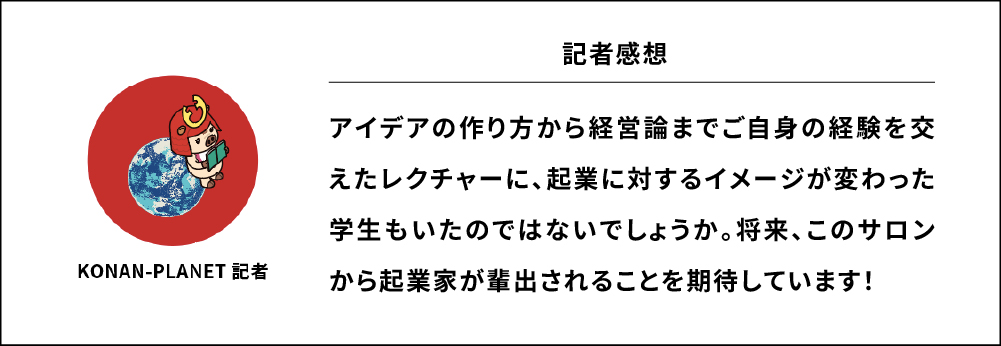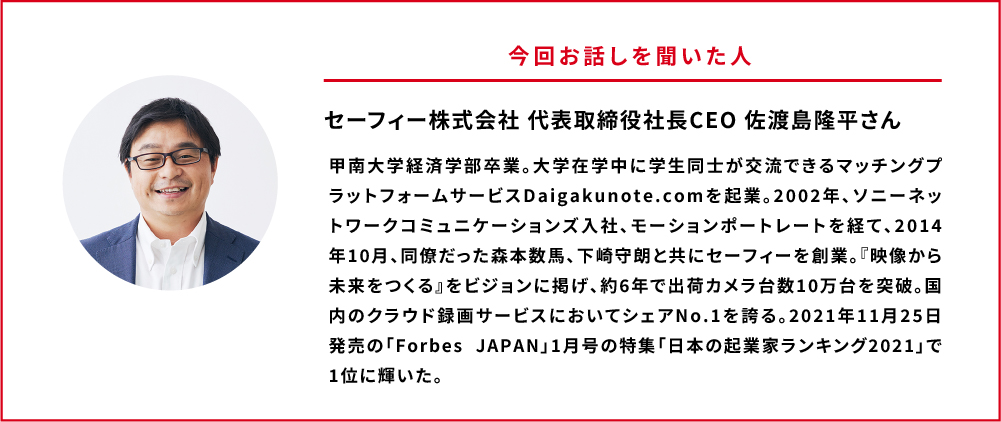「本学OBOG経営者に学ぶ 第1回経営者サロン」
イノベーションを起こすカギは
“辺境点”と、ありものの組み合わせにある
―セーフィー株式会社代表取締役社長CEO佐渡島隆平氏に学ぶ―
イノベーションを起こすカギは
“辺境点”と、ありものの組み合わせにある
―セーフィー株式会社代表取締役社長CEO佐渡島隆平氏に学ぶ―
2024年7月8日に開催した「本学OBOG経営者に学ぶ 第1回経営者サロン」に、セーフィー株式会社代表取締役社長CEOの佐渡島隆平さんにお越しいただきました。佐渡島さんは1999年、甲南大学経済学部在学中に初めて起業され、2020年に「Forbes JAPAN日本の起業家ランキング2021」1位を受賞。今回は、どのように起業して、そして上場企業にまで育てたその経験や考え方をお話いただき、学生たちからの質問にも答えていただきました。
起業で社会課題を解決する

佐渡島さん
甲南大学在学時から起業、プロダクトづくりと地道なビラ配りからスタート
皆さん、こんにちは。今日は、私が大学時代にどのようにして起業したのか、また、いかにして上場し、500人近くの従業員を抱える企業に至ったのかをお話したいと思います。私は大学生だった1999年、「Daigakunote.com(ダイガクノートドットコム)」を創業しました。この年は、iモードが登場して、携帯電話がインターネットにつながった年です。これを活用して、テスト前にみんなが取ったノートを集めて共有したり、メールマガジンを配信したりしていました。このサービスの利用者を増やすためにいろんな手を打ちましたが、例えば甲南女子大学に行って「休講情報、芸能ニュース、天気が分かります」とビラを配りました。女子学生の登録者が増えると、男子も登録すると考えたからなんです。実際、女子が利用してくれたおかげで男子の登録者も増え、ユーザーはどんどん増えていきました。

映像データの分析や無人店舗運営を実現
今、私が代表取締役社長CEOを務めているセーフィー株式会社は、日本の課題を解決するサービスを提供しています。日本が抱えている課題とは、少子高齢化に伴う労働力不足です。2040年、日本は生産年齢人口が現在より約2割減る“8がけ社会”になると言われています。そうした社会になっても、労働生産性を向上させることが求められています。弊社が提供しているのは、カメラを活用したサービスです。防犯カメラと似ていますが、このサービスは、撮影した映像をクラウド上で簡単に見られる上に、集まった映像データをAIで分析したり、DX化を推進したりするのに役立てられるのが特長です。
例えば、大手アパレルチェーンでは約1万3000台のカメラを設置して、店内のお客様の人数やどのアイテムを見たのかなど、あらゆる情報を映像から収集してAIで分析しています。小売店ならレジに並んでいる人数、飲食店なら空席数が分かり、建設現場で利用すれば、遠隔地からの施工管理が可能です。また、スーパーなら、どの場所におにぎりやお弁当を置けば最適化するのかなどもAIで導き出すことができます。
最近は、無人で店舗を運営する「省人力化」がトレンドです。これまでは、1店舗に店長が1人必ずいましたが、今はマンガ喫茶もフィットネスジムもほとんど無人で、1人の店長が複数の店舗をマネジメントするような時代です。そのサポートをしているのが弊社なのです。

どのように苦境を乗り越えて上場したのか
今でこそ弊社は上場していますが、創業当時は苦労と失敗の連続でした。最初、カメラを自社で作らず他社に作ってもらったところ、できあがったのはインターフェースがWi-Fiしかないのに、Wi-Fiがまったくつながらないカメラでした。当然、お客様から苦情が殺到しました。
バスタ新宿の渋滞を解消するための交通量調査でご利用いただいた弊社カメラが、夏の暑さで壊れたのも印象に残っています。新宿駅前のカメラを1車線封鎖して、再起動させたり交換したりしました。しかし、それが渋滞を引き起こしてしまい、「渋滞解消が目的なのに本末転倒だ」とお叱りを受けたこともあります。
そうした中でも建設現場での需要が増え、小さいカメラのニーズがあることが分かり、ウェアラブルカメラ「Safie Pocket2(セーフィー ポケットツー)」を4億円かけて作りました。しかし、その製造を発注した途端にコロナのパンデミックが起こり、営業活動ができなくなりました。当時は、毎月約8000万円近い赤字が続いていたため、弊社は、この新製品1機種に起死回生をかけることにしました。
パンデミックの間、ホワイトワーカーの方々はリモートワークが可能でしたが、建築現場などの責任者は、現場でしか仕事ができませんでした。そこで、「Safie Pocket2」を「現場作業者のリモートワークの決定版」とzoomでの記者会見でPRしました。これがヒットして、弊社は上場することができたのです。

プロダクトづくりと販売の苦難を越えて上場。2000万円で設立した会社が2000億円に
起業はゼロから、製品をつくり、人を採用し、組織をつくり、販売して、パートナーや株主などのステイクホルダーとの仲間づくりをしながらすすんでいきます。その過程で苦労が多く、面倒なこともたくさんあります。
こんな苦労をするのはしんどいと思うかもしれませんが、資本主義での、株式会社とはリスク、リターンの全体像でとらえる必要があります。日本では、起業に対してリスクに目がいきがちですが、資本主義の本質は、株式投資とはリターンが無限大という点もバランス良く考えていく必要があります。リスクは株主が担保してくれています。少ない資金で、ソフトウェアをベースに起業して、企業価値をあげながら、資金調達をしながら、小さく産んで、大きく育てることができます。
起業時、創業メンバー3人が投資した自己資金は、合わせて2000万円でした。それが、上場直後には時価総額2000億円に達しました。これが起業の面白いところです。起業は楽ではありませんが、仲間と一緒にさまざまなチャレンジができ、社会を変えることができます。ですから私たちは、起業家をどんどん育てて、社会の新陳代謝を促したいと思っています。ぜひ、みなさんには、起業で社会を変える仕事があるというのも、考え方のひとつとして心に留めておいていただけたらと思っています。
インターネット業界では1番でなければ意味がない
続いて、ファシリテーターの質問に答えていただきました。

ファシリテーター
起業に挑戦する原動力は何だったのですか?

佐渡島さん
学生時代に起業しましたが、それが大変なことをしたとは思っていません。行動すれば何かが起きると思っていただけです。もちろん、テクノロジーが社会を変えると信じていました。スケールする技術は人間の拡張機能なんです。足で走るよりも自転車を使った方が速いし、電車や飛行機はもっと速い。そうした便利なものがどんどん普及して、社会の産業構造が変わると価値観も変わります。私が高校生のとき、インターネットにその可能性を見出し、この分野の事業をやり切ろうと思いました。


ファシリテーター
新しいアイデアを生み出すコツを教えてください。

佐渡島さん
UberやAirbnbは新しいアイデアですが、これらのサービスを提供する会社が高い技術を持っていたというよりも、スマートフォンの位置情報を活用したイノベーションです。ですから、新しいアイデアを見つけたいのなら、次のデバイスや次のテクノロジーをもとにどんな世界を作ってみたいか、何を作ったら面白いかを考えるのが早いと思います。マーケットがあるから、儲かるから、とビジネスを始めるのもいいと思いますが、最終的には「それを自分がほしいかどうか」が大事だと思います。例えば、自分が好きなレストランに彼女を連れて行きたいとき、自分が美味しいと思っていると勧めやすいですよね。ビジネスも同じです。自分事化してプレゼンテーションをするから、聞き手も納得してくれるのだと思います。

ファシリテーター
インターネットはまだまだ世界を変えると思いますか?

佐渡島さん
はい。次の20年は、IoTを活用して、インターネットの中に住む時代が来ると思っています。それはアバターとしてメタバース空間に住むのではなく、リアルな空間とインターネットが直結して、自分が意志決定をしなくても世の中が勝手に動いていく社会です。そこに大きな可能性があると考えています。これまでは、自分が入力して情報を得るという使い方をしていましたが、今後は、デバイスが勝手にいろいろなことを教えてくれる時代になるでしょう。例えば、朝起きたらカメラが骨格の状態を認識して「右肩が凝っている」といった情報を提供してくれるような時代です。「お客様が来たら教える」「お客様の様子を認識して通知する」といった弊社が提供しているサービスは、次の時代の先駆けだと思います。

ファシリテーター
インターネットの未来が想像つかない頃から、
その可能性に賭けることに不安はなかったのですか?

佐渡島さん
周りに反対されても、やめようとは思わなかったですね。なぜなら、みんなが賛成するサービスやモノはすでに後発で、むしろ、みんなに反対されるものの方がイノベーションを起こすにはちょうどいいし、1番になれると思っていたからです。飲食店は2番でも3番でもよいですが、インターネットの世界では1番以外は見向きもされません。皆さんの中でLINE以外のメッセージアプリを使っている人はほとんどいませんよね。だから私は、誰も価値を見出していないニッチなニーズ、いわゆる“辺境点”をつかみ、1番になるために走り抜きました。学生の皆さんは柔軟な発想をお持ちなので、どんどん成長できるのではないでしょうか。

新しいモノ・サービス=突拍子のないモノではない
学生からの質問にも答えていただきました。

学生Aさん
今ないものや、「面白い」「ほしい」と思えるものを、
どのようにして見つけられたのですか?

佐渡島さん
実は、突拍子のないことをビジネスにすればいいというわけではないんですよ。例えば、飲食店をやるにしても、カレー、ラーメン、焼肉、カツ丼などイメージしやすい、頻度高く通えるものがいいですよね。いきなり、食べたこともない、外国の変わった料理を提供してもなかなか、ウケないものです。今社会にある技術やサービス、リソースを組み合わせたり、みんなが気付いていない“辺境点”を見つけたりすることが、需要に合った新しいサービスの創造につながると思っています。ただし、自分のアイデアを正しいと思い過ぎず、柔軟な思考を持ち、広い視野でたくさん動くようにしています。
また、社会最適できていないサービスなどをIT化するなど、多くの選択肢からわかりやすいテーマを一つ選んで、そこに注力することも大切だと思います。防犯カメラは一般的なテーマで、ローカルで録画されていたものを、クラウドにして、録画機をなくし、他社の1/6の価格で、性能を数十倍あげてローンチしました。誰もが思いつかないような突飛なアイデアではありません、辺境というのは、インターネット通信は切れるのがあたりまえなので、録画機に比べたら録画欠損してしまうと言われているなかで、大量データをインターネットで扱う動画システムは、コストがかかりすぎてしまうと思われたとろこからせめていきました。小さな成長するマーケットで独占する取り組みが大切です、競争していくことは無駄がおおいので、誰も目につけていない視点やビジネスモデルに進化させていくことが大切ですね。また、データを集めると、AIなどで人の代わりになるサービスが生み出させるスケールや、ビジネスモデルとしての発展性があったから成長していきました。私の場合は、お客様と同じ目線で現場を体験し、お客様の困り事や痛みを感じ、自分事化することを大切にしています。物事の本質を見ずに、お客様の課題を解決することはできないと考えているからです。

学生Bさん
需要から供給に至るまで、スピード以外に
大事にしていることは何ですか?

佐渡島さん
ベストセラーのビジネス書『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』にも書かれていますが、モノやサービスを作る前に、それらの需要があるかどうかを確認することは大事ですね。多くの人は、完成品を作って需要を生み出そうとしがちですが、実際は逆です。完成品がなくても、「何としてもほしい」と思われるようなモノやサービスが「本質的な需要」だと思います。
もう一つは行動です。うまくいっていない起業家は、提供者目線から脱却できていないケースがおおくあります。特にエンジニアリングをしてスケールできるプロダクトをつくりますが、技術的にすぐれていることをどんなに訴えても、顧客からみたコスト削減や、付加価値向上などをしっかり顧客視点から思考していくことが大切です。またプロダクトづくりで満足せずに、お客様の目の前にモノやサービスを届ける販売網の構築はとても大事で、それをやり切っているかどうかが、ビジネスの成否を大きく左右すると思っています。

学生Cさん
友人と6人で起業を考えていますが、
全員同じモチベーションを維持することに難しさを感じています。
リーダーとしてできること、やるべきことは何でしょうか?

佐渡島さん
チームを作る前に、リーダーや社長の人選だけでなく、その権限まで決めるべきです。正解のない答えを出すときに、誰が決断するかを決めていないと、いいチームであっても必ず崩壊すると思います。ですから私は、起業するとき、出資金50%以上を出して、共同創業者の出資金が50%未満になるようにして権限を持ちました。最後に誰が決めるのかははっきりさせておかなければいけません。また、同じ分野で成功した方にエンジェル出資してもらうなどし、支援者にするのもポイントです。自分たちがミスをしそうなときに、アドバイスをしてくれますから。
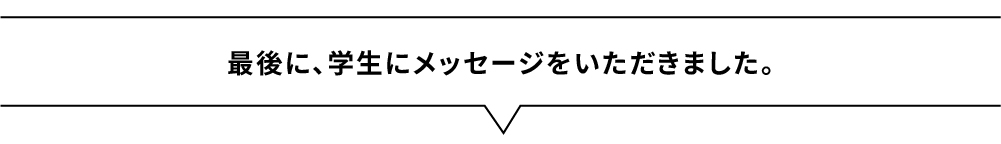

皆さんの中には、社会で何をしたらいいか分からないという人は多いと思います。しかし、その時点で社会のレールに乗っているわけですから、さっさとレールから降りた方がいいと思っています。
今の時代は希少性のある人材、ノウハウを持っている人が必要とされています。起業は“辺境”だと思われるかもしれません。でも、自分がやってみたいことにアクションを起こして、人よりたくさん失敗することで、ビジネスの基本である、人、モノ、金のノウハウを全て学ぶことができます。ファーストキャリアは大企業にいくべきだなどの横を見て意思決定するような人材より、自ら考えて行動できる希少性のある人こそが、価値があると思っています。自分が持つ希少性にかけて、ワクワクする人生を切り拓いてください。