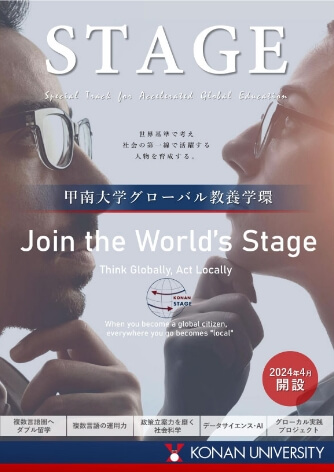6月19日(木)に実施された「SDGs概論」(担当教員:久保はるか教授)では、地域福祉の最前線でご活躍されている2組のゲストをお迎えし、「誰ひとり取り残さない社会」をテーマに講義が行われました。効率よりも人とのつながりを重視する福祉の価値観や、支える側・支えられる側という垣根を越えた地域福祉のあり方など、福祉について改めて考える貴重な機会となりました。
最初にご登壇いただいたのは、神戸市の地域福祉を支える東灘区社会福祉協議会の三浦由香氏と内田早紀氏です。地域福祉ネットワーカーとして活動されているお二人は、誰もが安心して暮らせる地域を目指し、相談者の課題を整理しながら、必要に応じて専門機関へつなぐ支援を行っておられます。なかでも、法制度の対象外にある方々には訪問や見守りを通じた伴走型のサポートを提供しており、個別支援にとどまらず、さまざまな関係機関との連携を通じて地域全体を支える「地域づくり」へと広げていくことを目指されています。近年は、経済的困窮に関する相談が増加しているが、その根底には「社会的孤立」があり、相談者はさまざまな課題を抱えていることが多いそうです。地域福祉ネットワーカーは、相談者の自己決定を支援する存在であるべきで、信頼関係を築くことが重要だと語られました。福祉は専門職だけのものではなく、誰もが関われるものであり、日常のさりげない挨拶も支え合いの第一歩になるというメッセージで締めくくられました。

続いて、神戸市東灘区で「子ども食堂ほんわかキッチン」を運営されている川西賢一氏がご登壇され、福祉サポートの現状と課題について紹介されました。「ほんわかキッチン」は、コロナ禍の4年前に、不登校の子どもとその保護者が安心感や自己肯定感を得られる「居場所」をつくりたいという思いから開設されました。こうした背景のもと、「子ども食堂=貧困家庭」というイメージを払拭し、多世代が気軽に集える場・子どもが安心して過ごせる場となることを目指して活動を続けておられます。同施設では、レスパイト・ケア(介護などをしている家族が息抜きをできるよう支援するサービス)をコンセプトに、場内での食事提供ではなく、テイクアウトのお弁当による支援が行われています。調理や準備、受付などには不登校の子どもや地域住民が参加されており、そうした関わりが自然な交流を生む仕組みになっていると説明されました。さらに、地域のつながりを深める活動として、不登校支援を目的とした「お母さん座談会」や、多世代が人生経験を語り合う「スタ場(人生のStudyの場)」などにも取り組まれています。川西氏は、現代社会においては学力や能力による線引きが効率性の面では必要とされる一方、人として助け合い、尊重し合える空間をつくるのは人間的な感覚で、そのためには地域のつながりが欠かせないと述べられました。

STAGE生からは、「福祉が他人事ではなく自分にも関わることだと実感した」「地域に暮らす全ての人が「誰かの支え手」となり、「誰かの受け手」にもなりうる」「誰もが安心できる居場所の必要性を強く感じた」「話を聞いてボランティア活動に参加することを決めた」といった反応が寄せられました。この授業は、福祉の現場から見えるリアルな課題と希望を学生たちに届け、地域社会の一員としての自分の役割を考えるきっかけとなりました。