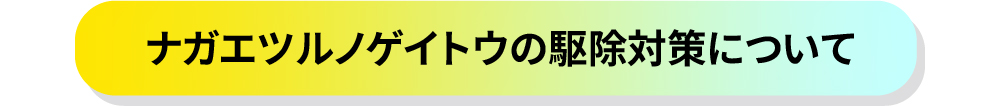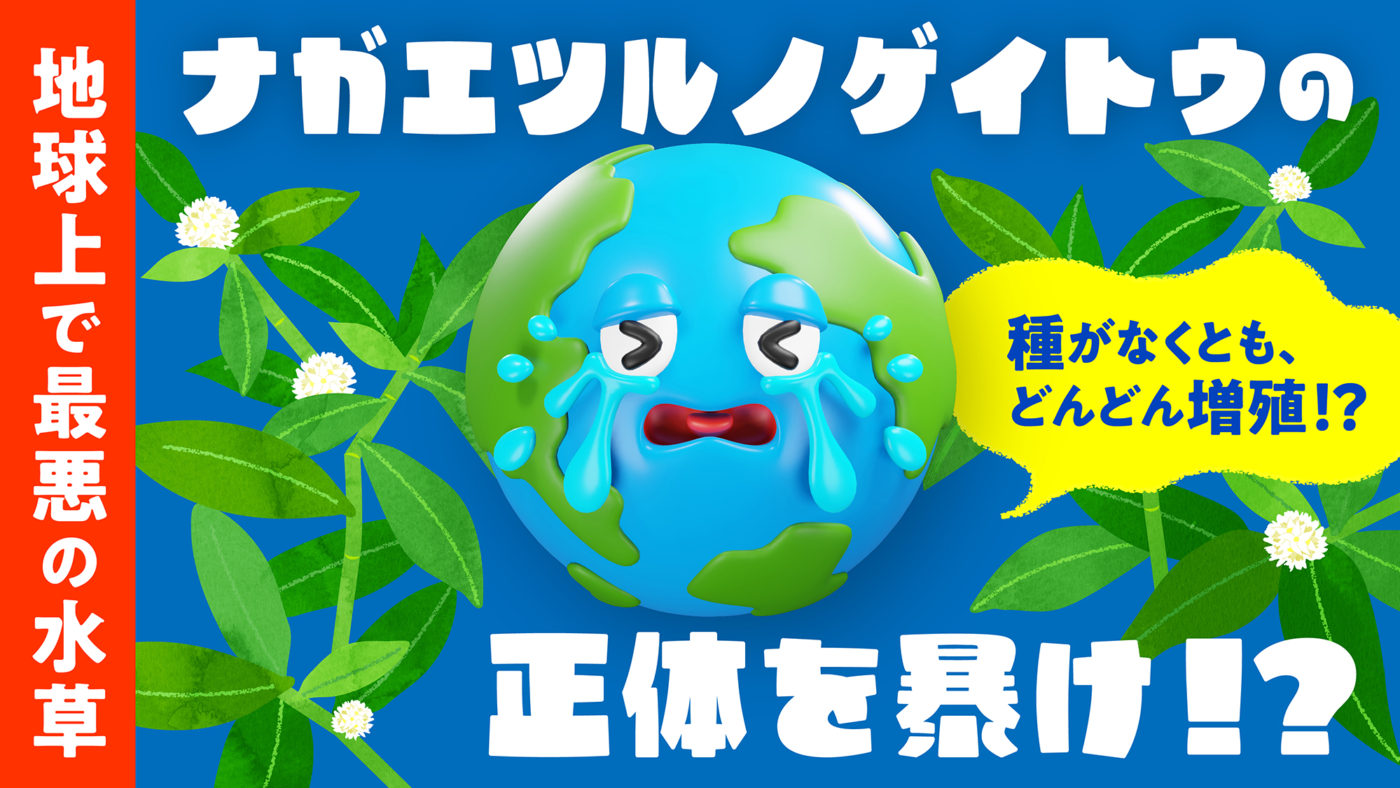
種がなくとも、どんどん増殖する!?
地球上で最悪の水草ナガエツルノゲイトウの正体を暴け!?
地球上で最悪の水草ナガエツルノゲイトウの正体を暴け!?
「地球上で最悪の水草」と言われ、世界各国で脅威となっている特定外来生物、ナガエツルノゲイトウをご存じですか?世界的にも明確な駆除方法は確立されていませんが、この方法の開発を目指して研究を続けている甲南大学理工学部生物学科の今井博之先生に、多くの人が知らないこの水草の特徴について詳しくお聞きしました。
Contents
・ナガエツルノゲイトウとは
・ナガエツルノゲイトウが引き起こす問題
・侵略植物の正体を解き明かせ!
・ 知れば知るほど面白い、その生態
・ 未知の生物を解き明かす面白さ
ナガエツルノゲイトウとは

KONAN-PLANET 記者
「ナガエツルノゲイトウ」という名前を初めて聞きました。
どんな植物なのでしょうか。

今井 博之 先生
「地球上最悪の侵略的植物」と恐れられる特定外来生物
南米原産のヒユ科の水草で温暖な地域に生息します。日本国内で最初の定着記録は、1989年兵庫県尼崎市となっていますが、現在では、兵庫県だけではなく、南は沖縄から、北は関東太平洋側まで分布していることが分かっています。5月~10月の時期の爆発的な繁殖が問題になっており、生態系や農業への悪影響の恐れがあることから環境省の「特定外来生物」に指定されています。その繁殖力の強さから「地球上最悪の侵略的植物」ともいわれ、英語では“Alligator Weed”という名前が付いています。
 提供:兵庫県
提供:兵庫県

KONAN-PLANET 記者
地球上最悪!そんなに恐ろしい植物なのですか!

今井 博之 先生
はい、もの凄い繁殖力です。水草ですが乾燥にとても強く、水上と陸上の両方に侵入し、いったん定着すると河川、ため池や田んぼだけではなく、水辺の環境をも破壊してしまいます。また、塩ストレスにも強いので海岸地域でも繁殖できる。とんでもなく生命力の強い植物なんです。
ナガエツルノゲイトウが引き起こす問題

KONAN-PLANET 記者
ナガエツルノゲイトウが繁殖するとどんな危険があるのでしょう。

今井 博之 先生
夏に爆発的に繁殖。周辺の生物を全滅させる恐れも
夏になると爆発的に増えて、小さな池などはあっという間に緑で覆われてしまい、水中の酸素が少なくなるため生物が全滅してしまう恐れがあります。田んぼではイネを覆い収穫できなくなりますし、農業水路を詰まらせたりします。大雨の時にナガエツルノゲイトウが大量に流れると水路が詰まって排水できなくなり、洪水を起こすこともあります。
茎はストローのような中空で、そのため茎の一部は水面をプカプカと浮いて移動します。また茎や節の断片から根や芽を出し容易に再生するので、刈り取っても根や茎の一部が少しでも残っているとそこから生えて、また増えていきます。この植物だけを駆除できる農薬も開発されておらず、現在は注意深く刈り取って燃やすことしかできない状況です。

KONAN-PLANET 記者
それは恐ろしい・・・
どのような地域で問題になっているのでしょうか。

今井 博之 先生
兵庫県下では広く分布しており問題になっています。最近は千葉県の印旛沼など関東でも被害が報告されています。海外では、温帯・熱帯地域の世界30か国以上で侵入・被害の報告があり、東南アジアや中国の暖かい地域で大きな被害が出ています。また、アメリカ合衆国の南部やオーストラリアのニューサウスウェールズ州でも問題になっています。今のところ、この植物を根絶やしにする有効な手立ては見つかっていません。
\ 農林水産省でも注意喚起! /
侵略植物の正体を解き明かせ!

KONAN-PLANET 記者
今井先生は、どのような研究をされているのですか。

今井 博之 先生
侵略的な特徴やしくみを物質レベルで解明する
ナガエツルノゲイトウの侵略的強害性を特徴づける代謝生理の分子機構を、遺伝子のレベルで理解することで、将来的にこの植物を駆除する除草剤の開発を目指しています。
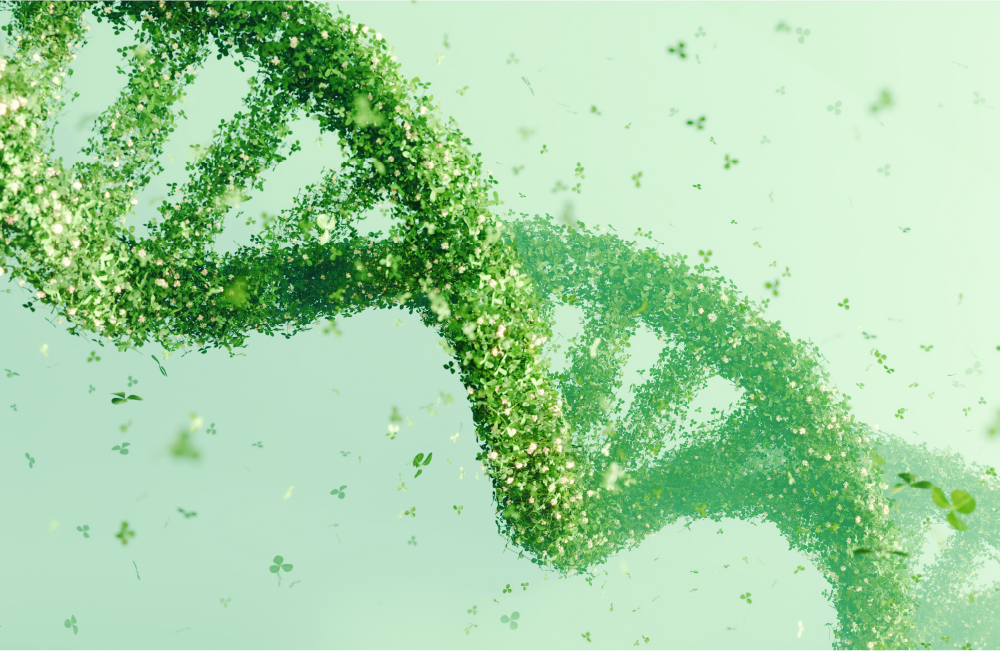

KONAN-PLANET 記者
むむ?もう少しわかりやすく教えていただけますか。

今井 博之 先生
ナガエツルノゲイトウは水草ですが、乾燥ストレスにとても強いという特徴を持っています。ということは、他の植物にはない特別な細胞レベルでのしくみを持っているのではないか、植物として生き延びるための戦略があるのではないか、そういう仮説のもとで、まずは、ナガエツルノゲイトウがどういう生き物なのか、物質代謝や遺伝子発現をキーワードにして、明らかにしたいと考えています。

KONAN-PLANET 記者
「物質代謝」とは?

今井 博之 先生
「代謝」とは、人間でいうと食べて、消化して、エネルギーにして生きること(生命活動のこと)をいいます。植物でいうと、太陽の光を使ってCO2を有機物に変える光合成を基本とする生命活動のことです。ナガエツルノゲイトウは根の発達もいいし、光合成も強いので、その結果、繁殖力がもの凄いです。そうした代謝のメカニズムを解き明かすことで、駆除できる薬品の開発につなげることが、私たちのミッションです。
知れば知るほど面白い、その特徴

KONAN-PLANET 記者
どのように研究を進められてきたのでしょう。

今井 博之 先生
まずは、研究室にある栽培室の人工気象庫でナガエツルノゲイトウを栽培することから始めました。気温や光度などをコントロールして同じ条件で栽培することを栽培の標準化といいますが、1年半かけて標準化ができるようになりました。ちなみに、ナガエツルノゲイトウは特定外来生物ですから、公的機関に申請し、厳しい制約のもとで栽培しています。みなさんが、ナガエツルノゲイトウと知った上で河原から持ち帰ったり、移動させたり、栽培したりすることは違法ですので気をつけてくださいね。

研究を進めると、ナガエツルノゲイトウが本当にユニークな植物だということが分かってきました。およそ2年研究してきて、ようやく何者かということがある程度見えてきたので、その一部をご紹介しましょう。
\ 2年に及ぶ研究で見えてきた! /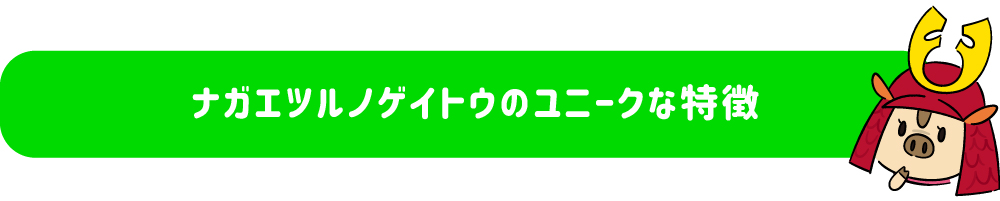
種からではなく、クローン化して増殖する
ナガエツルノゲイトウは、ぼんぼりのような花を咲かせるが、日本の系統は種子ができない。つまり、自分の身体を切って植物体を増やしていくクローン生物のような珍しい植物といえる。ほとんどの植物は、雄雌によって生殖成長するが、ナガエツルノゲイトウは栄養成長をする。つまりそれは、あえて生殖成長しなくても、暖かいところであれば生き延びている植物のひとつといえる。
葉の表と裏、両方から光合成ができる
植物は葉にある「気孔」から二酸化炭素を吸収して光合成を行う。植物は葉の裏側にほとんどの気孔があるが、ナガエツルノゲイトウは水草なので、葉の裏側と同じくらい表にもたくさんの気孔があり、葉の表と裏の両方から光合成ができる。

提供:兵庫県

KONAN-PLANET 記者
今後、どのような研究をされるのでしょう。

今井 博之 先生
ようやく、どういう植物かの一端が分かってきたので、ナガエツルノゲイトウを駆除するために、どのような物質が効くのか探る段階に入ってきました。しかも、環境にやさしく駆除できるしくみについても検討したいです。また、生殖成長をしないで生きる、ということは遺伝子の変化が少ないということを意味します。駆除することができる薬品が見つかれば、それは世界中のナガエツルノゲイトウを一網打尽にすることもできるのではないかと予想しています。

KONAN-PLANET 記者
「環境にやさしく駆除する」とは?

今井 博之 先生
例えば田んぼに繁殖したナガエツルノゲイトウを駆除しようと強い化学物質を撒くとします。そうすると、イネが枯れてしまうでしょう。イネはもちろん、周辺の植物や昆虫、川魚に影響を及ぼします。環境に配慮しながらナガエツルノゲイトウだけを駆除する、それが、もっとも難しい課題だと思いますね。
未知の生物を解き明かす面白さ

KONAN-PLANET 記者
そもそも、どのような経緯でこの研究が始まったのですか。

今井 博之 先生
甲南大学では近隣の博物館の学芸員の方々と交流があり、『兵庫県立人と自然の博物館』の河川の専門家の方から話を聞いたことがきっかけです。ナガエツルノゲイトウという植物の問題が深刻化していて、兵庫県でも拡散防止と駆除が強く求められているけれど、その植物生理学的な特徴については、ほとんどよく分かっていない、というんですね。
そういう訳で、ラボの研究の中心に据えて本腰を入れることにしたんです。私のゼミでも興味を持ってくれる学生がいて、今は4名が卒業研究の題材として取り組んでくれています。


KONAN-PLANET 記者
このような研究の意義や醍醐味とは、どのようなことでしょう。

今井 博之 先生
ユニークなこの生き物のしくみが知りたい!
生態系を破壊する植物を根絶することが目的ですから、SDGsの目標の一つである「生物多様性を守ろう」というテーマへの貢献にもつながります。一人の生物学者として重要なことをしているな、という思いはあります。
その一方で、「このユニークな生き物のしくみが知りたい」という純粋な探究心に突き動かされているような気もしています。研究をすればするほど不思議な植物で、つねに驚かされますし、本当に興味深いですね。もちろん、大学としては研究の成果を除草剤につなげることがミッションですが、未知の生物を解き明かすことの醍醐味を十分に堪能できる。
興味のある学生は、
ぜひ研究室の門を叩いてください。

- 今回お話しを聞いた人
-
甲南大学 理工学部 生物学科 今井博之 教授
総合研究大学院大学生命科学研究科博士課程修了後、オハイオ州立マイアミ大学博士研究員として、植物の物質代謝に関する遺伝子解析に従事。1995年に甲南大学に着任後、植物脂質、特にスフィンゴ脂質という”謎めいた脂質”の代謝に関する研究を行ってきたが、2022年度よりナガエツルノゲイトウの研究をスタートしている。