
「関西湾岸SDGsチャレンジ」で甲南大生が地域課題の解決に貢献。
この地球に暮らすすべての人々が平和と豊かさを享受できるよう、2015年に国連が掲げた「SDGs」という国際目標。甲南大学では早くからこの精神に賛同し、朝日新聞社とともに「関西湾岸SDGsチャレンジ」というプロジェクトを推進してきました。各地の自治体と連携して、持続可能な社会を実現するための方法に学生たちが取り組んできました。
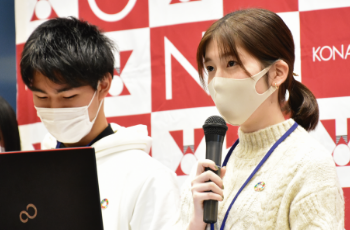
毎年高い評価を獲得している、学生ならではの視点と発想。
2020年の「関西湾岸SDGsチャレンジ」も、神戸市、堺市、和歌山市、徳島市、岡山市という5つの自治体の協力のもと、現地の高校生と甲南大生が協力して課題解決に挑戦。コロナ禍の影響を受け、対面での活動が制限される中、オンラインツールを活用し、作りあげた企画を各自治体にプレゼンテーションを行いました。学生ならではの柔軟な視点や発想から生まれたアイデアには実現可能性の高いものも多く、各自治体から高く評価されました。
-

竹林を資源化することで六甲山の生態系を保護する。
「神戸市における地域循環共生圏の取り組みを考える」というテーマに対してメンバーは六甲山に注目。放置竹林が生態系に悪影響を与える問題を知り、この竹を資源活用する方法を検討した。学生が授業やサークル活動を通じて竹林整備に協力し、切り出した竹を、土壌改良剤にしてブランド野菜を栽培・販売する、企業と連携してバイオマス発電の燃料にするといった「甲南学園モデル」を提案した。
-
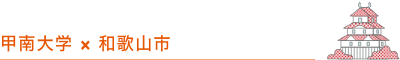
地域の足として重要なローカル電鉄を活性化させる。
利用者減少で存続の危機にある和歌山電鉄貴志川線。この現状を解決するため、運営事業者などに取材したうえで企画を立案。当初は観光客の集客などを考えていたものの、新型コロナウイルスの感染拡大など非常時には危機が拡大することを懸念。最終的には、地元の住民や学生と協力して駅を「健康」をテーマにしたコミュニティ拠点とし、電車利用者を自然と増加させるアイデアを提案した。
-

地元の人気サッカーチームと連携して地域に一体感を。
引きこもりや貧困といった困難を抱える社会的弱者が地域や人とのつながりを持つために、地元のサッカーチームと連携した啓蒙イベントを提案。サッカーJ2・ファジアーノ岡山の試合をみんなで応援する「Stay with Fagi day」を設定。来場者のマスクに趣味や好みを示すシールを貼って共通の話題づくりを促したり、人文字での一体感を体験してもらったり、そして選手やサポーターも交えた動画の制作を提案した。
-
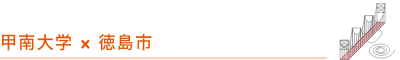
目と耳と足で調査した地域の魅力を親しみやすく発信。
吉野川とその支流による三角州「ひょうたん島」を中心に発展した徳島市。その魅力を守り、再発見し、発信していくための方法を模索。アピールの出発点として、ひょうたん島周辺を歩いて巡るためのマップを作りあげた。観光振興団体へのオンライン取材や、吉野川とその支流で清掃活動を続けるNPO法人へのインタビュー、1周6kmとなるクルーズの実体験などを経て、内と外、両視点から魅力を掘り起こした。
-

新たな愛称により「子ども食堂」のイメージを刷新する。
子どもの7人に1人が「相対的貧国」とされている現状、その受け皿にもなる「子ども食堂」のあり方を考察。堺市内にある2つの食堂で実態を調べた結果から懸念としてあがってきたのは、「子ども食堂=貧困」のイメージが利用を妨げているのではないかということだった。そこで「地域スクール・ラボ(スクラボ)」という愛称を考案し、みんなが集う学校のような新たなイメージをSNSなどで普及させていくことを提案した。





 甲南大学×東京海上日動×神戸市
甲南大学×東京海上日動×神戸市 





