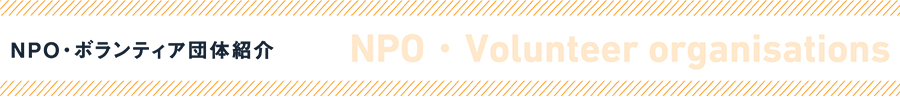

学習会の様子(写真:「特定非営利活動法人こうべユースネット」提供)
<団体プロフィール>
こうべユースネットは、2002(平成14)年3月5日、兵庫県より特定非営利活動法人の認証を受けた。「『人と人をつなぐ』『人が人をつなぐ』~青少年と共に、個から集団~」をコンセプトに掲げ、青少年が自分らしく過ごし、成長していくことのできる環境づくりに取り組んできた。設立以来、青少年が直面する様々な課題に向き合いながら、地域や学校、行政と連携した事業を通して、若者が社会とつながるきっかけや自信を持てる体験を積む機会を提供している。5つの重点目標は、「①人と人、人と社会をつなぐ青少年の居場所づくりを推進、②青少年の「生きる力」を育む場づくりとしての体験活動を推進、③今日的な課題を抱える青少年の支援を推進、④地域社会と連携した事業を推進、⑤青少年の育成にかかわる専門職の養成を推進」である。

インタビューの様子(乙井彩矢撮影、2025年6月14日)
——団体設立のきっかけを教えてください。
こうべユースネットは、2002(平成14)年3月5日に特定非営利活動法人として設立されました。しかし、前身団体があります。もとは「神戸市青少年団体連絡協議会(通称:青連協(せいれんきょう))」という、神戸市内で活動する16の青少年団体の横のつながりを持つ組織が母体です。青連協ができた1970(昭和45)年は、青少年の非行という社会問題を背景に「健全育成」という言葉が社会的に注目されていました。神戸市の青少年行政と連携しながら、キャンプや文化活動、地域での活動など、多様な取り組みに着手したのが始まりです。
ただ、神戸市民をはじめ兵庫県内、そして全国に「私たちはこんな活動している」とアピールする力を団体としてより広く持つためには、法人格が必要だと考えました。そこで、神戸市からのバックアップもあり、「法人格を持って活動を発信していこう」と決意して設立されたのが、「特定非営利活動法人こうべユースネット」です。設立以降、わたしたちは神戸市の青少年会館や活動施設の運営にかかわっています。ここでは、ただ施設を管理するのではなく、子ども、若者が自立し、自己実現や社会参加を果たせる場づくりに取り組むこと、というコンセプトのもとで活動をしています。
——キャッチコピーとして掲げている「であい・つながり・ひびきあい」に込められた思いをお聞かせください。
まず、「であい」は青少年会館の現場で、中高生と大学生、大学生同士、またはこうべユースネットの職員(ユースワーカー)との出会いを表しています。そこから自然と「つながり」が生まれていきます。いろんな人と関わることで「私ってこういう人なんだ」や「この人はこのような考えを持っているんだ」と、自己理解と他者理解が深まっていきます。すると、「この人と一緒にいたいな」、「この仲間と活動していきたい」と、関係が深まっていきます。そして、「ひびきあい」は、一番奥深い関係性です。例えば大学生が中心になってプロジェクトを立ち上げる時、お互いにいろんな意見をぶつけ合って、真剣に話し合いをします。最初は考えが違っても、話し合いを行う中で「じゃあ、この方向でやっていこう」と合意形成が生まれます。プロセスを通じて、「私たちはちゃんと響き合えてるな」と感じられるようになります。この「ひびきあい」は、大事な役割経験であり、生きた経験だと思います。
——こうべユースネットの生活困窮者学習支援ボランティアについて教えてください。
こうべユースネットでは、生活困窮世帯の中学生を対象とした学習支援事業を行っています。この活動は、課題を抱える若者が増えているという実感と、以前から連携のあった神戸市からの声掛けが重なったことをきっかけに始まりました。この学習支援では、単に勉強を教えることよりも、「居場所」になることを第一にしています。勉強ができるできないの前に、「私はここにいていいんだ」と感じられることが、中学生にとってのスタートラインです。その安心感があって初めて、勉強に自然と向き合えるようになります。大学生ボランティアは、その居場所づくりのキーパーソンとして大きな役割を果たしています。
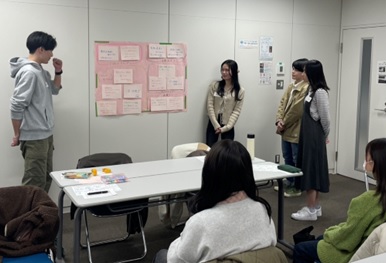
学習会の様子(写真:「特定非営利活動法人こうべユースネット」提供)
——生活困窮者学習支援では大学生ボランティアを募集されています。参加する大学生ボランティアをどのように捉えていますか。
活動の中で、大学生は学習支援スタッフとして参加してくれていますが、その前に「一人の人」として中学生と向き合ってくれる存在だと考えています。勉強を完璧に教える必要はありません。それよりも、自分なりに悩んだり工夫しながら、一生懸命中学生にかかわろうとする姿勢そのものが、中学生にとって大きな励ましになります。
また、大学生自身にとっても、この活動は成長の場になっています。活動の後には必ず振り返りの時間を設け、たとえば「こう教えたけど伝わらなかった」といった具体的な場面について、みんなで考えます。そして、お互いがチームとしてカバーをし合うことで、自己成長にもなると考えています。大学生同士が支え合いながら学び続ける姿は、支援の質を高めるだけでなく、一人ひとりの視野を広げる機会にもなっています。
さらに、勤労者に比べて中学生と年齢の近い大学生の姿を通して、「勉強って何のためにやるんだろう」、「高校ってどんな場所なんだろう」と中学生が将来を想像するきっかけにもなっています。ただ教えるのではなく、人と人とのかかわりを大切にするこの活動には、大学生の柔軟さと真剣さが欠かせません。
——大学生に伝えたいことをお聞かせください。
ボランティアに参加してくれる学生にもいろいろな大学生がいます。人によってボランティアを始めるきっかけも違います。「できることから、できる人に、できるときに」がこうべユースネットでのモットーでもあります。始めるきっかけは小さくてもいいんです。たとえば、友達に誘われたから、ちょっと興味があったからというものです。その一歩が、思っている以上に大きな変化に繋がります。社会人になった大学生が「こうべユースネットでの経験が、仕事で活きています」と報告してくれることもあります。その度に、「あの時、この場で出会えてよかった」と心から思います。だからこそ、まずはチャレンジをしてみてほしいです。どんな大学生にも可能性があると私たちは本気で信じています。
そして、ボランティアに限らず、なんとなく気になることがあれば、まずは飛び込んでみてください。「なんとなくやったら、やめとき」ではなく、「なんとなくやからこそ、やってみたら?」と、背中を押したくなります。大学生活にはたくさんの選択肢があります。だからこそ、今この瞬間にできることを全力でやってみてほしいです。そうした経験が、社会に出たときの選択肢を広げることにもつながっていきます。そして、その根底には、人との関係性を築くコミュニケーションがあると考えています。ボランティア活動でも、勉強でも、趣味でも真剣に取り組む中で自然と身につく力があります。余暇休暇に一生懸命になることも、人生の大切な一部です。それが人とのつながりを広げ、自分らしい人生を切り開く力になっていると考えています。

取材を終えて(乙井彩矢撮影、2025年6月14日)
話・辻 幸志氏
文・甲南大学 経営学部 2年次生 山崎薫
(2025年6月取材)