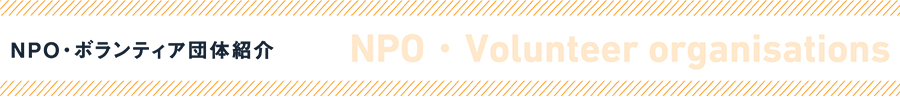

人と防災未来センター職員の大西さん
(榎本日菜撮影、2024年6月4日)
人と防災未来センター(以下、センター)職員である大西敏文(おおにし・としふみ)さん、および、語り部活動のボランティアとして活躍する近藤武士(こんどう・たけし)さんに話を伺いました。
―貴センターを設立したきっかけについて教えてください。
大西:1995(平成7)年に阪神・淡路大震災が発生し、政府の諮問機関である「阪神・淡路復
興委員会」において、国が講ずべき復興施策の一つとして、「阪神・淡路大震災記念プ
ロジェクト」が提言されました。その提言を受け、「阪神・淡路大震災メモリアルセン
ター構想」がとりまとめられ、その構想を具体化して出来上がったのが「人と防災未
来センター」です。国の支援を得て、兵庫県が2002年にセンターの西館を、翌2003年
に東館を設置しました。
―貴センターで活動するうえで、大切にしていることはありますか。
大西:兵庫県は、県民の参画と協働により県行政を進めていくこととしており、ボランティ
アとの協働によるセンターの運営はこれに合致すると考えています。加えて、「語り部
」活動は、ご自身の被災体験を語るという当センター職員にはできない活動であり、
語り部以外にも、語学部門や展示解説の部門において、来館者への解説や案内を担っ
ていただいており、ボランティアの協力なしにセンターの運営は成り立ちません。こ
のような点から、ボランティアの方々は当センターにとって「パートナー」とも言え
る存在であり、私どもはボランティアの皆さんが活動しやすい環境づくりを心掛けて
います。また、ボランティアの方々の高齢化が懸念される現在、持続可能な活動体制
を整えることを目標にして、大学生に向けて本センターでの活動を積極的にPRしたり
、活動をやめられる方の講話の様子を記録しておくなどの工夫もしています。
―近藤さんは、語り部のボランティア活動に参加されています。活動に取り組むきっかけを
教えてください。

ボランティアとして語り部活動に取り組む近藤武士さん
(榎本日菜撮影、2024年6月4日)
近藤:私は、このセンターの設立当初から現在までの22年間、このセンターでボランティア
として活動しています。大学職員をしていた経験を活かして、自分の震災体験を、学
生を含めた様々な人に語ることができるチャンスだと感じ、活動参加を決めました。
私以外にも、様々な経歴をもつ人たちがこのセンターでボランティアとして活動して
います。
―学生に対するメッセージをお願いします。
大西:学生の間にしかできない、様々な活動に挑戦してほしいと思います。学生同士だけで
はなく、様々な年齢層の人との交流を図ることで、多様な経験・知識を得ることがで
きると考えています。その活動が、これから社会に出ていく学生にとって良い経験に
なり、きっと将来役に立つと思います。
近藤:私は、世の中にプラスの影響が出る活動を、自ら進んで学生に行ってほしいと考えて
います。身近なことで言うと、地域の清掃活動が挙げられます。組織で行うほうが良
いとされる災害ボランティアなどの対人活動よりも、個人で自発的に、いつでもでき
る清掃活動のほうが取り組みやすいと考えています。また、活動を通して、地域の人
から感謝されることで、やりがいにも繋がると思います。
また、若いうちに、体力を養成し、好奇心を旺盛にして社会の動きに関心を持つこと
、歴史を調べ、図書館を利用して読書体験を豊かにすることをお勧めします。

ボランティア活動の様子(画像提供:人と防災未来センター)
〈団体プロフィール〉——————————————————————————————–
「人と防災未来センター」は、災害ミュージアムとして震災で起きたことを後世に語り継ぐ
とともに、実践的な防災研究や防災人材育成を推進している。また、国際的な防災・減災・
縮災の情報発信やネットワークの拠点としての役割を果たし、災害対応の現地調査や支援、
災害に関する資料収集・保存などに取り組んでいる。設立当初から現在まで、河田惠昭が
センター長を務め、組織としては研究部、事業部を有し、事業部には事業課、普及課、運
営課がある。登録ボランティアは、語り部部門が43名、語学関係部門が30名、展示解説部
門が92名の計165名、同センター友の会の会員数は、個人会員が30名、法人会員が1社であ
る(2024年6月現在)。
————————————————————————————————————————
話・人と防災未来センター職員 大西敏文氏、語り部ボランティア 近藤武士氏
文・甲南大学 経済学部 1年次生 中川あかり
(2024年6月取材)