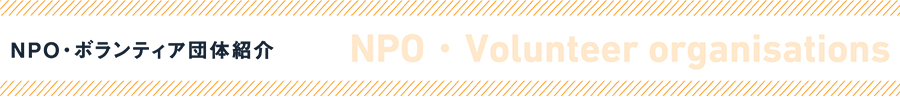
〈団体プロフィール〉———————————————————————————————–
みんなでハッピーキャンプ神戸地区実行委員会は、障がい者と健常者が出会い、交流し、共に生きていくことを目的としている団体である。みんなでハッピーキャンプは、兵庫県神戸市中央区に本部がある社会福祉法人「えんぴつの家」によって企画され、第1回目は1984(昭和59)年に淡路島の安乎浜(あいがはま)で開催された。キャンプは年々規模が大きくなり、県下1か所のキャンプ地では開催できないほどに人数が増えたため、今では6か所(神戸、明石、播磨、尼崎、西宮、芦屋)に分散して実施されるようになった。2025(令和7)年の今年で第40回目を迎える。コロナ禍以前は寝泊まりでキャンプを実施していたが、コロナ収束後はバーベキューや会話を楽しんだり、企画で盛り上がったりするなどの日帰りイベントとして開催されている。
—————————————————————————————————————————–
———みんなでハッピーキャンプの活動を実施することになったきっかけを教えてください。
堀之内:普段の生活で、障がい者と健常者が交流することが少ないので、出会うきっかけの場をつくるために、みんなでハッピーキャンプは活動を始めました。障がい者は、家とデイサービスを受ける施設との往復ばかりで学生や社会人と関わる機会が少ないため、学生や社会人に積極的に声をかけて多様な人々が参加する機会を増やしてきました。

実行委員長の堀之内さん(乙井彩矢撮影、2025年6月11日)
———障がい者と健常者が出会うことで、お互いどのような体験ができますか。
堀之内:キャンプにはいろいろな障がい者がいるので、一緒にご飯を作ったり、おしゃべりをしたりすることを通して、お互いに勉強になったらいいなと思います。
中尾:ヘルパーとは決められた時間による仕事としての関係ですが、ボランティアは違います。自分の話や悩みを話し合える関係、つまり友達のような関係です。堀之内さんは、学生との交流を長く続けているので、学生と一緒に遊びに行ったり、その人が卒業するときにはUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)に行っていました。他にも商業施設「ブルメールHAT神戸」で社会活動する学生グループと一緒にお茶を飲んだり、阪神・淡路大震災後に始まった神戸大学の学生を中心とした神戸市灘区の地域の復興祭である「灘チャレンジ」に学生と参加していました。このような活動を通して、障がい者は特別な存在ではなく、そこにいるのが当たり前になればいいなと思っています。
———大学生ボランティアについて教えてください。
堀之内:大学生ボランティアは全体では半数を占めており、キャンプ当日は介護含めて15名程います。キャンプ参加前にマッチングをして、車椅子の人の食事を手伝ったり、会話を楽しむなど、交流を楽しんでいただきます。そのうえで、興味があったら仲間や実行委員になることができます。しかし、もっと関わりたい、実行委員になりたいという人は、今の時点ではなかなかいないのが状況です。
山田:最近の学生は学業にアルバイトにと忙しいですよね。私の学生時代と全然違います。その中でボランティア活動の時間を確保するのは、なかなか難しいですよね。そういうこともあって実行委員になってくれる人はあまりいないのです。
堀之内:大学生のボランティアに求めていることは、たくさんの人と関わってアルバイトに生かしてもらってもいいですし、まずは単純に楽しんでもらうことを大事にしてほしいです。
中尾:実行委員になれば、さらに充実した運営経験や仲間を得ることができるかもしれません。先輩が後輩を紹介し、後輩が先輩になりまた後輩を紹介し、さらにその後輩が…というように、次の世代へ続いていくことを望んでいます。
———You Tube を観て、メンバー同士は仲がよさそうな印象を受けました。どのように信頼関係を築いているのですか。
堀之内:初めから信頼関係を築けているわけではありません。キャンプ当日までに話し合うべきことがたくさんあり、ときには言い合いになることもあります。しかし、最近は、みんなで一体になってキャンプをつくり上げているという実感を、当日には感じることができています。
山田:障がい者と健常者は考えていることや価値観が違うことが多いので、基本的に一つにまとまることはないです。きれいな言葉を使うと、多様性や個性を尊重しているからです。でも実際は混沌としています。
中尾:混沌としているけれど、それは悪い意味ではなく個性を前面に出しているということです。また、それをまとめることは非常に大変だと思います。学校のような、先生がいて生徒は素直に従うという状況ではないので、みんなはそれぞれ言いたいことを言い、意見をまとめざるを得ないという感じです。
堀之内:みんながみんなでハッピーキャンプのことを大切に思っているからこそ意見を出し、まとめることができます。
中尾:目標が一緒ということですね。みんなでハッピーキャンプを成功させる、そしてみんなで行って楽しんでみんなで安全に帰ってくるという安全面でも団結しています。
———今年でキャンプ開催40回目の歴史をもつ貴団体の今後の目標について教えてください。
山田:より多様な人と出会い、関わり、認識してもらいたいです。うちの団体は非常にマイナーなので、メジャーになるように頑張っています。たとえばインスタグラムを開設してみたのですが、あまり更新もできず、どのような団体か分かりにくくなっています。
堀之内:コロナがきっかけで再開されていないままの寝泊まりでのキャンプを復活させたいです。また、実行委員の年齢層が二極化しているので人数を増やしたいです。そのためには、参加者が無理をせずに今後も続けられるような、モチベーションをさらに高めてもらえるような工夫が必要だと考えています。参加者はもちろんですが、実行委員も楽しみながら続けていきたいです。

キャンプの様子(写真:「みんなでハッピーキャンプ神戸地区実行委員会」提供)
———ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)を手に入れるためにボランティアをする人をどう思いますか。
堀之内:ガクチカ目的で他の団体のボランティアに来る人も多いなと思います。ただ、みんなでハッピーキャンプにはガクチカが目的というよりは、やりがいを感じるために参加する学生が多い印象を受けます。また、積極的にボランティアをしようと思っている人が年々減ってきているように感じます。
山田:わたしが学生の頃は、ボランティアが就職につながるとは考えてもいませんでした。周りの目や評価ではなく、自分らしく生きる方が大事だと考えます。楽しくて、やりがいを感じて、本当に力を入れてきたかは、採用する側に見通されますから。また、人として礼儀正しいかということの方が注目されると思います。
中尾:他人の評価ばかり気にしていたら続かないと思います。しんどいことも楽しめられるくらいになったらいいと思います。楽しまないとできないですよ。

インタビューの様子(中尾聖子氏撮影、2025年6月11日)
話・堀之内和弘氏(代表)、山田智男氏(会計)、中尾聖子氏(福祉施設職員)
文・甲南大学 文学部 歴史文化学科 1年次生 乙井彩矢
(2025年6月取材)