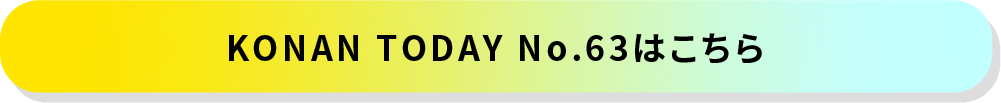ロボットと仲よく暮らす未来がすぐそこに!?
「ロボット付き合い」を良くするコツ教えます。
「ロボット付き合い」を良くするコツ教えます。
案内用ロボットや掃除用ロボット、配膳用ロボットなどロボットが身近な存在になってきた昨今。 製造工場で動く産業用ロボットはすでに普及期に入り、今後、ロボットと一緒に暮らす世の中になるのは必至です。では、ロボットが社会に溶け込むためには何が必要なのか。そのカギは「ロボット付き合い」にあると梅谷智弘准教授。知能情報学部でロボット研究に取り組む梅谷先生に、これからのロボットと人の関係について伺いました。

KONAN-PLANET 記者
梅谷先生、今日はよろしくお願いします!
2022年3月、甲南大学図書館のヘルプデスクに
かわいいロボットが登場したそうですね。

梅谷先生
はい、図書館お助けロボットです。
KONANプレミア・プロジェクト※の一つである
『AIロボット学びプロジェクト』の一環として、
知能情報学部の学生たちによって開発されました。


KONAN-PLANET 記者
このロボットはどのような役割を果たしているのでしょう。

梅谷先生
図書館司書が行う業務の一部を代行しています。図書館を利用される方と音声でコミュニケーションを図りながら、蔵書を検索したり、お勧めの本を紹介したりすることができます。たとえば、PLANET記者さんがヘルプデスク前にセットされたイスに座るとしますよね。その様子をカメラで認識し、ロボットの方から話しかけます。ロボットには数パターンの会話のシナリオが用意されていて、ロボットがリードする形で利用者の要望を聞き出し、リクエストに応える仕組みになっています。
開発のきっかけは、新型コロナウイルス

KONAN-PLANET 記者
そもそも、どうして図書館にロボットを
導入しようと考えたのですか?

梅谷先生
新型コロナウイルスの感染拡大にあたり、図書館でもできる限り人と人が接触する機会を減らそう、ということになり、ヘルプデスクへのロボットの導入が発案されました。

KONAN-PLANET 記者
人との接触を減らすためにこんなにかわいいロボットが
導入されたとは素敵ですね!
どういう仕組みになっているのですか?

梅谷先生
本をお勧めする場合なら、利用者のリクエストをロボットが聞き取り、インプットされた音声をデータに変換してインターネット検索する、という仕組みになっています。検索結果をコンピュータが読み取り、ロボットに発声させるので、できるだけ自然に人と会話ができるよう開発しました。

KONAN-PLANET 記者
たとえば、どんな工夫があったのでしょう。

梅谷先生
人の声や話し方には個人差がありますよね。同じコロナ関連の本を探す場合でも、話し方は人それぞれ違います。
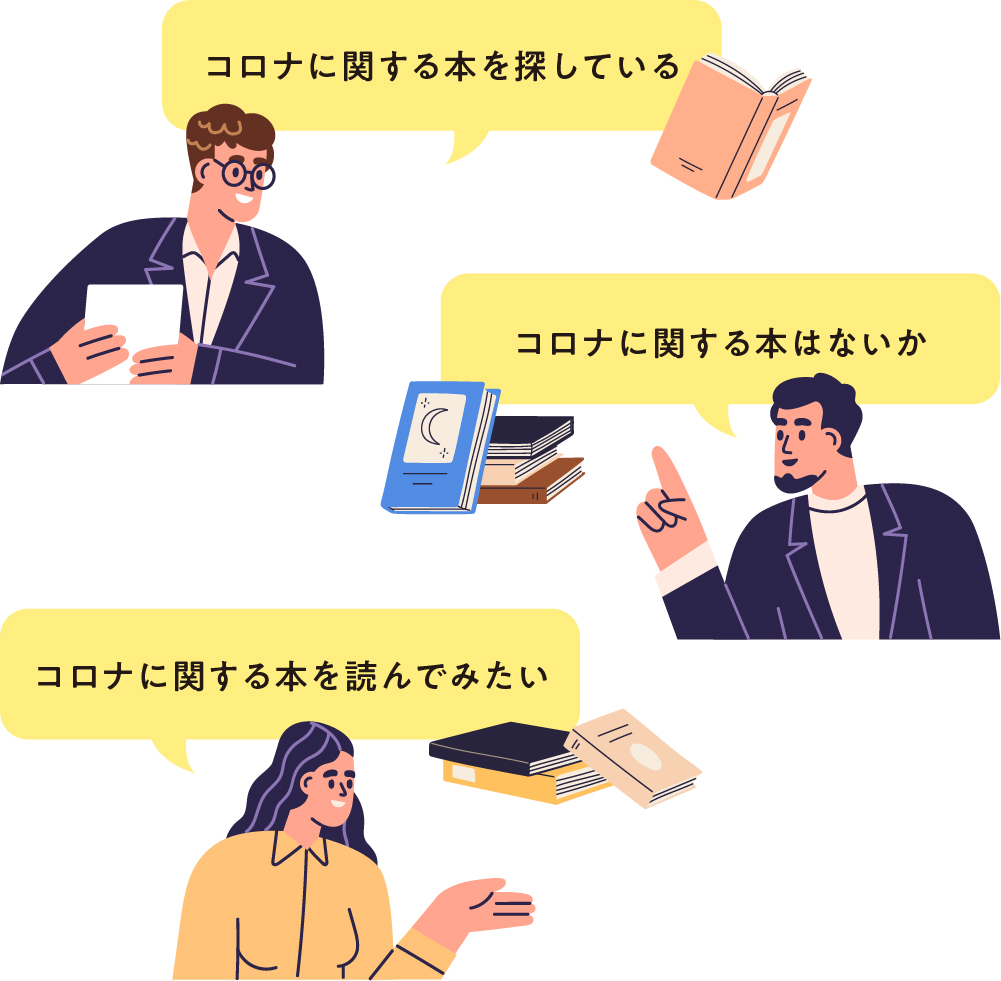

梅谷先生
このように、表現は異なっていても本質的な意味が
読み取れるような認識技術を構築しています。
さらに、マスク越しの声でも聞き取れるようにテストを重ねました。
だから人と自然に会話できるのです。
ちなみに、ロボットを動かすプログラムはクラウド上にあります。そのため、処理はすべてインターネット回線を経由してクラウドで行われています。プログラムに使われている言語は「Python(パイソン)」です。

KONAN-PLANET 記者
ロボットが実際に稼働するまで
どれくらいの期間がかかりましたか?

梅谷先生
3名の学生が開発に携わり、初期構築に約3か月、それから2か月ほどテストと調整を繰り返しました。とはいえ、担当するのは学生ですから、一日中作業にかかりっきりだったわけではなく、実際の開発時間はかなり短く抑えられています。
ロボットを賢く動かすには、状況とニーズの把握が必要。
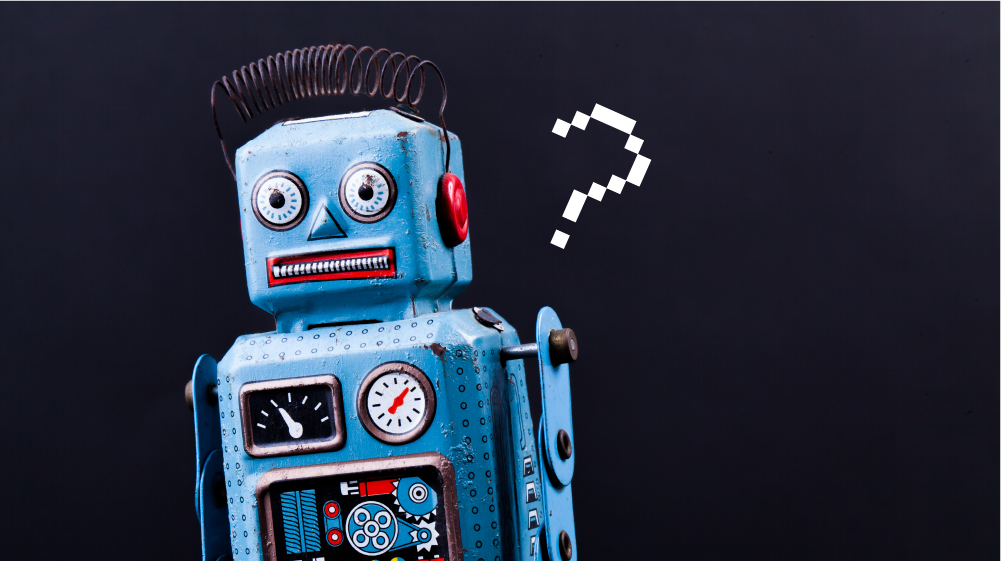
そもそもコンピュータは融通が利かず、プログラムした通りに動く機械です。だから、プログラムがきちんと挙動するためのお膳立てを、人が十分に考えておかなければならないのです。






ロボットとの「付き合い方」は人が決める

KONAN-PLANET 記者
これから、人とロボットの関係は
どうなっていくのでしょう。

梅谷先生
今後は、日常生活のさまざまなシーンでロボットが活用されるようになるでしょう。とはいえ人が、ロボットに使われるような世界には、絶対にしたくありません。あくまでも人が、ロボットを使うのです。
これから登場するロボットについては多種多様なものが考えられます。中には、映画に出てくるような人型アンドロイドに近いものが出てくる可能性もあります。そんなロボットからサービスを受けるときでも、「このロボットを使っているのは人間だ」という認識をもつ必要があります。確かにロボットは自動で動くけれども、最初にその動き方を決めるのは人なのです。
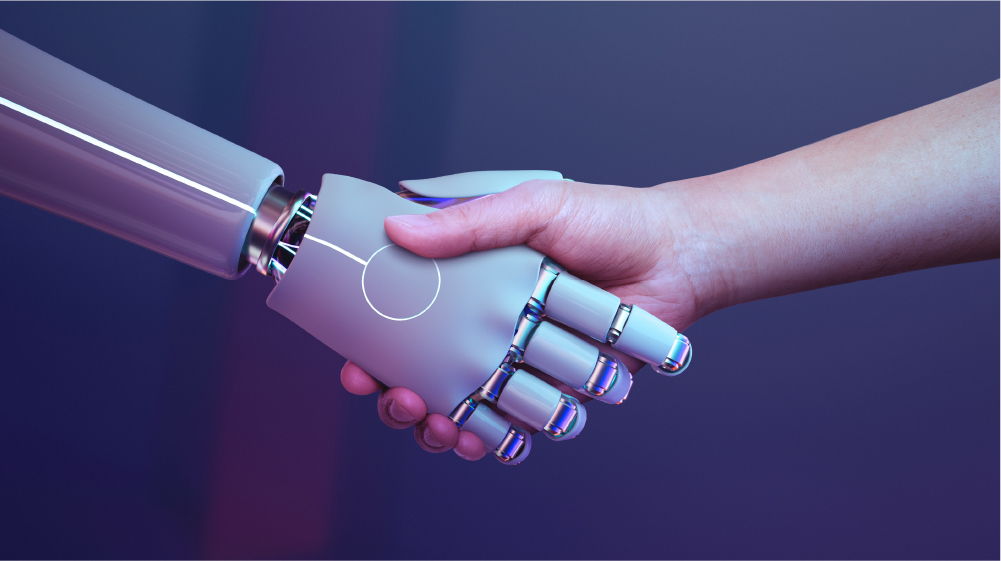

KONAN-PLANET 記者
ロボットの先には人がいることを忘れないようにします!

梅谷先生
ロボットたちとのかかわり方、つまり「ロボット付き合い」は、これからの社会の重要課題となります。ロボットがどんどん人に近づいてくると、そもそも「人とはなんぞや」という問いに向き合う必要も出てくるでしょう。まさにロボットを通して人を知る社会が、すぐそこまで来ています。
良いロボット付き合いをし、
ロボット技術を社会で活用していけば、
人の多様性がより生かされる社会になると思います。
例えば、言語や身体的特徴の違いといった「人と人の違い」をロボットを活用して補っていけば、誰もが暮らしやすい社会になる。そんな未来を見据えて、研究に励んでいます。

KONAN-PLANET 記者
今やロボットがいる生活はあたりまえ。
良い「ロボット付き合い」をして、
より豊かな社会を目指していきたいですね。
本記事は学園広報誌『KONAN TODAY NO.63』に 掲載中の「甲南アカデミア」を再編集しています。

- 今回お話しを聞いた人
-
知能情報学部 知能情報学科 准教授 梅谷 智弘
大阪大学大学院基礎工学研究科システム人間系専攻博士課程修了。前職の名古屋市立大学助教時代にデッサンから製品設計やプロダクトデザイン演習など、デザイン教育にもかかわっていたこともあり、今も趣味は美術館巡り。優れたデザインをたくさん見てインプットすることが、ものづくりにも生きている。