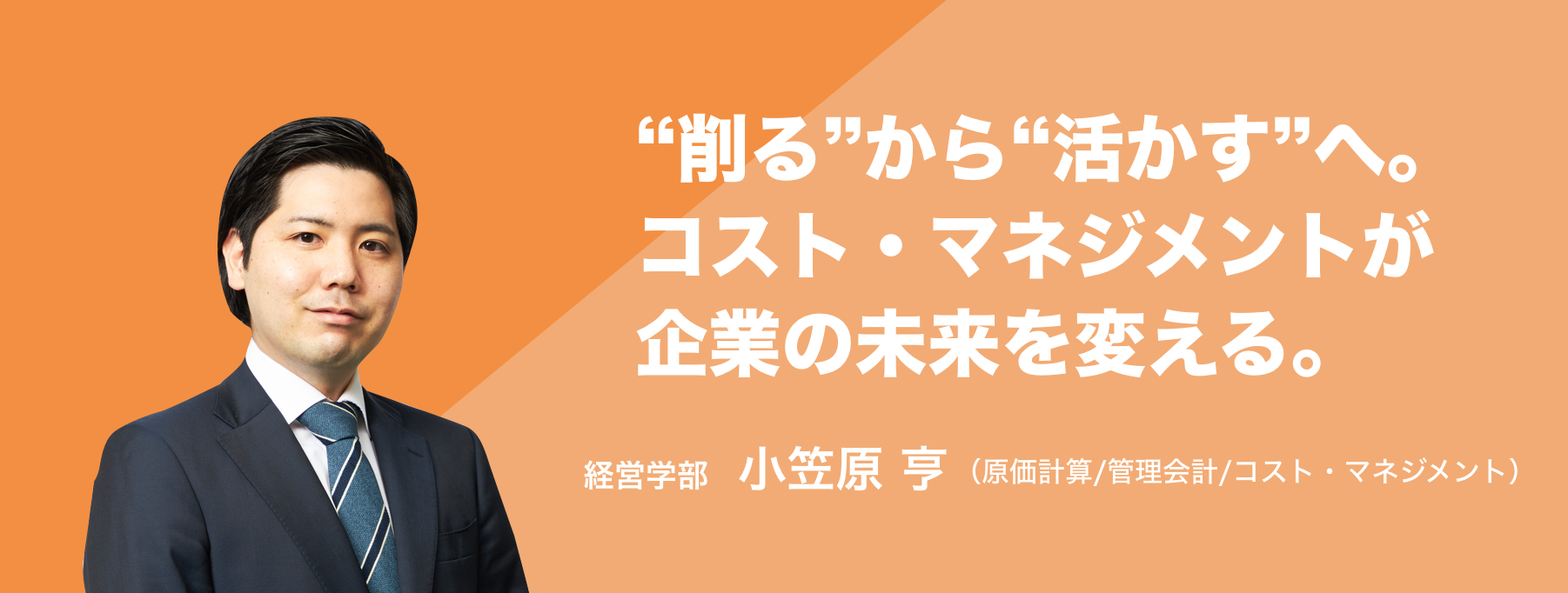コスト・マネジメントの専門家で、原価計算/管理会計について研究している小笠原亨准教授にお話を伺いました。
About Me ( OGASAWARA Toru )
大学時代、将来は会計専門職に就きたいと思い、もともとは簿記の勉強をしていました。しかし、勉強を進めるにつれて「数字は好きだが、大雑把な性格の自分にはあまり向いていないのでは」と悩んでいたところ、当時の指導教員に研究の道を勧められ、現在に至ります。
公開財務諸表や企業の内部データ(ex.業績評価や部門別数値)をもちいた統計分析を中心に、大学院時代から研究を続けてきました。写真は、博士論文の内容をアメリカ会計学会のポスターセッションで報告したときのものです。専門は管理会計という分野で、企業経営における会計の役割について研究しています。これまで研究や教育を通じて、実務家の方々の話を伺うたくさんの機会に恵まれました。こうした経験から、会計データにどのような意思決定や人間の行動が反映されているのかに強い興味を持っています。
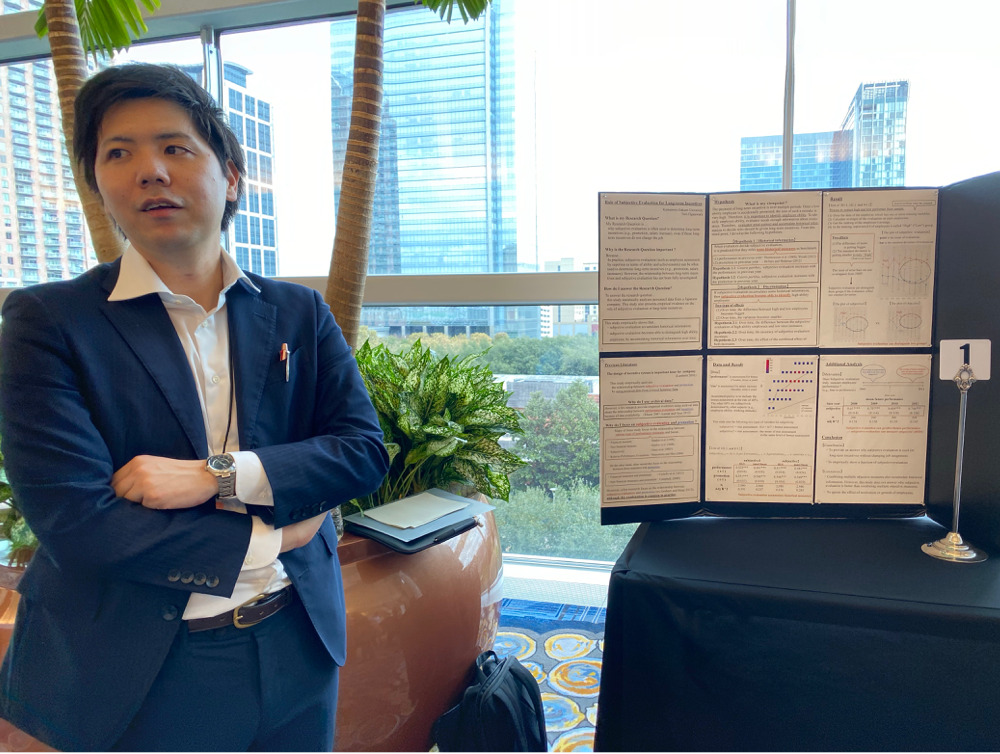
Research
Cost Structure
企業が活動を行うにあたっては、まず「どれだけの製品やサービスを提供するのか」を事前に見積もる必要があります。これは、何人の従業員を雇うか、どのくらい大きな工場や店舗を準備するかなどをあらかじめ決めなければならないからです。大量に製品やサービスを提供しようとすれば、それだけ多くの従業員を雇用し、大型の設備を先に用意しなくてはなりません。このように「生産のための能力(キャパシティ)」をどう決定するかは、企業のコストに直接影響します。キャパシティを拡大すればするほど、従業員の給与や設備の維持費といった、毎月かかる定額の支出も増えていくからです。これらの費用を「固定費」と呼びます。結果として、企業がどれくらいのキャパシティを確保するかによって、同じ業界でも企業ごとに固定費の割合(=コスト構造)が異なることになります。この違いが企業の行動にどのような影響を与えるのか、また、どのようなキャパシティ水準やコスト構造が望ましいのかといったことを研究しています。
コスト構造やキャパシティといった概念は、簿記のテキストでもCVP分析や生産能力の話として長年親しまれてきたものです。しかし、2000年代以降、こうしたテキストの伝統的な見解と相反する実証分析の結果が次々に提出され、現在に至るまで様々な観点から理論の見直しが進んでいます。教科書で学んだ内容が新しい研究によって更新されていく様子をリアルタイムで見られることは、この分野を研究する楽しみの一つです。
Strategic Cost Management
「コスト・マネジメント」と聞くと、「とにかくコストを削減すること」というイメージを持つ人が多いかもしれません。しかし、実際には「コストをかけること」が必要な場合もあります。たとえば、広告宣伝費や研究開発費を安易に削減すると、ブランド・イメージが損なわれたり、新製品を開発する機会を失うかもしれません。こうした広告宣伝費や研究開発費といったコストは、これまでコスト・マネジメントの主たる研究対象となってきた「売上原価」ではなく、「販売費及び一般管理費(通称、販管費)」に分類される費用です。
現代では、この販管費の重要性が高まっています。たとえば、私の所属する研究チームで行った分析では新しく上場した若い企業ほど総費用に占める販管費の支出割合が高くなるという傾向や、販管費支出の多い企業の方が長期的なパフォーマンスが高いという実証結果が得られています。類似の現象は、経済産業省からも指摘されています。現代では、日本企業の強みであったサプライチェーンの中流(製造)よりも、上流(企画・開発)や下流(流通・販売)のプロセスを担う企業の方が収益率が高くなるというスマイルカーブ現象が見られており、我が国における製造業の利益率低迷を招いた原因の1つとして指摘されています。すなわち、製造工程だけに注力するのではなく、より付加価値の高い上流・下流分野に戦略的に資源を投入できるかどうかが、企業の競争力を大きく左右しているのです。このような背景から、企業の長期的な収益性を高めるためには、「どのコストを削るべきか」よりも、むしろ「どこにコストをかけるべきか」を明らかにすることが一層重要になっています。とりわけ販管費をどのように活用するかは、企業価値の向上を目指すうえで今日的な課題といえます。
KONAN’s Value
甲南大学経営学部では「社会に貢献するビジネスパーソンの養成」を基本方針としています。たとえば、私のゼミでは「会計を使える」ようになることをテーマにゼミを運営しています。簿記試験の勉強だけをしていても、会計を使えるようにはなりません。ゼミでは、ボードゲーム等を通じた投資の仮想体験や財務諸表をもちいた企業分析など実践的なカリキュラムを通じて、実社会に役立つスキルを修得することを目指しています。
甲南大学の魅力の一つは、キャンパスが広すぎず、教員と学生はもちろん、学生同士の距離感も近いことです。私のゼミでは、企業分析に関するプレゼンテーションをチーム活動で行っていますが、ゼミ生同士でも頻繁にミーティングを重ね、熱心に取り組んでいるため、発表の質がとても高いです。私自身の研究では、上場企業全体を統計的に俯瞰することが多いのですが、ゼミでは学生が個々の企業の財務諸表を丁寧に分析して報告してくれるため、研究では「鳥の目」、教育では「虫の目」で企業を見ているような感覚があり、この両方の視点が新たな研究アイデアを生むきっかけにもなっています。こうした研究アイデアをもとに分析を行い、それを次年度の授業資料に反映させるなど、研究と教育の良い循環も生まれています。こうした研究と教育の連携が実現できるのは、人との距離感が近い甲南大学ならではの特徴だと感じています。


Private
趣味は美味しいものを食べることです。友人から「CMに出られそうなくらい美味しそうに食べるね」と言われたことが何度もあるほどです。甘党で、カクテルやスイーツが好きです。なかでも、カクテル作りは、珍しいスピリッツやリキュールを買ったり、百貨店のスイーツとのペアリングを考えるなど、趣味として楽しんでいた時期もありましたが、最近では健康を意識して控えています。
双子が生まれてからは、育児中心の忙しい日々を送っています。食べ盛りでわんぱくな小さな二人に振り回される毎日ですが、最近は少しずつ落ち着いてきて、ようやく外出を楽しむ余裕も生まれてきました。


Profile

経営学部 准教授
小笠原 亨
(OGASAWARA Toru)
専門領域
原価計算、管理会計、コスト・マネジメント
キャリア
神戸大学大学院経営学研究科 博士課程後期課程修了
熊本学園大学商学部 講師および准教授
所属学会
American Accounting Association
日本会計研究学会
日本管理会計学会 日本原価計算研究学会