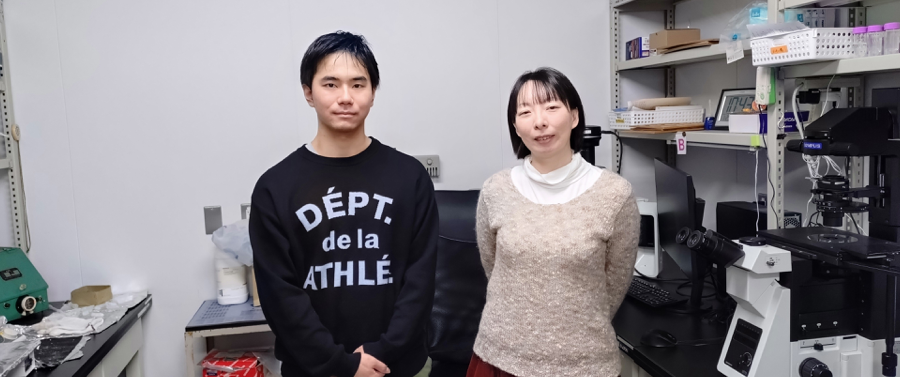理工学部 准教授 後藤 彩子 × 経済学部 三野 聡一朗
後藤先生が行っている研究はどのようなことですか?

専門は生物学で、アリの研究を行っています。その中で、他の研究者がまだ研究を行っていない女王アリの精子の保存に関する研究です。女王アリは、10年以上生きることができ、その間は死ぬまで卵を産み続けます。しかし、女王アリは一生のはじめの頃しかオスアリと交尾しません。オスアリは交尾した後はすぐに死んでしまいます。通常なら、交尾された時の精子は長くはもたないのですが、女王アリは10年以上も生きることができ、その間精子をおなかの中に貯めて保存することができます。現在、家畜やヒトの精子を保存する方法は液体窒素を利用していますが、液体窒素は電気がないと製造できないので、災害などにより停電が起きると、液体窒素の供給が途絶え、精子が死ぬ恐れがあります。女王アリの精子貯蔵の仕組みを解明することができたら、さまざまな生物の精子の人工保存に応用できるかもしれません。
なるほど、よく分かりました。

女王アリはどのような仕組みで生まれるのでしょうか?

アリでは、受精卵がメスに、未受精卵がオスになります。女王アリだけではなく、働きアリも実はメスです。アリは卵の時点で、女王になるのか働きアリになるのかが遺伝的に決まっている種もいれば、その後の幼虫期に決まる種もいます。アリは1万種いるので、多様なのです。幼虫期に運命が決まる種では、その時に与えられる餌や日長や温度などの環境により女王になるか働きアリになるか決まると言われていますが、細かいところは分かっていません。アリはハチの仲間なのですが、ミツバチであればロイヤルゼリーを食べた幼虫が女王バチになることが分かっています。
そんなにも種類があるかつ幼虫の段階で決まるのですね。驚きです。

その研究を始めるきっかけとは何でしょうか?

元々アリが好きで、小学生の頃からアリの行列を観察するぐらい好きでした。多くの研究者がアリの研究をしてきましたが、女王アリの精子が10年も保存できるメカニズムは研究されてきませんでした。理由は、女王アリは確保することが通常難しく、様々な条件で行うのには圧倒的に数が足りないからです。私は、女王アリを大量に採集でき、飼育もしやすい種を選び、実験に使うことにしました。人ができない部分をオンリーワンでやろうと思ったのが、「きっかけ」です。
かっこいいですね。まさしく最先端の研究をなされています!

女王アリはどうやって集めているのですか?

1年に1回に起きるアリの大発生のタイミングを狙って、捕獲しています。交尾する際、女王1年アリは明るいコンビニといった場所に飛んでいきます。交尾後に巣を作るために地下に潜ります。地下に潜ってしまうと一気に集めるのが難しくなってしまうため、明るい場所で待機して捕まえています。さらに、この種の女王アリは9月の蒸し暑い夜に大発生するのですが、それがいつかは予想できないため、採集のために他の予定は立てられませんが、楽しみです。
本当に地道な努力が必要なのですね。

採取できなかった場合はどうなさっていますか?

年によって、交尾直後の女王アリを採取することができなくても昨年の女王アリを使って研究をしています。アリが長生きするので、年々飼育しているアリの数は増えています。

体験:女王アリや研究室を見せて頂けますか?

採取した場所と年を記録して、アリの巣を管理しています。交尾した女王アリはほかの働きアリと比較して断然大きいです。特徴として、アリも人間と同様にゴミを置くための場所を作っています。アリは家族で密集して過ごしているので、何かに感染してしまうと一気に巣の中で感染が広がって全滅する恐れがあります。それを防ぐために、アリたち自ら汚いものを遠ざけて綺麗にする衛生行動を進化させています。研究室には、10年以上前から生きている女王アリもいますし、多種多様なアリを多く育てています。部屋は温度を25℃に設定し、環境を整えています。
人間社会の構造とほとんど似ていますね・・・。

甲南大学で研究して、この大学だからこそ良かった点は何ですか?

自由に好きなことを行える点と、職員さんや警備員さんの「大学愛」が大きい点です。学生がアリを採取するときには見守ってくれました。
「大学愛」が強いのは、私も講義を受けて非常に強く感じています。

今後の研究面での目標を教えてください。

今行っている女王アリの精子保存の研究を完全に解明することです。長く研究して最終段階になっています。
楽しみにしています!

学生時代にやった方がいいことはありますか?

知的好奇心を持つことが生きていく中でも大事です。その中で、本を読むことは学生時代に是非した方がいいかなと思います。最近は、本を読まない子が増えており、文章を書くのに苦戦している人が多いように思います。本を読むことは知識の増加や集中力の増加ができると思います。
学生から学んだことは何かありますか?

自由な発想力があるところです。研究室には、基本的な研究器具はありますが、それを使って自分の実験に合わせた装置を開発するなどです。例えば、羽アリがいつどのタイミングで飛ぶのかを調べるために、アリを飼っている天井にテープを貼り付けて、そこに貼り付いた羽アリを数えることで、いつ何匹飛んだかを調べる装置を発明していました。また、プレパラートの観察にもっと良い観察方法があるのではないかと工夫を加えるなど行っており、こちらも勉強になりました。
今、私が取り組んでる就職活動で求められる自発性と知的力を学べる環境と同じですね。自分も何か役に立つものを残したいです。

インタビューの感想
後藤先生へのインタビューの機会をいただき、ありがとうございます。先生は、今まで誰も挑戦したことがないことに挑戦をされています。インタビューの時間があっという間に過ぎてしまうほどの研究内容の面白さ、そのための地道な努力の積み重ね、常に学びを心掛ける、ということを学ばせていただきました。
学生、教員、社会人と関係なく、生きていく自分に投資をするために、自分が好きなことや疑問に思った事の解決を知識として蓄えることは重要なポイントになります。価値を高めること、何かを成しえるには、まずは自分に投資をし、学びを得ることが大切だと思いました。お忙しい中、貴重な機会をいただき誠にありがとうございました。