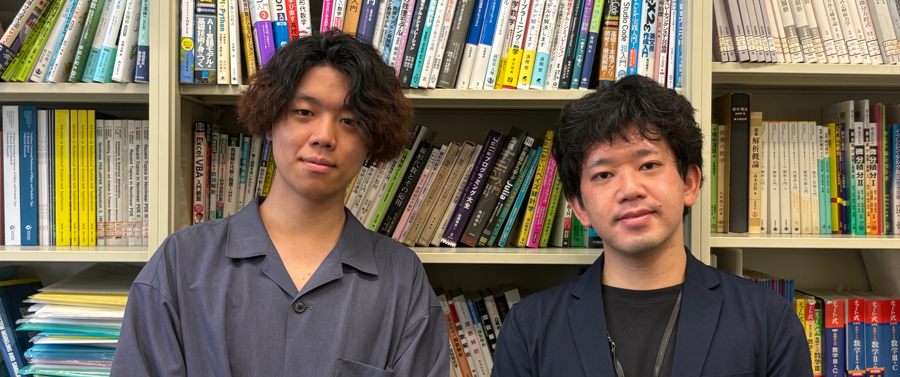知能情報学部 講師 奥村 真善美 × 知能情報学部 金地 康幸
現在の専門分野に興味を持たれたきっかけは何だったのでしょうか?

一番のきっかけは、これまでまったく別のものだと思っていた「数学」と「情報(プログラミング)」が、実は深くつながっていて融合できると知った時の面白さですね。
もともと私は高校の数学教員になりたくて教育大学へ進学しました。ただ、そこでは2つの教科の免許を取る必要がありまして、私は「数学」と「情報」を選びました。
それまで数学は数学、情報は情報と、完全に独立したものだと考えていたのですが、学んでいくうちにこの二つを組み合わせられることに気づきました。例えば、数式を立てて、それをプログラミングでシミュレーションして現実の現象を再現したり、あるいは純粋な数学の問題をプログラミングの力で解いたり。
数学という完結したと思っていた世界に、プログラミングという全く新しい視点や道具が入ってくる。この「融合できる面白さ」こそが、私が現在の専門分野に進むことを決めた、一番大きなきっかけです。
数学と情報の融合にご興味が深まる中で、学部卒業後さらに大学院へ進学しようと決められたのは、どのような経緯だったのですか?

一番大きな理由は、学部での4年間だけでは、この分野の研究のスタートラインに立てていないと感じたからです。
数学系の研究というのは、本格的に始めるまでに膨大な理論という”武器”を揃える必要があるのですが、正直なところ、学部時代はその武器を学ぶだけで手一杯になってしまうのです。まだ学問の本当の深みにも入れていないし、“武器”を応用して研究するところまでできないので、卒業が近づくにつれて、このまま終わってしまうのはあまりにも「もったいない」という気持ちが日に日に強くなっていきました。もちろん、高校の数学教員になる道もギリギリまで考えてはいたのですが、最終的にはもっと探求したいという気持ちが勝りましたね。
あとは、単純に所属していたゼミの活動がとても楽しかった、というのもあります。研究室の雰囲気がとても良くて、仲間と議論したり、時には一緒に遊んだりする時間も含めて、「この環境でもっと学び続けたい」と自然に思えたのも、大きな一因です。

大学院での「研究」と、学部での「勉強」は、具体的に何が違うのでしょうか?

一言で言うなら、「勉強」が受動的なのに対して、「研究」は自発的である、という点が最も大きな違いです。
学部での「勉強」というのは、先人たちが確立してくれた理論や知識を学ぶことです。そこには必ず「答え」が用意されていて、大変ではあっても、努力すればいつかその答えにたどり着けます。
一方で、大学院での「研究」は、その勉強で身につけた知識という“武器”を使って、全く新しいもの、まだ誰も知らない結果を生み出す活動へと変わります。ここでの決定的な違いは、そもそも答えがあるかどうかさえ分からない、ということです。
答えが見つかればラッキー、という世界で、未知の領域に自ら挑んでいく。誰かが用意したゴールを目指すのではなく、自分でゴールそのものを探しに行くのが研究だと言えますね。
大学院生の1日のスケジュールは、どのようなことが多いのでしょうか? 研究とプライベートの両立など、少しパーソナルな面もお聞かせいただけますか?

大学院生のスケジュールは、いくつかの固定された時間(授業やゼミ)と、多くの自由時間で構成されているのが特徴ですね。ただし、その自由な時間をどう使うかは本人次第、という自己管理が求められる生活です。
授業は学部時代よりずっと少なく、修士1年生のうちにだいたい終えます。活動の中心になるのは、週に1〜2回ある「ゼミ」で、ここで自分の研究の進捗を発表します。ですから、授業がない空き時間は、すべて次のゼミ発表のための準備期間になるわけです。ここで進捗を生み出しておかないと、後で大変なことになります(笑)。
プライベートとの両立ですが、時間は決して作れないわけではありません。特に私の分野のように、一度プログラムを実行すると計算に数時間かかる、といった「待ち時間」が発生する研究では、その時間を上手く使うことが鍵になります。計算が終わったらメールが届くように設定しておいて、その間にアルバイトをしたり、趣味に時間を使ったり。学内でTA(ティーチング・アシスタント)や食堂のアルバイトをすれば、移動時間も節約できて効率的でした。
ただ、少しパーソナルな面でお話しすると、社会人になった友人とのギャップは感じることがありましたね。彼らは働いていて社会人としての収入もありますし、多くの友人が土日が休日でしたが、大学院生の場合はそうもいかないので、会う時間がなかなか合わなかったり、食事に行った時にお金の使い方の違いを感じてしまったり…というのは、大学院生ならではの悩みかもしれません。
学部で卒業するのではなく、大学院に進学することの最大の魅力(メリット)は何でしょうか?

メリットは大きく2つあると考えています。1つは専門分野の「本当のスタートライン」に立てること。そしてもう1つが、社会で即戦力となる「実践的なスキル」が身につくことです。
前者については以前にもお話ししましたが、学部時代に揃えた知識という“武器”を使って、ようやく専門的で深い研究の世界に足を踏み入れることができるのが大学院です。
そして、もう1つの大きなメリットが、後者の「実践的なスキル」です。例えば、大学院では学会発表の機会が格段に増えます。専門外の人にも研究の価値を分かってもらえるよう、試行錯誤を繰り返す中で、物事を分かりやすく伝えるプレゼンテーション能力が徹底的に鍛えられます。これは、企業で企画を通す時など、どんな仕事にも役立つ力です。
また、論文には厳しい締め切りがあります。その中で成果を出す経験を通して、タスク管理能力やスケジュール管理能力が嫌でも身につきます。
専門知識だけでなく、こうしたポータブルなスキルを高いレベルで習得できること。それが大学院に進学する最大の魅力だと思います。もちろん、学会で色々な土地へ行って、美味しいものを食べられるというのも、嬉しいおまけですけどね(笑)。
スキルを身につけた大学院修了生の方々は、研究者という道以外に、企業などでどのように活躍されているのでしょうか?

研究者以外ですと、やはり「開発系」の職種で活躍する人が非常に多いですね。ソフトウェア会社などが代表的です。研究のプロセスとシステム開発のプロセスは親和性が高いので、大学院で培った能力を直接活かすことができます。その他、アプリケーションの「運用」といった専門的な業務を担うケースもあります。
そして、修士課程を修了してからの就職は、学部卒より専門分野における就職の選択肢が大幅に広がります。
なぜなら、企業は大学院修了生を「即戦力」として見ているからです。もちろん入社後の研修はありますが、企業としては、なるべく早くから第一線で活躍できる、深いスキルを持った人材を求めています。特に、事業の「よりコアな部分」を担うような業務には、大学院レベルの専門知識や研究経験が必須となることが多いのです。
ですので、大学院で研究に打ち込み、それに付随するスキルを身につけた人材は、企業にとって非常に魅力的ですね。
これから進路を考える高校生の視点から質問をお伺いします。「こんな発見が楽しい!」と感じる人は大学院での研究に向いている、というようなサインはありますか?

やはり先ほどお話しした「研究」と「勉強」の違いである、「受け身か、自発的か」という点が1つ大きいです。自発的に自分で調べて自分で行動する、といった人が研究に向いていると思います。自分の興味に純粋に向き合い、自分で行動できることが特に向いています。新しいものを突き詰めるには、自分で行動に移さないと何も得られませんし、受け身のままでは何も生まれないからです。
ただ、最初は受け身でもいいのかもしれません。途中から何か興味を持つものが急に生まれて、そこから自発的にシフトしていくことも、十分にあり得ることです。
ですから、頭のどこかで「受け身だけではなく、自発的になることが大事だ」と意識しておくのがよいかと思います。また、あえて「自発的にならざるを得ない環境」、例えば「誰も支えてくれない」ような状況に身を置けば、自然と自発性は身につきます。そういう場に勇気を出して踏み込んでみるのも一つの方法です。
私自身も、元々は受け身の性格だったと思いますが、ゼミなどの活動を通じてだんだんと自発的な性格にシフトしていきました。ですから、最初から自発的である必要はありません。徐々に変わっていけばよいのです。もちろん、最初から自分で動ける人は、そのまま頑張ればよいと思います。
この研究室で大学院生たちと一緒に挑戦していきたい目標や夢があれば、教えてください。

難しい質問ですね。こちらの大学に着任してまだ3年目で、研究室が立ち上がって間もないものですから、これまでは目の前のことを対応していくことに必死な状況でした。ようやく、少し先の夢を考えられるようになってきたところです。
目標の一つは、数式とそれを用いたシミュレーションによって、現実世界の現象を予測したり分析したりすることです。例えばコロナ禍で、感染者数の拡大予測がニュースになっていましたが、あのような形で、現実の事象を研究対象にしたいと考えています。コンピューター(バーチャル)の世界では、現実ではできないような実験も自由に行えるのが大きな魅力です。
一般的に、数学の研究は「地味」だと思われる人もいらっしゃると思います。ですから、シミュレーションという分かりやすい形で、一般の方々にも「これはすごい、面白い」と感じてもらえるような、「キャッチーな研究」に挑戦したいのです。
そして、その挑戦はぜひ、学生たちと一緒に、むしろ学生に主役を担ってもらい、私はそれを後ろから支えながら進めたい、というのが私の夢です。例えば、学生が主体となって企業と連携し、私たちのシミュレーション結果を実際の製品開発につなげていく、というようなことができればと思います。
学生や企業の方々、そして一般の方々まで、誰が見ても「面白い!」「こんなところに数学が使われているんだ!」と感動してくれるような研究を、学生と一緒に実現できたら最高ですね。
最後に、大学進学やその先のキャリアについて考える高校生たちに向けて、メッセージをお願いいたします。

みなさんにまずお伝えしたいのは、ご自身の「純粋な興味」にまっすぐ向き合い、それを道しるべに進路を選んでほしいということです。
私自身、最初は教員を目指していましたが、大学での出会いをきっかけに、より情熱を注げる研究の道に進みました。このように、大学で興味が変わってもまったく問題ありません。みなさんにも、そういう素晴らしい出会いがきっとあるはずです。
そして大学に入学したら、卒業するまでに「これだけは誰にも負けない」と胸を張って言えるものを、最低一つ身につけることを目標にしてください。学問でもサークル活動でも趣味でも、何でも構いません。その揺るぎない「一つ」が、これからの人生を支える大きな自信となります。
その過程で大切にしてほしい心構えが二つあります。一つは「イプシロンずつ進め」という言葉です。これは私の指導教員からの言葉でもあるのですが、「イプシロン」とは解析学という数学の分野では微小な正の数を指すことが多く、「たとえ後退しても、少しずつ着実に努力を続ければ道は開ける」という教えです。みなさんが日々積み重ねる努力は決して無駄になりません。
もう一つは、常に「なぜこうなるのか?」と問い続ける探求心です。
高校の教科書では、「答え」にたどり着くまでの過程が省略されていることが多いので、その部分にも疑問を持ち、自問自答を重ね、ご自身が納得できる「なぜこうなるのか」に対する答えを探してください。最終的にそれを「自分の言葉でうまく説明できる」ようになれば、その力は大学での学問やその先の人生において、みなさんを助ける最も強い武器になるはずです。
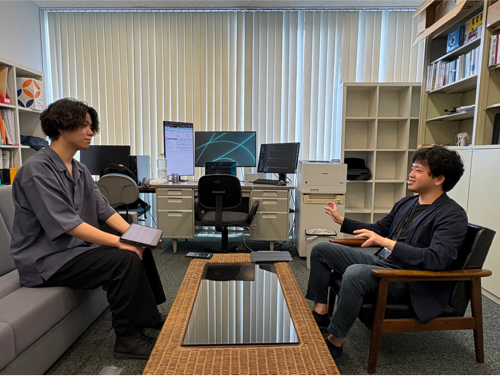
インタビューの感想
一連のインタビューから、先生の誠実な人柄と、学生の成長を願う一貫した教育哲学が浮かび上がりました。ご自身の経験を元に「興味は変わってもいい」と語る現実的な視点と、学生の可能性を信じる温かさが印象的です。
大学院での学びを「プレゼン能力」など社会で役立つ実践的スキルにつなげ、研究における目標や夢については「学生が主役」と語られ、常に学生の自立を促す姿がありました。
特に「誰にも負けないものを一つ見つけなさい」という言葉や、「イプシロンずつ進め」「『なぜ』と向き合え」といった師から受け継いだ哲学は、学生が未来を切り拓くための具体的な指針となっています。
授業での専門知識の伝達に留まらず、学生一人ひとりが自信を持って歩むための心構えと武器を与える、懐の深い教育者としての姿に感銘を受けました。
そして、研究に対する姿勢や学生に対する思いから、先生の素敵なお人柄を感じました。今回はこのような貴重な機会を設けていただきありがとうございました。