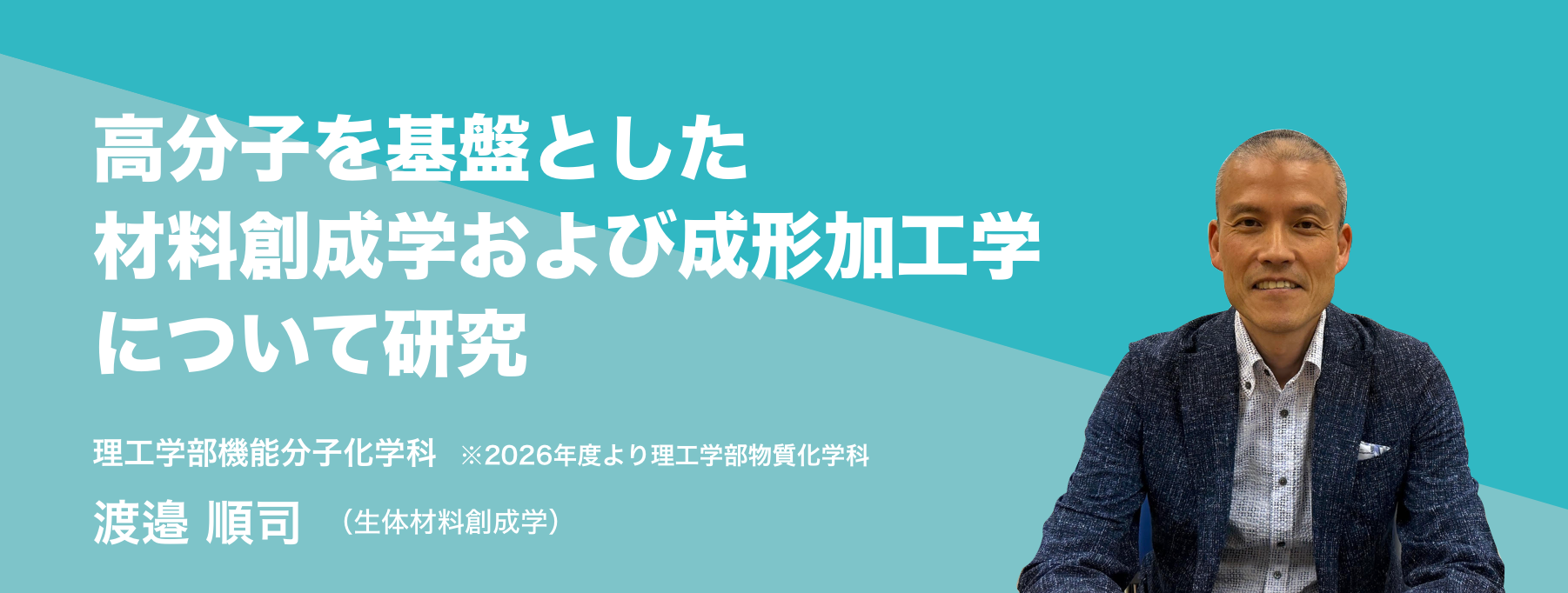材料化学の専門家で、高分子材料について研究している渡邉順司教授にお話を伺いました。
About Me ( WATANABE Junji )
学部四年生の時に配属された研究室では、先輩と過ごす毎日が楽しく、そのまま大学院修士課程に進学しました。修了後は民間企業で実用化を見据えた研究開発職に就きたいと考えていました。ところが、入社式の日に受け取った辞令は工場の染工課、わずか二週間の研修を経て、工場のオペレータとして綿製品の漂白作業を担当する交代勤務の日々が始まりました。研究開発職への異動を人事部に交渉しましたが受け入れてもらえず、退社して大学院博士後期課程に入学する道を選びました。
学位取得後は大学教員として教育・研究に従事する道を選びました。大学の研究室には毎年多くの卒研生と大学院生が入ってきます。学生さんが研究テーマを進めるにあたり、研究の基礎的な科学の部分と応用的な工学の部分をバランス良く習得できるよう工夫しています。私自身ができる研究には限りがありますが、研究能力を身に付けた人材を輩出できれば、将来にわたってより多くの研究が進展して暮らしが充実します。一人でも多くの学生に研究開発の心得を教授したいと思っており、大学教員はとても魅力的な職業です。
Research
Fundamental Strategy for Materials Design
私たちの身近にある材料のうち、高分子材料に焦点を当てて研究しています。成形加工性に優れ、軽量である高分子材料は、金属やセラミックスの代替材料としても有望であり、あらゆる場所で使われています。一方で、マイクロプラスチック問題がクローズアップしており、環境負荷の低減に向けた使用量の削減を含め、適切なリサイクルと廃棄プロセスをさらに整えていく必要があります。
研究室で取り組むテーマの設定において、次の項目を組み込むことを重視しています。
・汎用性の高分子材料を基盤とすること
・合成や化学修飾はシンプルであること
・従来の課題を解決する機能をもつこと
・科学から工学までカバーしていること
・試薬およびルートの安全性が高いこと
また、個々の学生が取り組むテーマの方向性は異なるものとし、研究室内で他の学生のテーマに自然に触れることで習得できる知識を広げることができるようにしています。
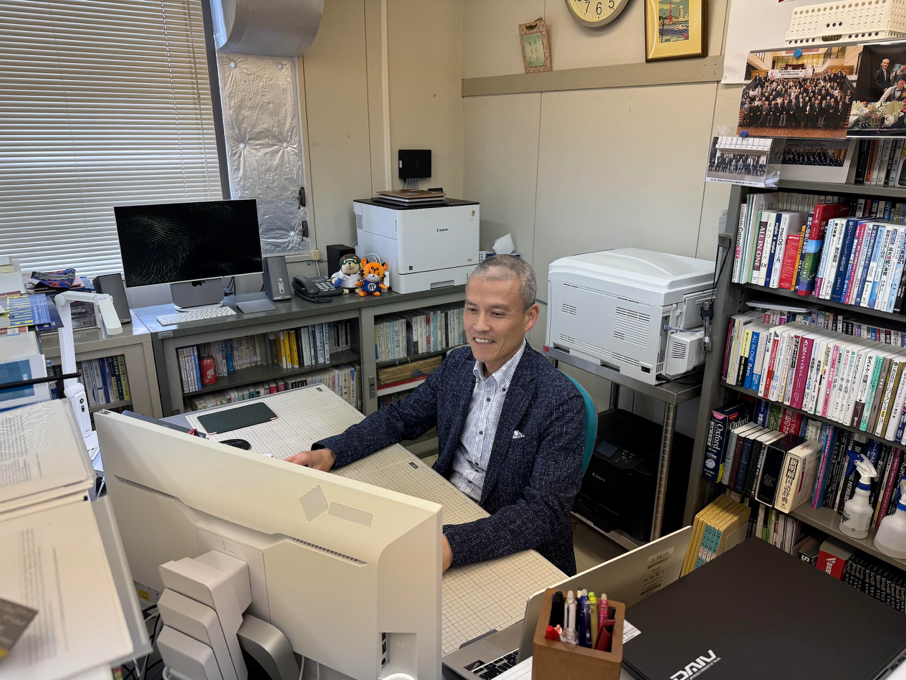
Representative Research Theme
高分子をシート状に成形加工する際、可塑剤とよばれる化合物を添加すると軟質性を付与することができ、逆にフィラーとよばれる充塡剤を添加すると強度を高めることができます。同じ高分子を用いているにもかかわらず、用途に合わせた力学強度を持たせることができます。研究室では、添加する可塑剤や充塡剤の安全性がより高いものを開発し、シート中にうまく分散させる技術の開発を進めています。
性質の異なる高分子をブレンドして得られる材料をポリマーアロイ(高分子合金)とよび、金属から作られる合金の概念に似ています。個々の高分子の優れた性質を兼ね備えることができるようになりますが、高分子は分子量が大きいためブレンドすることがとても難しい問題があります。研究室では、うまく混ぜ合わせるための新たなアプローチについて検討しています。
高分子を溶剤に溶かすとあらゆる表面にコーティングして薄膜を形成させることができます。撥水性を高めることや潤滑性をもたせるなど、用途に応じた特性を表面に付与することが可能となります。相反する性質の高分子を同時に薄膜内に組み込むことができれば、使用環境によっていずれかの高分子に基づく表面特性が得られるようになり、例えば乾燥時は撥水性を示し、湿潤時に親水性を示すような表面が得られます。研究室では、撥水性と親水性の変化の幅をより広げるための設計について検討しています。
材料全体を高分子で作るのが基本ですが、軽量化や新たな機能を付与する目的で内部に無数の空孔を備えた多孔質構造を形成させる加工法があります。代表例としてウレタンフォームが知られており、ウレタン合成時に二酸化炭素ガス(気体)で発泡させています。他にも相分離した液体や固体粒子をテンプレートにして多孔質化する手法が知られています。研究室では、ハイドロゲルとよばれるゼリー状の粒子を分散させて多孔質化する新たな方法を提案しています。
KONAN’s Value
誠実な人材を育成して世の中に輩出することが本学の教育であり、本学の複合施設であるiCommonsにも「正志く 強く 朗らかに(正しく 強く 朗らかに)」というフレーズが掲げられ、教職員の想いがその言葉に凝縮されています。教職員は多様な教育コンテンツやクラブ・サークル活動を通して成長していく学生を近い距離から見守っています。
Private
一人で静かに過ごすのが好きですね。最近はスピーチや寄稿文の依頼を受けることが増え、思考のアウトプットが多くなってきました。そのため、ジャンルを問わず読書量を増やし、インプットを増やすように心がけています。何かスポーツをやっているように見られることが多いですが、初心者レベルのスキーしかできません。最近は健康維持のために、場所と距離、日程を自由にアレンジできる低山ハイキングに一人で出かけています。

Profile

理工学部機能分子化学科 教授
※2026年度より理工学部物質化学科
渡邉 順司
WATANABE Junji
専門領域
生体材料創成学
キャリア
学士(工学)[大阪府立大学]
修士(工学)[大阪府立大学]
博士(材料科学)[北陸先端科学技術大学院大学]
グンゼ株式会社
東京大学大学院工学系研究科助手
大阪大学大学院工学研究科特任准教授
所属学協会
日本ゴム協会
日本MRS
他
受賞歴
日本ゴム協会科学技術奨励賞(2020)
他