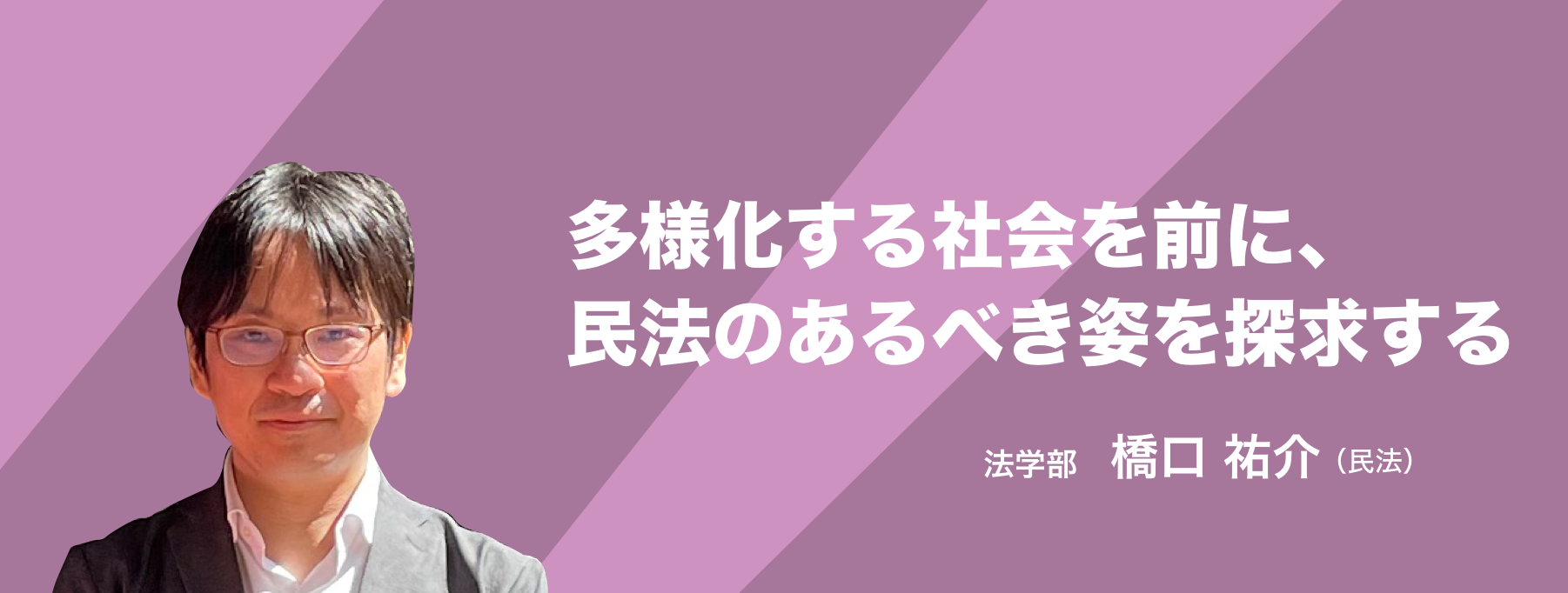民法の専門家で、賃貸借を中心に民法の現代化をめぐる諸問題を研究されている橋口祐介教授にお話を伺いました。
About Me ( HASHIGUCHI Yusuke )
皆さん、こんにちは・こんばんは・おはようございます - そして、はじめまして。法学部で民法を研究している橋口祐介と申します。
大学では、民法の研究者として契約や不法行為について講義を行っていますが、講義を受講してくれる学生の皆さんからは、その量の多さに驚かれることがよくあります。契約や不法行為は社会の基礎を構成する重要な制度ですが、それだけに、社会の多様性を反映して、法的ルールや裁判例が山のように存在しているからです。もっとも、そうした契約・不法行為ですら民法の数ある制度の1つに過ぎず、民法にはその他にも、時効・土地・金融取引から結婚・親子・相続に至るまで、驚くほど多くの法分野が存在しています。この法学の中でも1・2を争う裾野の広さが、移り気な私にはとても魅了的に感じられ、「民法を本格的に研究してみたい…!」と考えた私は、京都大学の大学院に進学し、2010年から新潟大学で研究者生活をスタートさせました。
新潟での研究活動は、私の研究イメージを大きく変えるものでした。それまでの私にとって、民法の研究とは、議会資料や分厚い専門書を読み込み、専門的な研究会に参加して論文を書くといったものでしたが、それらに加えて新潟では、実務家の先生方と共同して「事実は小説より奇なり」を地で行く問題の解決にあたったり、遠くドイツで最新の立法動向を調査してみたり、あるいは自動運転など先端技術に関わるELSIに取り組む研究チームに参加するなど、その活動の多彩さに驚かされるばかりでした。
こうした新潟での研究はとても充実したものでしたが、移り気な私は、生まれ育った関西の地でさらに研究を深化・発展させてみたいと考えるようになり、2018年からは、この甲南大学で第2の研究者生活をスタートさせていただくことになりました。
Research
How to do things legally with words in modern society?
多彩な制度を有する民法について、様々な研究アプローチを採ってきた - と言えるとカッコ良いのですが、移り気な私ですので、実際には右往左往してきたと表現するのが適切かもしれません。
問いに対する答えが研究であるとすれば、私にとって初めての問いは、「チャーシュー抜きのチャーシュー麺はチャーシュー麵と言えるか」でした。このようにお伝えすると、冗談を言うなとお叱りを受けるかもしれませんが、事の本質はそれほど誤ってはいません:法的ルールは言葉で表現するために、法的ルールをより良く理解するためには、言葉それ自体について深堀りする必要がある。たとえば、「売買」という言葉を選んだとき、その言葉で指示される契約に代金支払が含まれないことはありえないが、その支払期日は必ずしも予定されることがない。「売買」という言葉との関係で、この両者はどのように区分されているのか、というわけです。
この問いにチャレンジする中で、私はたくさんの新たな問いと出会うことになりました。またそれ以外にも、ドイツでの在外研究やいくつもの共同研究を経て、異なる文脈に位置づけられる問いにも取り組むようになりました。その結果として、現段階では大きく次の2つの問いに挑んでいます。その1つは、物などを「貸す」とはどういうことか、という問いです。民法学では、古く明治の時代から「貸す」といえば不動産を想定し、その言葉の意味を探求してきましたが、今日ではレンタカーなど物品を貸す取引も重要であり、令和に入ってはサイバー空間を貸すことすら頻繁に行われています。このような取引の広がりを踏まえると、「貸す」の意味はアップデートされるべきではないか、というわけです。
もっとも、リニューアルが求められているのは「貸す」取引に限られません。民法の成立した明治の時代から令和の今日に至るまで、私たちの社会は様々な形で複雑化し、多様化してきました。このような時代の変遷を踏まえると、民法の多くの制度で、いや、もしかすると民法それ自体の現代化が必要とされているのかもしれません。実際、ヨーロッパでは2000年以降、「現代化」を旗印に各国で民法の抜本的な改正が実現されていますし、日本でも2010年以降、民法のアップデートが段階的に推し進められています。ただし、民法は社会の基本ルールを定めるものですから、その抜本的な改正は私たちの生活に大きな影響をもたらします。ゲームで大きくルールが変更されると、たとえその変更が良いものであったとしても、プレーヤーには基本戦略を練り直す必要が出てくるのと同じことです。そうすると、時代に合った民法を継続的に創造していくためには、現代化をどのような方法で実現するのが適切であるのかについても同時に検討する必要がありそうです - これが、私がいま取り組んでいるもう1つの問いになります。


KONAN’s Value
私が甲南大学にもっとも価値を感じるのは、その「近さ」です。
ミディアムサイズの大学として、私たち教員と学生との距離は極めて近く、自分の学生時代と比較して、質問や相談が頻繁に行われていることが印象的です。受講生の率直な質問にはハッとさせられるものが多く、その疑問から私自身が気付きを得た経験も少なくありません。また専門を異にする先生方と気軽に意見交換できる近さは、研究の進展にとってはもちろんのこと、講義にとっても価値あるものだと感じています。日頃から研究や講義について話し合えているからこそ、講義中に憲法や刑法など他の法分野の話題を安心して展開することができ、法のイメージを立体的に伝える大きな手助けとなっています。
加えて、神戸・大阪に短時間で移動できる立地の良さも、学外とのつながりとの観点からは見逃すことができないでしょう。各地で開催される講演や模擬講義のご依頼をいただいた場合、どうしても学内予定との調整が必要となりますが、移動時間の短さから、柔軟な対応を採ることができています。この柔軟さから、家族法の現代化と強いつながりを持つ社会活動にも取り組むことが可能となり、研究の広がりを実感しています。教員のみならず、学生にとっても、距離的な近さから講義と課外活動との両立がスムーズに図れているようで、インカレや地域活動に積極的な学生が多いように感じます。また学内には「Café Porte」や「Language LOFT」など英会話を気軽に楽しむ空間が用意され、留学を後押しするプログラムも数多く展開されていることから、海外への心理的な距離が近づけられている印象があります。実際、私のゼミに在籍する学生が留学しており、その充実した経験を楽しそうに語る姿は、学生時代に留学することのなかった私から見て、とても心強く感じられます。
Private
家族のほか、ドイツと赤ワインをこよなく愛しています。
ドイツでのはじめての在外研究があまりに充実していたためか、滞在先のミュンスターという都市を「第2の故郷」といってはばからず、12月になると各地で開催されるクリスマス・マーケットに足しげく通います。2020年のコロナ騒動以降、ドイツに行けない日々が続いていますが、いつか現地のクリスマス・マーケットに行ける日を夢見ています。
また家族の影響で数年前から赤ワインを好んで飲むようになり、長期休みにはワイナリーまで足を運ぶまでになりました。ドイツといえば、日本ではビールの印象が強いのですが、当のドイツ人からはむしろワインの方が美味しいとの話をよく聞きます。次回ドイツに行く機会があれば、ぜひ赤ワインを楽しみたいですね。

Profile

法学部 教授
橋口 祐介
HASHIGUCHI Yusuke
専門領域
民法
キャリア
京都大学大学院法学研究科・博士後期課程・単位取得退学
新潟大学 法学部/法科大学院 講師
所属学会
日本私法学会