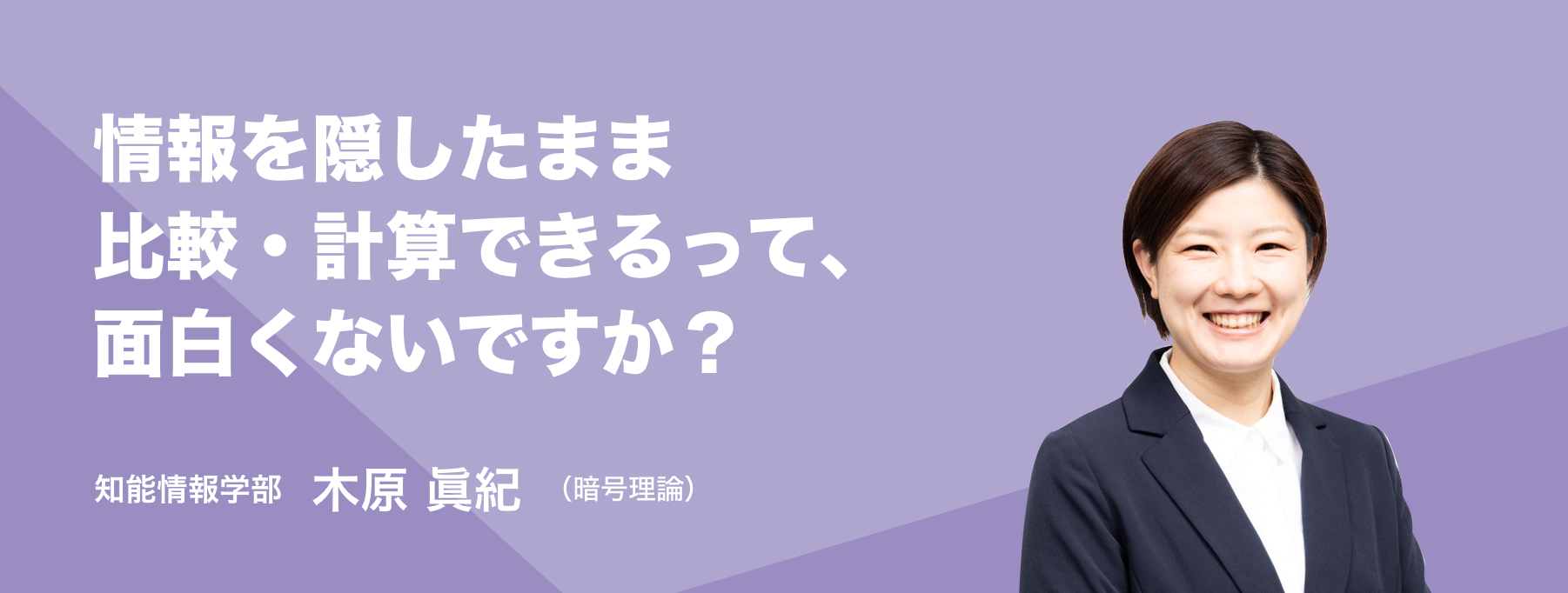暗号理論の専門家で、秘密計算とその応用に関する研究をしている木原眞紀講師にお話を伺いました。
About Me ( KIHARA Maki )
千葉県で生まれ育ち、これまでの人生の大半を千葉県で過ごしてきました。
2024年度より知能情報学部の教員として着任し、人生で初めて千葉県以外の土地での生活を始めましたが、関西での生活はこれまで慣れ親しんできた関東とは多くの点で異なり、着任から1年以上が経過した現在も、日々新たな発見や戸惑いを感じながら生活しています。
さて、私の専門領域は情報セキュリティの中でも、「暗号理論」と呼ばれる数学的側面の強い分野です。この分野では、情報理論・符号理論・計算複雑性理論・数論・代数幾何・離散数学など、さまざまな数学的な理論が密接に関係します。その中でも、修士課程在籍中に興味をもった「秘密計算」とその応用に関する研究を、現在も継続して行っています。
Research
秘密計算は、「大切な情報」を他者に見せることなく処理を行うという、情報の取り扱いに関する本質的な課題を扱う分野です。この分野は次のようなある研究者による次のような問題提起から始まります。
二人の大富豪AliceとBobはどちらが裕福なのか知りたい。しかし、お互いの財産に関する情報は不用意に知りたくない。このような会話をするにはどうしたらよいだろうか?―A. C. Yao, “Protocols for secure computations,” SFCS 1982, pp. 160-164 (訳は引用者による).
このような処理を実現するためには、単なる暗号化技術にとどまらず、数論・代数学・計算理論など多様な数学的手法を駆使して安全性を定式化し、それを具体的なプロトコルとして構築する必要があります。そのため、理論と応用の間を往復するような設計思考が求められ、そこにこの研究の難しさと面白さがあると感じています。
これまでには、「2つの情報を秘匿したまま比較できる」という暗号的性質に関する理論的研究を行い、それを応用して高速かつ安全な認証アルゴリズムの構築や実装にも取り組んできました。暗号理論自体は数学的側面の強い分野であるため、紙とペンを使った理論的検討が多くなりますが、プログラミングや実装作業も非常に重要な要素です。実際に私の研究でも、理論的成果を踏まえてそれを応用・実装へとつなげる試みに取り組んできました。
たとえば、秘密計算を応用した認証システムの実装として、ICOCAや学生証などのNFC型ICカードを用いた方式や、指紋情報を利用した方式を開発してきました。これらは軽量な暗号技術に基づいており、Raspberry Piなどの小型コンピュータ上での組み込み実装も行っています。また、認証結果の出力のためにLEDやモーターを使った電子工作に取り組んだこともあり、中でも指紋認証システムの実装では、中学生以来の「はんだ付け」にも久しぶりに挑戦しました。回路設計やはんだ付けはあまり得意ではないので、「今後はあまりやりたくないな」と思ってしまいましたが(笑)。
こうした実装や応用の背景には、実は高校で学ぶような基本的な数学の知識が活きていることも多く、理論と現実をつなぐ橋としての数学の重要性を日々実感しています。暗号理論は、高校数学で扱う「整数の性質」「対数」「確率」などの概念と密接に関係しており、現在広く使われている暗号技術にも、たとえば合同算術のような基礎的な数学が応用されています。「数学って何の役に立つの?」と尋ねられることもありますが、暗号理論の研究では、高校生がまさに今勉強している数学の知識がそのまま基盤となっており、数学が“実際に役に立つ”ことを実感しやすいという点も、この分野の大きな魅力の一つです。
KONAN’s Value
甲南大学の大きな特長は、学生と教員、教員同士といった人と人との距離の近さにあると感じています。知能情報学部においては、「徹底したインタラクティブ教育」というキーワードのもと、少人数ゼミによる学びの土台づくりから、学生どうしでチームを組んでプロジェクトに取り組む授業など、段階的かつ実践的なカリキュラムが構成されています。いずれの授業においても、学生が教員に気軽に質問や相談ができる雰囲気があり、学びに対する積極性を自然と育める環境が整っていると感じます。
また、教員同士の専門分野を越えた連携も活発で、たとえばデジタルツイン研究所の活動では、本学の創設者・平生釟三郎先生を生成AIによって再現するという、「なになに? 面白そう!」と思わず引き込まれるような未来創造型研究も行われています。
さらに、「プレミアプロジェクト」では、学生が自らの意欲に応じてプログラミングスキルの向上に挑戦したり、研究室配属前から研究活動に触れたりする機会が提供されている点も、大きな魅力のひとつです。
Private
美味しいものを食べることが好きで、美味しい料理を楽しめる旅行が趣味のひとつです。
研究職という立場柄、学会発表などで国内外を問わずさまざまな土地を訪れる機会があり、各地の料理を味わえることをとても幸せに感じています。
写真は、2024年12月に学会発表のために訪れた福井でいただいた蒸したてのせいこ蟹で、非常に美味しかった一品です。
そのほか、きれいな海や自然も大好きで、長期休暇には沖縄を訪れ、シュノーケリングやトレッキングを楽しむこともあります。
普段の休日には、「年間100本映画チャレンジ」(現在3年目)に取り組んだり、推し活として好きなアーティストのライブに足を運んだりすることも多いです。
最近では、関西での生活を始めたことをきっかけに、本場のお笑いライブにもぜひ足を運んでみたいと考えています。

Profile

知能情報学部 講師
木原 眞紀
KIHARA Maki
専門領域
暗号理論
キャリア
東京理科大学理工学部情報科学科(学士)
東京理科大学大学院理工学研究科情報科学専攻(修士・博士)
東京理科大学創域理工学部情報計算科学科(旧・理工学部情報科学科)助教
所属学会
IACR,電子情報通信学会