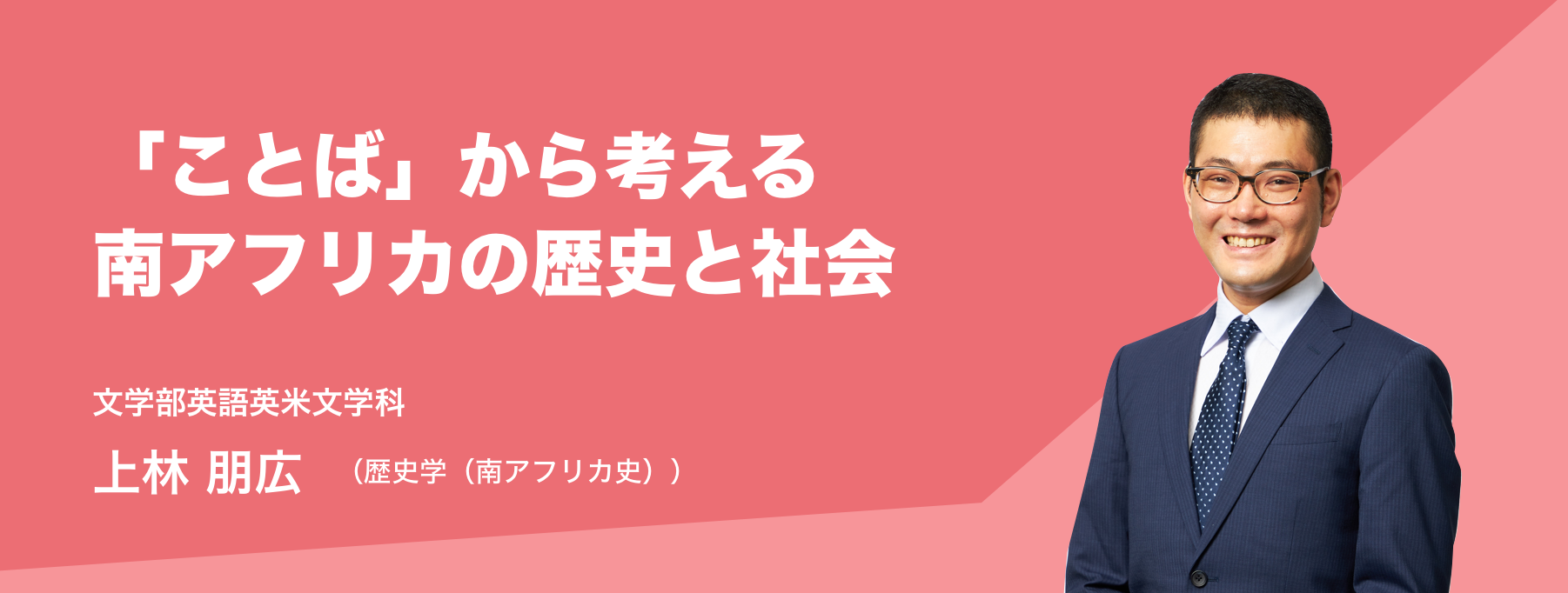南アフリカ史の専門家である上林朋広講師にお話を伺いました。
About Me ( KANBAYASHI Tomohiro )
南アフリカの歴史を研究しています。英語に加え、ズールー語というアフリカ諸言語の一つで書かれた歴史的な史料を分析して、人種隔離・アパルトヘイトという過酷な時代を人々がいかに経験してきたのかを理解し、書いていきたいと思っています。
Research
南アフリカの歴史を研究してきました。
いままでの主な研究成果は以下の2冊です。
『ズールー語が開く世界 : 南アフリカのことばと社会』(風響社、2022年)
http://www.fukyo.co.jp/book/b614847.html
この本は、ズールー語という南アフリカのことばを学んだ私の体験記です。ズールー語とは聞きなれない言葉かもしれません。しかし、(手話を含め)12言語も公用語のある(!)南アフリカでもっとも母語話者の多いことばで、普段は別々の言語を話しているアフリカ系の人々の共通語にもなっています。いかにことばを学んできたのかについて書くことは苦労自慢のような気もして恥ずかしくもありますが、この本ではいつも書いている学術的な論文では取り上げることはできないけれど、多くの人に伝えたいと感じている事柄を描いてみました。クリック音という舌打ちのような音を含むことばを聞いた時の新鮮な驚きや、日本人である著者がズールー語を話すことで引き起こされた現地での様々なエピソード、そして困難な状況下でズールー語の作品を残した作家たちが母語で書くことに込めた思いなど、小さな本ではありますが、いろいろと詰め込んでみました。
『南アフリカの人種隔離政策と歴史の再構築 : 創られた伝統、利用される過去』(明石書店、2025年)
https://www.akashi.co.jp/book/b660373.html
1990年代まで、南アフリカは悪名高い国でした。アパルトヘイトと呼ばれる過酷な人種差別政策を実施していたからです。本書は、なぜこの体制が20世紀末に至るまで維持されたのかを、政治や社会運動だけでなく、博物館や学校教育など日常的な事例に焦点を当てて考察しました。南アフリカに住む人々がいかに人種差別を経験し、抵抗したのか、本書の記述を通して考えてもらえればと思っています。
最近は、南アフリカの文学者・政治活動家の作品の日本語翻訳について調べています。それらの作品の出版経緯を調べることで、南アフリカと日本のつながりの歴史が分かってきました。先駆的な研究はあるものの、日本以外ではあまり知られていないアパルトヘイト体制の廃止に尽力してきた日本の市民運動の歴史を英語で発表していくこと。これが、現在の目標です。写真は、南アフリカで詩人・翻訳者のSandile Ngidiさんにインタビューしたときのもの。

KONAN’s Value
甲南大学に限った話ではないですが、4年間という限られた時間で、自分のやりたいことを見つけ、使えるものは何でも使って学んでいってもらえればと思っています。甲南の先生方は、学ぼうとしている学生への支援を惜しまない人が多いな、と2023年に着任してから実感しています。
Private
あまり趣味と言えるものがないのですが、最近は写真や絵画を研究対象として取り上げようとしていることもあって美術館にいくことが多いです。少し落ち着いたら、神戸ゆかりの作家の作品(具体美術協会や芦屋カメラクラブなど、解説書で読んだ神戸関係の団体も多くて楽しみです)を見学に、美術館を訪問してみようと思っています。美術館に加えて、元町映画館など映画館も充実しており、2023年に引っ越してきてから、神戸いい街だなと実感しております。
締め切りのある仕事に追われて、なかなか映画や小説など落ち着いて楽しむことができないのが目下の悩みです(息抜きと称して楽しんではいますが)。
研究と密接に関連しているので、あまりプラベートとは言えませんが、もっとズールー語を含めて言語を勉強する時間を捻出できないかなと思っています。写真は、左が私、右がズールー語の先生ムバリさんです。

Profile

文学部英語英米文学科 講師
上林 朋広
KANBAYASHI Tomohiro
専門領域
歴史学(南アフリカ史)
所属学会
アフリカ学会
歴史科学協議会
西洋史学会
Japan Society for Afrasia Studies