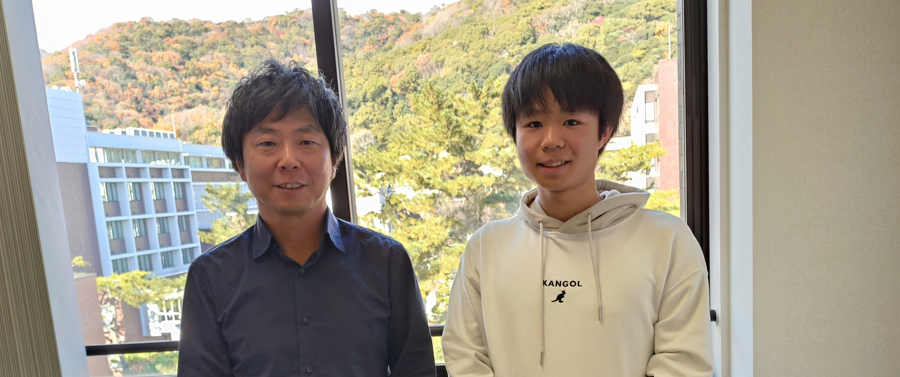文学部 教授 阿部 真大 × 経済学部 岡村 俊佑
まず先生が行っている研究について教えてください。

私は社会学を研究しています。その中でも主に労働社会学を中心に取り組んでおり、家族社会学、地域社会学、文化社会学も研究しています。
なぜその研究を行おうと考えられたのでしょうか?

最初に労働社会学に関する論文を書いたのが大学院生の頃でした。私が卒業する頃は就職氷河期で、大学を卒業しても正社員になるのが割と大変だったんです。正社員にならずに、違った働き方をするっていう同世代が多かったように感じます。好きなことを仕事にするとすごくいいよ、という話がある一方で、実は超ブラックな会社で低賃金で働かされているっていう、その両方を見て、自分の中でモヤモヤするところがあって、「働く」ということについて研究をしよう思ったのがきっかけです。のちに僕が書いた論文から派生して「やりがい搾取」という言葉が生まれました。
そんな背景があったでのすね。僕も「やりがい搾取」という言葉をよく耳にします!では研究を行う中での楽しさや苦労などはありますか?

基本、楽しいですよ。あまり苦労は感じません。でも自分が分かるだけじゃダメで、人に理解してもらわないといけない。いかに分かりやすく伝えるかという「発信」の部分は、いつも苦労してます。
「発信」は私も苦手としているところです。では現在の教授というご職業は気に入られてますか?

もちろん気に入っています。僕は、研究者としては少しイレギュラーなキャリアなんです。大学に就職する前に何冊か本を出してデビューして、同時に非常勤をいくつか掛け持ちしていて、メディアとかで発言してました。それはそれで楽しいんですが、就職しないと経済的に安定しないので、研究が続けられません。教授はそれを仕事にして、お給料がもらえるのでほんとに今の仕事には感謝してます。私は甲南大学でしか教授をしたことがないので他大学のことは分からないですけど、いい大学だなと思いますよ。甲南大学には感謝しています。
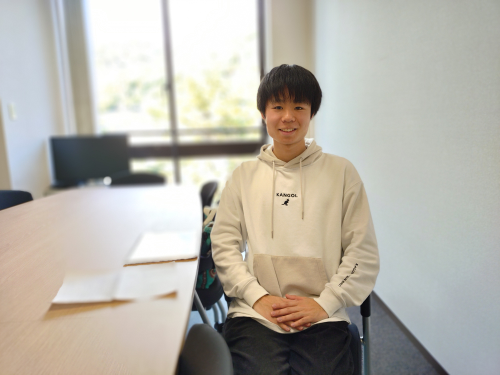
教員側から見ても甲南大学はいい大学なのですね!現在大学教員という立場で学生を指導されていますが、どのような学生を育てたいとお考えですか。

そうですね。まず、研究者をメインで育てているわけではないので、あくまで学部を卒業して社会人になる学生に関して言うと、私としては、色々な人と出会って、いろんな経験をして、豊かな世界観を持てる学生を育てたいと思っています。地域連携センターで所長もしていますが、どんなプロジェクトであっても、極論、学生が誰か面白い人に出会えればいいと思っています。様々な人に会うことによって、それだけで若い人はもう様々な刺激を受けることが出来ますよね。私の役割は、学生に色々な世界を見せたり、色々な人に出会ってもらう場を提供することで、最終的に世の中を多面的に理解できる学生を育てることだと思っています。
私自身やはり大人の方と話すと学ぶことが多いと感じます。人それぞれ考え方があるので多くの人と関わりを持つことが大切だと改めて感じました。甲南大学で研究するになってあたって、この大学だから良かったことはなんでしょうか?

先ほども述べたように、甲南大学でしか研究をしたことが無いので他大学については分からないですが、この大学は研究しやすいと思います。フロントの方もすごくサポーティブに色々とお話聞いていただけるし、何かこれをしたいと伝えるとこうした方がいいとか、こういう形で執行してくださいみたいな感じで助言してくださるので、本当に助かる。研究するにしても教育するにしても、サポート体制がしっかりしているので、すごくありがたいなと感じています。私自身、小中学校は国立、高校は県立、大学は国立でずっと公立だったので、甲南大学はトイレも綺麗だし、研究室も綺麗だし、就職してから驚きました。駅近であるのと「神戸」という場所もまた魅力的に感じます。
この環境が当たり前と感じていたのですがそうではないのですね。今まで様々な研究をされてきたと思うのですが、今後の目標がございましたらお願いします。

そうですね。1990年代以降、日本も色々と変化し、仕事の世界では「やりがい搾取」という新しい問題が起こってきました。その問題を提起して、次の世代の研究者がその枠組みを批判的に検証し、引き継いでくれている点で、僕の使命は終わったとも言えます。研究と言うのは、世代から世代へと繋いでいくことが何より大切だからです。しかし、僕自身の研究者人生はまだ残っていますので、今行っているプロジェクトを進めていきたいと考えています。実は来年、ある著名な人類学者の翻訳書を出そうとしています。国内の研究は国内の研究で大事ですが、学問はグローバルなものです。ここのところ、海外の研究の紹介を怠っていたので、当分、翻訳の仕事が続くかなと思っています。
ありがとうございます!最後に先生のことをお調べしていく中で、2016年に日本テレビの「世界一受けたい授業」という番組に「新・家庭内問題」というテーマで出演されていたのを拝見したのですが、そこでそのような内容をお話になったのかお伺いしたいです。

私は家族社会学も研究しています。労働と家族の問題は離れているように感じられますが、ワーク・ライフ・バランスという言葉があるように、実はすごく関係しているんです。家族社会学の方でも少し論文を書いており、そのため依頼がきたという感じです。テーマとしては家族の問題だったので家庭内問題として、教育虐待の問題と、孫疲れについて語りました。しかし、やはりテレビという媒体は、キーワードで話さないといけないので、伝えられることは本当に少なく、表面的な話に留まってしまう。これをきっかけにこの問題を知ってもらい、いろんな情報に繋がって、この問題の裏にある社会背景について考えてもらいたいという思いで出演していました。
インタビューをした感想
阿部先生と直接お会いするのは今回のインタビューが初めてでしたが、先生が話しやすい環境を作って頂けたおかげで緊張もとれ、あっという間に時間が過ぎていました。先生からのお話にもありました通り、甲南大学は学生目線で見ても支援が手厚く素敵な大学だと思います。先生の言葉の中で「様々な人と関わりをもって欲しい」という言葉が私の中ですごく腑に落ち、研究や学生に対して熱い思いをお持ちになっている事を知りました。残りの大学生活や社会人になっても様々なコミュニティーを築いていこうと思います。今回は貴重なお時間をいただきありがとうございました。