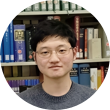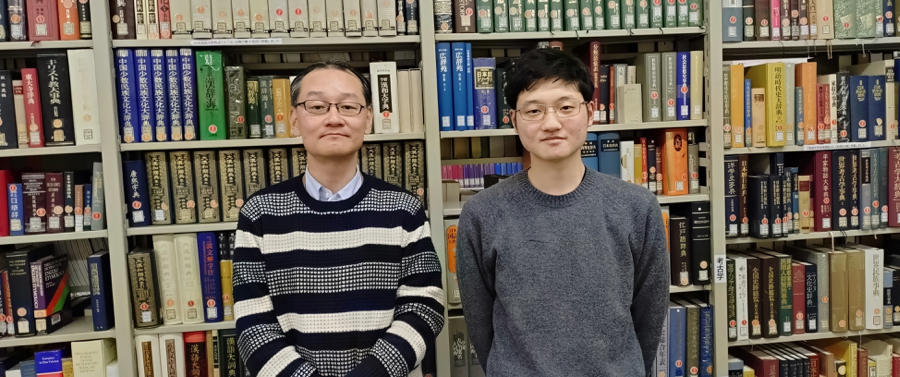文学部 教授 東谷 智 × 文学部歴史文化学科 霧嶋 晃弘
先生は江戸時代の藩政史を研究していらっしゃいますが、なぜその研究を行おうと考えたのでしょうか?

大学院の修士課程に進むにあたって大学の卒業論文をベースに藩政史をしようと思っていましたが、私の先生も藩政史を研究しており、しかもその研究成果が優れたものでした。とても同じ分野ではできないと考え、少しテーマをずらして下級武士の研究を進めました。本来の関心の周辺部から経験を積んでいき、力をつけてから自分のしたかった研究がようやく出来るようになりました。修士の頃に藩政史をしていたらきっと途中で挫折していましたね。
最近では大名御殿の復元をする仕事もしています。関わることになったのは偶然ではありますがそれも面白く、藩政史以外のところにも関心が広がっていますね。
東谷先生の講義では必ずと言ってよいほどフィールドワークが実施されますが、それはどうしてでしょうか?

20代で大学院の研究室に入り、古文書の調査で村に行ったことがあります。現地の方が所有している古文書に神社などが出てくると実際に行ってみようと思うわけです。すると現地の方も興味を持ってくれたのが嬉しくなって、現地の神社とか古くからある用水路などに連れて行ってくれるんですね。現地の人と一緒になって調査することが楽しく、史料の調査とフィールドワークは過去と現在がピタッと繋がる、まさに表裏一体なんだということを実感したからです。
フィールドワークは、事前に調べてきたことを学生に話すガイド形式ではなく、知っていることに加えて現地で発見したことも共有することが大切だと思っています。とは言え誰でも発見できるものではありません。これまでに培ってきた経験と知識、あと閃くセンスも重要ですね(笑)。
文学部歴史文化学科の特色の1つである博物館学芸員課程についてです。このカリキュラムでしか得られない経験は何だとお考えですか?

学芸員はもちろん専門的な職業だと思うんですが、この課程では社会に出てから役に立つスキルを身に付けられるとも思っています。例えば作品を200字で解説するという力は、営業などで商品の要点を簡潔に伝えるための力になってくれます。また、学芸員は人と話す機会も多いんです。講演会など色んな形で人と話しますが、これも社会に出た時にきっと役立ちます。自分の好きな分野から、単なる就職のためとは違った方法で社会性や社会人としてのスキルが身に付くはずです。
大学院に進学し、将来的には学芸員になって博物館で仕事をしたいと考えているので、重要なエッセンスがあることは話を伺って改めて実感できました。学芸員のみではなく社会で幅広く役に立つ経験ができますね。
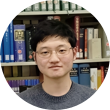
白鶴美術館と甲南大学との合同ワークショップ企画がありますが、始まるにあたってどのような経緯があったのですか?

何かの折にゼミ生を白鶴美術館へ連れて行った際、学芸員さんが「解説しましょうか?」と声を掛けてくれました。それがきっかけで学芸員課程の学芸員実習や、美術史の講義もお願いするようになりました。そんな紆余曲折を経て白鶴美術館と甲南大学との合同で取り組む企画を立ち上げましょうという話になりました。
きっかけは先生の縁からだったんですね、1年生の時から参加していましたが初めて知りました。これまでにどのような活動を行なってきたのですか?
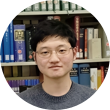

学生が主体でワークショップを実施することはもちろん、文化財の修復をする工房へ見学に行ったことがあります。ワークショップの題材を実際に扱っている職人さんの現場に行って、その技術を取り入れたワークショップを実施することが自分たちにも来館者にもより良い体験ができると考えています。講義時間では伝えきれない情報を提供できる機会ではないでしょうか。
銅板に円状の装飾をいくつもする体験をしましたが、とても上手くできたとは言えない出来でした。職人さんの技術力が垣間見える非常に貴重な体験でした。
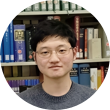

文学部歴史文化学科の、教員と学生との距離感についてはどう思われますか?

私が甲南大学に赴任した時は「昔ながらの大学教授」という言葉がぴったりな先生が多かったんですが、次第に学生メインの学科にしよう、フィールドワークを中心に据えよう、という方針に変わりました。単に教えるだけではなく、学生と共に学ぶという姿勢ですね。一方通行ではなく双方向の学びが歴史文化学科内で展開しているかと思います。オープンキャンパスでも高校生を歴史文化学科の研究室に案内して、普段の姿をそのまま見せるようにしています。
僕自身も学生生活の中で、歴史文化学科の先生方と学生との良好な関係はひしひしと伝わってきています。先生と共に様々な場所へ旅行することは特に楽しいです。
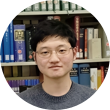
甲南大学でどのような学生を育てたいとお考えですか?

専門性と社会性を歴史文化学科ならではの手法で身に付けて、社会で発揮してほしいですね。博物館学芸員課程を受講したからと言って学芸員にならなければいけないというわけではありません。自分の力になる要素はあちこちに散らばっていますので、是非とも自分の力として吸収していってほしいです。
甲南大学で研究するにあたって、この大学だから良かったことはなんでしょうか?

学生と共に学ぶスタンスの良さを実感しています。様々なテーマに学生が取り組むことで、私が知らなかった領域に踏み入れるきっかけになるんです。研究者としての幅を広げられ、成長を促されていることはとてもありがたいです。その機会は、学生自身の個性と大学の雰囲気によって形作られていると考えています。
研究面での今後の目標はなんでしょうか?

今までの研究成果を文化財の現場で還元する役回りを担う年齢になったのかなあと思っています。社会貢献ですね。私の研究を活かした学生教育と社会貢献とを上手く融合させていきたいという思いがあります。
最後に、私たちの生活で歴史学がもたらす利点についてお聞かせください。

古いことをやっているから新しいことが生まれないと思われますが、過去は異文化なんです。例えば、江戸時代の慣習を知ることは現在との文化の違いを知ることです。時代と地域を越えて、異文化にどう触れるかを考えることができるのは歴史学の最大の利点だと考えています。私たちには不便に思えることや理解できないことを「なぜしているのか」と思った際に、それが行為者にとっては重要なこと・当たり前なことだという受け取り方をしなければ、その文化は「劣っている駄目なもの」という考えに至ってしまいます。
先生のゼミでも「現在の当たり前ではなく、当時の価値観で」とおっしゃっていたことを思い出しました。
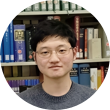

まさにそうです。私たちはスマートフォンを便利だと思って日々使っていますが、100年後の人は「こんな大きいものを毎日持ち歩いていたなんて考えられない」と思うかもしれませんね。不便なことをしていたのではなく便利だからそうしていたのだろうな、という柔軟な発想を持たないといけないのではないでしょうか。
インタビューをした感想
東谷先生が私たち学生のことをどのように考えて接して下さっているのかを知ることができた、かけがえのない時間でした。私が東谷ゼミに所属したいと思う決め手となった、先生の人間性に加えて歴史学に対する考え方について様々なお話を伺うことができました。自分とは異なる価値観を受け入れる余裕を持つことは、歴史学に限らず身近なところでも十分に役立つと思います。学芸員としての資質についても意見を交わすことができ、学芸員を目指す心意気がますます大きなものとなりました。 将来につながる、とても内容の濃いお話を伺う機会をいただき、ありがとうございました。