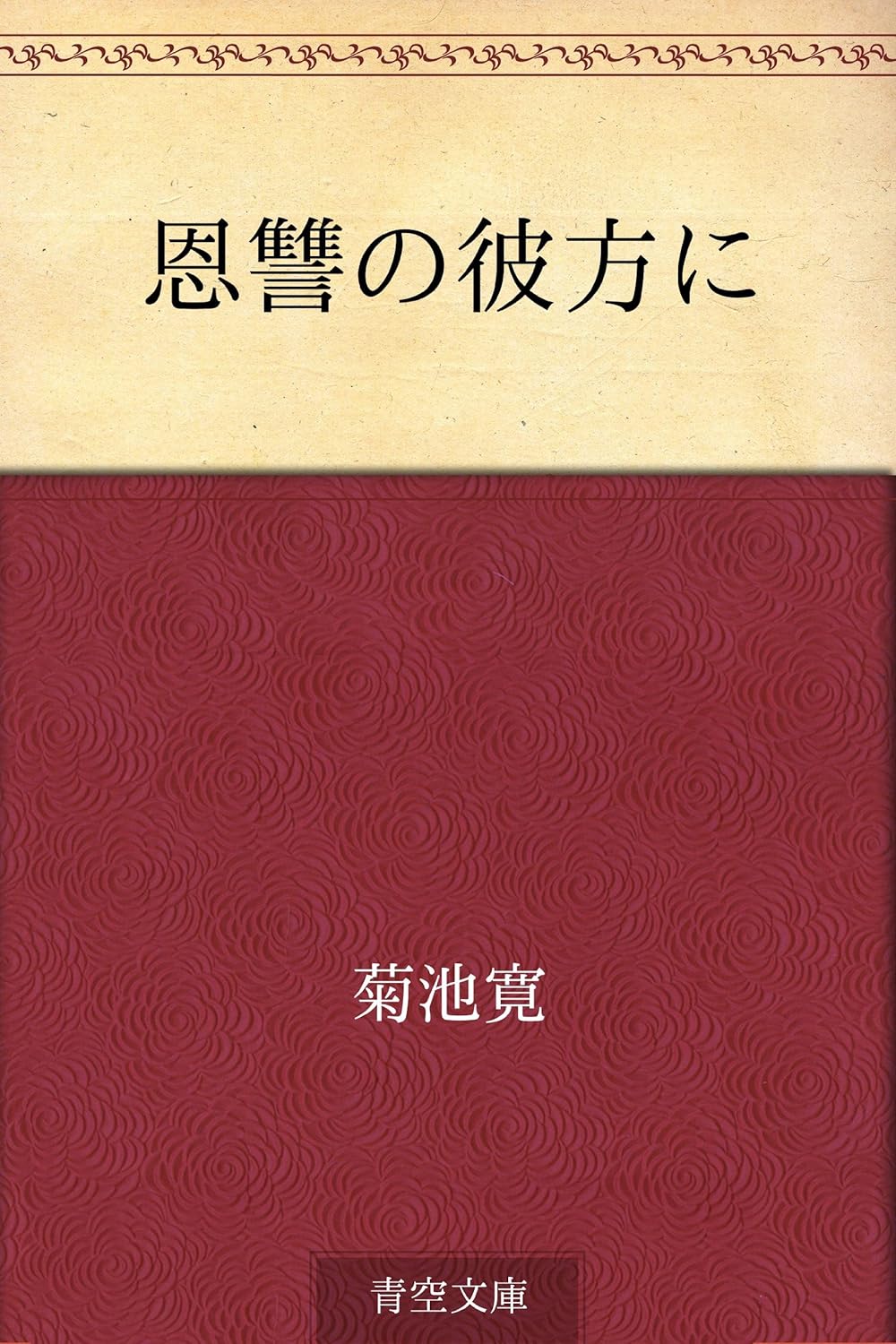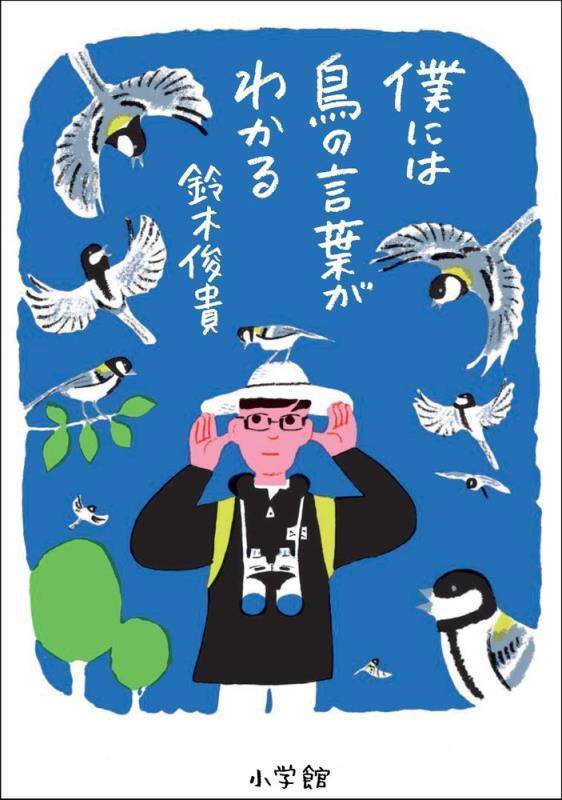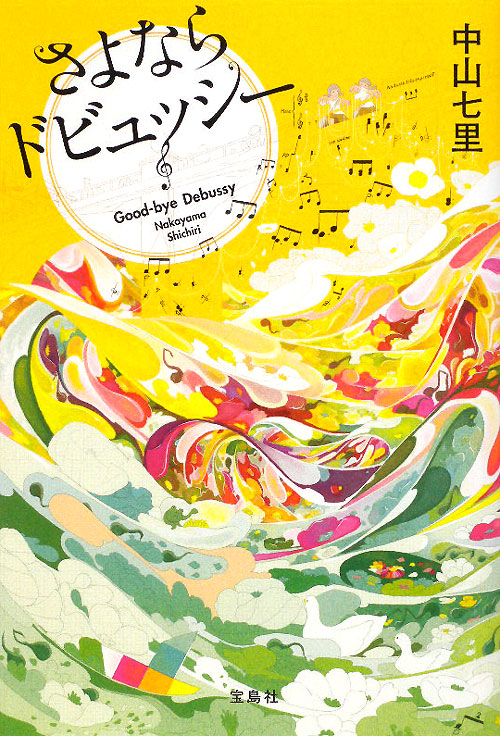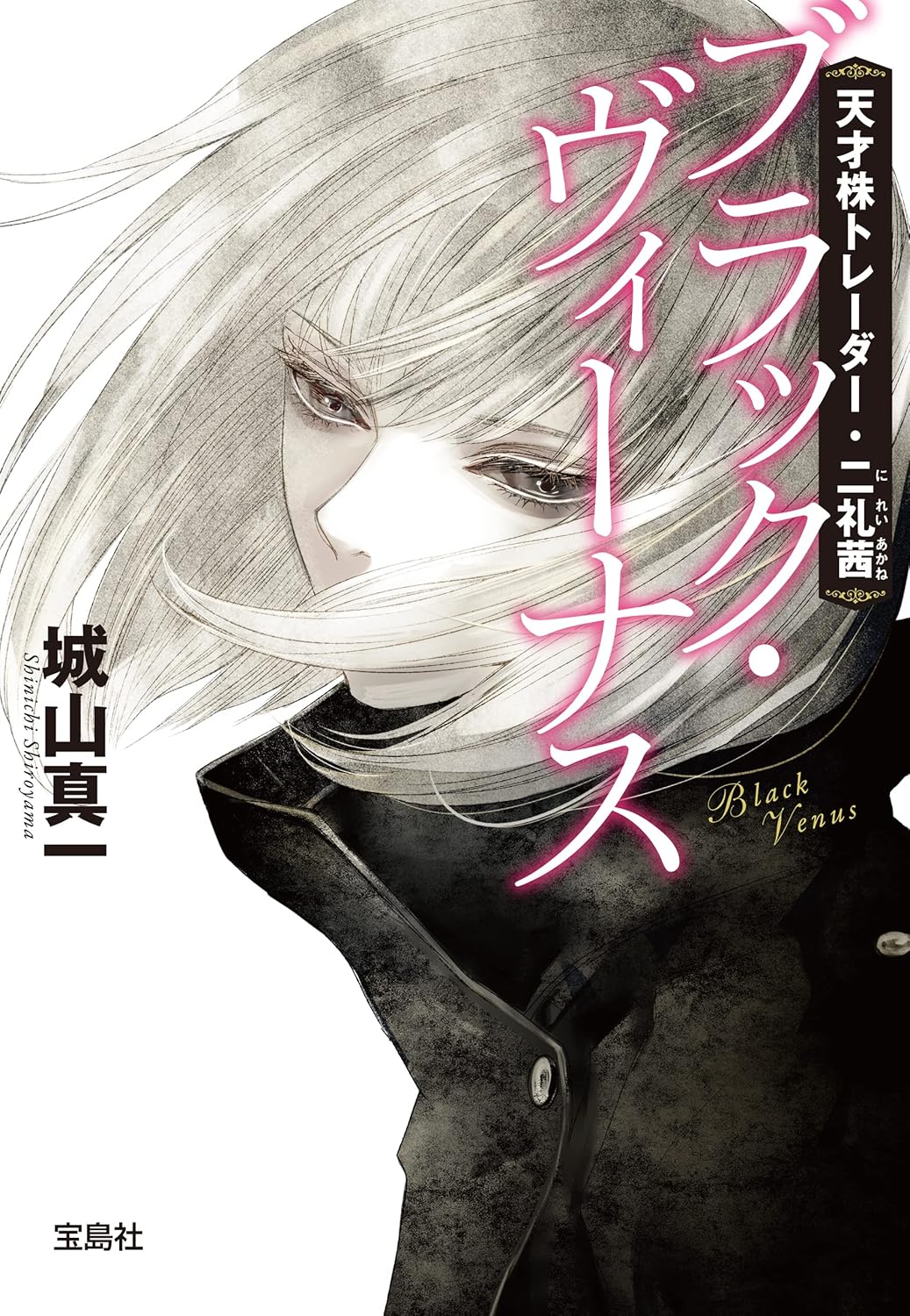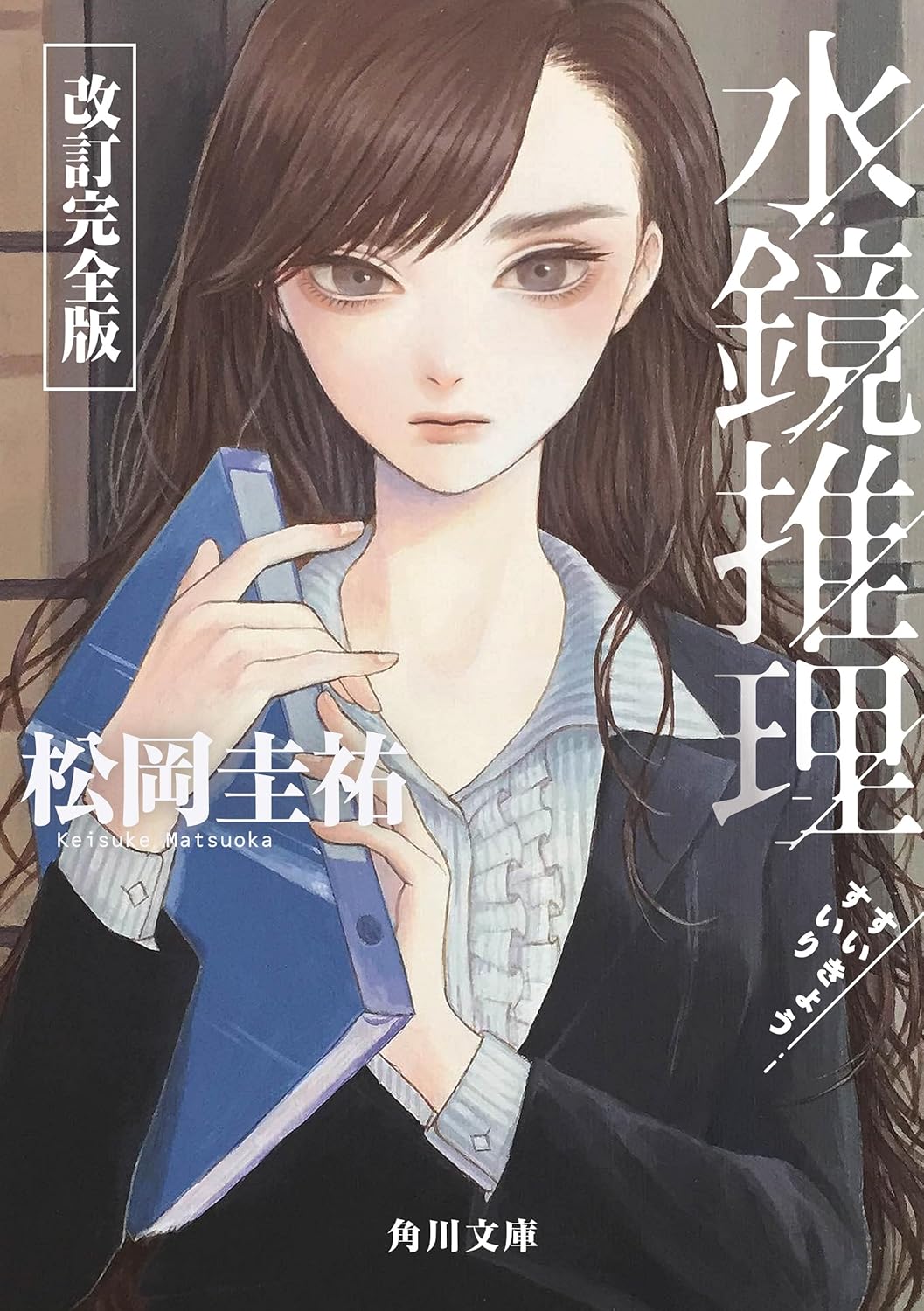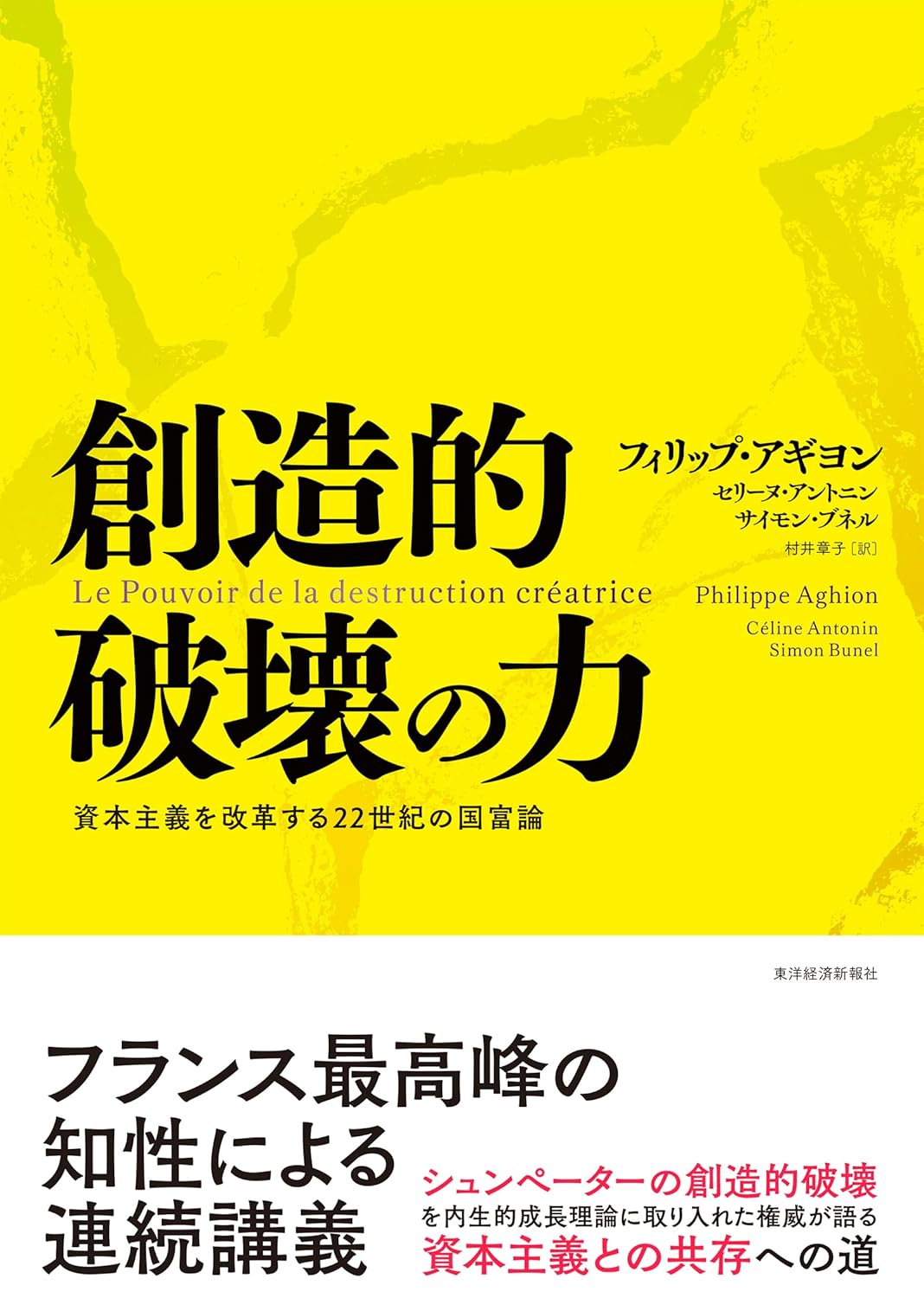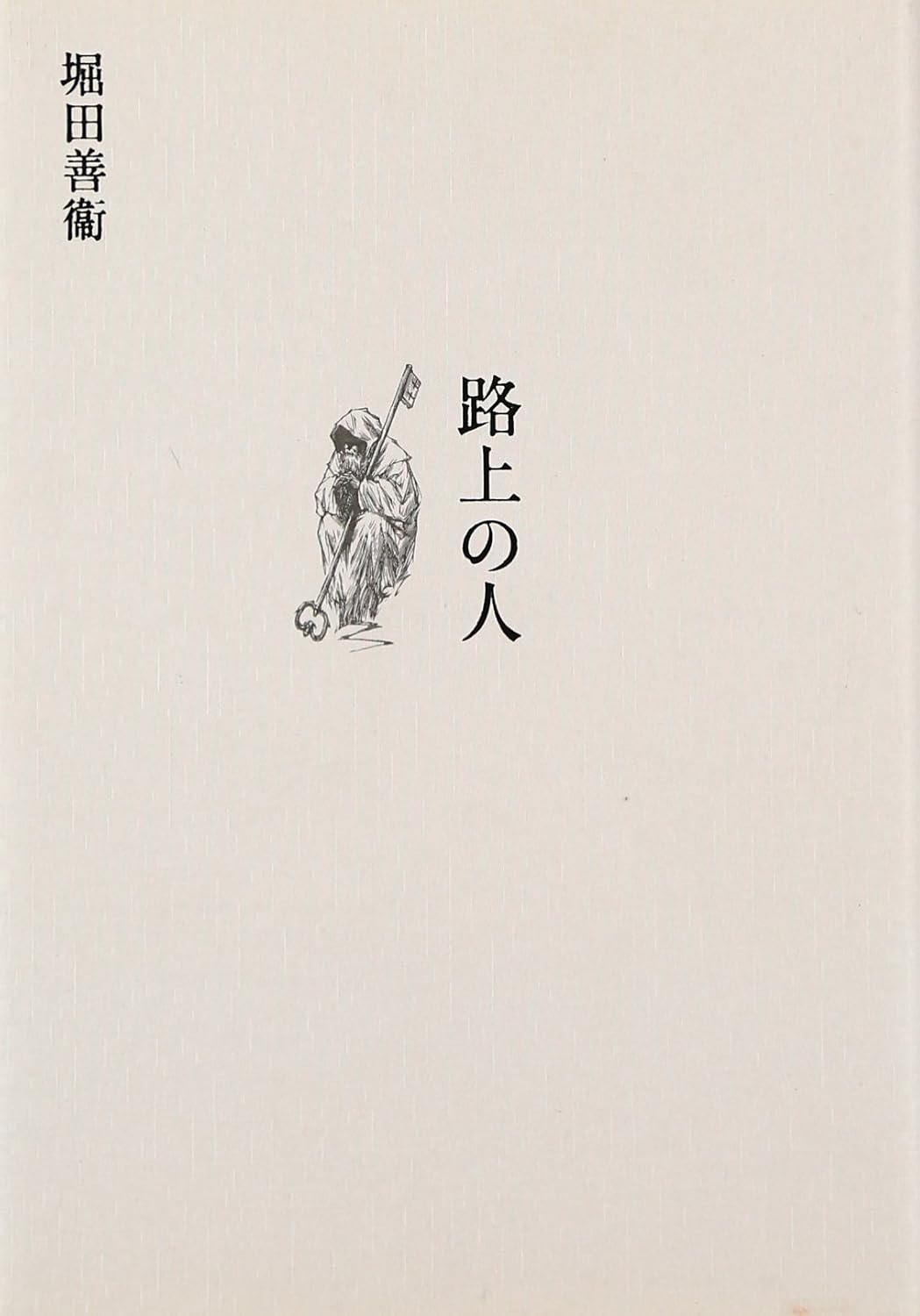文学部4年生 Iさんが、経営学部 平野 恭平先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
―読書の頻度はどのくらいですか?
研究に関する本は週2―3日、最低1―2時間読むようにしています。なかなかその時間を確保できないこともありますが、論文を執筆するときなどはほぼ毎日、本や論文を読んでいることもあります。娯楽の本だと、月に数日読むことができればいいかもしれません。小説も好きなのですがなかなか時間が取れず、出張の際の新幹線や飛行機の移動時間に読むようにしています。
―図書館や書店はそれぞれどのくらい利用されますか?
本や論文を執筆しているときは頻繁に図書館に行きます。ILLで本や論文を取り寄せることも多く、図書館職員の方に助けてもらっています。学生の時は図書館の閲覧室に籠っていましたが、今は研究室があるので研究室で過ごすことが多くなりました。書店は気の向くまま、大学の帰り道や何となく時間を潰すときに利用することもあります。
―面白そうな本の見つけ方や、手に取る決め手を教えてください。
実際に書店に行き、自分の専門である日本史や経済学、経営学などのコーナーに寄って面白そうな本を見つけています。本を手に取って、序文や注、あとがきなどをパラパラと捲ってみると面白いですよ。決め手はやはりタイトルと帯。あとは直感です。小説や新書の帯は面白いのが多く、目について手に取ることも多いです。
―読書の魅力は何だと思いますか?
専門書は、新しい知識や情報が増えるということです。今はインターネット上でもすぐに論文が読め、AIでも簡単にまとめられます。しかし、そのような論文の集大成として書かれた本を読むと、著者の思考がより整理された形で体系的に理解できるように思います。これは著者の思考を読み解く、自分たちにしかできないアプローチだと思います。
娯楽の本については、映像化されているものも良いのですが、原作を読みながら自分の脳裏でビジュアル化するという独自性は読書ならではだと思います。相手を理解し、考え方や感情を想像することは、対人関係や人間力を高める訓練にもなるのかもしれませんね。
―本は紙派ですか、電子派ですか?その魅力も教えてください。
圧倒的に紙派です。以前、図書館の本の落書きを調べたことがあるのですが、そういったものは電子書籍では残らないものですよね。古本に書き込みや落書きの痕跡が残っていたり、貴重な写真が挟まっていたり、所有者の様々な痕跡が残るのは紙の本ならではの魅力だと思います。あとは、本の装丁にこだわりが見られることや、年齢的に長時間の電子デバイスがしんどいというのも理由にあります…。
―先生のお気に入りの本を教えてください。ジャンルや作家でも構いません。
歴史学だとリュシアン・フェーヴル『歴史のための闘い』でしょうか。私は西洋史には詳しくないのですが、非常に上手く訳されていて読みやすく、歴史学を考える1冊としておすすめです。経済史などに関するものだと中岡哲郎『日本近代技術の形成:〈伝統〉と〈近代〉のダイナミクス』、阿部武司『日本綿業史:徳川期から日中開戦まで』も面白いです。小説だと、池波正太郎さん、城山三郎さん、三浦しをんさん、玉岡かおるさんの本を読むことが多いです。
―学生の間に読んで欲しい本を教えてください。
まずは何でも良いので読んでください。最初は新書でもライトノベルでも良いので1冊手に取って、最初から最後まで読んでみてください。最近はAIが要約してくれることもあり、読書という行為が失われつつあると感じますが、自分の力でインプットして自分なりの解釈に繋げることが大切だと思います。
あえて1冊挙げるなら、お気に入りの本でもある中岡哲郎『日本近代技術の形成』をおすすめします。中岡先生には大学院生の頃からお世話になっていたので思い入れが強いというのもありますが、この本は経済史・経営史・技術史的に考えさせられる内容になっており、特に近代史を学ぶ人には読んでほしい1冊です。
【感想】
読書とAIの話を聞いて、本当にその通りだと納得しました。確かに、自分の力で読み解くことや想像することは私たち人間にしかできないことであり、私たちは読書を通してその力を培わなければならないと思いました。最後に、先生には急な依頼にも関わらずインタビューを受けてくださったことを、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
☆先生からのおすすめ本☆
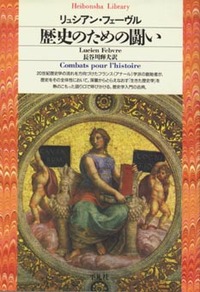
■『歴史のための闘い』
■ L.フェーヴル著 ; 長谷川輝夫訳
■ 東京 : 創文社 , 1977.5
■ 請求記号 201//33
■ 配架場所 図書館 . 3F書庫一般
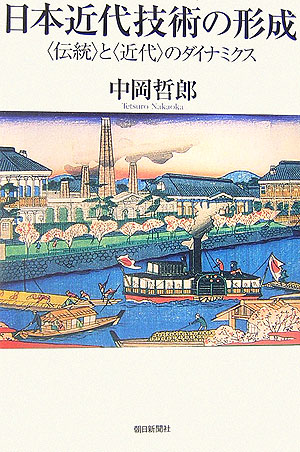
■『日本近代技術の形成 : 「伝統」と「近代」のダイナミクス 』
■ 中岡哲郎著
■ 東京 : 朝日新聞社 , 2006.11
■ 請求記号 509.21//2025
■ 配架場所 図書館 . 3F書庫一般 サイバー . 一般和
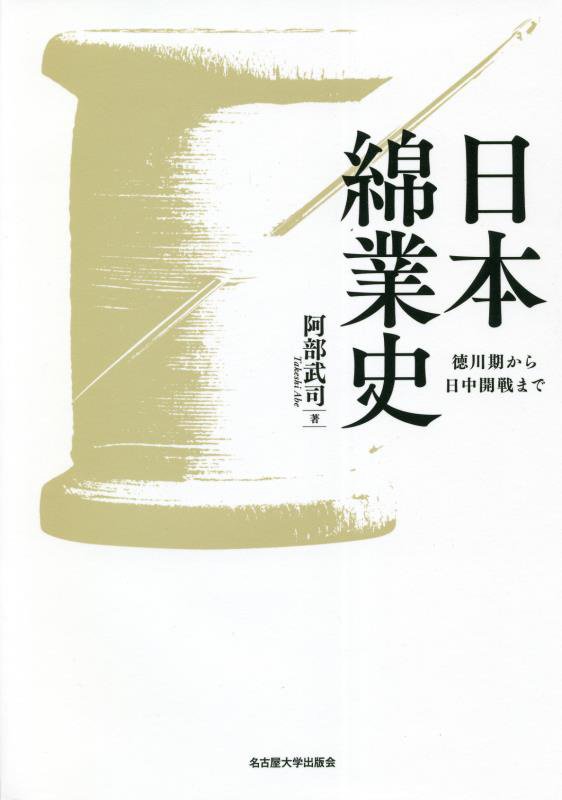
■『日本綿業史 : 徳川期から日中開戦まで』
■阿部武司著
■ 名古屋 : 名古屋大学出版会 , 2022.2
■ 請求記号 586.221//2006
■ 配架場所 図書館 . 1F開架一般
(インタビュアー: 文学部4年生 Iさん)