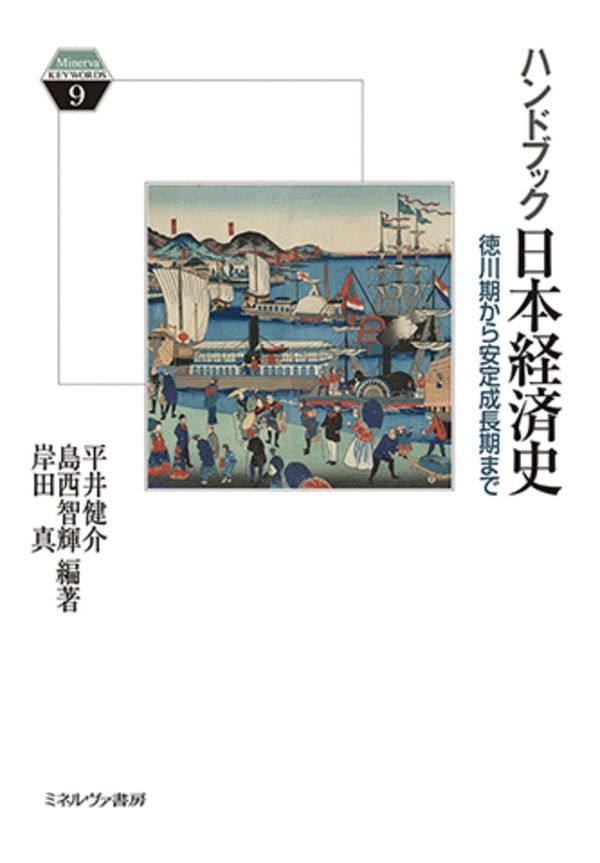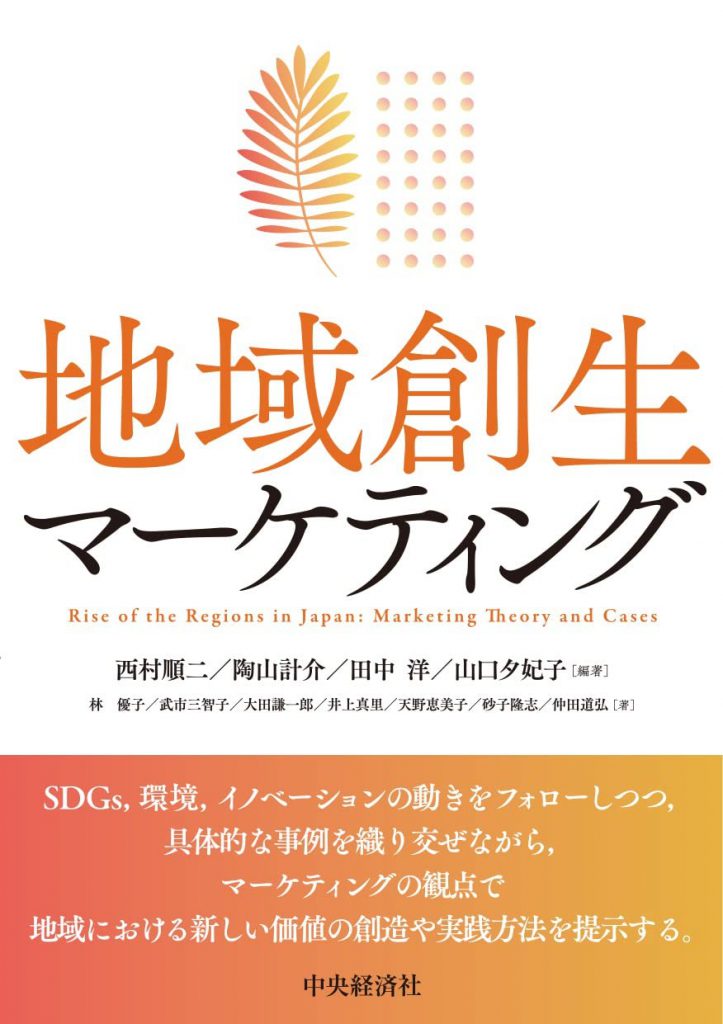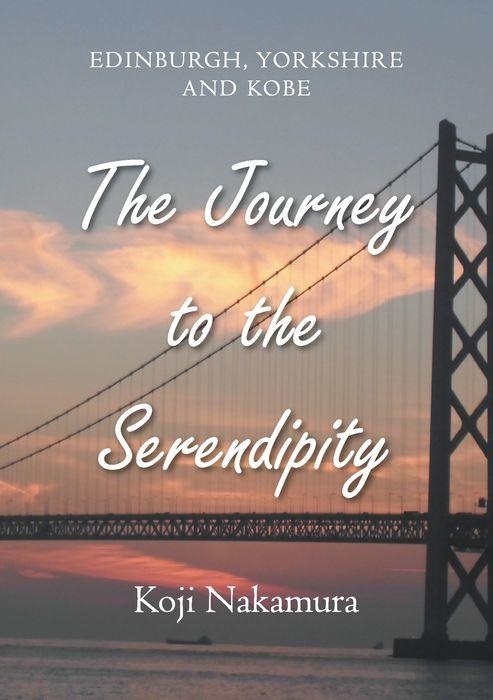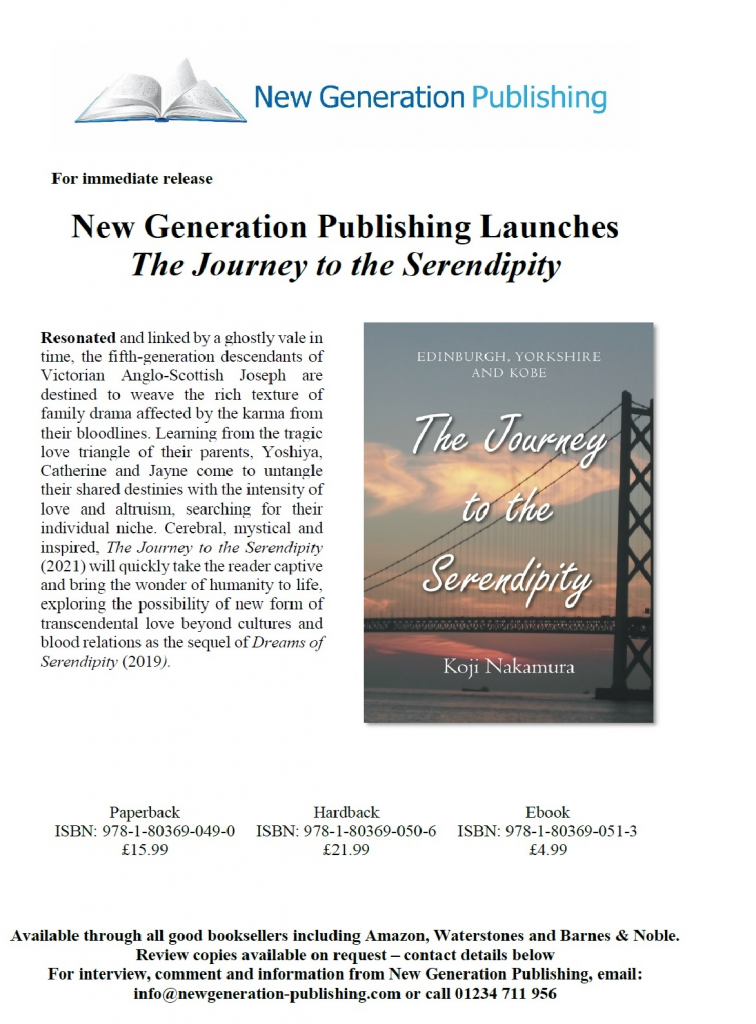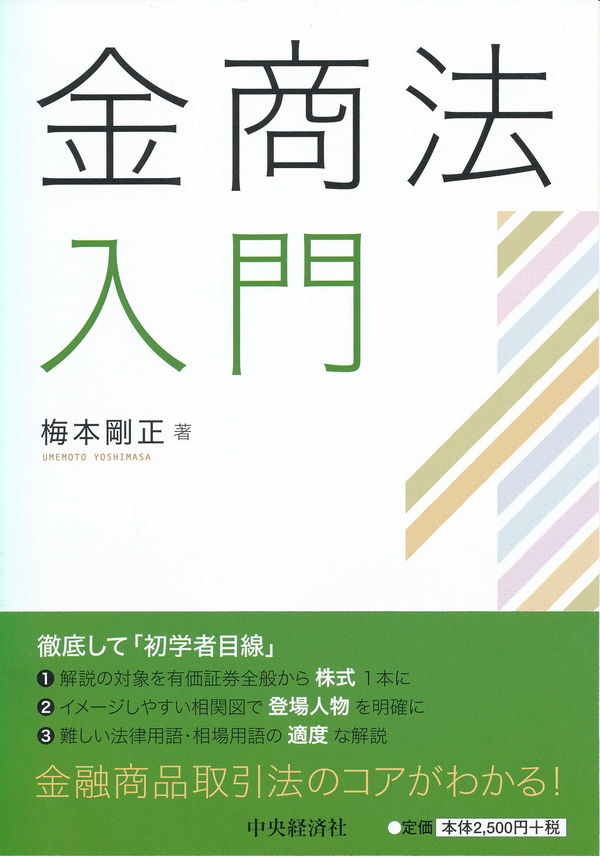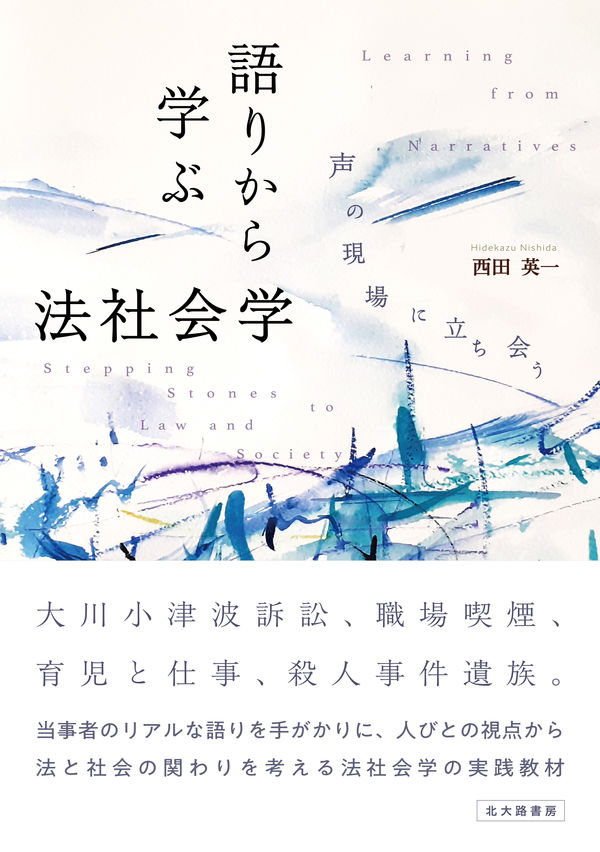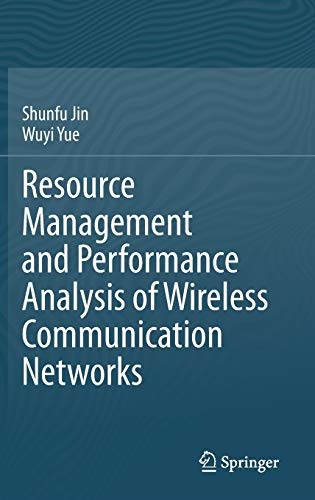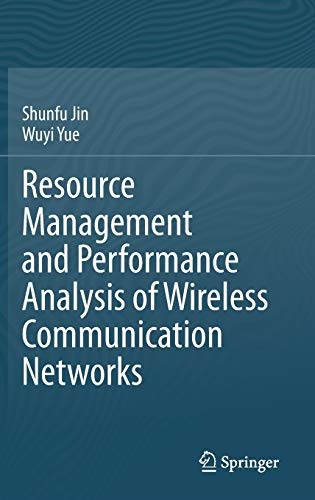
<教員自著紹介>
インターネットサービスが多種多様化し、モバイルユーザが増加するに伴い、ネットワークリソースの効率的な管理は無線通信ネットワーク(WCNs)分野の極めて重要な課題となっている。このようなネットワークにおいて、ユーザの要求をより良く満たすためにはエンドツーエンドで十分な適応性を有するサービス品質(QoS)管理メカニズム(適応型リソース管理)が必要となる。モバイル機器需要の急増以来、特に無線通信システムおよびネットワーク設計と構築、運用における経済効率改善のための有効手段として、適応型リソース管理は必要不可欠とされている。
しかし、無線通信ネットワークにおける適応型リソース管理は、ネットワークユーザのサービス品質を維持するだけでなく、エネルギー消費やコストの効率的削減によるネットワークリソースシステム全体に関わる最適化も行う。そこでは、適応型無線アクセスネットワークの構成、リソースユニットの設計、構築及びプロセス方式、適応型無線周波数リソース割当方式、リソース管理システムそのもの、など多方面の技術が求められている。これらに対して、様々な無線通信ネットワークに要求されている異なる通信サービス品質を保ちながらエネルギー消費やコストの効率的削減を可能にする新たな通信ネットワークの制御技術を有するシステムの提案が必要不可欠である。さらに提案システムに関し、ネットワーク通信サービスから生成される通信トラヒックの確率振る舞いについて、システムの数学モデルに基づき理論的解析ならびに数値的評価を行い、提案システムの有効性と合理性を示す必要がある。
一方で、通信サービス、通信トラヒックの形態、アクセス方式、そして制御方式等により、ネットワーク上に流れている通信トラヒックは、非常に多様で複雑な確率的性質を持つ。こういった多種多様な無線通信ネットワークにおける通信トラヒックの性質の解明にあたり、伝統的な確率モデルおよびそのモデルに対する解析手法や関連評価量の適用だけではもはや行き詰まっている。現在、それらのネットワークシステムの通信トラヒックがもつ確率的性質を表現可能な通信トラヒックの数学モデルの構築、及びそれらの確率モデルに対する新たな解析手法の確立と数値的評価は重要かつ主要なテーマとなっている。
このような背景のもと、私の研究の歩みの中、かつて指導し、その後共同研究者となっているShufu Jin教授ととともに20年以上行ってきた、日本を含め多くの世界トップクラスの学術論文誌に公表された多種多様な無線通信ネットワークについて、夫々に合致した適応型リソース管理とその性能解析に関する研究成果を中心にまとめたのがこの著書である。本書は3部21章479ページからなっている。
これまでの待ち行列理論とマルコフ過程を用いた無線通信ネットワークに関する既存の書籍では、無線通信ネットワークにおける資源管理とエネルギー消費の効率的削減ネットワークリソースの戦略的最適化問題ついて、トピックはカバーされていない。本書では、著者らが、多種多様なタイプの無線通信ネットワークにおける限られている資源管理やエネルギー削減に対して、通信サービス品質を保ちながらエネルギー消費やコストの効率的削減を可能にする新たな通信ネットワークの制御技術を有するシステムについて体系的に述べる。そして、ネットワーク通信トラヒックの確率的振る舞いを数学的にモデル化し、待ち行列理論とマルコフ過程などの数学手法を用いて、理論的解析ならびに数値的評価を行い、それらの新たなシステムの有効性と合理性を数値的に本格的に論考する。
また本書では、多種多様なタイプの無線通信ネットワークに対するシステムモデリング手法、通信トラヒックの数学モデルに基づく数値的評価のための厳密ならびに近似分析解法、理論的解析ならびに数値的評価法、そのアプローチとシミュレーション方法等も豊富に論じる。さらに、インテリジェントな検索アルゴリズム、シミュレーション技術、システム最適化手法などを駆使した、理論的および数値的研究の事例である無線通信ネットワークにおけるサービス品質の評価と通信リソースの最適割り当てに関して体系的かつ詳細に解説する。
本書で示された多くの無線通信ネットワーク(主にブロードバンドワイヤレスアクセスネットワーク、コグニティブ無線ネットワーク、クラウドコンピューティングシステムなど)のリソース管理および性能分析の方法は、コンピュータサイエンスと通信工学の大学院生、ならびにネットワーク設計、ネットワーク管理、性能評価、待ち行列に興味のある研究者やエンジニアに有用な専門知識を提供する。また、WCNのモデル化のために待ち行列理論に興味を抱く学生、アナリスト、管理者そして産業界の人々への参考書としても十分に役に立つはずである。
また、本書は、待ち行列理論とマルコフ過程理論、ゲーム理論、インテリジェントな最適化、そしてオペレーションズリサーチの応用方法を多数紹介している。それらを理解するためにはコンピュータネットワークの基本概念と待ち行列理論の基本的知識が必要であり、確率過程を熟知していることも役立つ。
■ 『Resource Management and Performance Analysis of Wireless Communication Networks(和訳): 無線通信ネットワークのリソース管理と性能解析』
■ 岳 五一( Wuyi Yue)著 , Springer, 2021.
■ 請求記号 547.483//4001
■ 配架場所 図書館 1F 教員著作
■ 著者所属 岳 五一 (知能情報学部)
https://www.springer.com/gp/book/9789811577550
DOI:https://doi.org/10.1007/978-981-15-7756-7