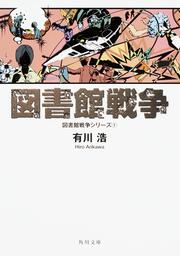文学部 2年生 匿名さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名:ヒカルの卵
著者:森沢明夫
出版社:徳間書店
出版年:2015
優しくて温かくて、元気がもらえるお話を読んでみませんか。
この物語は、故郷を愛する、自称ツイてる、養鶏農家の村田二郎が、村おこしのため、森の奥に世界初の卵かけご飯専門店をオープンさせようと計画するところから始まります。村落の人々の反対や幼馴染との仲違いなどの様々な困難に直面しながらも、自称ツイてる男、通称ムーさんは、周りの人々に励まされたり支えられたりしながら計画を実行していきました。
私がこの物語をおススメする理由は三つあります。まず一つ目は、主人公のムーさんや村落の人々や幼馴染などの登場人物一人一人がすごく魅力的だからです。励まし合ったり、気遣い合ったりしながら頑張っている姿からは元気がもらえるのではないのでしょうか。
それから二つ目は、この物語の形式が複数人の語りであるからです。このことには、様々な視点から物語が楽しめると同時に、それぞれの人の思いや抱えているものをより深く知れるという効果があるということを感じました。これにより、物語が重層的で味わい深いものになっているのではないのでしょうか。
そして三つ目は、幸せの定義や生き方や考え方についても考えさせられる本であるからです。それは、ムーさんを始めとする登場人物一人一人が誰かを思いやって発する言葉や、地の文、物語全体、あとがきにまでも表れています。
炊き立てのご飯で作った、ほっこりとしてふわふわの卵ご飯のような物語をぜひ味わってみて下さい。