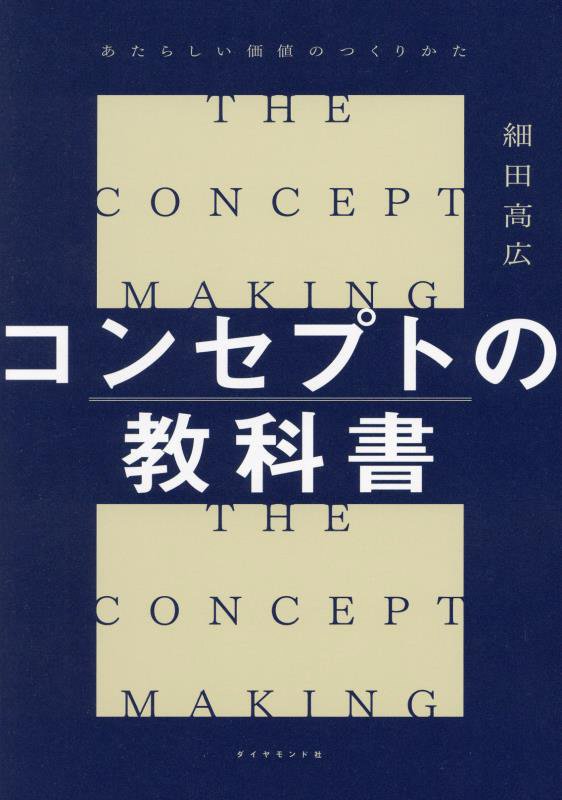
知能情報学部 4年生 Kさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : コンセプトの教科書 : あたらしい価値のつくりかた
著者 : 細田高広著
出版社:ダイヤモンド社
出版年:2023年
本書籍は、コンセプトを「つくる」ために書かれた。どのように発想し、構想を膨らませ、言語に落とし込むのか。最初の一手から仕上げまでの一連の流れひとつの体系にまとめられている。「コンセプト」という単語は、「全体を貫く新しい観点」と説明する辞書が多い。ビジネスシーンでのコンセプトの構成は、判断基準になること、一貫性を与えること、対価の理由になることの3つと言える。
また、最初の一手で重要なこととして、コンセプトメイキングがある。「新しい意味の創造」を意味し、コンセプトメイキングは問いからはじまるが、意味のある問いでなければ意味がない。意味のある問いから意味のあるコンセプトが生まれるからだ。
問いの良し悪しは「自由度」(問いが誘発する答えの幅)と「インパクト」(答えることで生まれる社会や生活への影響力)で決まる。良い問いは受け手の発想に自由を与え、決定的な答えを導く。設計には、顧客目線で設計する「インサイト型ストーリー」と、未来目線で設計する「ビジョン型ストーリー」の2種類がある。「インサイト型ストーリー」は、顧客を救済するもので、4つのC(Customer:顧客、Competitor:競合、Company:会社、Concept:コンセプト)から構成される。
コンセプトの設計ができたならば、1行化(ワンフレーズ化)しなければならない。ここではまず、3点整理法を用いて意味を整理する。次に、目的か役割かに応じて情報を削ぎ落し、最後に2単語ルールに則って言葉を磨き上げる。コンセプトに役立つ10の構文も存在するので、それを用いるとより良いコンセプトに仕上がるだろう。
ここまで到達すれば、試作品を作成すると良い。製品の開発コンセプトであれば、1枚の紙にまとめる、マーケティングコンセプトであれば、1文にまとめることが効果的だ。
このように、この本はコンセプトのつくり方を最初から最後まで懇切丁寧にまとめられている。
