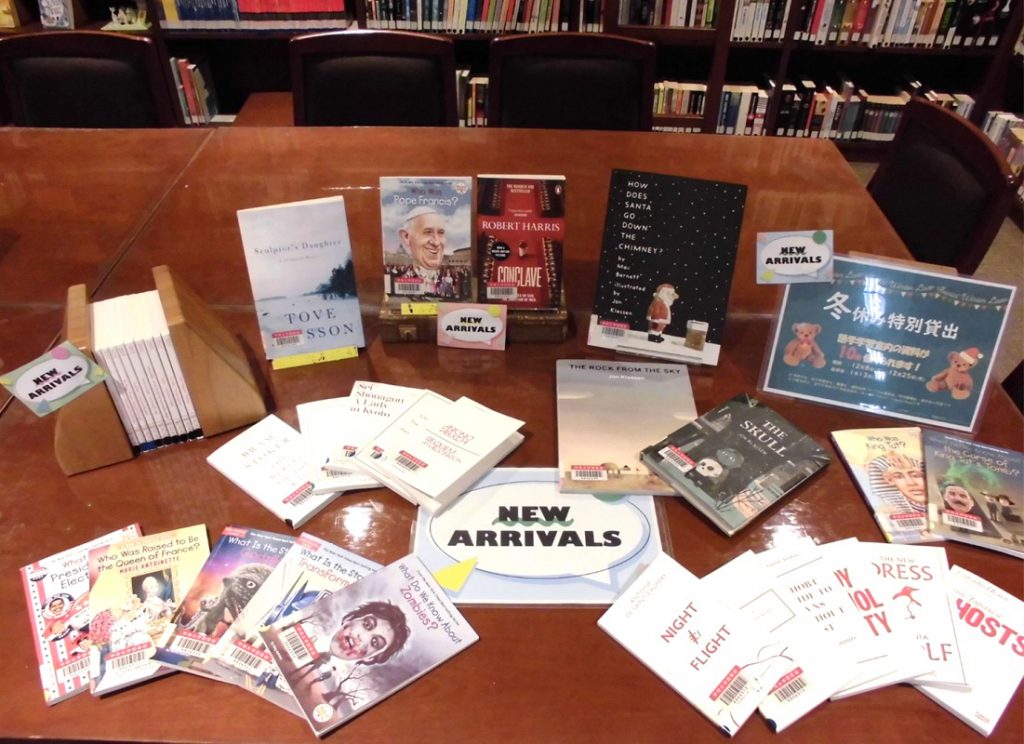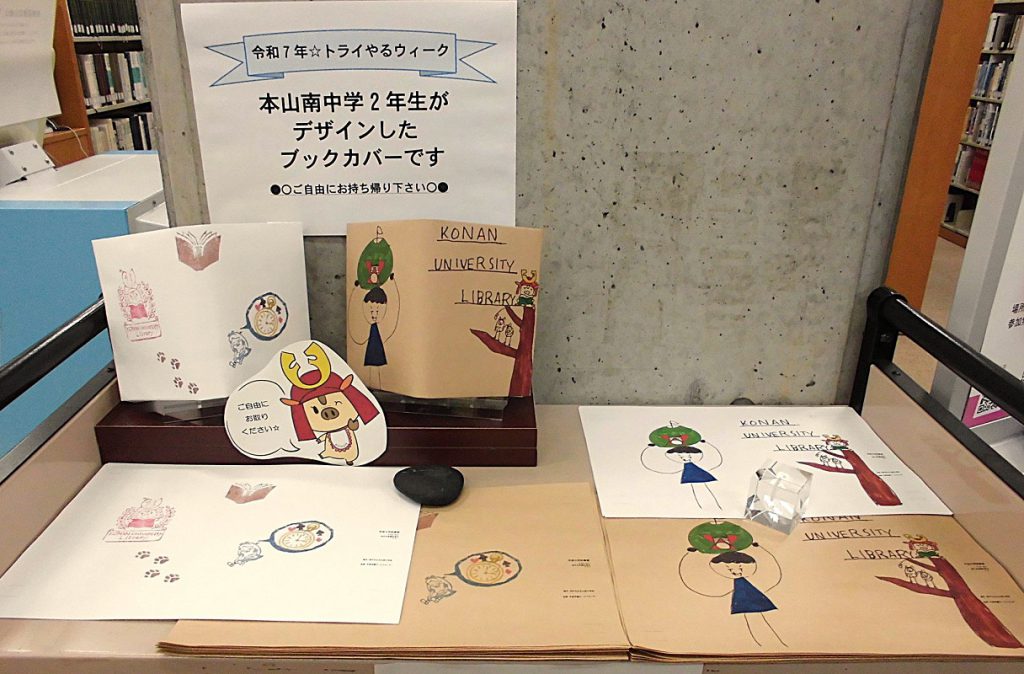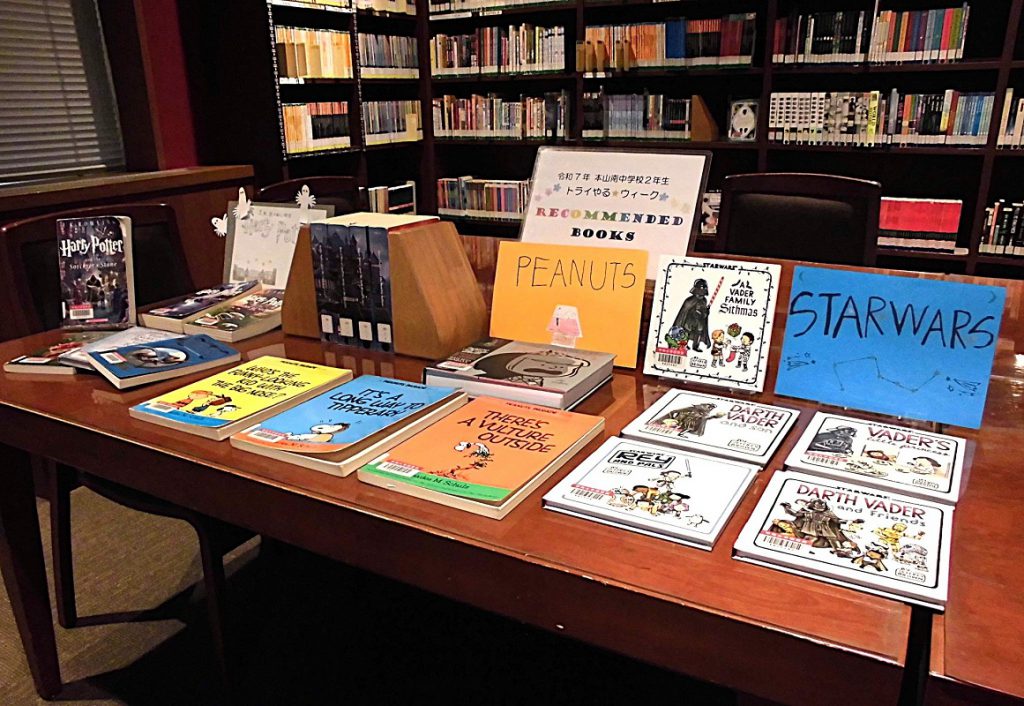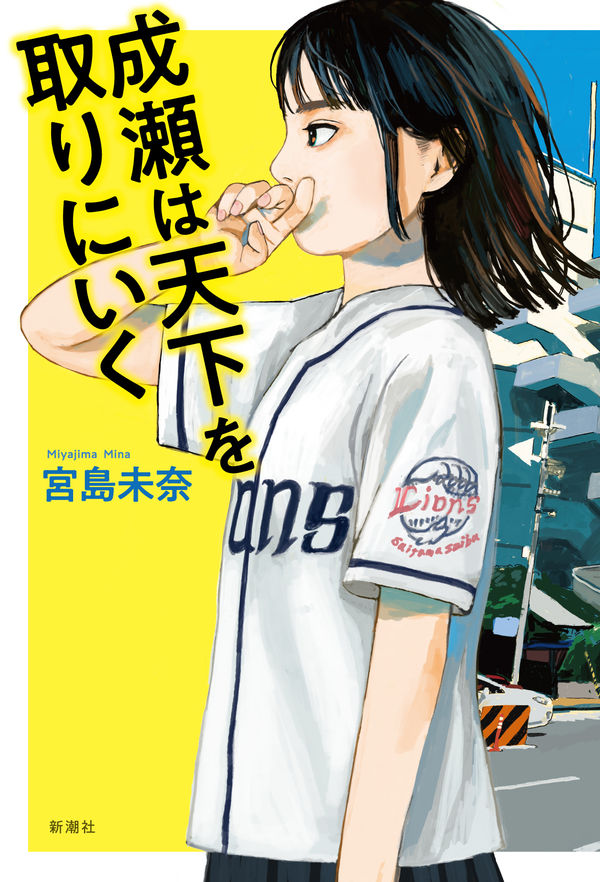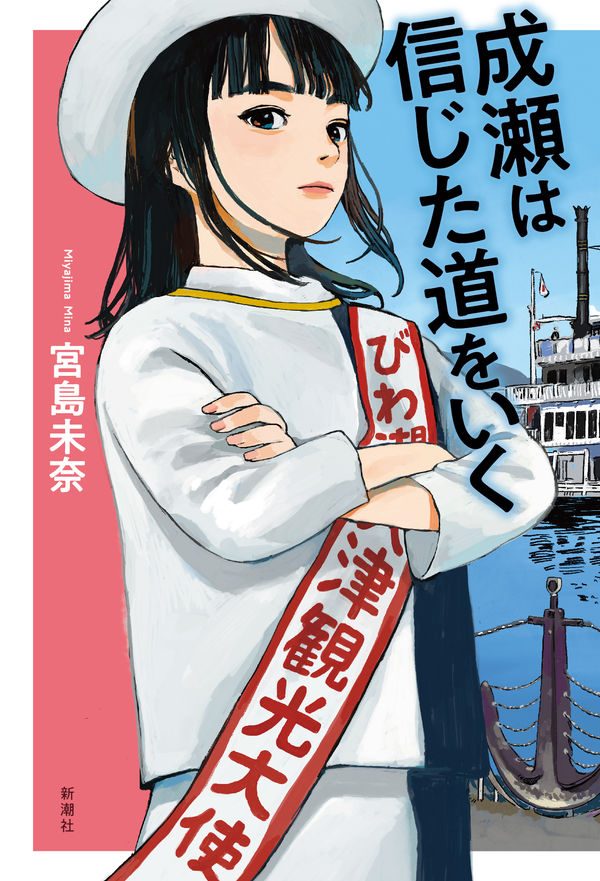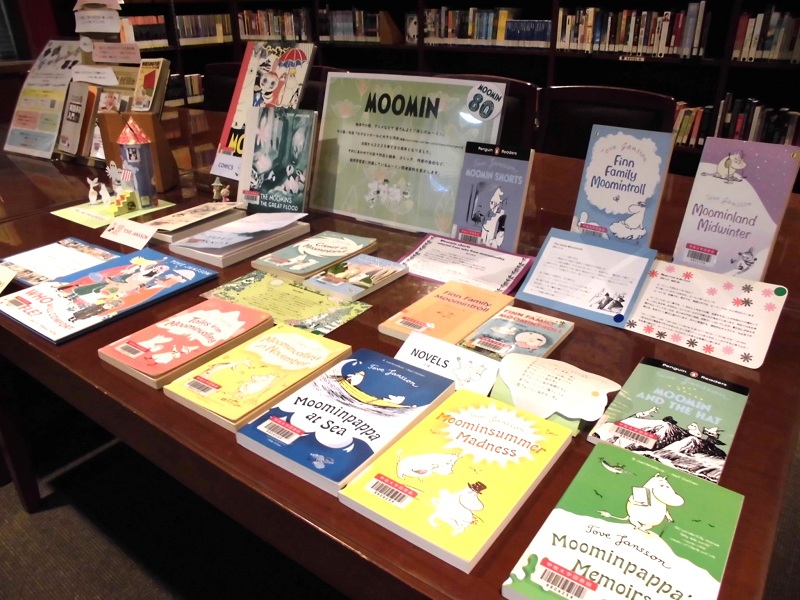図書館報『藤棚ONLINE』
マネジメント創造学部・榎木美樹先生より
民際学者、アジアをあるく: 中村尚司と仲間たちの時代(林真司、みずのわ出版、2024年)
今年(2025年)は、戦後80年の節目の年だった。日本は、世界唯一の被爆国として広島・長崎の経験を世界に伝え、核軍縮・不拡散に中心的な役割を果たそうと努めている。
例年に比して特徴的だったのは、こうした日本の被害の側面のみならず、日本の加害の側面も直視しようとする動きだったと思う。公式サイトの閉鎖を受けて平和教育の点で話題になった漫画『はだしのゲン』(中沢啓治著)への注目も然りだ。これに著わされた主人公のゲンや、ゲンの生き方に決定的な影響を与えるゲンの父親の姿を通して、作者(中沢)は徹底的に戦争反対を貫き、戦時中の朝鮮人差別とも向き合っている。
こういう節目の年だったからこそ、若者にぜひ読んでもらいたい本がある。
戦後日本の歩みをアジア各国の人びととのかかわりの中で「アジアの一員として」「日本人として恥ずかしくないように」道筋をつけてくれた中村ら先人たち生き方と実践の記録である。
「日本はアジアの一員」を当たり前だと思ってくれる若者、あるいは「日本はアジア民衆を犠牲にしてきた責任があるのだから、それに真摯に向き合わねばならない」と考えている人なら、彼らの思想や生き方が一朝一夕にできあがったものではなく、連綿と連なる託されたバトンのリレーの中にあることを確認してほしい。
アジアに学び、共に生きていく姿勢を貫き、「民際学」を提唱する人たちの記録が『民際学者、アジアをあるく』(2024年、みずのわ出版)である。
「民際学」は、「国家」の枠組みをこえる民衆の学としての知識と実践の体系・あり方で、「あるく・みる・きく」を実践するため、フィールドワークを重視する。私自身がアジアに軸足を置き、フィールドワークに基づくヒト・モノ・コト調べをしたいと思った原点の学問体系である。
民際学を大きく打ち出した中村尚司*は、日本に暮らすマイノリティの生活条件を少しでも改善しようと、東奔西走してきた研究者であり実践家である。彼は、鶴見良行**との知的・実践的交流を通して、その思想と体系を発展させた。 中村が民際学を打ち立てる上で、多大な影響を受け、半世紀以上ともに仕事をしてきたのが田中宏***だ。田中は、在日外国人の処遇改善に長年奔走してきた、この分野におけるパイオニア的な存在である。「日本人として恥ずかしくないのか」という気持ちが、田中の仕事の原動力で、自分が取り組んできた一連の仕事について、日本という国が、どういう国なのかを示す、格好の教材になっていると言う(本書pp.135-137)。その田中の人格形成と生き方に大きな影響を与えたのは、真っ当な「人間であるために」日本人の価値を再吟味し続けた、穂積吾一**** である。
本書の筆者・林真司は、「彼らは、鬼畜米英という、敵役がいなければ成り立たぬ、反動としての興亜主義者ではない。アジア諸民族と平等な関係を作るために、全身全霊を傾け続けた、真のアジア主義者なのである」と評する(同、p.137)。
中村がともに仕事をしてきた彼らに共通するのは、仮想敵を想定して攻撃して奪い取る姿勢ではなく、戦争の加害の側面を意識しつつも、「日本人として恥ずかしくない行い」を念頭に、苦しみのただなかにある人、在日外国人の不運と不幸に対する共感(empacy)と義侠心をベースに人と人との関係性を重視する「民際」の立場で行動を起こすという点である。他者への共感と義侠がゆえの行動の上に「民際学」は立っている。
被差別部落のみならず、在日のアジア人たちも、日本社会において差別や貧困に直面してきた。有色人種に対する蔑視観は、明治以降の欧米を手本とした国家の発展観に基づく。さらに日本はアジア各地を侵略し、大勢の住民を犠牲にしたにもかかわらず、そうした責任を認めようとしてこなかった。これらの反省と義侠心ゆえの「脱欧入亜」であり、国民国家を前提とする「国際」ではない、人・民が中心の「民際」なのである。本書を読むと、民際学のよって立つ思想基盤と実践のありかたの流れが必然であることがよくわかる。
戦後80年の今、また外国人へのヘイトが日本を守るうえで正統性を持つかのような錯覚が起きやすい今だからこそ、この本を手に取り、戦後の日本人の来し方を見つめなおし、行く末を見定めてもらいたい。
中村のバトンは私や同時代に学んだ当時の大学院生・学部生・出会った人々に渡されていると思っている。そのバトンをあなたは受け取ってくれるだろうか。
*)中村尚司(1938年-現在)。経済学者。地域経済論、エントロピー論、南アジア研究などをフィールドにした「民際学」を提唱。主著は『人々のアジア』(岩波新書、1994年)など。
**)鶴見良行(1926-1994年)。アジア学・人類学者。主著は『バナナと日本人』(岩波新書、1982年)『ナマコの眼』(ちくま学芸文庫、1993年)など。
***)田中宏(1937年-現在)。経済史学者。主著は『在日外国人』(岩波新書、1993年)
****)穂積五一(1902-1981年)。社会教育家。アジア学生文化協会、アジア文化会館の創設者として知られる。