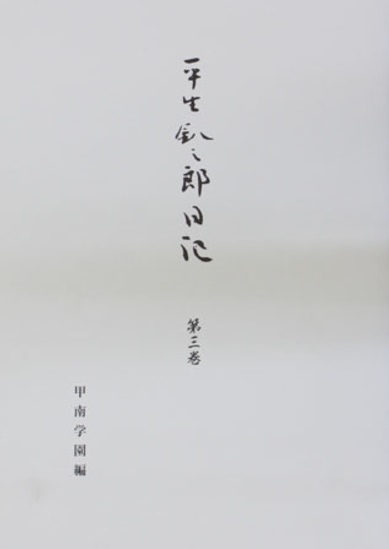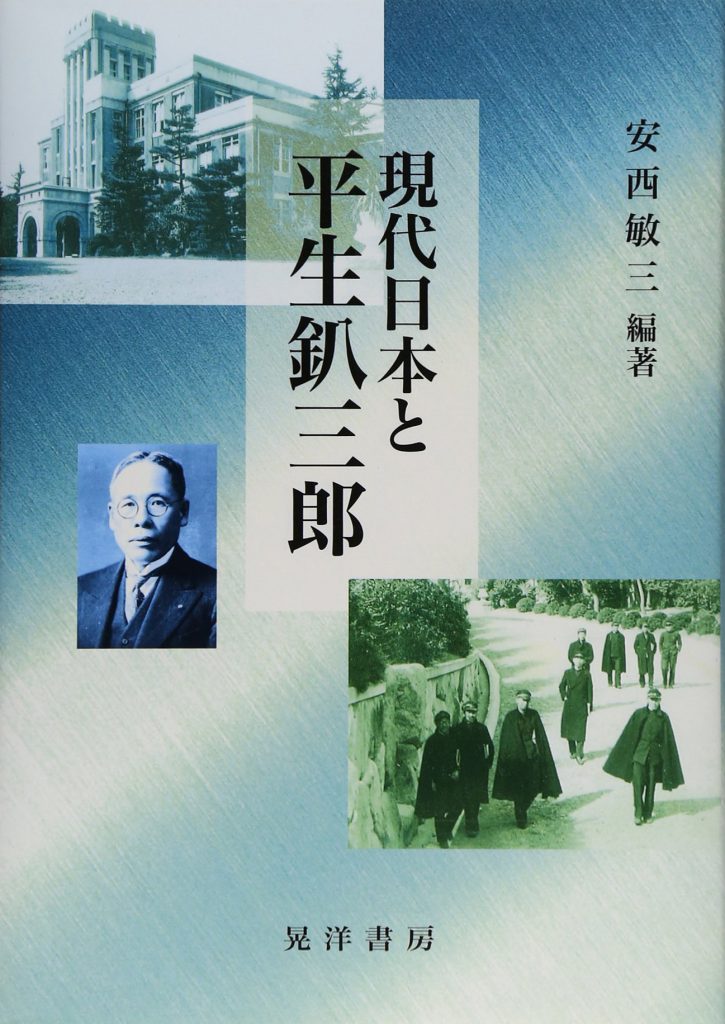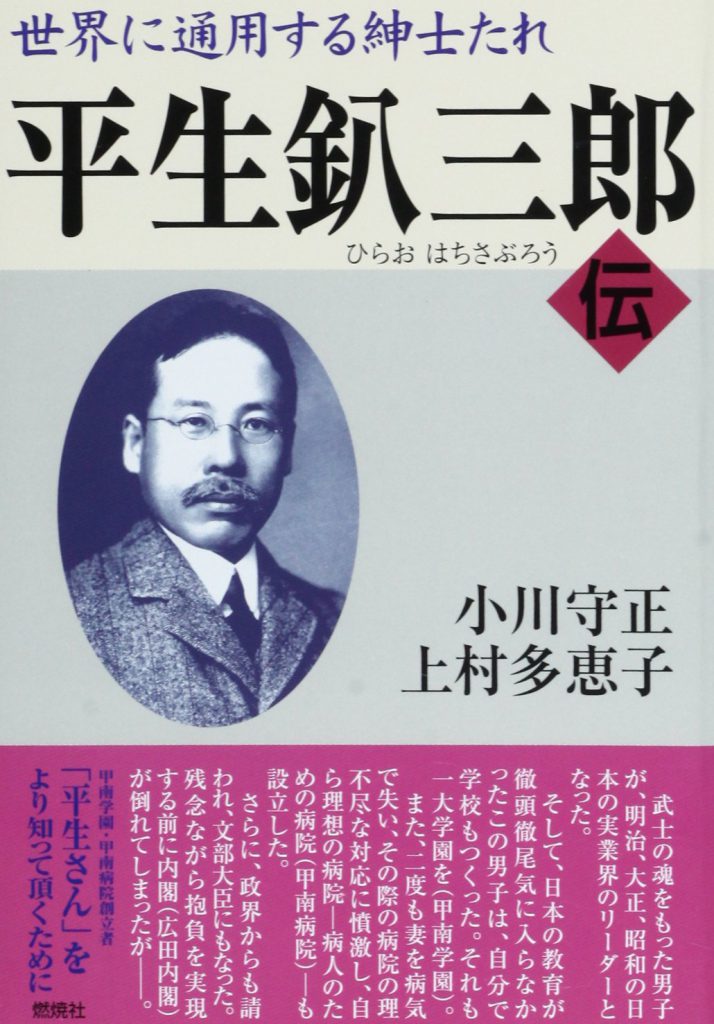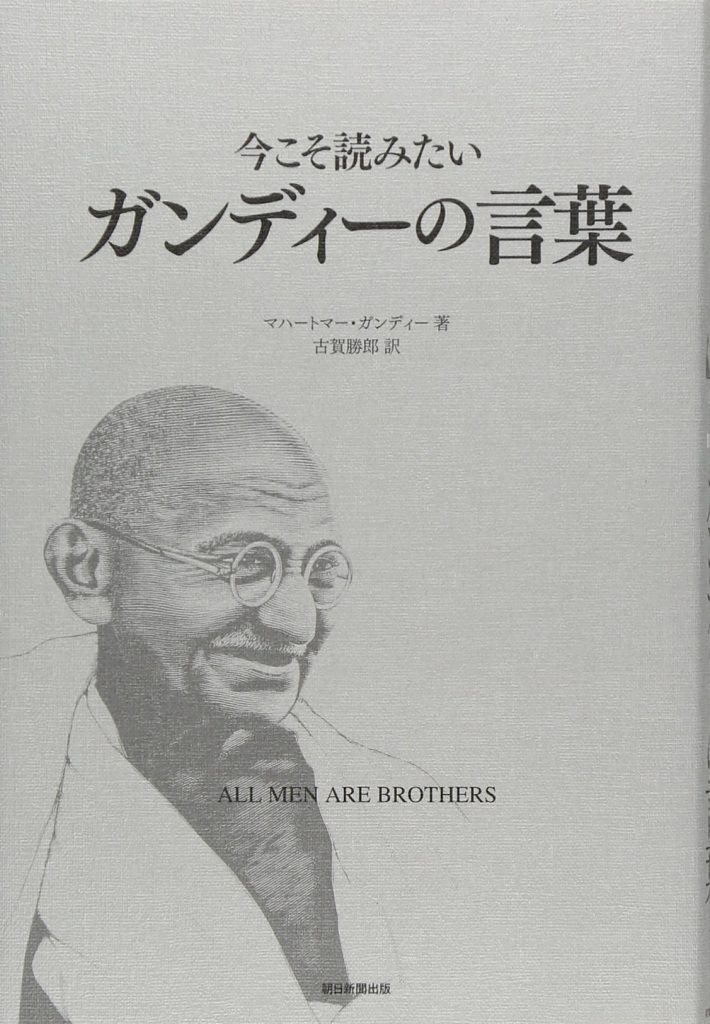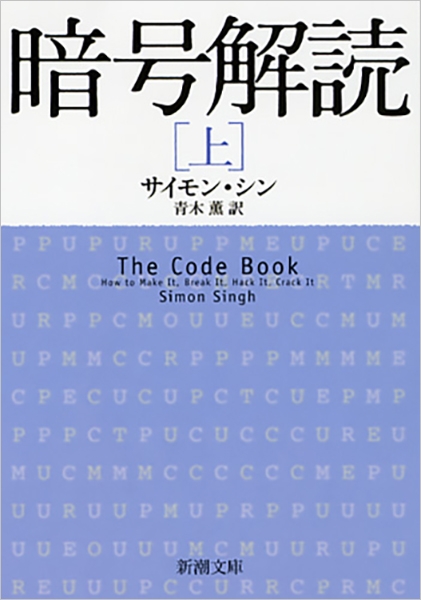
知能情報学部 4年生 Kさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : 暗号解読 (上)
著者 : サイモン・シン著, 青木 薫訳
出版社:新潮社
出版年:2007年
暗号に興味があるけど難しそう。そう思っている方にお勧めなのが、フェルマーの最終定理で有名な著者 サイモン・シンの「暗号解読」です 。
人は、昔から秘密を守るために暗号を考案してはそれらを破ってきました 。古代ギリシャから現代にいたるまで今も昔も情報の重要性は変わりません。文字を入れ換えたり表を使ったりいろいろな方法があります 。
本書には、一度は聞いたことがあるものの、その仕組みや復号(解読)方法が分からない方、興味津々な方や推理小説に出てくる暗号を自力で解いてみたいと思うような方に向いていると思います。文系理系関係なく楽しめるものとなっています。暗号を作る天才たちとそれらの暗号を解読する天才たちの戦いに 読んでいくうちに引き込まれます。
皆が難しいと思っている暗号解読を 本書では 過去の事例などを出しながら面白くわかりやすく説明されています。推理小説やスパイ映画などでしか見ないと思っていた暗号が 意外にも自分たちのすぐそばにあることにとても驚 きました。小さなころに遊びで文字を入れ換えて暗号化などと遊んでいた人がいたように自分たちで暗号化したり、皆が使っているスマホやパソコンにも暗号化が大きく関わっていたりします。
暗号化して当人たち以外のものに見られないようにしていても、作るための法則があるならそれさえわかれば簡単に復号化されます。暗号化した密書を解読されて処刑された女王や、暗号化して戦争に勝利したものなどいろいろなエピソードが楽しめるものとなっています。
本書では、文系の方々でも理解しやすいように説明されています。著者である サイモン・シンは 難しいものをかみ砕いて説明することに長けている方だと思います。 難しい説明も図解付きで解説しています。謎解きや暗号に興味がある方に是非お勧めしたい作品となっています。

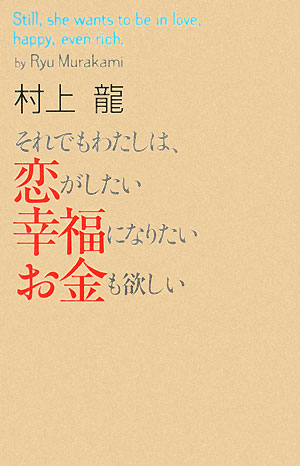 知能情報学部 4年生 Kさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
知能情報学部 4年生 Kさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)