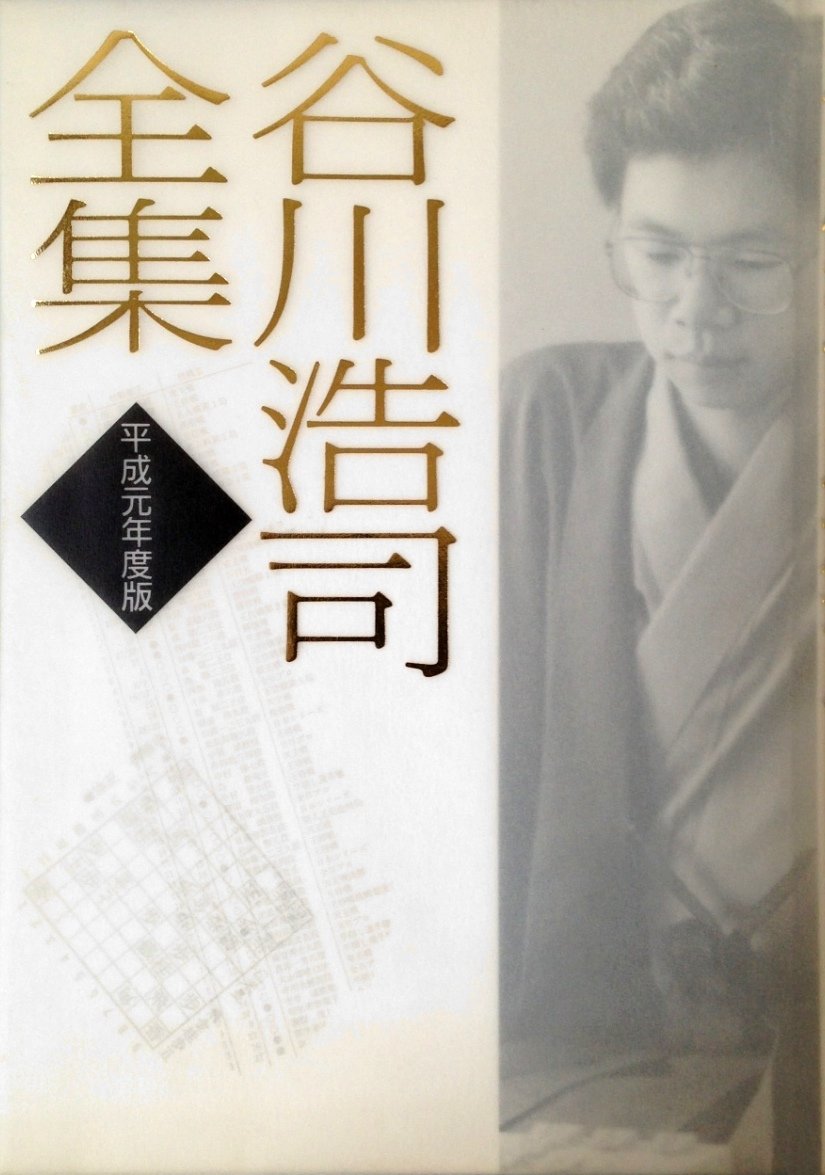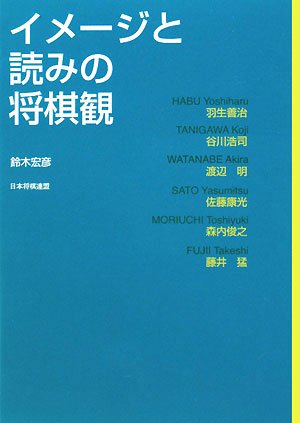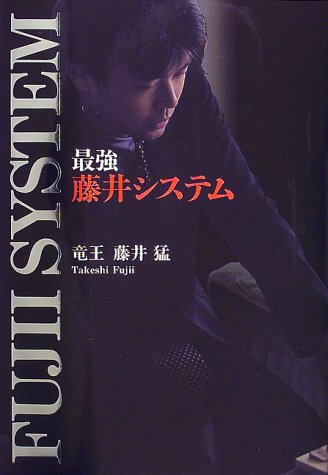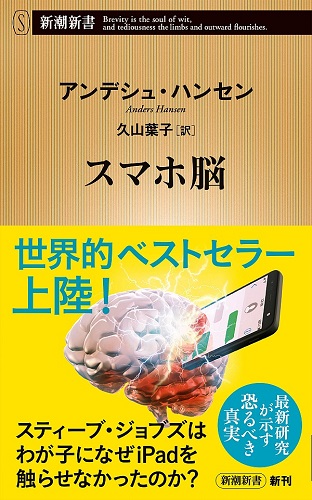図書館報『藤棚ONLINE』
文学部・安武留美先生 推薦『夢酔独言/Musui’s Story』

『夢酔独言』
勝小吉 著、勝部真長 編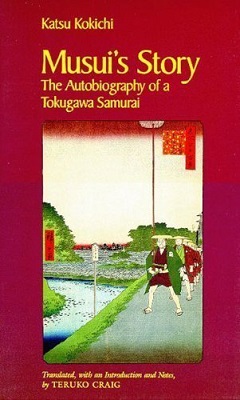
“Musui’s story : the autobiography of a Tokugawa samurai”
Katsu Kokichi ; translated, with an introduction and notes, by Teruko Craig
最近話題を呼んだNHK BS ドラマの「小吉の女房」をご存知ですか?
このドラマは、勝海舟の父親小吉が、自分の歩んだハチャメチャな人生を猛反省し自ら反面教師となるよう子孫に書き残した話がベースになっています。勝海舟の伝記や研究書で引用され『海舟全集』にも収録されたというこの話は多くの人の目にとまり、編集されて勝小吉の自叙伝『夢酔独言』として日の目を見ました。
BSドラマで古田新太演じる小吉は、原作を基に書かれた子母澤寛の小説『父子鷹』に出てくる「正義の味方」的要素の強い善良な人物ですが、『夢酔独言』から浮かび上がる小吉と家族の姿はもっと複雑です。小吉は、特権階級である下級武士の妾の子として生まれ、幕末の大きな社会変化に対応できない旧態依然の身分社会で永久的失業者として生きていかねばならず、決死の覚悟でその不運や社会の矛盾に抗う不良者です。またドラマでは沢口靖子演じる良妻賢母の「小吉の女房」が原作に登場することはほとんどなく、唯一の逸話には、小吉が他の武家の女性に惚れ込んだ時、彼女が自分の命と引き換えにその女性の家族と談判しようと申し出る様子、そして小吉がその妻の苦労と献身に周りの助言で気づくことが書かれています。一家は幕府から授かる扶持(年金)だけでは極貧の生活を強いられるのに、小吉は武士、町人、農民、乞食、ならず者の境界線を行き来しながらやりたい放題、つまり『夢酔独言』は今の常識−特にフェミニスト的視点−からするととんでもない話ばかりです。それでも、矛盾に満ちた社会の中で一本筋を通しながら着実に自分の居場所を築いていった小吉とその周りの人々の姿には、考えさせられたり気づかされたりすることも多いのです。
ここに挙げたのは入手しやすい勝部真長氏の編集した当時の文体そのままの『夢酔独言』です。勝部氏による現代語訳版は絶版なので、Teruko Craig氏が平易な英語に訳したMusui’s Storyも挙げておきます。実はMusui’s Storyはアメリカの大学の(学部生向け)日本史授業の副読本として人気があり、古文書に読み慣れない方々にお薦めします。