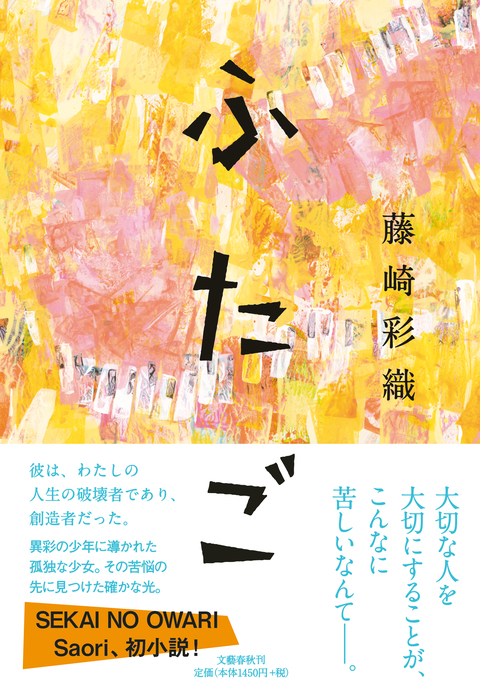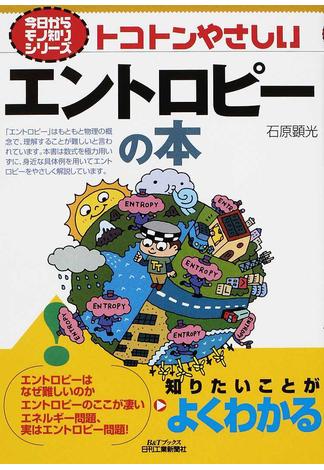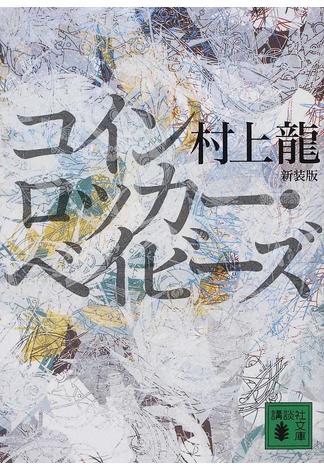
法学部 1年生 Oさんからのおすすめ本です。
書名 : コインロッカー・ベイビーズ
著者 : 村上 龍 著
出版社:講談社
出版年:2009年
みなさんは「コインロッカーベイビー」という社会現象を知っていますか。
コインロッカーベイビーとは、鉄道駅などに設置されているコインロッカーに遺棄された新生児のことです。コインロッカーに新生児を入れることには、遺棄した側の匿名性が保持されやすい、異変に気づいても第三者が中を確認することは難しい、そもそもコインロッカーに人間を入れることが想定外であるという特徴があります。
そのため、1971年にコインロッカーで乳幼児の死体が発見されて以来この問題はどんどん深刻化し、1973年には大都市のターミナル駅を中心に46件の遺棄事件が発覚しました。この問題を題材にして書かれたのが、『コインロッカー・ベイビーズ』です。
この本の主人公のキクとハシは、生まれてすぐコインロッカーに入れられます。コインロッカーに入れられた子どもは殺されてから捨てられている場合もありますし、生きたまま入れられても亡くなってしまうことが多いのですが、キクとハシは奇跡的に助かりました。
それから2人は乳児院で育てられますが、行動から病気かもしれない、ということで精神科医に連れていかれました。そこで乳児院のシスターたちは精神医から、生後わずか数十時間でコインロッカーの中で死に直面し覚えたであろう無意識下の恐怖、自分の肉体がそれに抵抗して打ち勝ったこと、2人を生き延びさせた強大なエネルギーの3つが脳のどこかにセットされており、そのエネルギーが自分で制御できないほど強くなっている、ということを告げられます。そして、2人はそのままでは正常な成長が出来ないので、そのエネルギーを眠らせる治療をすることになります。その治療法が、胎児が母親の体内で聞く心臓音を聞かせて2人をもう一度母親の体内にいた状態(強大なエネルギーを持つ前)に戻す、というものでした。
治療は順調に終わり、シスターたちは最後に精神医から、変化した(変化をもたらした?)のが自分たちであることや、心臓の音を聞いて治療をしたことは人には教えてはいけないと言われました。
乳児院で過ごしていたキクとハシは小学校入学の一年前に養子縁組が決まり、それからは里親に育てられました。2人が中学生になってしばらく経ったある日、あることがきっかけで、ハシが幼い頃病院で聞いた心臓の音をもう一度聞いてしまいます。それからというもの、ハシはあの日病院で聞いた音が分かるまで学校に行かないと言いだし、家にこもり、心臓の音を探すためにテレビから流れる音をずっと聞いていました。そしてついには理由も言わず東京へ家出をしてしまいます。ですがキクにはハシの行動が、母親を探すためだとすぐに分かりました。そんなハシを追うため、キクも東京に行きます。
ここからコインロッカーで生まれた2人の人生は大きく変わり、壮絶な人生を送ることになります。
私たちも、思い通りにならない事がたくさんあり、誰もが見えないコインロッカーに閉じ込められているかもしれません。そんな時にこれを読むと、閉ざされたコインロッカーから1歩踏み出すヒントをもらえるかもしれません。
ハシは自分の生みの親に出会えるのか、キクはハシを追って東京に行き何をするのか、2人の破壊劇を見届けてみませんか。

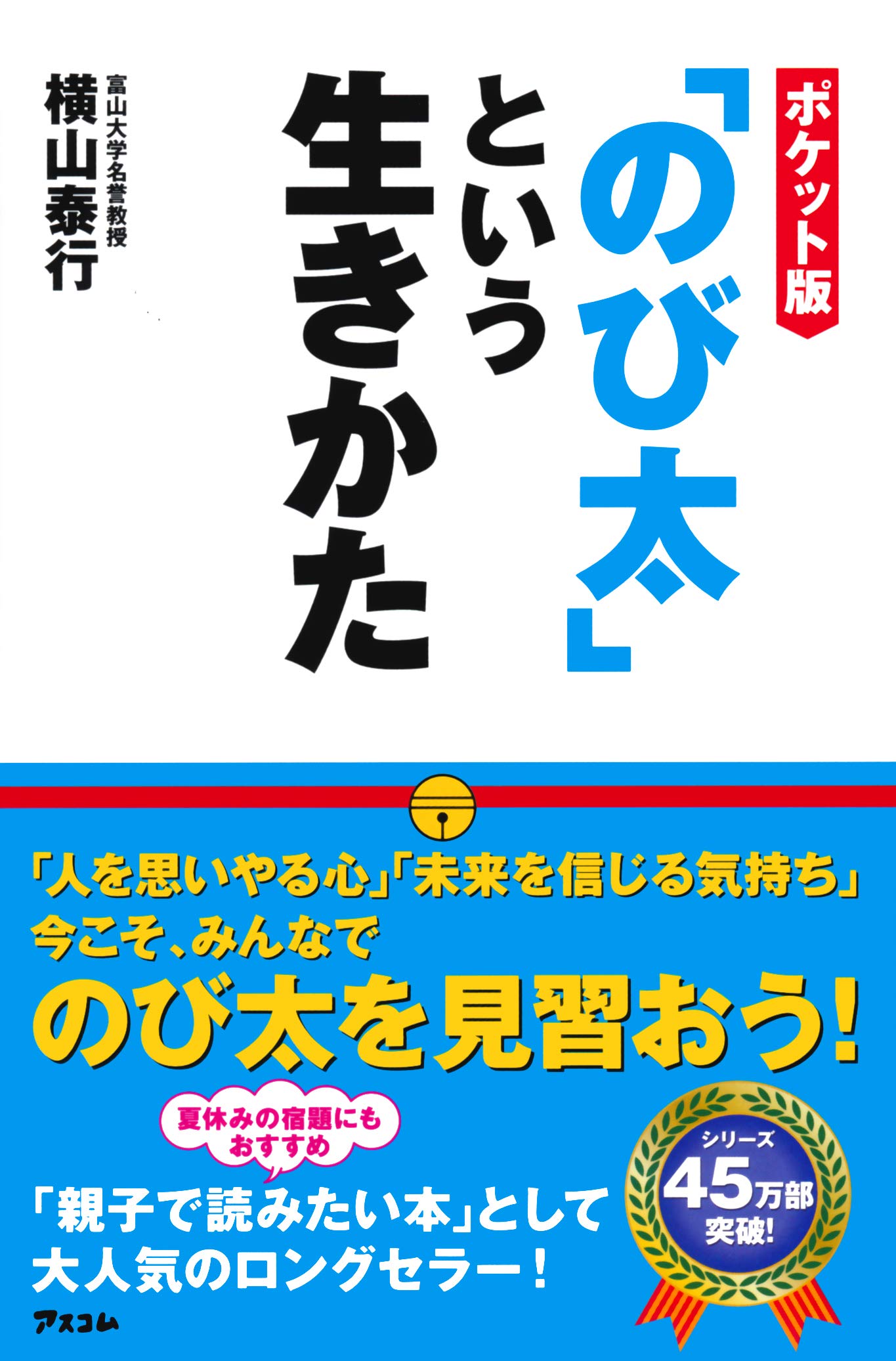
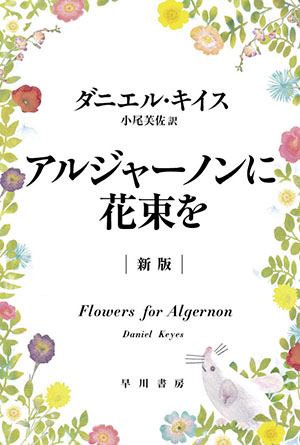
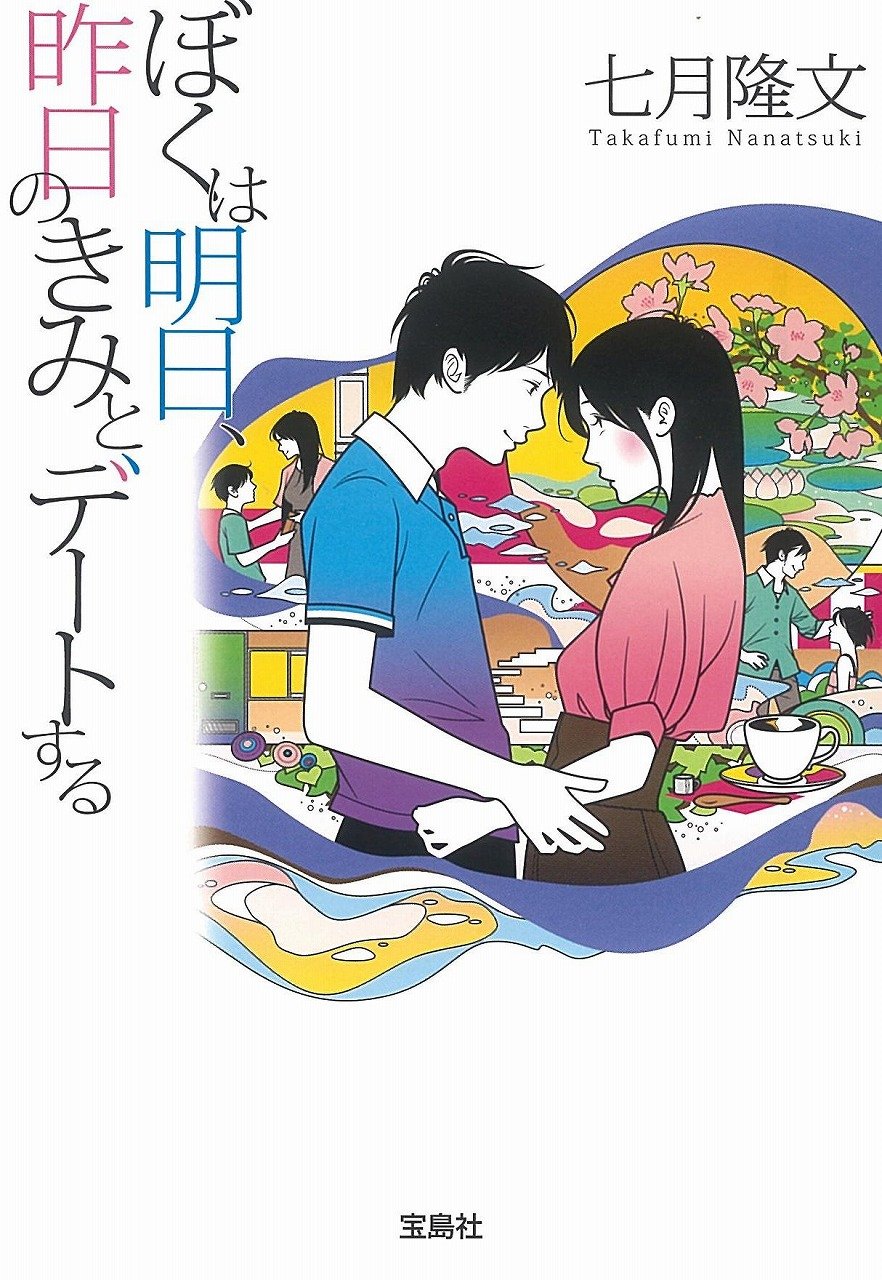 法学部 1年生 建内 桃さんからのおすすめ本です。
法学部 1年生 建内 桃さんからのおすすめ本です。