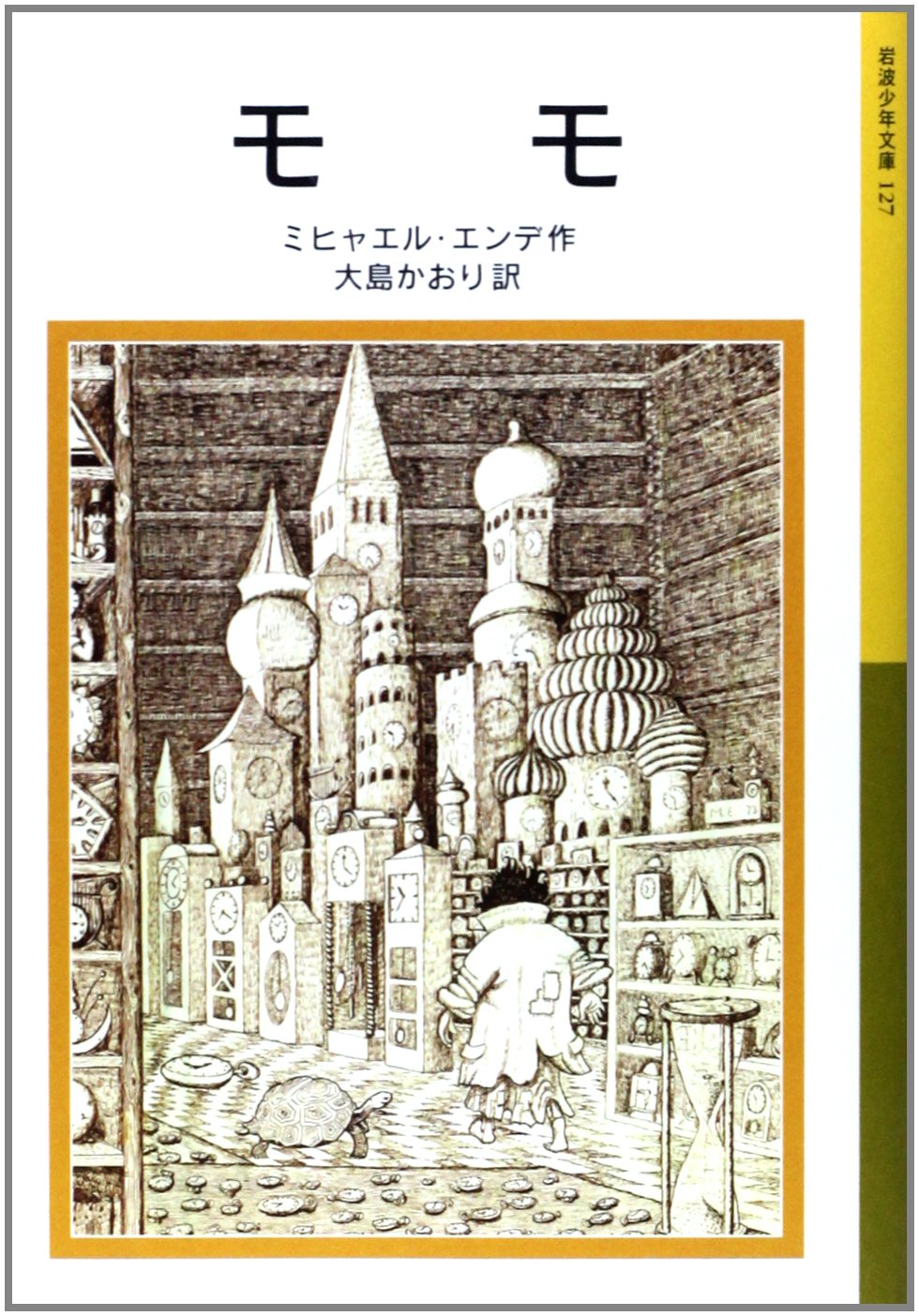
経営学部 4年生 大堀 舞佳さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : モモ
著者 : ミヒャエル・エンデ 著、大島かおり 訳
出版社:岩波書店
出版年:2005年
小学校の推薦図書の中に、この題名を見たことがある人も多いだろう。
だが、大人になった今!ぜひ読んでほしい1冊である。
主人公モモは身寄りがなく、劇場の廃墟にくらしている。髪や目はまっくろで、いつもはだし。お世辞にも清潔感があるとは言えないものの、この少女には、「ひとのはなしを聴く」特技がある。どんなに怒っていても、モモがはなしを聴けばたちまち怒りが収まるのだ。そんなモモには2人の友人がいる。道路掃除夫のベッポと観光ガイドのジジ。ベッポはいつものんびりゆっくり道路の掃除をし、ジジは本当かわからないような作り話(?)が得意。モモがくらす街はみんなおだやかでいい街だった。
しかし、そこへ灰色の男たちがやってくる。灰色の男たちはたくさんの煙を出す葉巻を吸い、みんな同じようなかっこう。互いを数字で呼び合い、せかせかと街の人々に話しかける。
「あなたはこんなに時間を無駄にしているのです。もっと節約しなければなりません」と言いより、時間を盗むのだ。みんな仕事をいやいやこなすようになり、子どもは学校につめ込まれてしまった。おだやかな街があっというまに灰色に染まってしまう。そんななか、灰色の男たちはモモが邪魔に感じてくる。モモは灰色の男たちの時間泥棒から逃げるため、カシオペイアというカメに助けを借りてマイスター・ホラというおじいさんのもとへ。
マイスター・ホラは時間をつかさどる。彼の話を聴き、モモは時間とはなんなのかを知っていく。灰色の男たちに立ち向かうため、モモとマイスター・ホラ、彼の仲間のカシオペイアが奮闘する。
この物語の素敵なところは、モモ目線の描写である。マイスター・ホラの家で食べる黄金のパン・あつあつのチョコレート。灰色の男たちから逃げるときの気持ち。時間の花から聞こえる音楽。これらが子どもらしい例えや言葉で豊かに描かれている。モモはいつも外からの刺激を全身で受け止める。この力が、「ひとのはなしを聴く」ときに活かされているのかもしれない。
大人になった今、しなければならないことに追われてせかせか生きてしまっている人も多い。私もそうだ。だが、本当にしなければならないことなどないのだ。時間とは時計で測り切れるものではなく、一瞬にも永遠にもなりうる。その時間をどう使うか、だれのために使うかを今一度考えるきっかけをくれる。
『モモ』はそんな作品である。

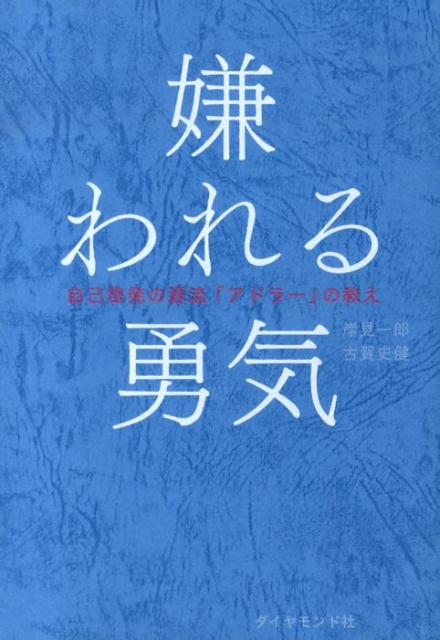
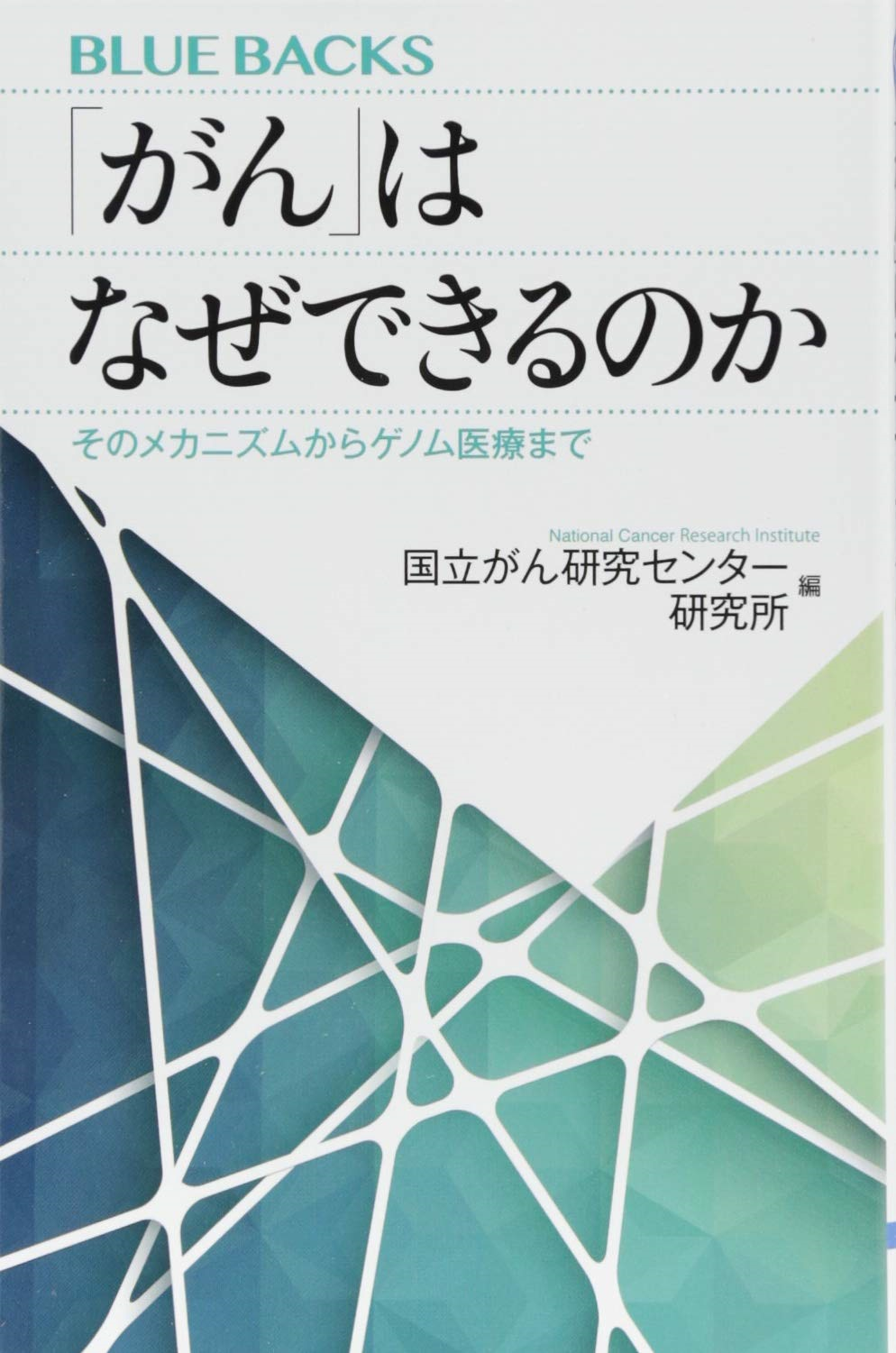
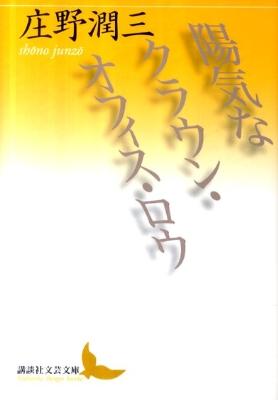
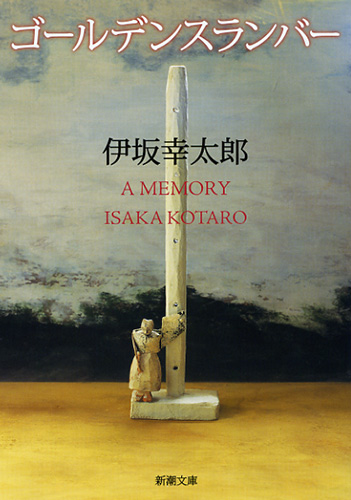
 文学部 2年生 畑田 亜美さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
文学部 2年生 畑田 亜美さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)