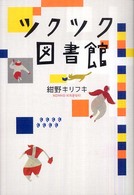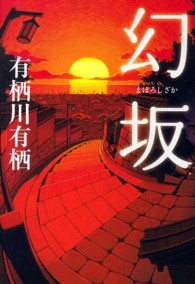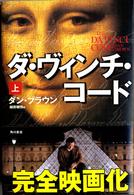書名: 徴候・記憶・外傷
著者: 中井久夫
出版者: みすず書房 , 2004.4 出版年: 2004年(初出2002年)
場所: 1階開架 請求記号: 493.7//2014
日本には、「中井久夫」という、精神科医がいます。
旧制甲南高校のご出身で、神戸大学医学部をご退官後、甲南大学大学院人文科学研究科でも教鞭をとっていただきました。阪神大震災直後から被災者の「こころのケア」に取り組まれ、平成25年度には文化功労者に選出されています。
つまり、この人が日本にいてよかったと思える人物の一人です。
本書は、1995年(阪神大震災)から2004年までに、中井先生が本学の臨床心理学専攻の学生・大学院生に向けた「心的外傷(PTSD)」や「記憶」についての講演や論文を集めたものです。
専門的な内容も含まれるので簡単ではありませんが、専門家外の人でも読むことができる本です。
まず、『「踏み越え」について』(p.304~328)を、読んでみていただけないでしょうか。
この論文は、甲南大学大学院人文科学研究科が行ったシンポジウムで発表され、同研究科の紀要『心の危機と臨床の知』4巻(2002.12)に掲載されたものです。
http://doi.org/10.14990/00002486
論文中の「踏み越え」(transgression)とは、「広く思考や情動を実行に移すこと」です。
実行するために「壁を越える」ことが必要な行為のことで、例えば、大学入学やファーストキスといった個人の成長に係る事例から、薬物や暴力、殺人といった犯罪や、テロや戦争などの反社会的な事例まで、様々なケースがあります。
思い返してみると、人生を決定する「踏み越え」は、熟慮した後に実行に移すことより、その場の雰囲気や勢いで行動してしまったことが多いのではないでしょうか。
中井先生は、太平洋戦争開戦時のご自身の体験や、精神科医として携わった症例などを基に、「踏み越え」を容易にする条件を整理・分析されました。そして、「実行に移さないように衝動に耐えて踏みとどまる」ためには、「自己コントロール」が重要であると結論付けられています。
とはいえ、どうすれば自己をコントロールできるようになるのでしょう。引用が少し長くなりますが、中井先生はこう述べています。
” 私たちは、「自己コントロール」を容易にし、「自己コントロール」が自尊心を増進し、情緒的な満足感を満たし、周囲よりの好意的な眼差しを感じ、社会的評価の高まりを実感し、尊敬する人が「自己コントロール」の実践者であって、その人たちを含む多数派に自分が属することを確信し、また「自己コントロール」を失うことが利益を生まないことを実際に見聞きする必要がある。
抑制している人が嘲笑され、少数派として迫害され、美学的にダサイと自分も感じられるような家庭的・仲間的・社会的環境は、「自己コントロール」を維持するために内的・外的緊張を生むもので、長期的には「自己コントロール」は苦行となり、虚無感が忍び寄って、破壊するであろう。戦争における残虐行為は、そういう時、呆れるほどやすやすと行われるのではないだろうか。
もっとも、そういう場は、短期的には誰しも通過するものであって、その時には単なる「自己コントロール」では足りない。おそらく、それを包むゆとり、情緒的なゆるめ感、そして自分は独りではないという感覚、近くは信頼できる友情、広くは価値的なもの、個を越えた良性の権威へのつながりの感覚が必要であろう。これを可能にするものを、私たちは文化と呼ぶのであるまいか。”
この本には、他10数編が収録されています。
他にも、評論や翻訳などが多数ありますので、一度蔵書検索してみてください。
また、『甲南Today』No.45,2014には、中井久夫先生へのインタビューも掲載されています。
合わせてご参照ください。
>http://www.konan-u.ac.jp/kouhou/pdf/today45.pdf