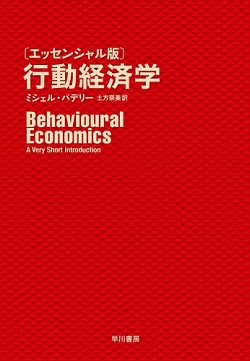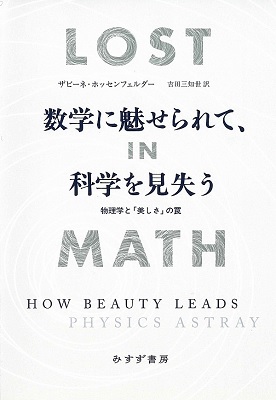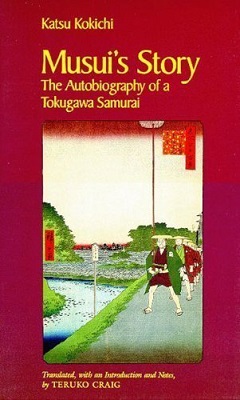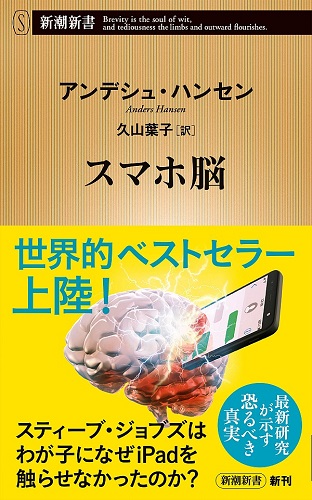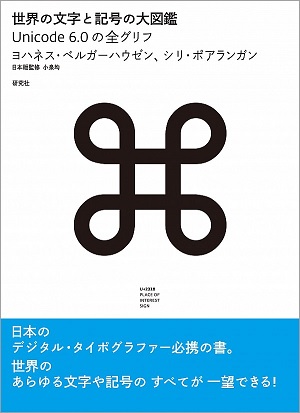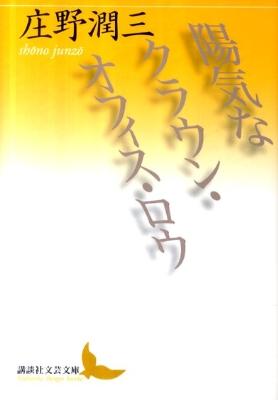図書館報『藤棚ONLINE』
図書館長・笹倉香奈先生(法学部) 推薦
新しい年度が始まりました。
コロナウィルスに翻弄された昨年度を経て、今年度はどのような1年になるでしょうか。私は1年ぶりに大きい教室での対面の講義をすることができました。オンライン講義では分からなかった学生の皆さんの反応を確かめながら、対面講義の楽しさを実感しています。
これからも波はあると思いますが、少しずつ日常が戻っていくことを願っています。引き続き、体調管理や感染症対策に気をつけながら大学生活を過ごしましょう。
図書館でも万全の対策をして、新学期を迎えています。
さて、今日は『スマホ脳』という本をご紹介します。
皆さんは一日にどれくらいスマホを見ているでしょうか。
スマホは時計代わりにも、パソコン代わりにも、本代わりにもなります。もはや、仕事でもプライベートでも、なくてはならない生活の一部になっています。常にスマホを持ち歩き、ふとしたときにすぐ取り出して操作する。バッグの中に見当たらなければ、財布が見つからない時以上に焦るのではないでしょうか。
一度「スクリーンタイム」を見て、自分が一日にどれくらいスマホの画面を見ているのかチェックしてみて下さい。きっと驚くような数字が目に飛び込んでくると思います(私はそうでした)。
本書は、スマホが私たちの脳にどのような影響を与えるのか、そのメカニズムはどういうものなのかということを解き明かします。筆者は、スウェーデンの精神科医です。数多くの研究を参照し、人間の脳の生物学的メカニズムから出発して、スマホが私たちの脳にどのような影響を与えるのかを考察します。
人間の脳は、実は現代社会に適応していません。20万年前に地球上に現れてから99.9%の時間、人間は狩猟や採取をして生きてきました。人間の脳は、いまだに当時の生活様式に適応するようにできており、めざましく発展した現代社会に適応するようにはできていません。この「ミスマッチ」から様々な問題が生じることになると本書はいいます。
例えば、進化の過程から見れば、脳は常に「新しいもの」を欲します。周囲をよく知れば、生存の可能性が高まるからです。そこで、新しい情報を獲得すると脳はドーパミンを放出するようにできています。新しい情報を得ると、脳の報酬システムが作動し、さらに情報を得る過程で「得られるか得られないかわからない」というときの方が、ドーパミンが増えるようです。スマホやSNSはまさに、このメカニズムに直接的に働きかけているのです。スマホやSNSをいじればドーパミンが放出され、その結果、脳はハッキングされてしまうのです。このようにして私たちは「スマホ中毒」になっていくわけです。
このほかにも、スマホが記憶力や集中力を弱め、メンタルヘルスや睡眠を阻害していくメカニズムを本書は明らかにします。デジタルの発展が余りに早く、デジタルライフが人間に与える影響についての研究が追いついていないため、その影響の全体像を我々はつかめないでいるというのが現状のようです。
本書は最後に「では、どうすればいいか」について具体的なアドバイスもしていますが、基本的な考え方は「人間がテクノロジーに順応するのではなく、テクノロジーが私たちに順応すべき」だということでしょう。スマホやSNSは、人間の依存を引き起こすように巧妙に開発されています。だからこそ、テクノロジーには大きな落とし穴があることを意識しなければなりませんし、私たちが心身ともに健康でいられるような、「人間に寄り添ってくれる製品」を求めなければなりません。人間の脳のメカニズムを理解し、デジタルライフから受ける影響を認識して賢く対応しなくてはならないのです。そのためにコンパクトにまとめられたヒントを、本書は与えてくれます。
電車に乗ると、9割の人がスマホを凝視しているという、ひとむかし前には考えられなかった異様な風景が出現しています。コロナ禍で社会全体のデジタル化が1年前に比べて格段に進みました。大学の講義もオンラインで行うことが日常の風景になっています。
そのような生活の中でも、テクノロジーに支配されないようにするために、たまにはスマホやパソコンの電源を切って見えないところに隠し、ゆったりとした気持ちで紙の本を手にとって、読書に集中する時間を作ってみてはいかがでしょう。
図書館は紙の本の宝庫です。館員一同、皆様を図書館でお待ちしています。
【図書館事務室より】
コロナに始まりコロナに終わった2020年度。2021年度もまだまだ翻弄される日々が続いています。しかしながら、『藤棚ONLINE』は新年度も平常運転!で頑張って更新したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
今年度も、第1号は図書館長の法学部教授・笹倉香奈先生よりおすすめ本をご紹介いただきました。甲南大学図書館にも所蔵がある本ですので、ぜひ読んでみてください!
オンライン授業に移行しつつありますが、図書館は通常開館しております。オンライン化に合わせてキャンパスも人の姿が減りつつありますが、対面授業の合間に図書館でゆったり読書というのも充実した時間の使い方ではないでしょうか。学生の皆さんのご来館をお待ちしています。