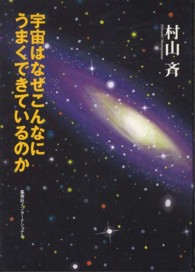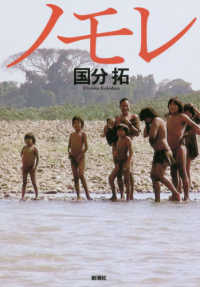図書館報『藤棚ONLINE』
須佐 元 先生(理工学部) 推薦
「宇宙はなぜこんなにうまくできているのか」という問いを発すること、あるいはこの事実に感嘆を覚えることができれば物理学の面白さの一端を掴んだ、ということになると思います。著者は極めて優れた素粒子物理学者・宇宙論学者ですが、可能な限り平易な言葉で物理学の面白さ、もっというとこの世界の不思議な調和について述べています。
我々の住む宇宙は人類が住むのに適したように、とても微妙に調整されています。様々な物理定数、例えばクオークの質量が少し違うだけで、この世界は似ても似つかないものになってしまいますし、宇宙が膨張する速度と「ダークエネルギー」の大きさとは不自然とも思える調整が行われ、宇宙に銀河や星、ひいては生命が誕生するのに適した環境が実現されています。そしてこの「不思議さ」は、それをよりシンプルな理論によって説明し、解消しようとする新たな研究の原動力となります。
この本では「自然科学の理論」についての考え方がそこかしこで語られています。
自然科学の理論の本質は、複雑な自然現象の中に法則を見出しそれを説明することにあります。
「自然界の原理や法則は、よりシンプルなほうが説得力がある。説明が複雑になればなるほど、そこには何か無理があるように思えてしまいます。」というくだりにあるように、できるだけ少ない法則によってシンプルに物事が説明できることがより良い理論の指標とされ、人はしばしばそこに美を見出し、深遠な宇宙の調和を感じることができます。
理系の人にとってはもちろんですが、文系の学生の皆さんにとっても読みやすく親しみ易い文章で書かれている良書です。
理論物理学や宇宙物理学について知りたいと思っている方にぜひ手にとっていただきたいと思います。