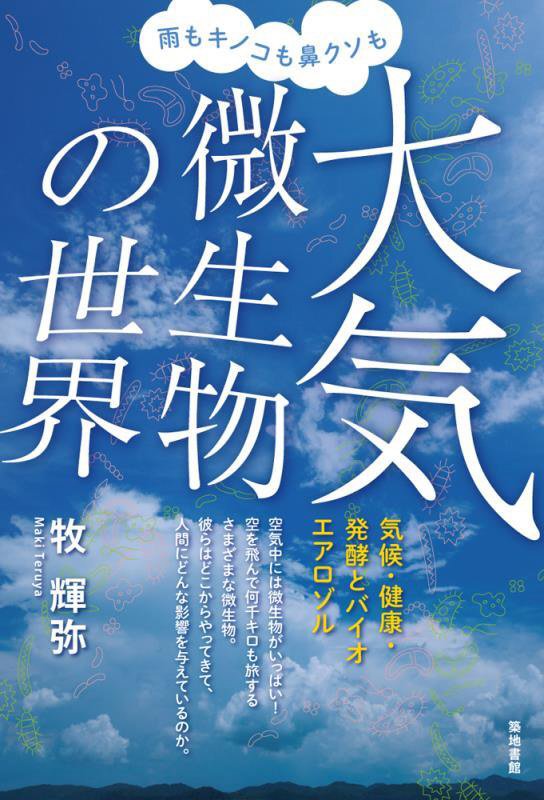
知能情報学部 4年生 Mさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : 大気微生物の世界 : 雨もキノコも鼻クソも : 気候・健康・発酵とバイオエアロゾル
著者 : 牧輝弥著
出版社:築地書館
出版年:2021年
一般的に微生物と聞くと、感染症や腐敗菌を思い浮かべ、よい印象を持つことは少ないだろう。実際、人に対し有害な種もあり、そのイメージは間違っているわけではない。しかし、微生物があるからこそ今の我々の生活があり、高等生物の進化につながったものもある。一概に微生物を、その恩恵や影響を考えずに悪者扱いすることは無理がある。
そんな微生物も研究が進展している最中であるが、大気中を浮遊する種、いわゆるバイオエアロゾルについてはまだわからないことだらけである。ここでも、大気中の微生物は悪影響を与えるものが想像されやすいが、実際には無害、もしくは有用な種も存在している。特に高度三千メートルの大気中の菌から納豆を作るという内容は、その先入観を覆すには十分な記事であった。本書ではここ十五年で盛んになってきた大気微生物に研究について、筆者自身の取り組みを交えながら、エッセイ風に紹介されている。
筆者の研究が一筋縄ではいかないエピソードが興味深くもあり面白く、特に衝撃を受けたのが中国の砂漠への出入りが禁止されたことに関係するエピソードである。黄砂発生源でのバイオエアロゾルの採取のためには中国の砂漠で観測する必要があり、それには中国の研究者との共同研究体制がなければ実現はしない。しかし、黄砂によって健康に良くない微生物が飛んできていると論文で発表したため、中国側からの反感を買ってしまい出入りが禁止されてしまった。
この時から、これまでのバイオエアロゾルによる悪い影響を調べるというストーリーが、よい影響を調べるというストーリーに変化した。その結果、美容医療、健康食品などにバイオエアロゾルの持つ効果を適用できないかの研究が進み、この過程で大気中の細菌から納豆を作り製品化することも実現した。実際に機内食としてこの納豆を紹介している記事を読んだことがあるが、このような背景があったことは知らなかったため、研究に対する熱意をこの本から改めて感じることができた。
微生物と聞いて、あまりよくない影響を思い浮かべてしまった方にこそ、この本を読んでもらい、様々な場面で我々の生活と密に関わっていることを知ってもらいたい。もしかすると、思わぬ形での関わりに気づくことができるかもしれない。
