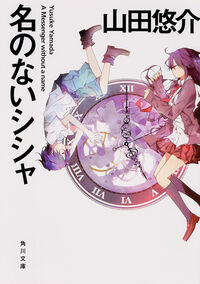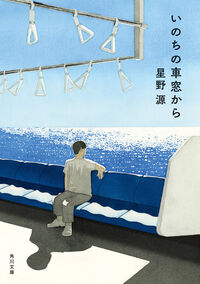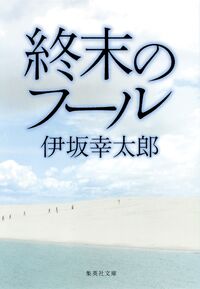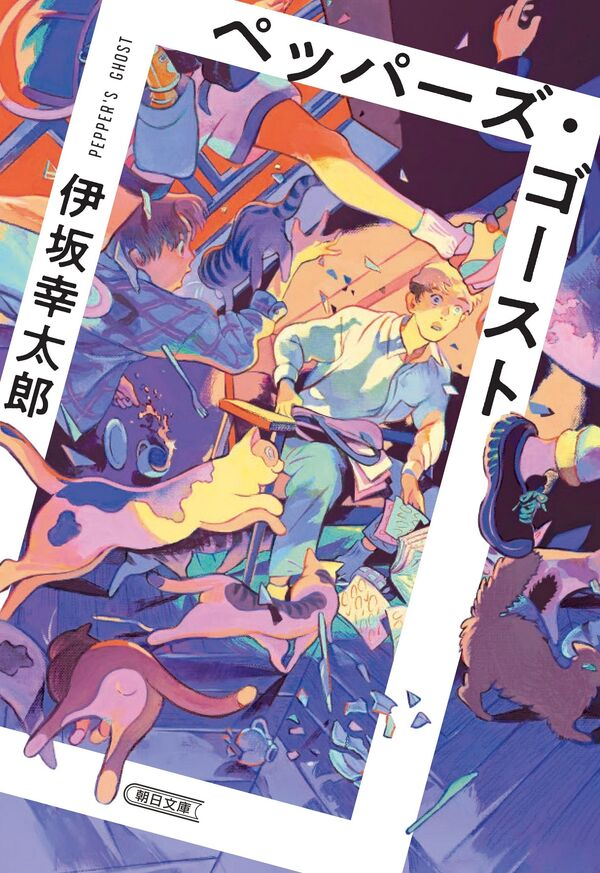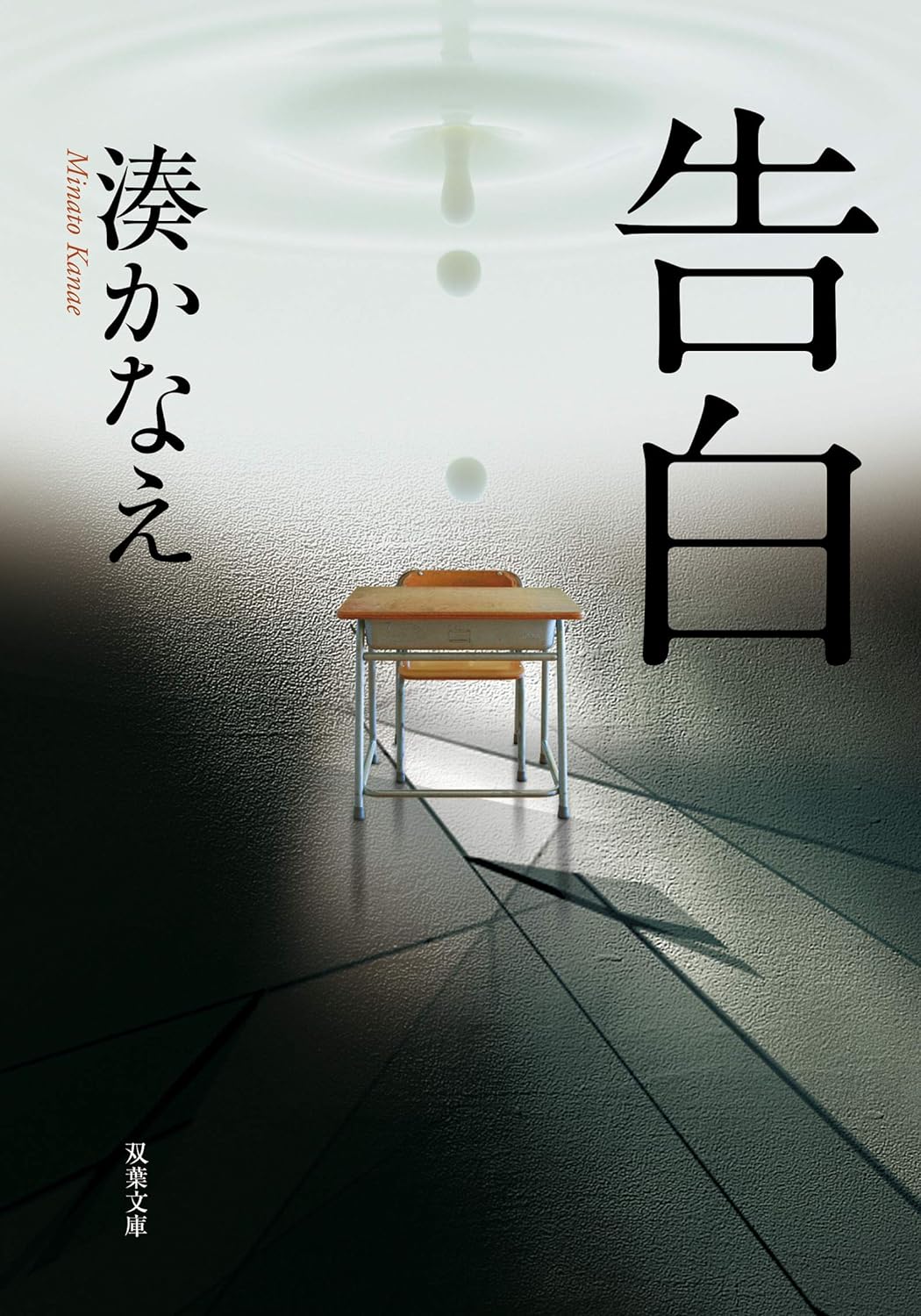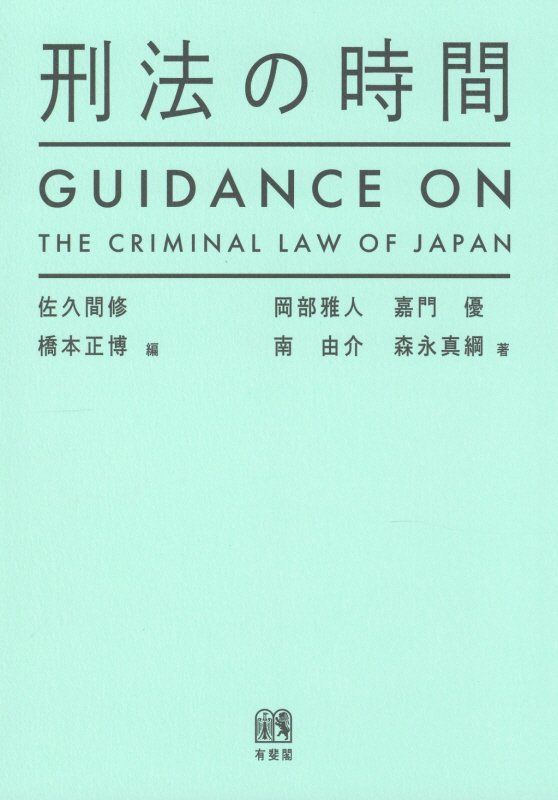
フロンティアサイエンス学部 4年生 島村 大地さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : 刑法の時間
著者 : 佐久間修, 橋本正博編 ; 岡部雅人 [ほか] 著
出版社:有斐閣
出版年:2021年
皆さんは、「刑法」というのにはどのような印象を持つでしょうか。例えば死刑や禁固刑などのワードからこわいものであったり、そもそも法律の一種ということから堅苦しいものだと感じるかもしれません。特に条文を開くと過失傷害や業務上過失致死傷など一見難しい言葉が何個もみられ、それだけみても理解が滞ってしまうかと思います。そういったときに、このような法律の用語がどのような意味なのか、またどのようなところで使われるのかなどを学べるのがこの『刑法の時間』という本です。
この本では、総論と各論という二部構成で分かれています。総論ではそもそも刑法とはなにかであったり、法律のなかで使われる過失と故意の違いであったりなどの言葉をかいつまんで解説しています。一方、各論では「窃盗罪とは」であったり、「詐欺罪と窃盗罪ってどう違うのか」であったりとそれぞれの罪状に関して論じています。実際に刑法を学ぶ際も同じように総論と各論というように分かれて学んでいくので、司法書士などの刑法を含む資格試験の最初の取っ掛かりにも最適だと思いました。
この本の特徴としては主人公たちが刑法のゼミに入りながら、それぞれの言葉や罪について会話形式で進んでいくのが大きな特徴です。そのなかで、様々なシチュエーションを交えて刑法の条文とそれに対応する解説を複合的に例示しながら理解していくような本となっています。例えば、SNSによる発言にたいして、どのような発言をすると侮辱罪や名誉棄損罪になるか、また、それらに該当せずとも不法行為に当たる可能性があるなどの具体例もここで示しています。そのため、読者からしても非常に理解しやすい構成になっています。
最後に、刑法など主に法律を学ぶ法学部というのは世間一般的には文系の学問として知られており、理系からはなかなか授業の機会が少ないと思われますが、そんな中でも、今回この刑法の本を読むことによって、「他の法律ではどうなのだろう」であったり、「この条文と別の条文ではどのような違いがあるのか」といった様々な場面に応用ができるような本だと思うため、文系理系問わず読んでみてほしいと感じました。是非判例などもみながらこの本で得た知識を活かしてほしいと思います。