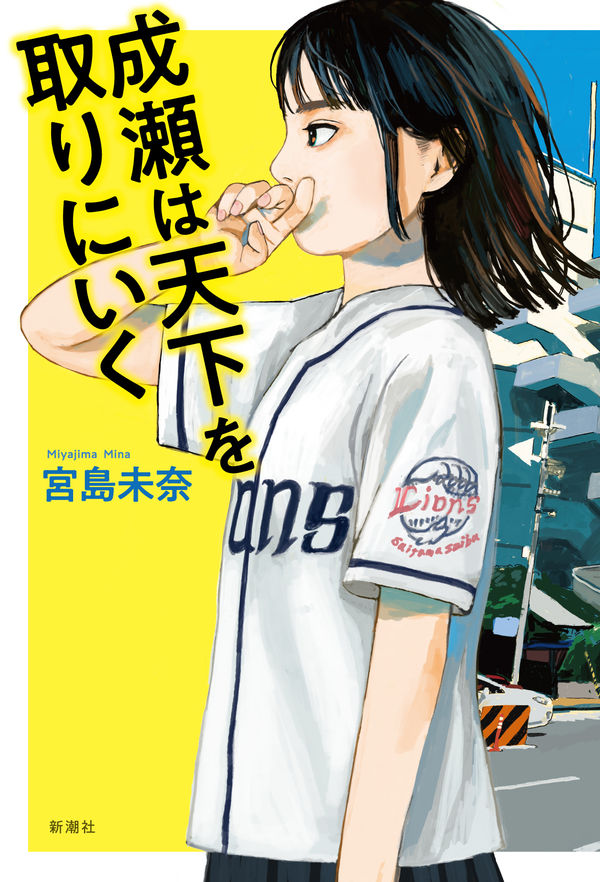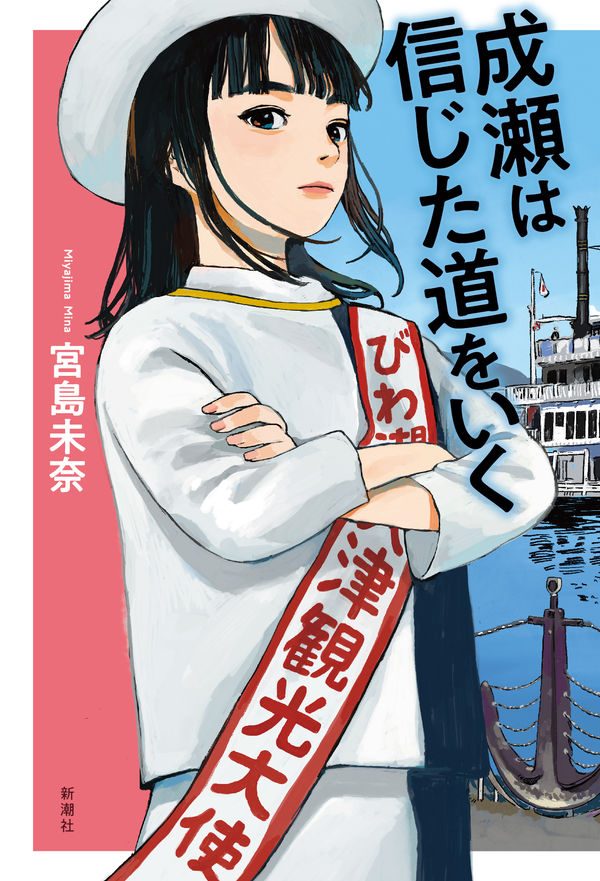図書館報『藤棚ONLINE』
甲南大学フロンティアサイエンス学部教授 赤松謙祐先生より
近年、「学生はあまり紙の本を読まなくなった」と耳にすることが増えました。スマートフォンやタブレットが身近になり、必要な情報を素早く検索できる現在、その変化はごく自然な流れとも言えるでしょう。電子媒体は利便性が高く、学習や研究においても大きな役割を果たしています。一方で、紙媒体に触れる機会が以前より減っていることも、また事実のように感じられます。
その影響と断定することはできませんが、学生のレポートや卒業論文を読んでいると、句読点の位置が少し分かりにくかったり、主語が省略されすぎて文意が一度ではつかみにくかったりする文章に出会うことがあります。いずれも致命的な欠点というほどではなく、少し整えるだけで読みやすくなる場合がほとんどです。ただ、「自分の書いた文章を、第三者がどう読むか」を意識する経験が、やや不足しているのかもしれないと感じることがあります。
そこでおすすめしたいのが、「紙の新聞を読む」という習慣です。新聞記事は、日本語表現のプロである記者が執筆し、さらに校閲のプロが丁寧に確認を重ねています。限られた紙面の中で、事実を正確に、かつ誤解のないように伝えるため、無駄のない構成と明確な日本語が用いられています。言い換えれば、新聞は「正しい日本語の実例集」とも言える存在です。
特に、新聞の一面記事は、国内外の重要な出来事を簡潔にまとめており、文章の骨格を学ぶのに適しています。毎日すべてを読む必要はありません。一面を中心に、10分程度目を通すだけでも十分です。これを継続することで、自然と「正しい文章のシャワー」を浴びることになります。新聞の記事内容は、新聞社によって傾向が異なりますので、1種類の新聞だけでなく幅広い種類の新聞を読めば、「物事に対する異なる見方、立ち位置」を学ぶことにもなります。
実際に、筆者の研究室では、長年にわたり学生に新聞を読むことを勧めてきました。全員が同じように効果を実感するわけではありませんが、日々の習慣としてきちんと継続した学生ほど、文章の構成力や表現の明瞭さが目に見えて向上していきました。特別な作文訓練を課さなくても、正しく書かれた日本語に触れ続けるだけで、文章感覚は確実に磨かれていくようです。
さらに新聞を読むことは、文章力だけでなく、社会への視野を広げることにもつながります。日本や世界が直面している課題、経済や科学技術の動向、文化や教育の話題などに日常的に触れることで、知識が点ではなく線として蓄積されていきます。これは、将来社会に出たときに求められる「社会人力」の基盤にもなるでしょう。
読む際には、ぜひ「朗読」も試してみてください。声に出して読むことで、文章のリズムや構造がより明確に感じられますし、発声や滑舌の練習にもなります。人前で発表する機会が多い大学生活において、プレゼンテーション時の発話能力向上にも役立つはずです。
このように、新聞を読むという行為は、特別な道具や多くの時間を必要とせず、文章力・語彙力・表現力を総合的に高めることができる、非常にコストパフォーマンスの高い方法です。図書館に並ぶ紙の新聞を、ぜひ一度手に取ってみてください。そこから始まる小さな習慣が、皆さんの「書く力」を静かに、しかし確実に伸ばしてくれるはずです。