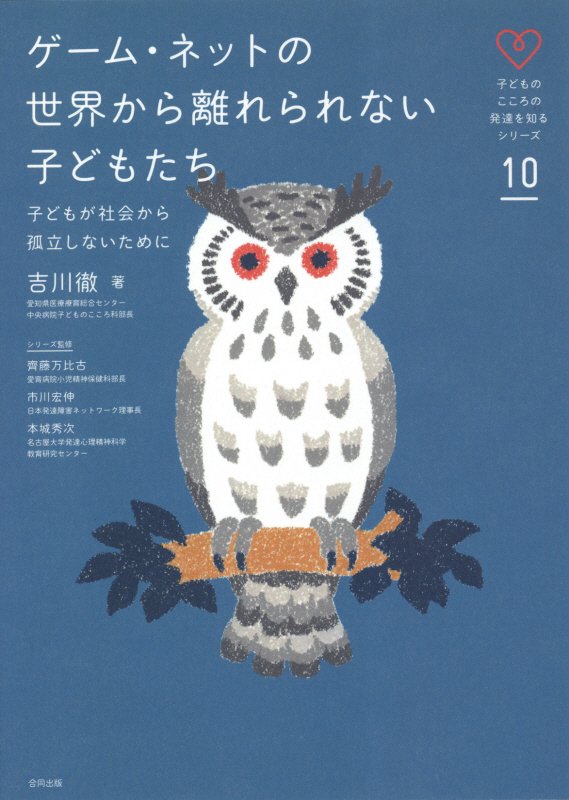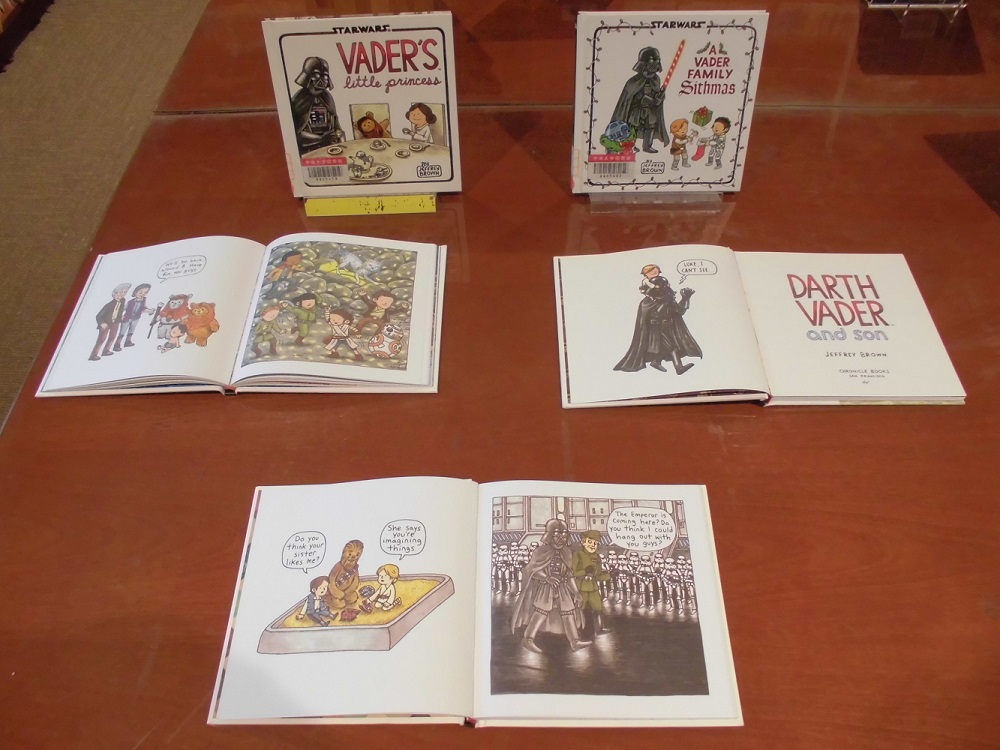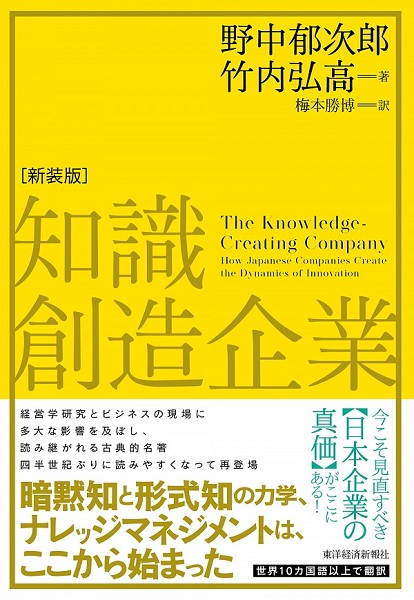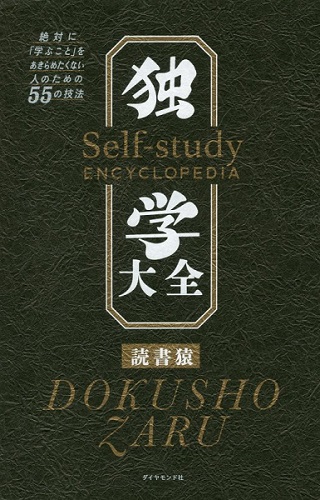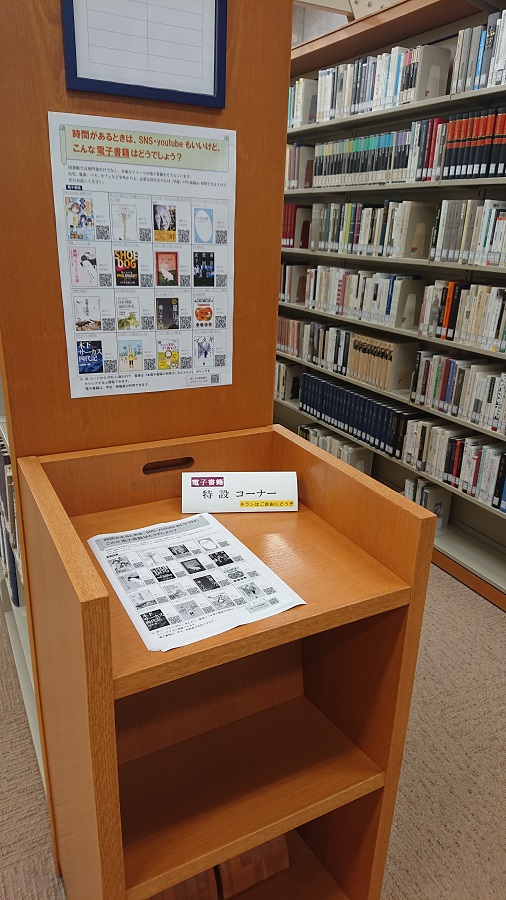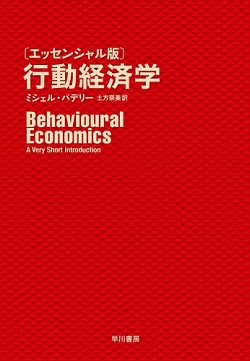図書館報『藤棚ONLINE』
知能情報学部・田村祐一先生 推薦
『 ゲーム・ネットの世界から離れられない子どもたち : 子どもが社会から孤立しないために 』
まず,はじめにお伝えしておくことがあります.本ブログがどのあたりの層に最も読まれているのか十分に把握しておりませんが,学生の方よりも教職員,特に中高生のこどもがいる方に最適な本です.
学生でも保護者からの干渉が強く,ゲーム・インターネットの利用についてことあるごとに色々と言ってくるという状況の方は知識として知っておいてもいいかもしれません.
さて,書評を始めます.はじめにこの本のタイトルからどんな印象をうけましたか?
私が最初にタイトルを見たときには,よくある「ゲームのやりすぎは良くない」「インターネット中毒」という内容の本かと思いました.(多分,そのような内容の本であれば読みませんでした.)
確かに,本書の中にはそのような内容もみられます.一方で,著者(児童精神科の医師です.)は豊富なデータとそのデータを考察し,客観的な見解を述べています.
例えば,巷でよく言われる「ゲーム脳」,「スマホ中毒」がそもそも明確に定義されていないことに驚くかと思います.
内容についてですが,9章構成になっていて,1~3章は若い世代とICTの関わりをSNSやゲームを題材として述べられています.
この部分が特に若い人の親世代が理解しづらいところかもしれません.一方でICTを利用している側からすると,知っていることばかりなので,すでに使っている人からすると,少し退屈な内容です.
4, 5, 6章は「発達障害とゲーム,子供」というような章になりますが,定型発達の人でも発達具合には個人差がある(発達障害と定型発達は地続きなのです)ため,「発達障害の人と自分とは別」と思わないで読むと,自分にも当てはまる部分があり,はっとさせられます.
6, 7章は使いすぎを防ぎ,使い方を身につける方法,さらにはもしも依存症になった場合にどうするのかについて,医師の立場から書かれています.
この部分はいわゆる「ゲームをやめる方法,スマホを使わずに済む方法」といったICT機器との関わりを0にする方法を説明しているのではなく,そもそも依存症とはどのような状況なのかの説明がされています.現代社会は長時間のインターネットの利用を「ネット依存」とすぐに決めつけ過ぎであり,ある時期に依存性があるように見えても,数年でそのような傾向がなくなるという記述もあり,スマホを取り上げるといった行動の危険性についても述べられています.
最後に,この書評で十分に本書の内容を述べらたと思いませんので,特に育児中の皆さん,さらにはZ世代と呼ばれる保護者のもとにいる皆さんが上の世代からはどのように見えるのかを知るために,一度手にとって読んでいただければと思います.