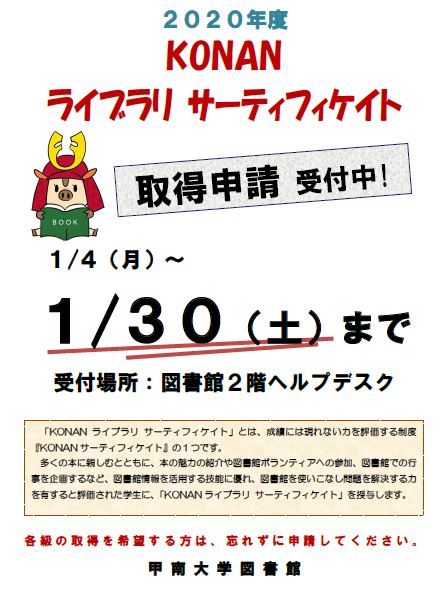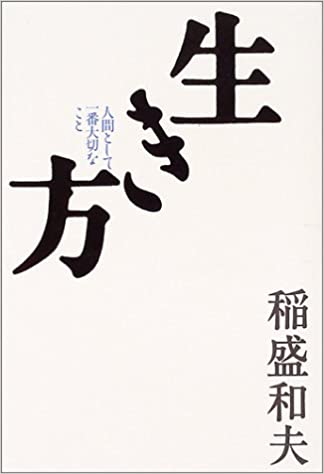文学部 2年生 畑田 亜美さんが、文学部 中辻 享 先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
Q. 本はよく読まれますか。
A. 研究や授業準備のために専門書や論文をよく読みます。
Q. 幼少期からよく読まれたのですか。
A. 小学生の頃はよく読みました。中学高校の頃は少し減りましたが、高校時代に友達の影響で読んだロマン・ロランの『ジャン・クリストフ』が本当に面白かったです。
Q. 大学生時代に読んだお気に入りの本はありますか。
A. ロシアの文学者、トルストイの本を読みました。同時代のロシアの文学者としては、ドストエフスキーもたいへん有名ですが、私はトルストイの方が好みです。トルストイの本は、風景描写が綺麗です。また、 『青年時代』の主人公や『アンナカレーニナ』のレーヴィンといった主人公に共感しました。日本なら太宰治です。著作をすべて読みました。その中でも『惜別』が特に面白いと思います。この他にも面白い著作がたくさんあります。太宰の作品は人間の弱みをさらけ出していますが、ユーモアがあるのでクスッと笑えます。サービス精神があります。そして、語りかけるような語り口に引き込まれます。また、太宰も風景描写が綺麗です。
Q. その本は現在の専門と関係していますか。
A. 直接は関係ありません。しかし、好きな作品はどれも風景描写が綺麗でした。太宰治の『津軽』は地誌のようで、読んでいると背景が浮かんできます。院生の頃に読んだロレンスの『息子と恋人』もそうでした。
Q. 地理学に関心を持ったきっかけとなった本はありますか。
A. 地理学へは中学高校の授業や時々テレビで見た旅番組から興味を持ちました。大学に入ってから梅棹忠夫の『モゴール族探検記』を読み文化人類学に興味を持ち、人文地理へ進みました。
Q. 現在のお気に入りの本は何ですか。
A. エミリー・ブロンテの『嵐が丘』です。授業のない夏季休暇中に読み、久しぶりにハマった一冊です。風景や景観描写が綺麗で、文章から光景が思い浮かびます。ブロンテは三姉妹で、全員作家です。今は姉のシャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』を読んでいます。
Q. 大学生におすすめしたい本は何ですか。
A. ・『嵐が丘』
・ルソー『告白』 これはルソー自身の半生におけるありとあらゆることを告白しています。「普通の小説より面白い」です。
・五木寛之『大河の一滴』
・アラン『幸福論』
・トルストイ『アンナカレーニナ』
感想: 教授の読まれている本には昨年初めて研究室に入った時から興味を持っていました。普段の授業のプリントなどに記されている参考図書で研究に関する本は目にすることがありますが、趣味の本を聞く機会は滅多にありません。
本は人柄をよく反映するので、今回話を聞く中でも教授の新しい面を知ることができたように思います。また、話を聞く中で興味を持った本がいくつかあるので、時間を作って読んでみます。
<中辻 享 先生おすすめの本>
エミリー・ブロンテ 著 鴻巣友季子 訳 『嵐が丘』 新潮文庫 , 2003年
(インタビュアー:文学部 2年 畑田 亜美 )

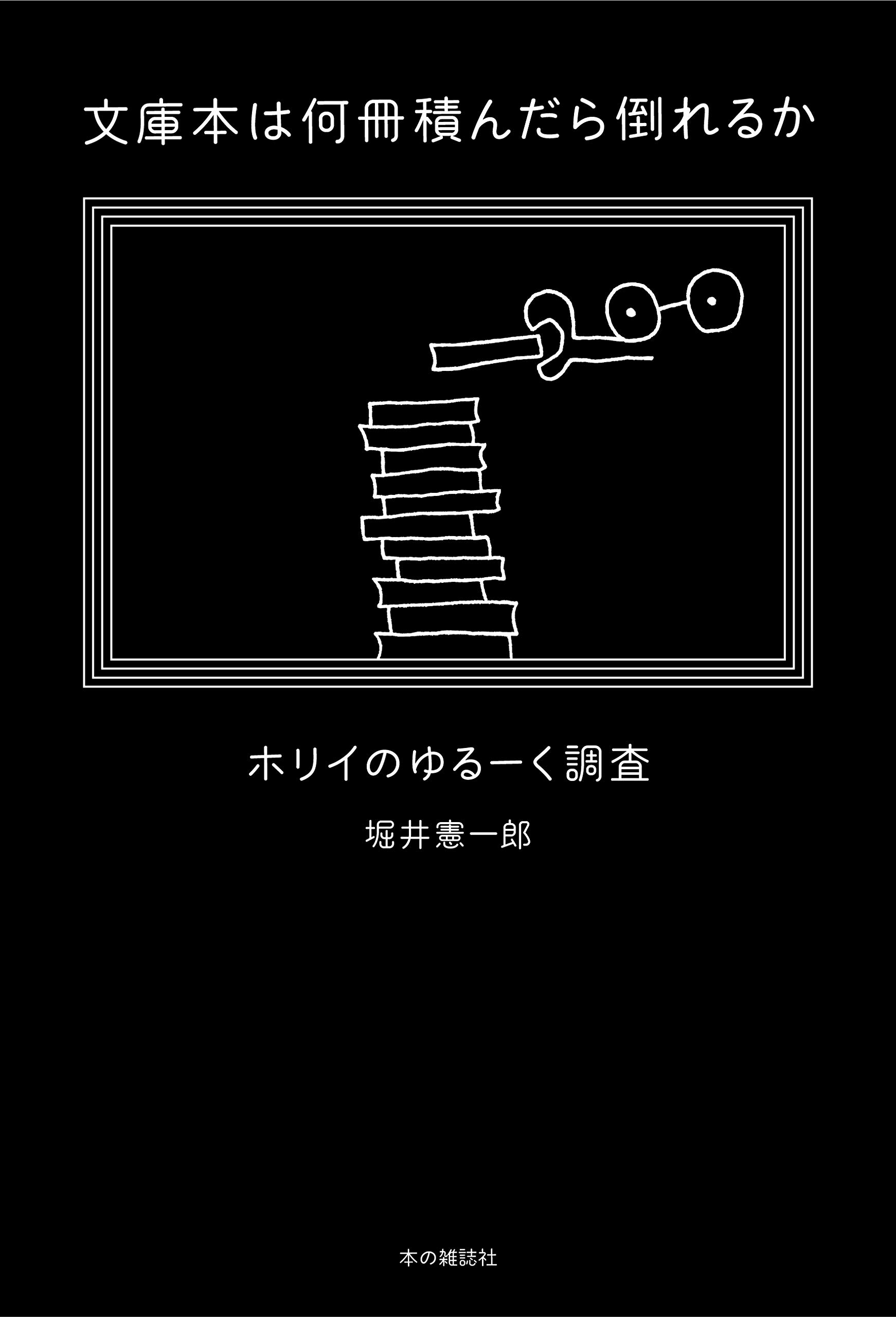
 文学部 2年生 畑田 亜美さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
文学部 2年生 畑田 亜美さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)