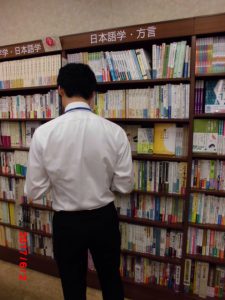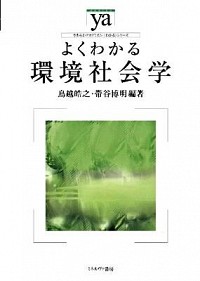2017年6月2日(金)、ジュンク堂書店大阪本店において、学生と図書館職員が店頭選書を行いました。当日は、図書館に置きたい本を書棚から選んで、 ハンディーターミナルを使って裏表紙に記載されたISBN(バーコード)をスキャンしていきました。
ご協力いただいた学生の方、ありがとうございました。 図書館では年1~2回、店頭選書を実施しています。 興味を持った人は是非次回参加してみてください。
選書した本は、近日中に図書館1階、新着コーナーの左隣に並べる予定です。 (一定期間を過ぎると通常書架に並びます。)
店頭選書参加学生の感想
**文学部歴史文化学科 金澤舞奈さん**
私は六月二日に行われた選書ツアーに参加しました。一言でいうと、非常に面白かったです。 参加した理由は、甲南ライブラリーサーティフィケイトの取得要件に入っていたのが一つ。あと、昨年から興味があったというのがもう一つ。参加するのには少しばかりの勇気がいりました。参加するといった連絡をするまでの過程であれこれ悩み、ただ連絡をするだけで緊張しました。ツアーはジュンク堂大阪本店で行われました。ここはとても広く、本の数も種類も多くありました。本を選んでも選んでも、気になる本が現れました。次はこの本が読みたいとかあの本を買いたいとか、気になる本を見つける度に思いました。まったくキリがありませんでした。夢中になって本を選んだので、自分が疲れ切っていることに気がつきませんでした。私は休息をとることを重視しなかったので、帰宅したころにはもうクタクタ。休憩をはさめばよかったと後悔しました。ツアーに参加して、私はまだまだ何も知らないのだと思いました。というのも、他の参加者が知らない本や作者について話していたのです。もっと読書をしなければいけない。もっと読書して、様々なことについて学ばなければいけない。そう、考えさせられました。
*************************************
**文学部日本語日本文学科 冨依佳央さん**
私が選書ボランティアをするのは二回目の事となります。前回初めて参加した時は当日少し緊張する事もありましたが、今回に至っては終始リラックスして選書をすることが出来たと思います。
この選書ボランティアを通して得ることが出来るものには、二つの大きな要素があると私は思っています。まず一つは自分自身の読んだことのないジャンルの本に触れ合えるという点です。書店を使う時は自分の興味のあるジャンルを主に見る人がほとんどだと思います。しかし、この場を通じて普段目を通すことのない学術書や自身の興味外のジャンルにも目を通す事で自分自身の視野を広げる好機にもなります。元々本を読む人にとってはこれまで以上に本に接する機会を増やせるものだとも思います。
もう一つは、普段本を読んでいる自分以外の視点で本に接する事が出来るということです。この選書ボランティアの目的は図書館の利用者を増やす事や、貸出冊数を増やす事にも目的を置いています。そのため、自分自身が読みたいと感じた本を選ぶという事もするのですが、どのような本が読まれるのかという事。どのような本を置けば利用者が増えるのかという事も考えながら選書をしたりしています。そのため、図書館司書の講義を受けている人にとってはより現場に近い場所を知る機会にもなり得ます。
これら二つが私自身が選書ボランティアを経験して感じた特に大きなものとなりますが、これら以外にも普段図書館で働かれている方々と図書館外でお話をさせていただくことによって、公私を含めてたくさんの本を読まれてきた方の意見を聞くことができたりします。これまで、あまり本を読む機会の無かった人でも本をより好きになれる機会なので、普段本を読む人読まない人に拘らず本をこれまで以上に好きになれる良い場であると私は思います。