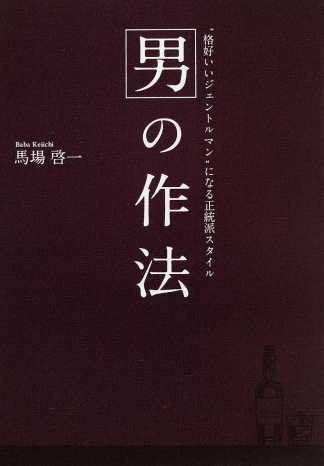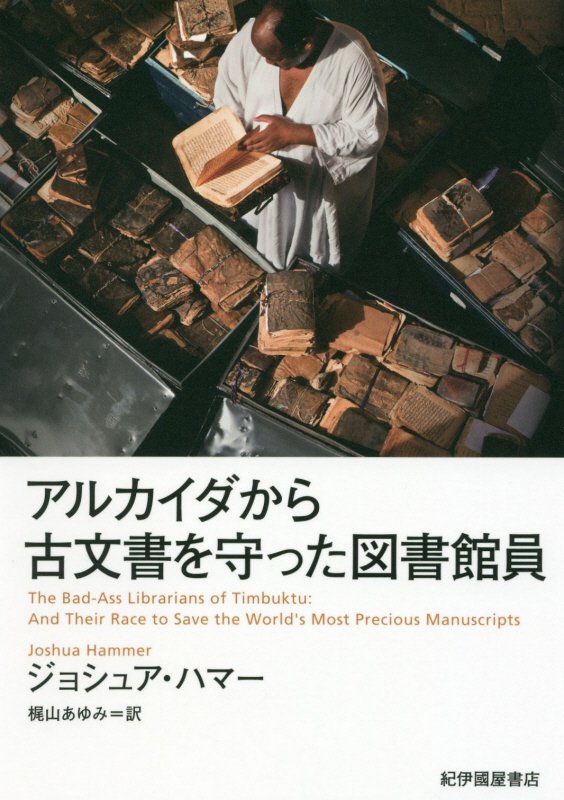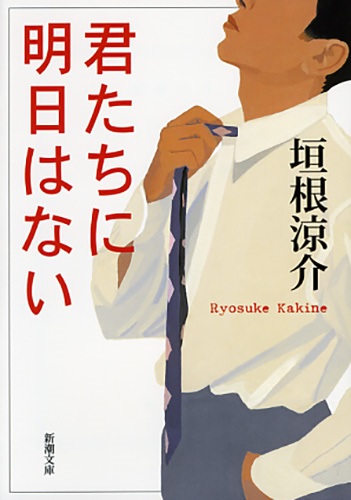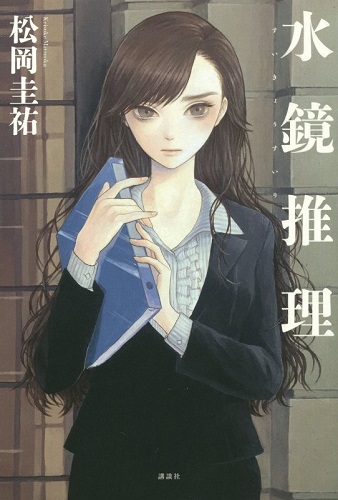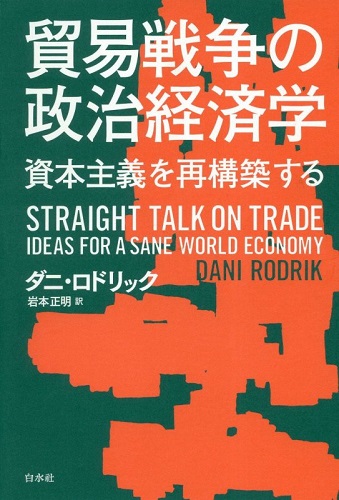法学部 3年生 松浦 亮介さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : 男の作法“格好いいジェントルマン”になる正統派スタイル
著者 : 馬場 啓一
出版社:こう書房
出版年:2008年
僕がこの本を手に取ったのは、イギリスの短期留学の後、英国紳士というものにあこがれ、この本の“ジェントルマン”という言葉にひかれたからでした。
まずこの本を読んで印象に残ったのは、著者が「型」というものを重んじていることでした。現代の社会では、失敗しましたがゆとり教育など、どちらかというと「個性」といったものが重んじられ、「型」は後ろ向きに捉えられてきました。しかし、「型に当てはまらない」ということが「個性的」であることなのでしょうか。「型」がない、ということは即ち手本がないともいえるのです。
手本がないということは、どう行動すればいいのか、どう考えればいいのかわからない、つまりアイデンティティの喪失につながるものなのです。しかし、確かに同じ「型」が100年、200年、1000年、2000年とその時代に通用し続けるということはありません。しかし、日本には守破離という言葉があります。これは、人から物を教わるときに3つの段階があり、守は言われたことを守る段階、破は今まで教わった人を超える段階、離は今まで教わった人を離れ、新しく独立して、今度は人に教える段階の3つに分かれるという考えです。少しずつ市はなるかもしれませんが時代に合わせて適合・進化することができます。
この本では、“格好いいジェントルマン”になるための「型」について説明しています。
まず、最初に説明していたのが、「背広」についてでした。本書では背広を大人になった証として説明しています。また、背広の色についても、紺がいいと断言しており、そこにはそれなりの理由が述べられていましたが、個人的には黒がいいなと思いました。
次に、酒場での流儀について言及しており、酒場ではタバコは吸わず、そして何より酔っぱらってはいけないと書かれています。そもそも酔うために酒を飲んでいる人も少なくないと思われるのですが、確かに、酔っぱらうと人に迷惑をかけるかもしれないし、何より飲んでいる酒の味がわからなくなるということもあり得ます。しかし、酒を飲んだうえで酔っぱらうなというのはかなりの難題だと個人的に思いました。
さらに、挨拶や手紙の書き方についても言及しており、企業や団体の中でもあいさつによって評価されることは少なくないが、「型」という考えが薄れ、挨拶という考えが弱くなっているとも書かれていました。
この本の中に書かれていることは、現代の若者、特に大学生から見れば古臭いものに映るかもしれません。しかし、個人的には、この本に書かれていることは一つの「見本」として、また、自分の中の「見本」を見つけるためのきっかけとして役に立つのではないかと思います。