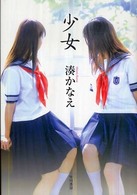☆新入生向けの図書案内
よく授業等で「先生、答を教えてください。」という質問(?)を受けることがあります。これまでの受験勉強の中では限られた問題のパターンを調べてその答を覚えるということが「賢明な」勉強法であったのかもしれません。しかしある問題に関して答を知り、それを覚えるということには実はあまり意味がありません。なぜなら現実世界の問題は、答があるのかどうかすらわからない類のものであるからです。覚えるべきなのは問題の答えがなぜそうなるのか、その原理を理解することです。そのためには眼前の問題を「ああでもない」「こうでもない」とひねくりまわしてみることが必要です。そうすると時間はかかりますが、その問題の輪郭が徐々に見えてきて、やがて本質が理解できるようになります。これが知識ではなく智慧を得るということであり、大学生活はまさに様々な智慧を蓄える時期です。問題の本質は何か、深く思考し反省するマインドを養っていただきたいと願います。
「寺田寅彦全集」―― 寺田寅彦著
寺田寅彦は明治から昭和初期にかけて活躍した物理学者で、日本における物理学者の草分けとも言える存在です。また夏目漱石と親交があったことでも知られています。寺田の物理学における研究は極めて興味深いものですが、一方で多くの素晴らしい随筆も残しています。その中に非常に短い「科学者とあたま」という随筆があります。この随筆の中で寺田は、「科学者はあたまが良くなければならないが、同時に悪くなければならない」ということを述べています。短いですので詳細は読んでいただければ分りますが、「あたまが『良い』人は見通しが効きすぎるために、単純で一見わかりきっていると思われる問題を調べようとしない。一方であまり見通しに効かないあたまの『悪い』人はそのような単純な問題を『非効率』に調べ続けるものである」、ということが述べられています。しかし大きな発見は常識を覆すことにあり、その意味であたまの「良い」人が素通りした、つまらない(と思い込んでいた)問題の中にブレークスルーの端緒が潜んでいるものであるというのが趣旨です。
これは科学的研究に関する話ですが、皆さんにもよく考えていただきたいと思います。試験対策でネットや先生、友達、先輩の情報を信じて答えを覚えるというのは、ある意味「賢明に」学ぶということなのでしょう。しかしそれでは決して得られない智慧が、愚直に自分の頭で考えるということによって培われていくはずです。学びにおいて、効率は確かに多くの場面で重要ですが、同時に短絡的に効率を求めるあまり、却って自分の真の能力を磨くチャンスを捨てているということを覚えておいてほしいと思います。「急がばまわれ」です。
甲南大学図書館報「藤棚」(Vol.34 2017) より