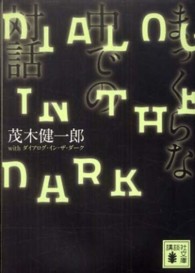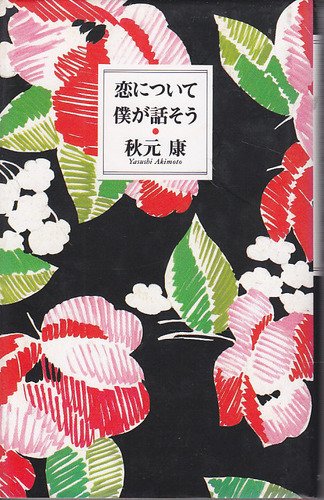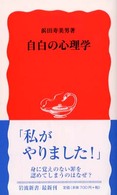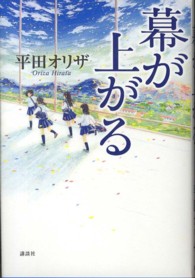文学部 4年生 水口正義さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名:まっくらな中での対話
著者:茂木健一郎
出版社:講談社
出版年:2011年
この本で取り上げられている、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」は、ドイツで発祥したエンターテインメントである。視覚障害を持つ人に連れられ、本当の暗闇の中に入る。その空間では、何も見えないながらも、そこに何が置かれているかを当てたり、食事をしたりする。それによって、人は何を感じ、人の中に何が起こるのかを、脳科学者の茂木健一郎が語る。内容の要旨ごとに評していきたい。
第一に、現代の人は光のある世界から逃げられないでいるという事実を、この空間に入って初めて知るという点。暗闇の中で目を開けて何も見えないとき、じっと一点を見つめたりして、目の前に何かを見ようとする。そこには、見えないという事実を受け入れたくないという気持ちと、見えるはずだという思い込みがあるという。何も見えずあたふたする人の、子供っぽくて、マヌケな様子が詳述されているところが評価できる。
第二に、光があるか否かで、人の感情はいとも簡単に大きく変容するという点。真っ暗闇の空間では、人の心は揺さぶられるという。何もしていなくても、ただ見えないというだけで、最初は不安に襲われ、次に慣れが起こり、最後には一種の安心感が得られるらしい。この感情の変容について、氏は体験者の一挙手一投足と語りを併せて分析しており、各段階の感情を理解する助けとなっている。
第三に、視覚障害者と健常者の話し合いから見えてくる事実が述べられる点。人間の知覚の一つがないことは、それがマイナスになっているわけではないと氏は述べる。目が見えないから何かをしてあげなければならないなどと考えるのは、たまたま目が見えている健常者の勝手な妄想であるということが、この空間に入った後のアテンドと健常者の知覚能力の差から読者に伝わるところが良い。
総じて、この一冊は暗闇の中にいる人がどうなるかだけが書かれているのではなく、そこから派生して、健常者の弱点、視覚障害者の考えと立ち位置まで書かれている点が特筆に値すると言えよう。