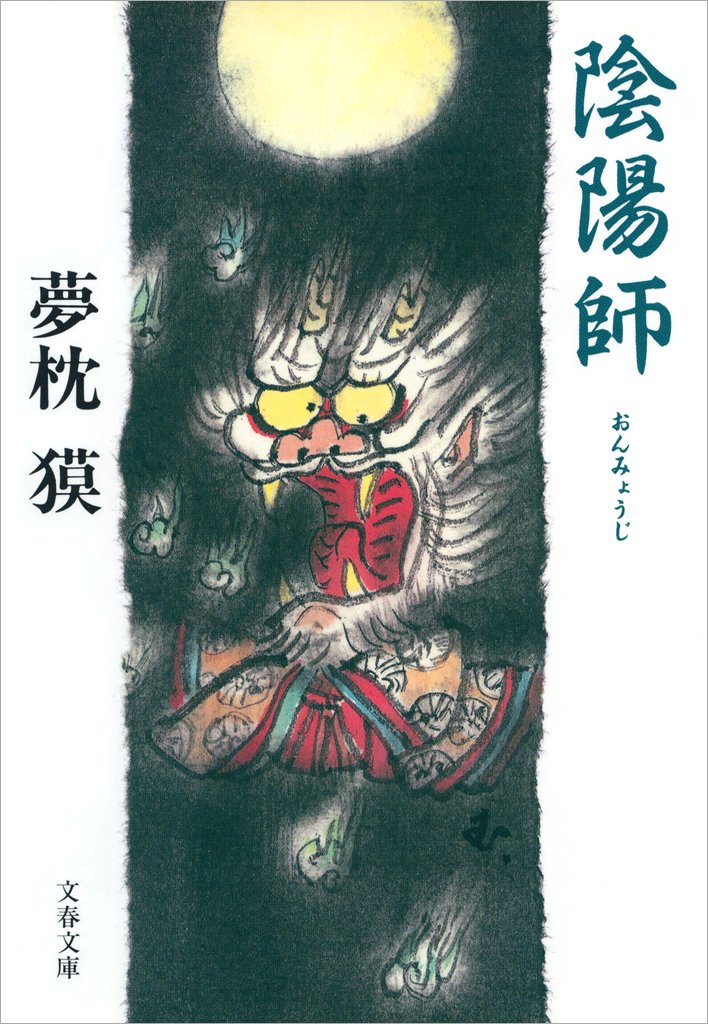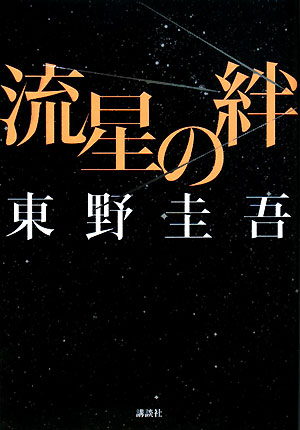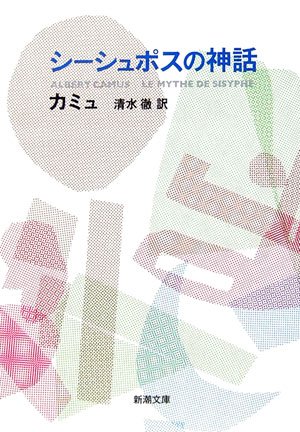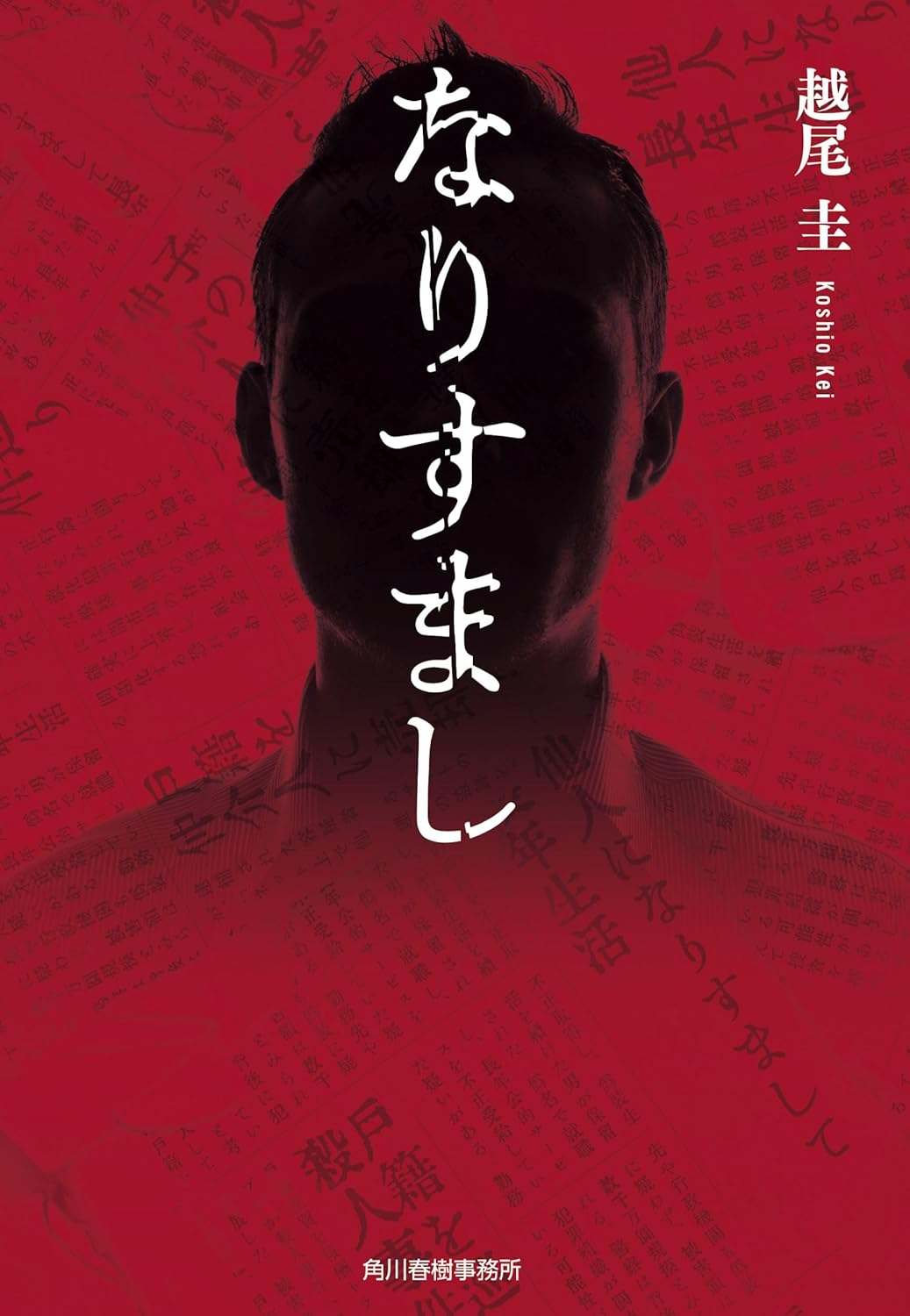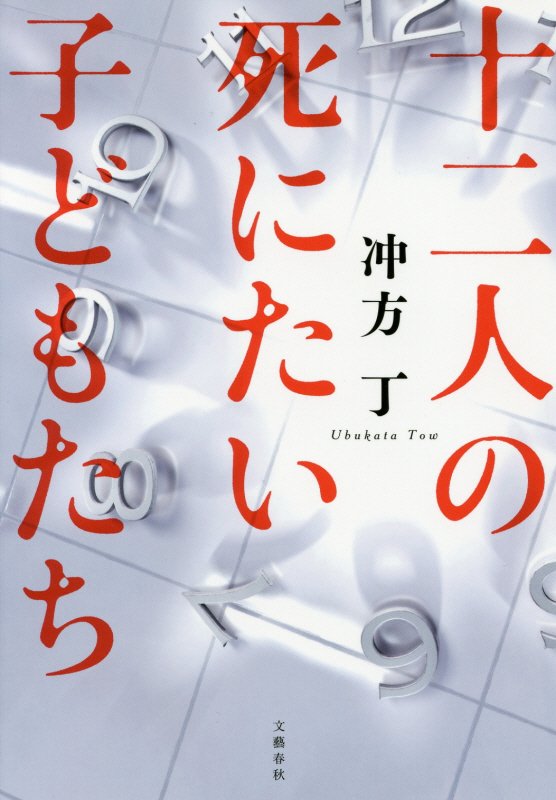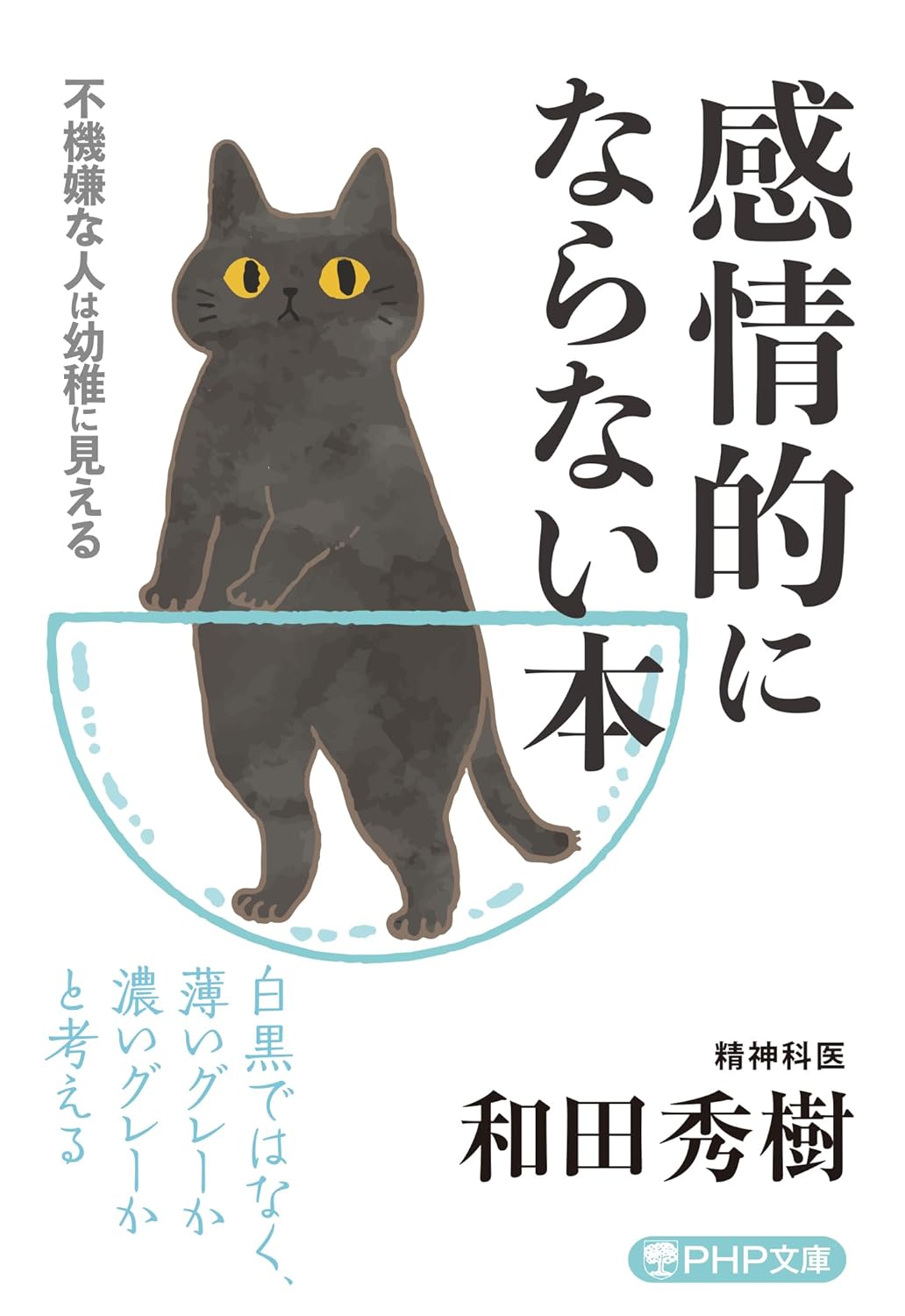
知能情報学部 4年生 Tさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : 感情的にならない本 : 不機嫌な人は幼稚に見える
著者 : 和田秀樹
出版社:PHP研究所
出版年:2020年
本書は、人間関係や社会生活の中で避けることのできない「感情の揺れ」を出発点に、穏やかに生きるための現実的な方法を提示する一冊である。雲が青空に浮かぶさまや、こんこんと湧く水の透明さといった比喩を用いて理想の心の状態を描きながらも、著者はそれが常に保てるものではないことをはじめから認めている。不満や怒り、不安、苛立ちといった感情は、電車に乗り、職場に向かうだけで自然と生じるものであり、それ自体を否定しない姿勢が本書全体を貫いている。
本書の特徴は、感情的になることを単純に「怒りの爆発」として捉えていない点にある。むしろ問題視されるのは、内向きに溜め込まれる怒りや不安、いつまでも頭の中を占拠するもやもやした感情であり、さらにはパニック状態に陥る心の動きまで含めて扱われる。精神医学の専門的な知見が背景にありながらも、語り口は平易で、日常の実感に即しているため、読者は自分自身の心の動きを重ね合わせながら読み進めることができる。
また、精神科医である著者自身が、感情に振り回されてしまう一人の人間であることを隠さず語っている点も印象的だ。専門家であっても感情は乱れるという率直さが、説教臭さを和らげ、むしろ信頼感を生んでいる。提示される方法も、感情を無理に抑え込むのではなく、揺れを前提にどう整えていくかに重点が置かれている。
本書は、感情を制御するためのマニュアルというよりも、感情と付き合うための視点を与える書である。読み終えたとき、心が劇的に変わるわけではないかもしれない。しかし、自分の感情を、少し距離を置いて眺めるきっかけを与え、穏やかな「感情生活」へ向かうための確かな足場を用意してくれる。その静かな効き目こそが、本書の持つ最大の魅力であると感じた。