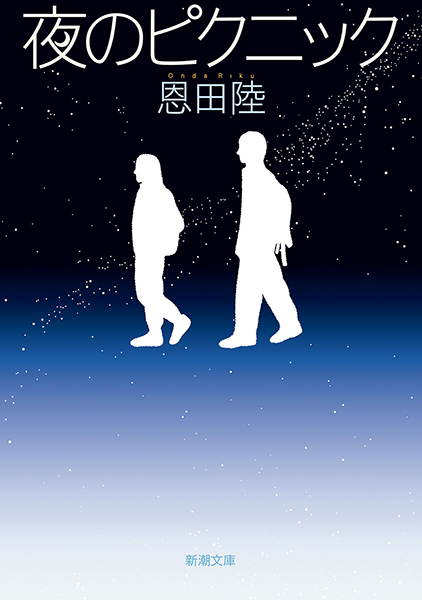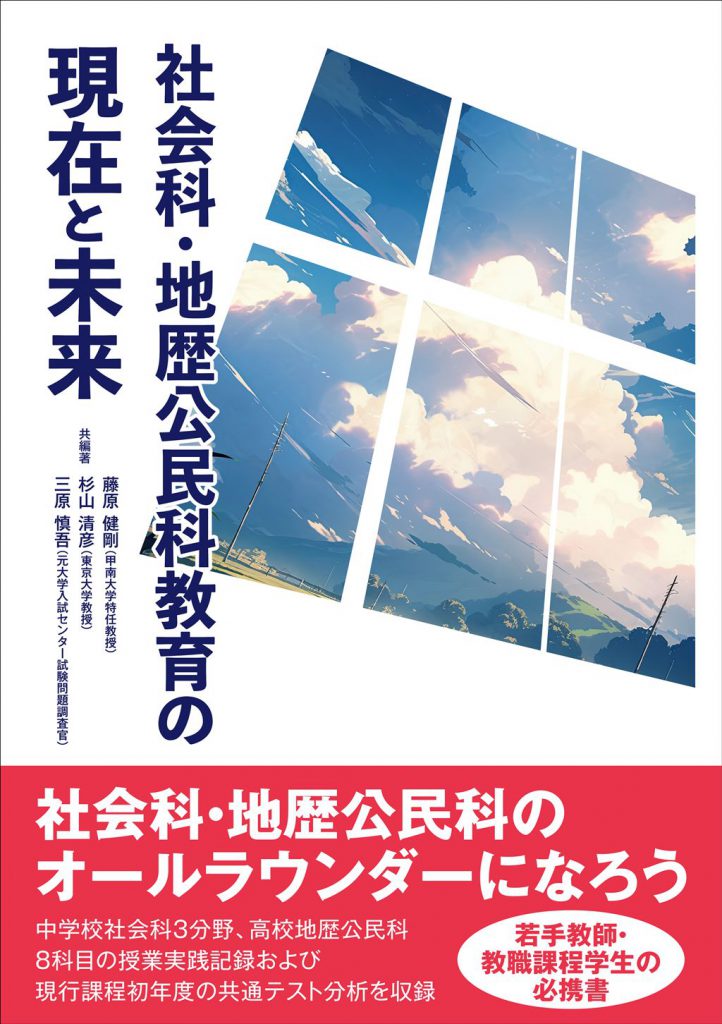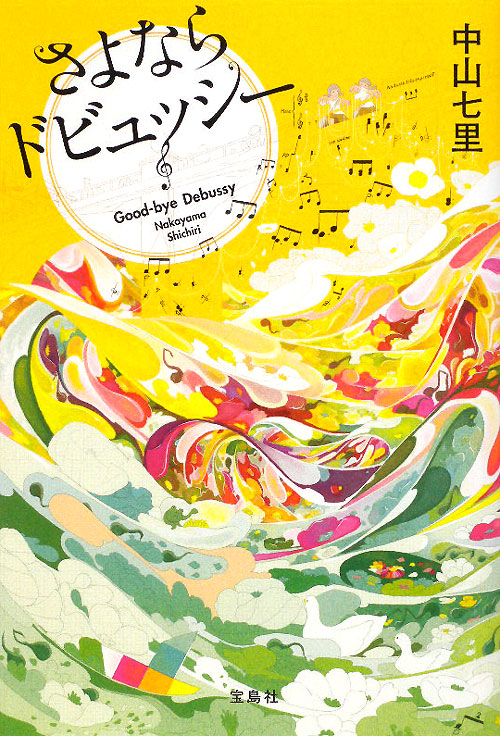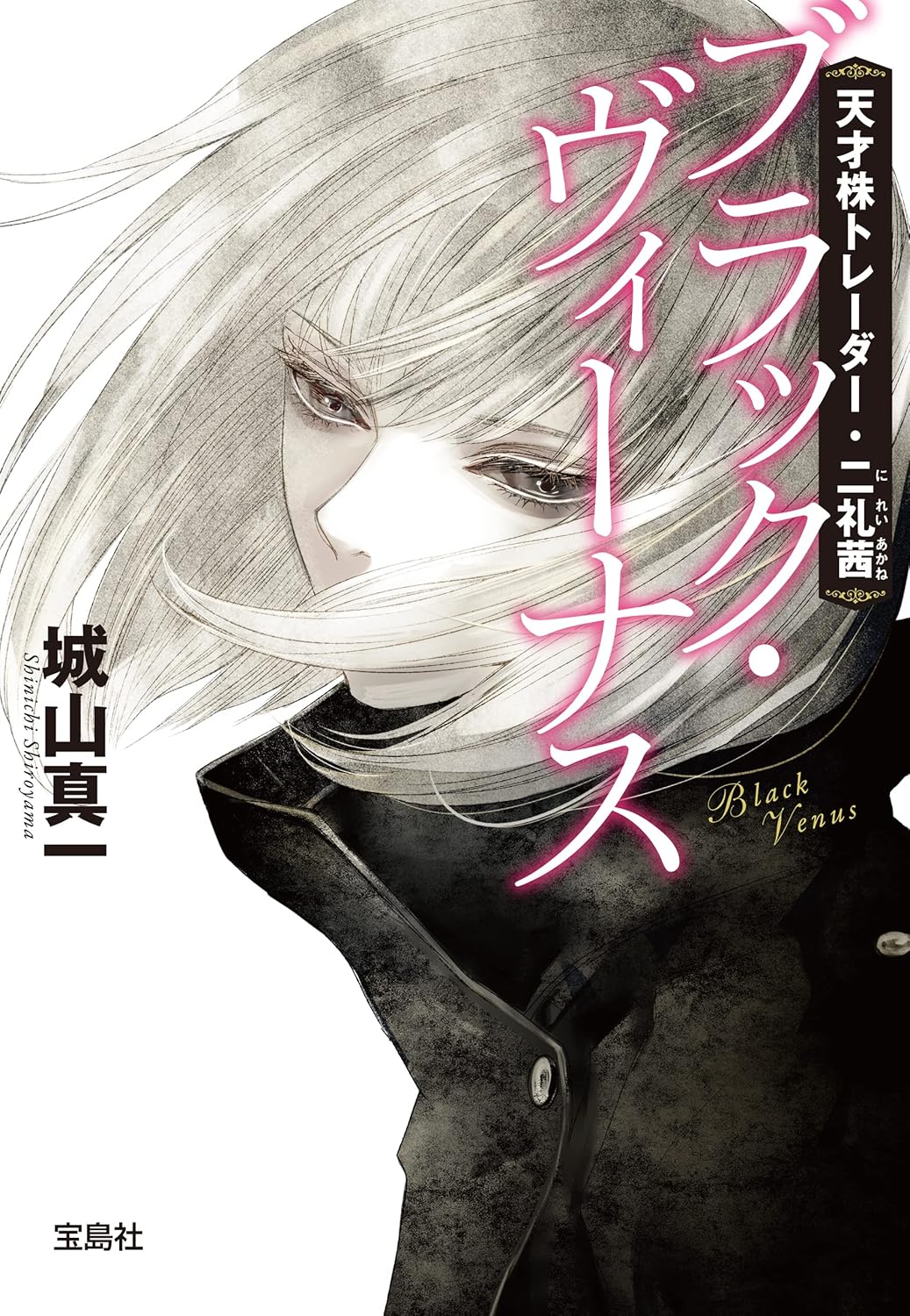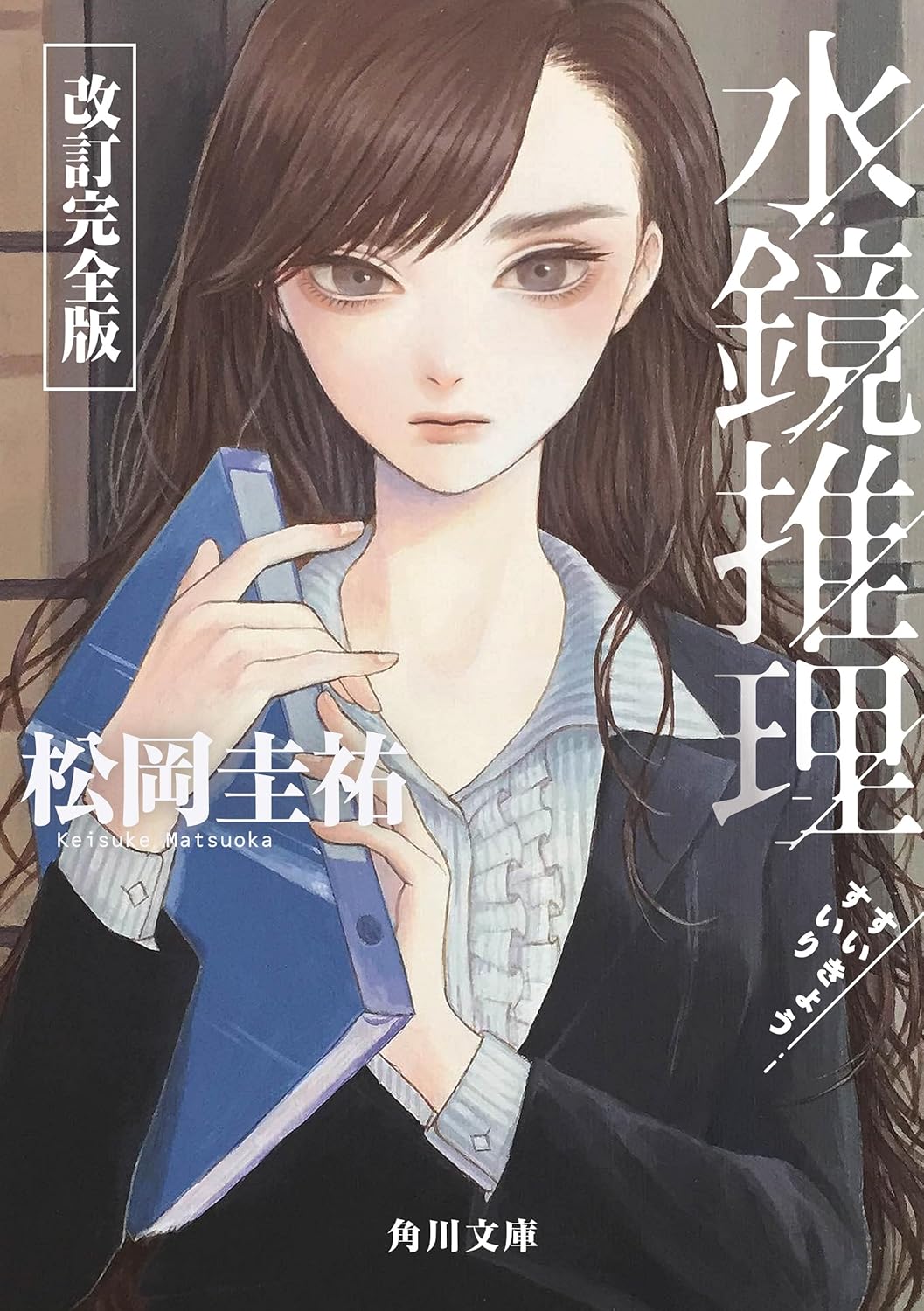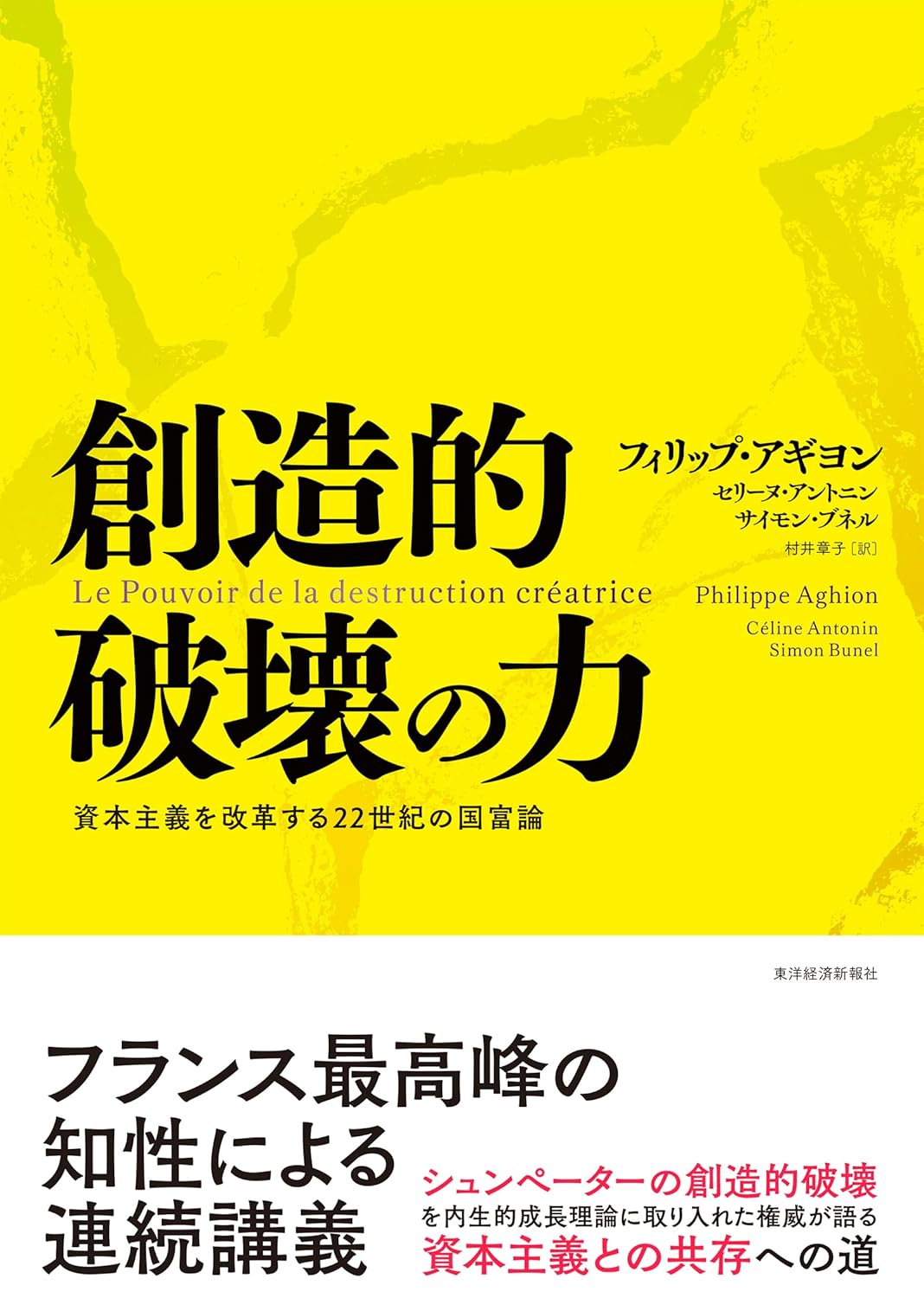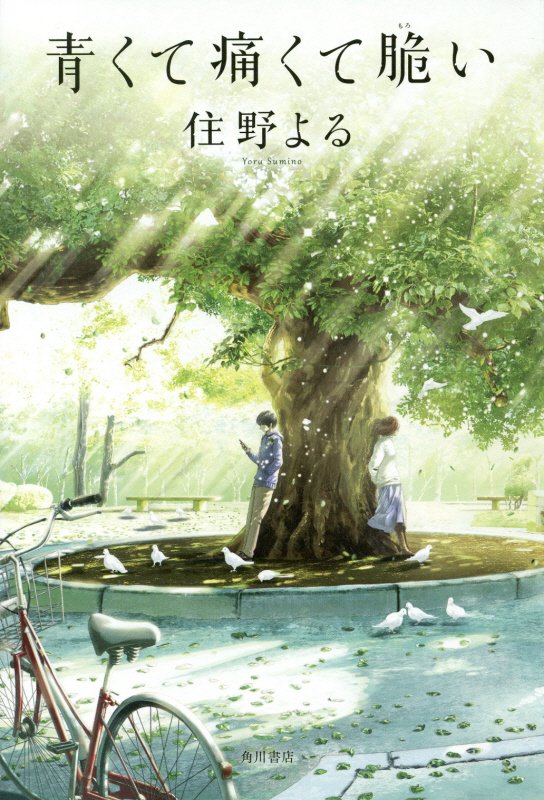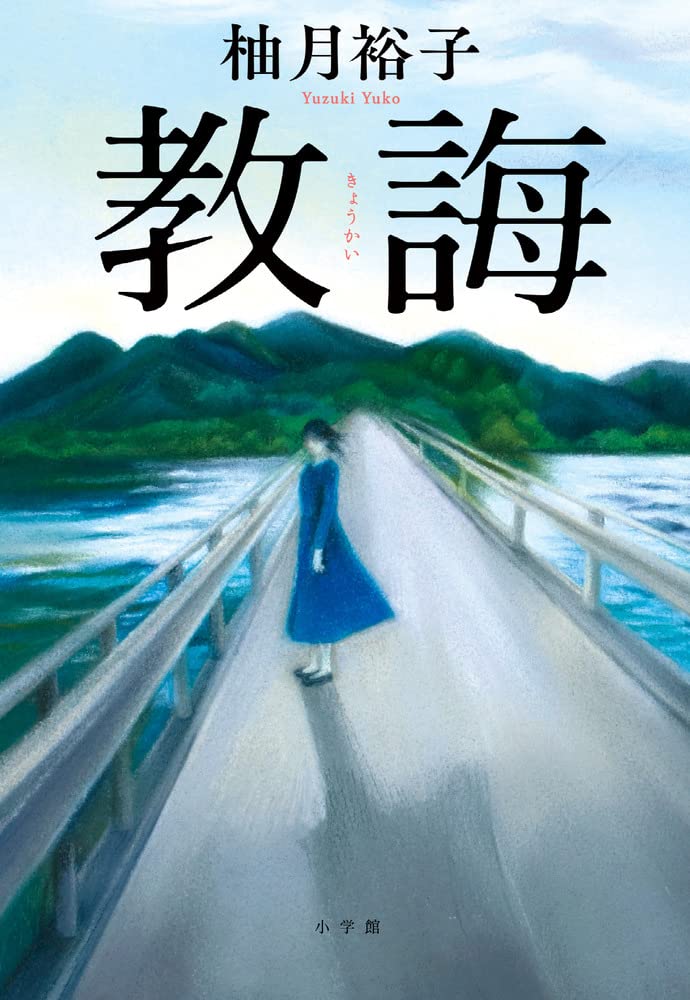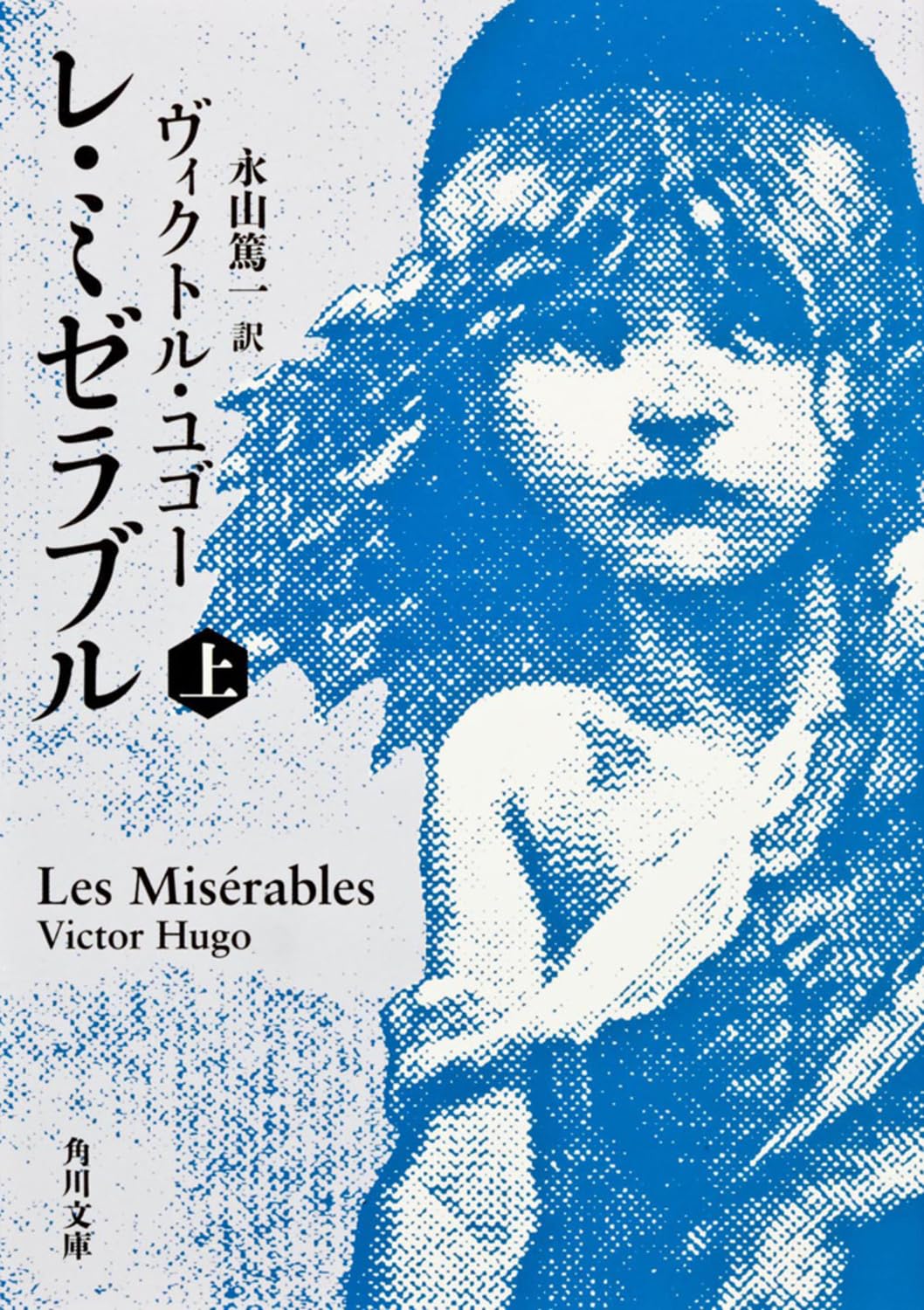文学部4年生 Iさんが、マネジメント創造学部 S先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
―読書の頻度はどのくらいですか?
専門書は毎日ではないですが、論文にないものを求めてかなりの頻度で読んでいます。娯楽の本に関しては月1~2回程度で、本を買ったら読むという感じです。ただ娯楽の本は読み始めると最後まで読まないと気が済まないので、仕事を優先してここ4、5年読めていません…。
―図書館や書店はそれぞれどのくらい利用されますか?
図書館については、楽しみの本を求めて、西宮キャンパスCUBE近くのアクタ西宮にある西宮市立北口図書館を利用していました。最近は専門書を調べるために、甲南大学図書館のweb検索のみを利用しています。
書店は月に1~2回程度利用しています。書店には、新刊に加えて2、3年前の見過ごした本がまとめて置いてあることもあって、専門書だとこの章を読んだら授業に活かせるかも?これと合わせると面白いかも?と考えながら本を探しています。
―面白そうな本の見つけ方や、手に取る決め手を教えてください。
やはりタイトルと帯の面白さです。帯に関しては誰が推薦しているのかも気にしていて、例えば好きな作家さんが推している新人作家さんには興味がわきます。あとは雑誌に書かれている書評を読んだり、好きな作家さんの新刊だったら買ったりすることもあります。
―読書の魅力は何だと思いますか?
「自分の知らない/知りえない人が書いたものだ」ということです。普段生活していると、自分と似たような人ばかりと知り合い交流することが多いと思います。だから、身近な人ならば、人としてどういう反応をするのか想像できてしまいます。ですが、本だと自分とは全く異なる環境で生きてこられた知らない方が、自分には理解できない「人の行動」について書いているから、驚きと感動を経験します。結果として、自分が人を深く理解できていない“事実”を改めて実感することができるわけです。実社会にいたら自分がシンパシーを感じない人とは分かり合えないけれど、そういう人も含めて書ききるという点で、そこまで人を理解している作者に凄いなぁと正直尊敬しています。
―本は紙派ですか、電子派ですか?その魅力も教えてください。
紙派です。電子の魅力がそもそも実物を買わなくていいというくらいで、私の場合、本は紙じゃないと集中できない気がします。
―先生のお気に入りの本を教えてください。ジャンルや作家でも構いません。
好きなジャンルは経済(なかでも国際金融や国際情勢に関するもの)、ミステリー、宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズです。好きな作家は宮部みゆきさん、専門書で読んでおこうと思うのはダニ・ロドリック先生、ダロン・アセモグル先生、トマ・ピケティ先生などです。宮部みゆきさんは、予想した展開と違う方向に内容が飛んでいくという意味で一級品の作品ばかりで、凄い能力を持っている方だと尊敬しています。
楽しみで読む本の作家の作品の中では、読みやすく前向きで心が温まり、かつ、いい意味での裏切りを感じさせてくれる作品が好きです。例えば中山七里『さよならドビュッシー』、城山真一『天才株トレーダー・二礼茜 ブラック・ヴィーナス』、松岡圭祐『水鏡推理』シリーズがお気に入りです。
人に理解させようという意味で分かりやすいなと思える専門分野の書籍だと、フィリップ・アギヨン『創造的破壊の力: 資本主義を改革する22世紀の国富論』があります。
―学生の間に読んで欲しい本を教えてください。
お好きなものをどうぞ!その人その人で心に響くのは違うので、「とりあえず読んでみてください」と言いたいです。どのような本でも、読んだ先に必ず何か見えてくるものがあると思います。
【感想】
本を選ぶ時は私も帯を見て選ぶことが多いので、やはり帯から得られる情報は大きいのだなと思いました。また読書の魅力について、自分が理解できていない人を知ることができるというお話にはなるほどなぁと納得しました。たしかに自分自身が共感できないキャラクターだとしても、作家の方は最後まで書ききるので本当に凄いと思います。
最後に、先生には急なインタビューの依頼にも関わらず快く受けてくださり、感謝申し上げます。非常に楽しく有意義なインタビューを行うことができました。素敵なお話をありがとうございました。
☆先生からのおすすめ本☆
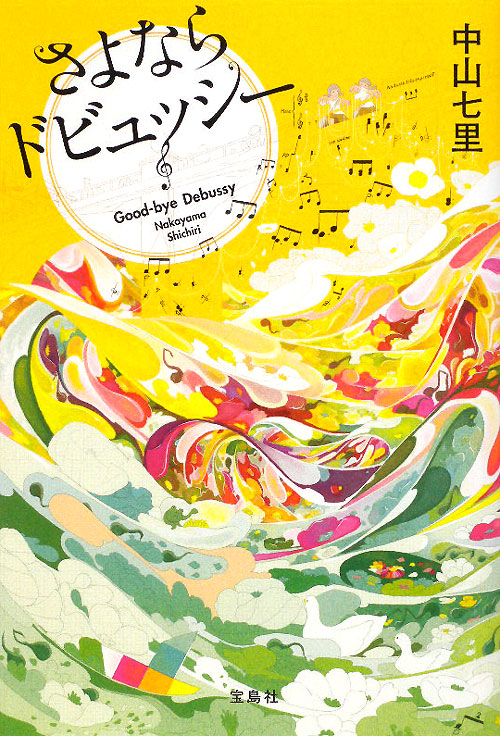
■『さよならドビュッシー』
■ 中山七里著
■ 東京 : 宝島社 , 2010.1
■ 請求記号 913/N
■ 配架場所 図書館 . 2F中山一般
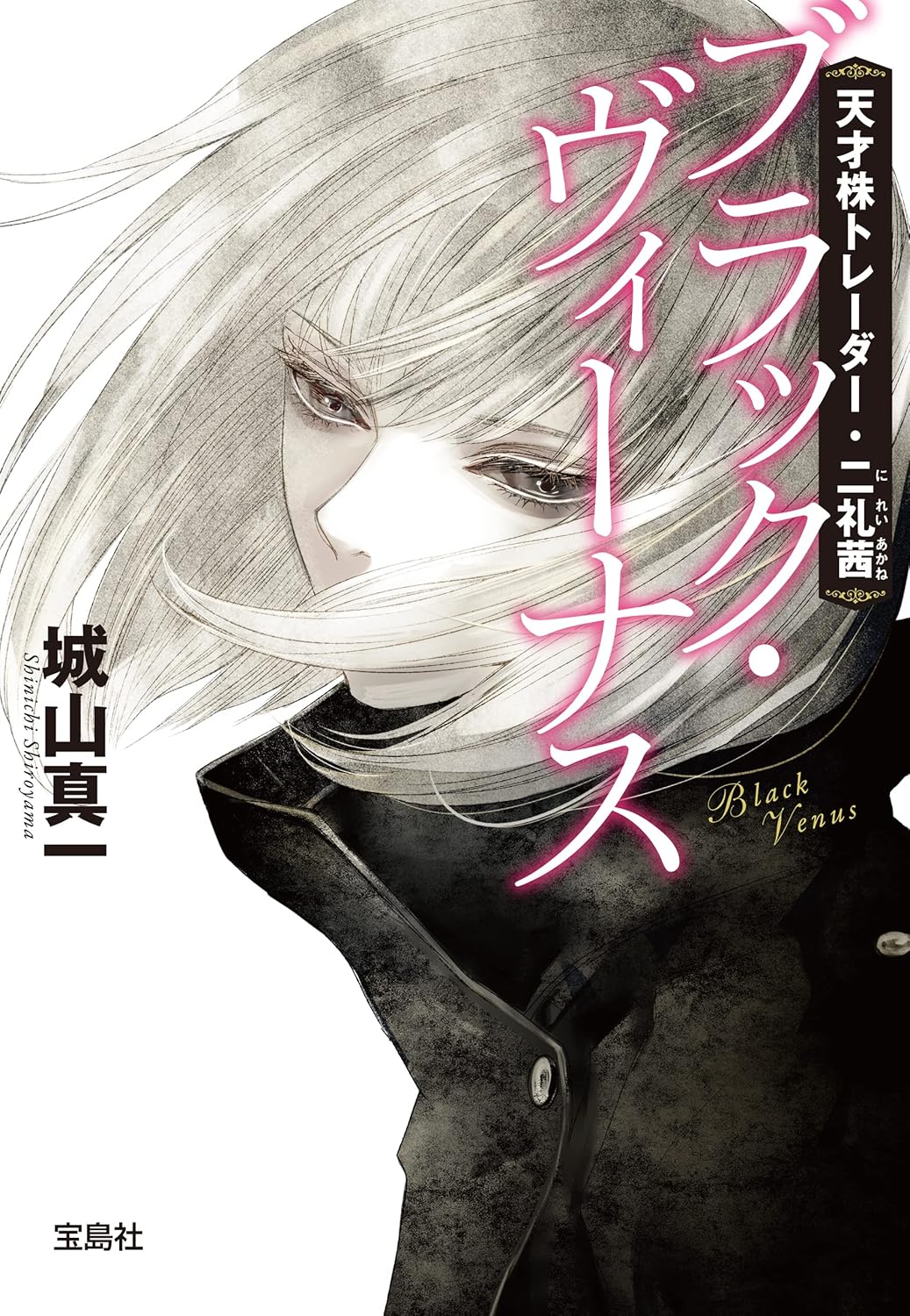
■『ブラック・ヴィーナス : 天才株トレーダー・二礼茜』
■ 城山真一著
■ 東京 : 宝島社, 2017.2
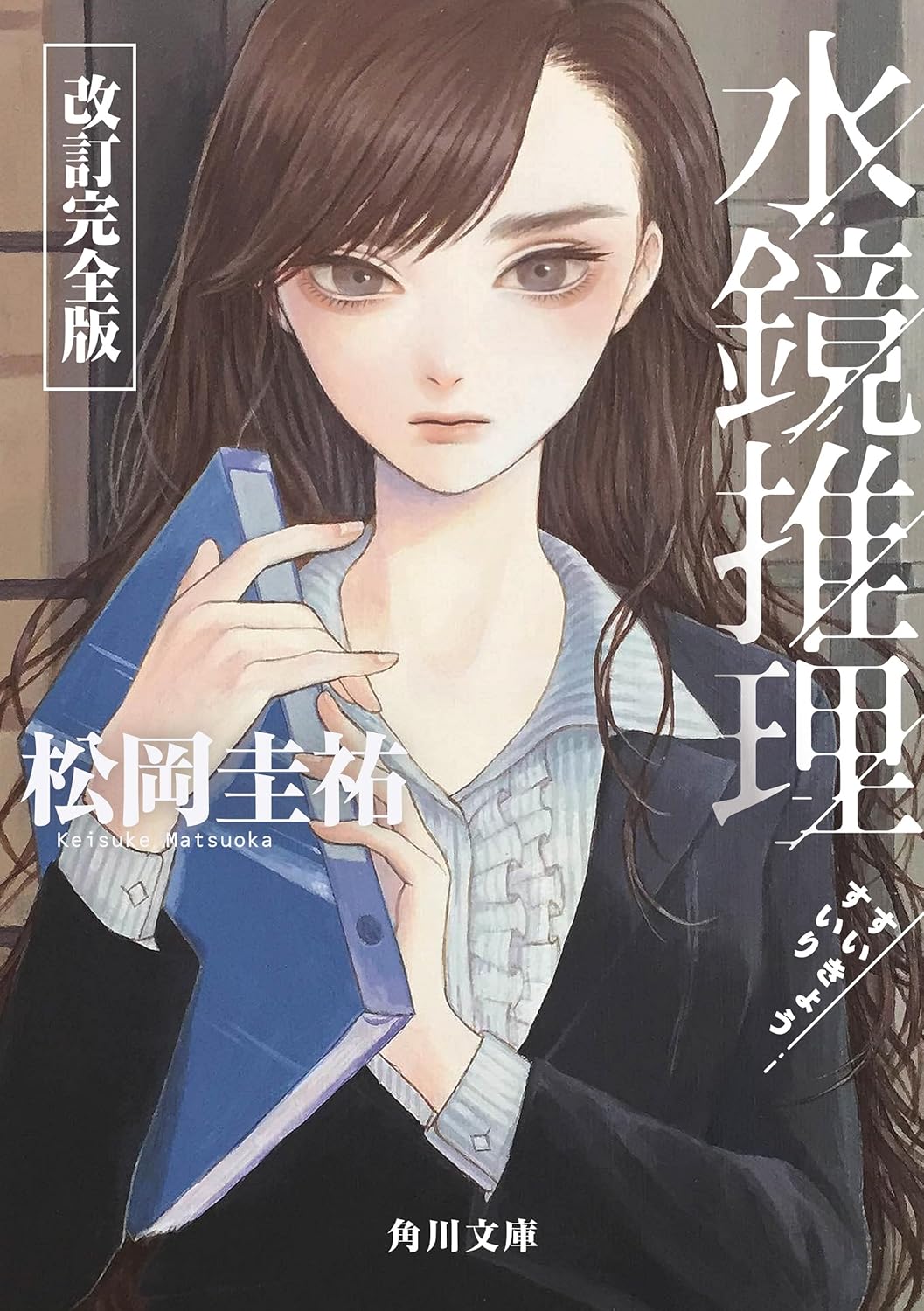
■『水鏡推理』
■ 松岡圭祐著
■ 東京 : 講談社, 2015.10
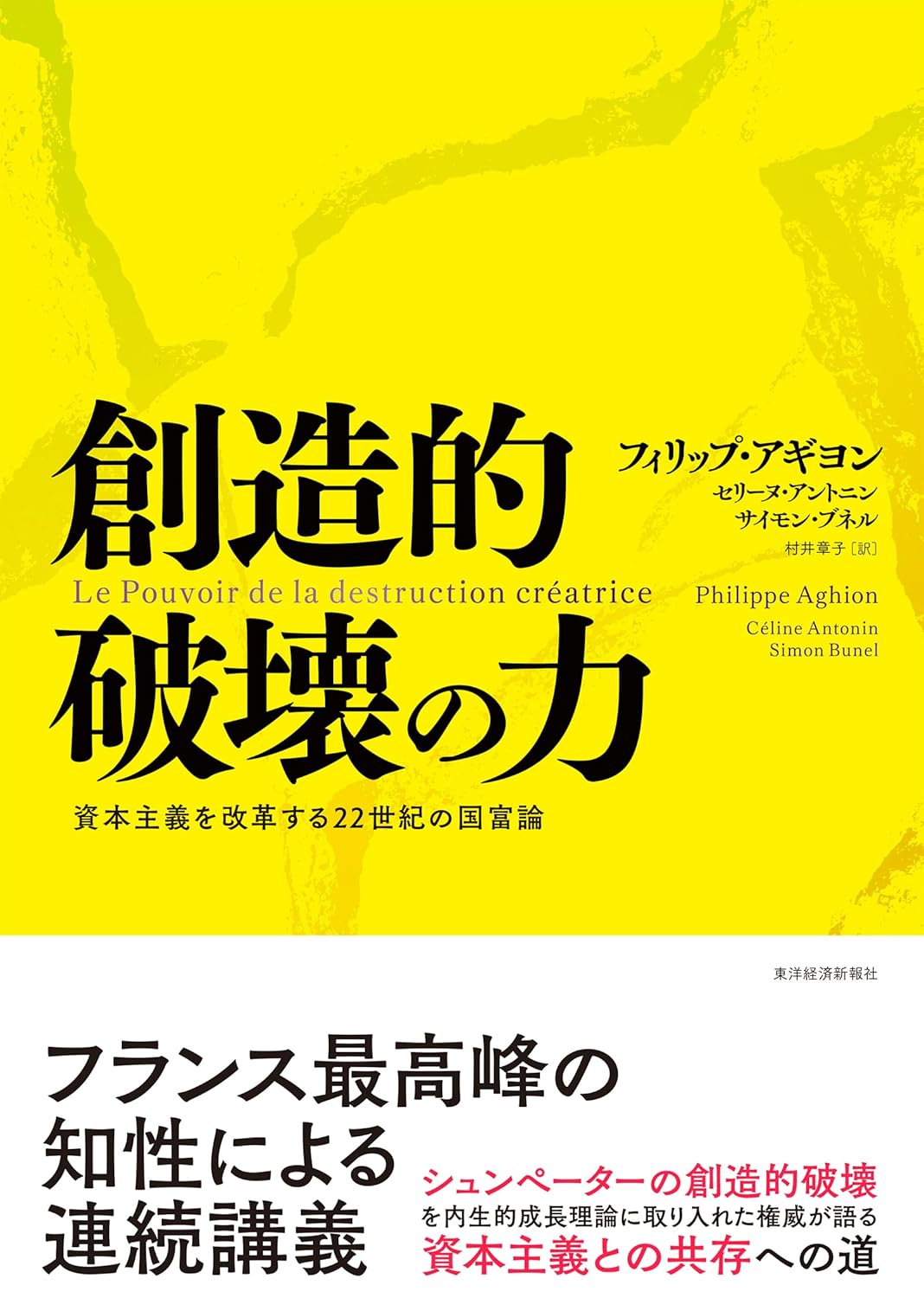
■『創造的破壊の力 : 資本主義を改革する22世紀の国富論』
■ フィリップ・アギヨン, セリーヌ・アントニン, サイモン・ブネル著 ; 村井章子訳
■ 東京 : 東洋経済新報社 , 2022.12
■ 請求記号 332.06//2166
■ 配架場所 図書館 . 1F開架一般
(インタビュアー: 文学部4年生 Iさん)