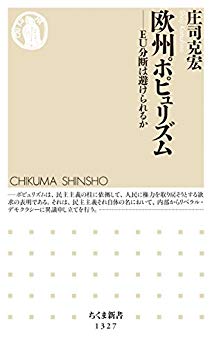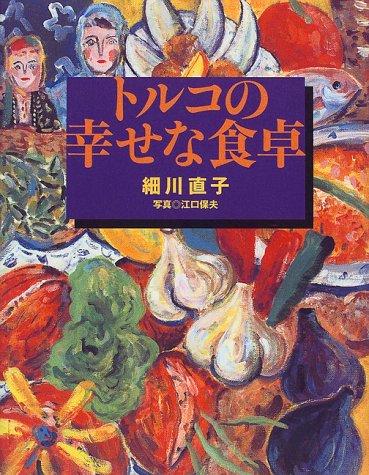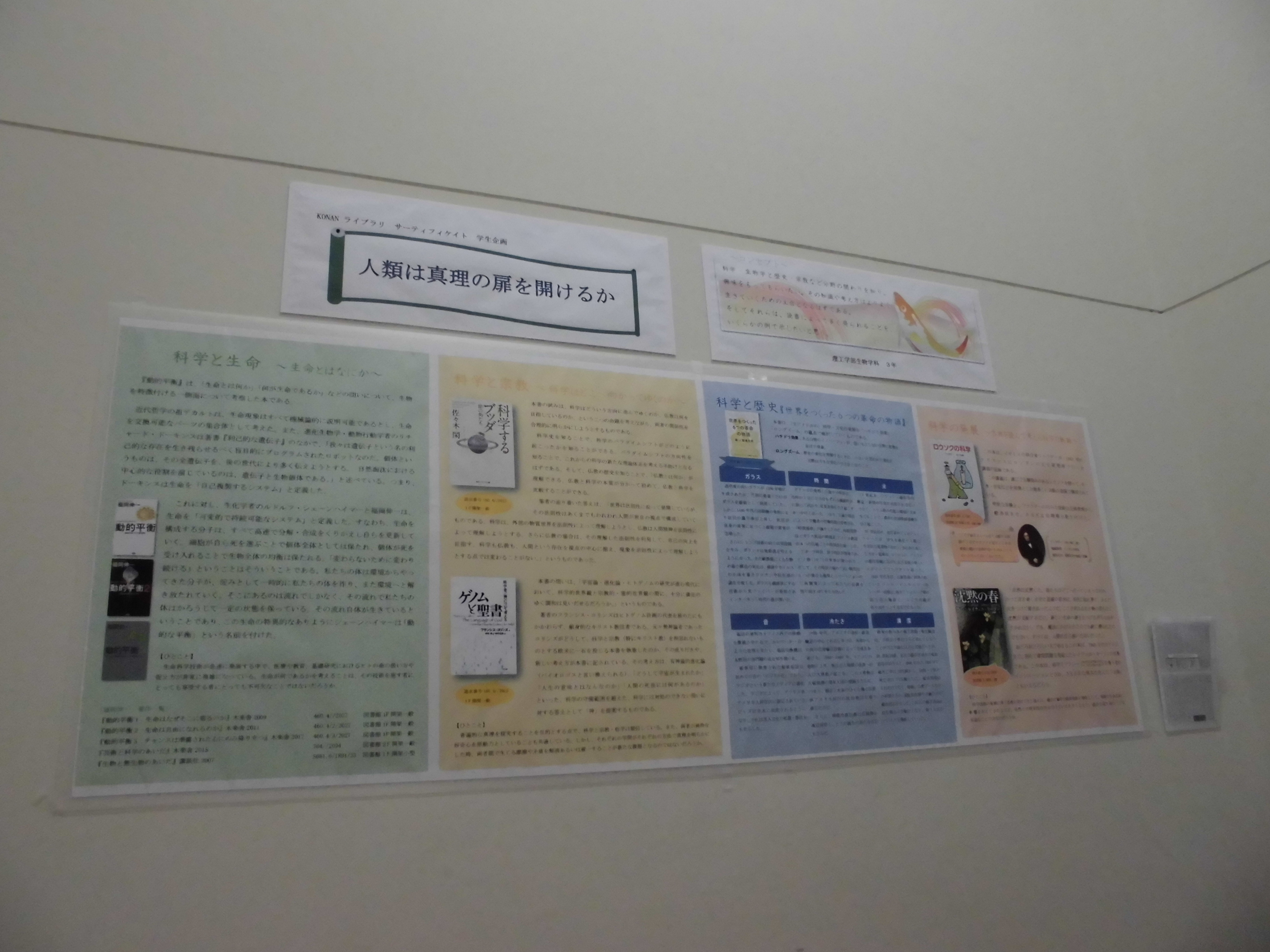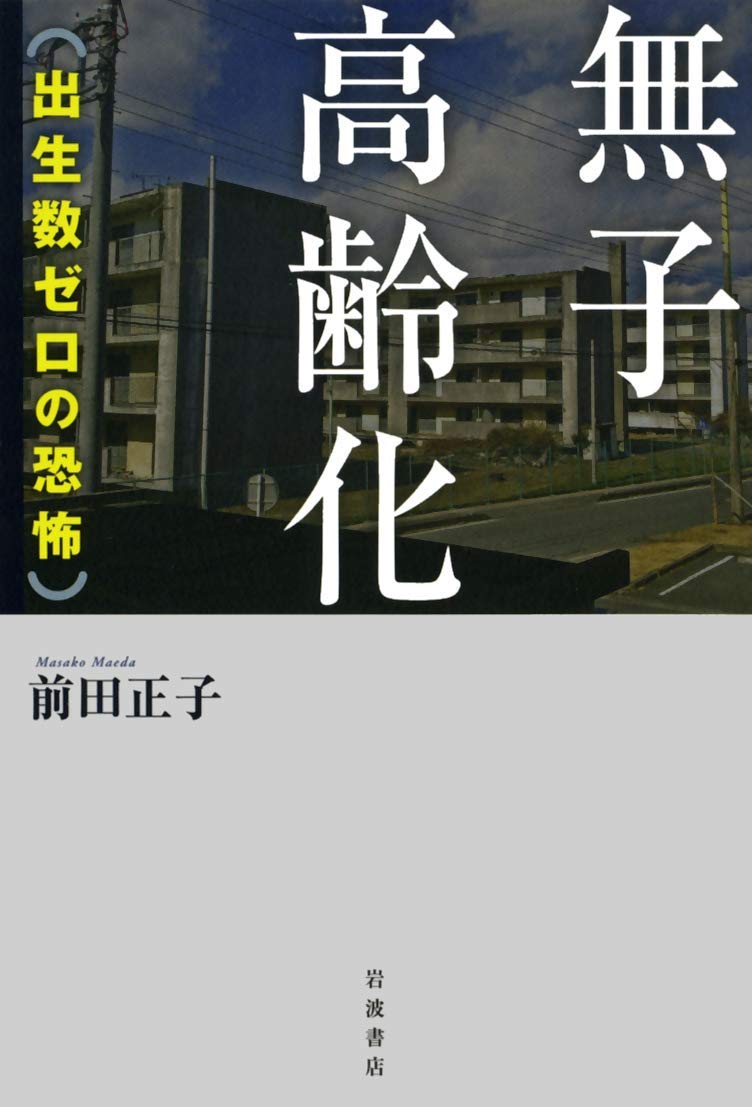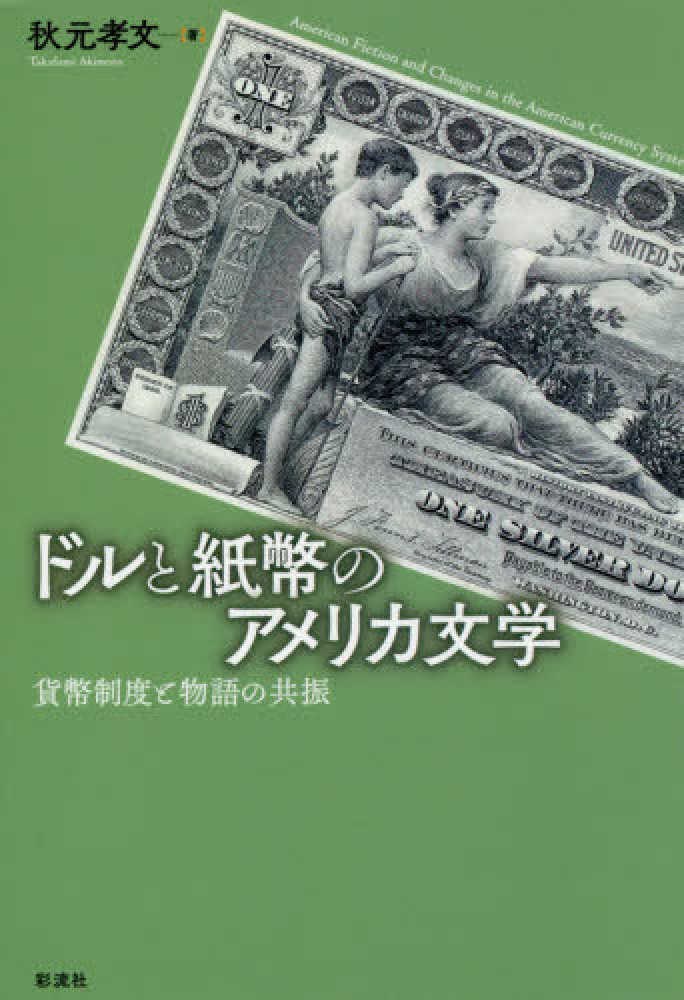法学部 1年生 匿名希望さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名: 欧州ポピュリズム EU分断は避けられるか
著者: 庄司 克宏
出版社:筑摩書房
出版年:2018年
近年、欧州がポピュリズム化している現状がある。このような現状に作者は、EUの組織がどのような存在であるか、EUの運営がどのようになっているかを述べ、ポピュリズムがなぜ欧州で発生したのか、これからのEUがどうなっていくのかをこの本で解説している。
また、このポピュリズム化する欧州に対してリベラルなEUという組織がどうあるべきか述べられている。EUという組織はリベラル・デモクラシーであり、多元主義、法の支配、多文化主義があげられる。それに対して、近年欧州に現れてきたポピュリズムとは、反エリートであり、強い主導者を求める傾向がある。このようにEUとポピュリズム化する流れのある社会の中で亀裂が生じている。EU組織は今、欧州ポピュリズムを封じ込めるよう模索している点があるが、果たしてよい結果となるのだろうか。EU組織やポピュリズム化する欧州について詳しく本書で書かれていて、これからの欧州について考えるに良い本である。
興味がある人はぜひ、読んでいただきたいです。