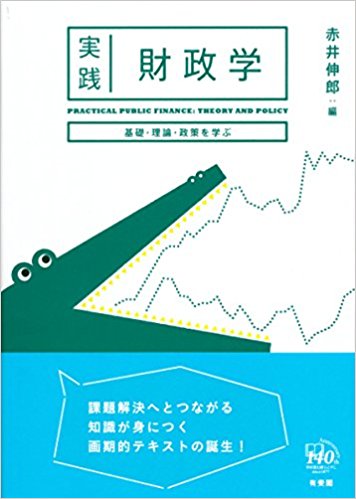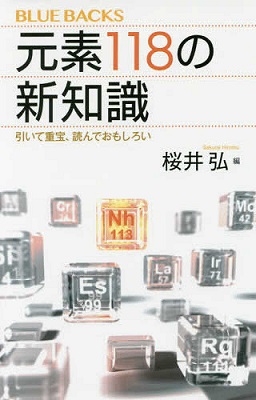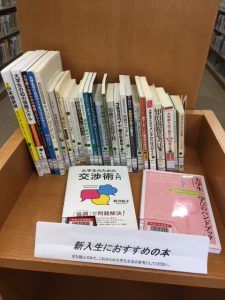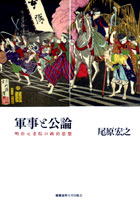文学部 4年生 中西聖也さんが、フロンティアサイエンス学部の村嶋貴之先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
―本はよく読まれますか?
本は好きなのでよく読みます。最近は忙しいですが月に6冊程度、ミステリーや古めの純文学をよく読みます。最近はkindleで読むことが多いです。
―小さい頃はどんな本を読んでいましたか?
昔から僕は理科少年だったので、自然科学分野の本が好きでした。小学生の頃は図書館で借りて読んでいました。ホームズやルパンなども好んで読みました。
―化学の分野に興味をもったきっかけは何ですか?
理科は全般的に好きでしたが、高校の化学の先生の影響はすごく受けたと思います。化学が苦手な子に対して、「有機化学は少し違う分野だから、頑張ったら化学が好きになるよ」と教えていて、実際に大学の講義では、これまでの暗記する化学とは違う印象を受けました。自分の手を動かして新しいものを作り出せることにも興味を持ったので、有機合成を選びました。
―現在図書館長に就かれていますが、何か展望はありますか。
現在は本棚が埋まってしまっている状態なので、大学生が本当に必要としている、役に立つ本を選べるように学生たちの意見を取り入れていきたいと考えています。
―有機合成化学に興味がある方、一般的な大学生に薦める本をそれぞれ一冊ずつ教えてください。
有機化学に興味がある方にはピーター・サイクスの『A Guidebook to Mechanism in Organic Chemistry』(『有機反応機構』)。僕が学生の頃に「この本を読んだら絶対有機化学が好きになる!」と学生同士で言っていて、自主ゼミで輪読していました。大学生の中でも新入生には、梅棹忠夫『知的生産の技術』。知的なことを生み出すために、日頃どういうことを実践したらいいかなど、論理的にものを考える方法が具体的に書かれています。
―インタビューを終えて
私はずっと文系の道を歩いてきたので、理系の方の話を聞けるのはとても新鮮なことでした。物心ついた時から理科が好きだったと話されていて、学問への好奇心の大きさに驚きました。図書館の展望についてもお話いただき、とても貴重な経験となりました。
<村嶋貴之先生おすすめの本>
ピーター・サイクス/久保田尚志著 『有機反応機構(第5版)』 東京化学同人,1984年
梅棹 忠夫著 『知的生産の技術』 岩波新書,1969年
(インタビュアー:文学部 4年 中西聖也)