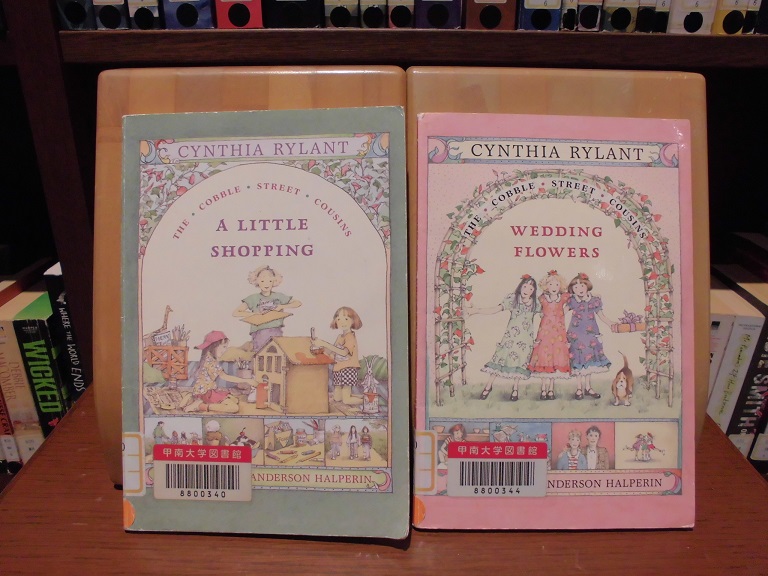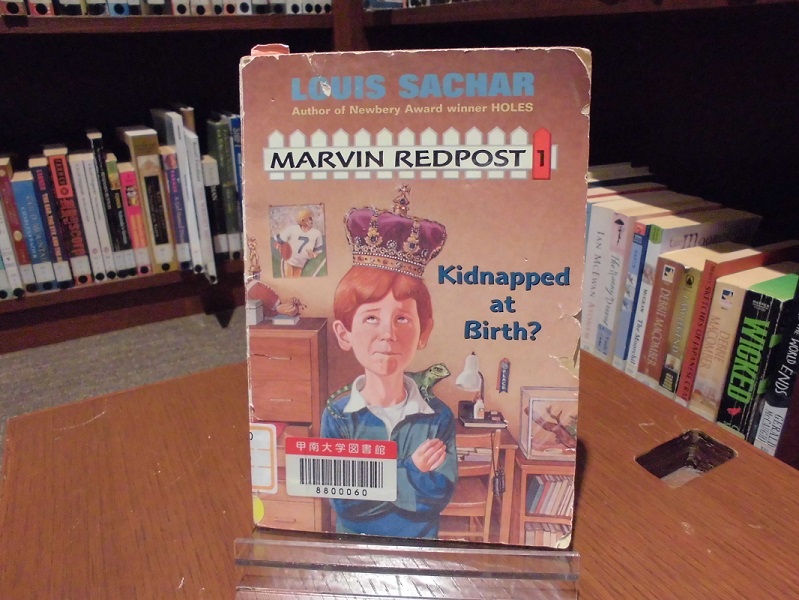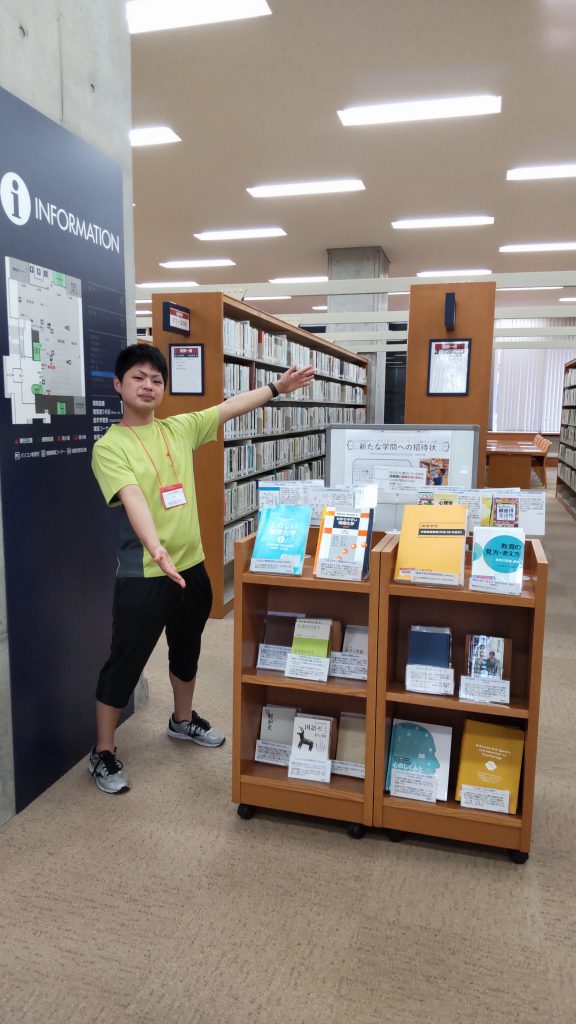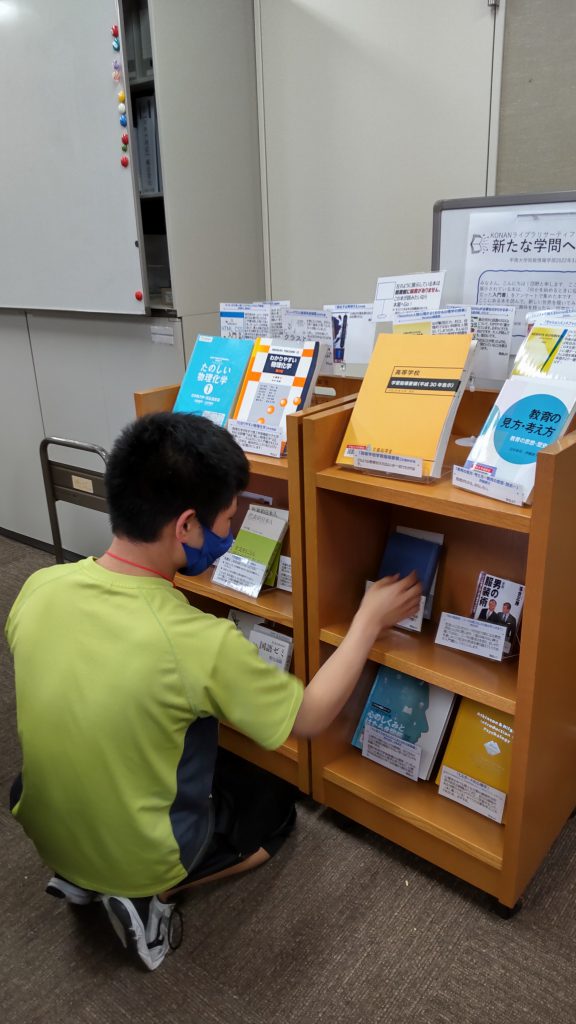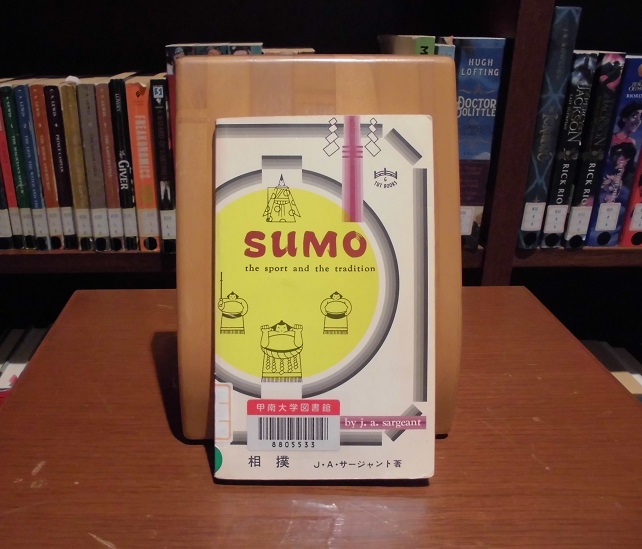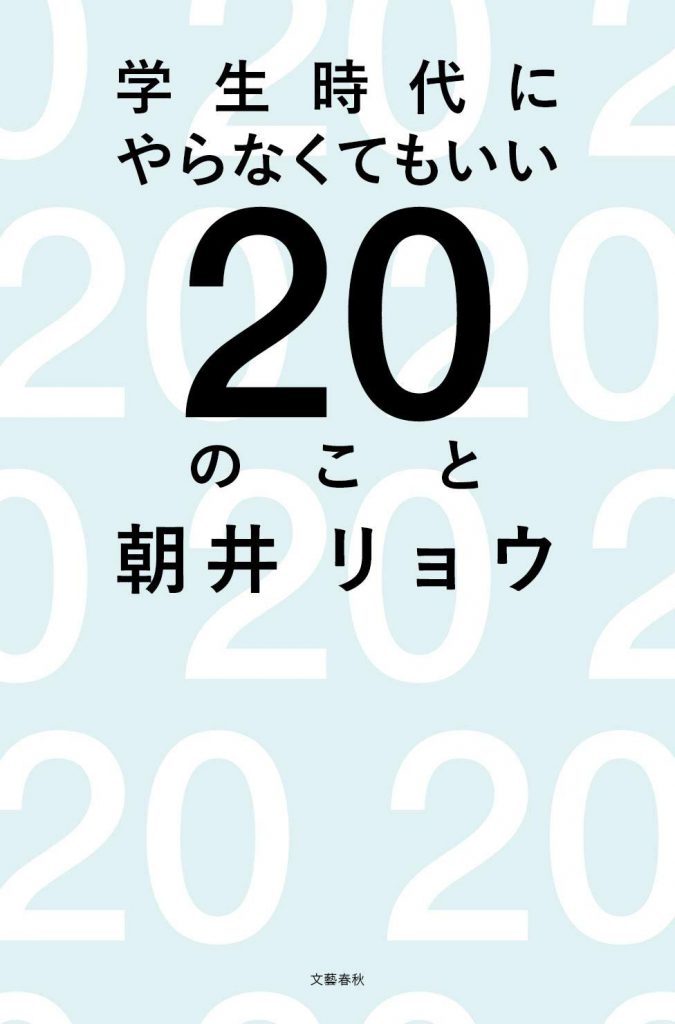
文学部 3年生 Sさんからのおすすめ本です。
書名 : 学生時代にやらなくてもいい20のこと
著者 : 朝井 リョウ著
出版社:文藝春秋
出版年:2012年
この本は『桐島、部活やめるってよ』で有名な朝井リョウさんのエッセイである。大学で100キロ歩いたり、旅行に失敗したりする話をはじめ、作者の様々な大学生活が20に分けて語られている。
読みどころは、つい笑ってしまう作者の体験である。私は、甲南大学のある授業で様々な感情の中で「おもしろい」を表現することは難しいと学んだ。嬉しいや悲しい感情はある程度共通するものの、「おもしろい」はそれぞれ人によって笑いのツボが違うからである。しかし、この本は個人的には笑う箇所が多かった。
なぜ「おもしろい」を上手く表現していたか考えると、予想を裏切る展開が多いからだと思う。世間の人が一般に想像する展開を裏切るほどギャップが大きくなり笑いを生みだすと別の本に書かれていたことを思い出した。例えば、作者と美容師の会話である。自慢のシャンプーの効能を当ててほしいという美容師に対し、作者はしぶしぶ髪がつやつやになるとありきたりな回答をするが、美容師からは意外な答えが返ってくる。このように、作者のエッセイでは大抵の人が想像する展開を見事に裏切る箇所が散りばめられていたのだ。
最近では、大学時代には○○をすべき、○○はやってよかったなど、読むことに意味を見出す本やネット記事が多くある。しかし、目的を持たずに一人の学生時代の日々をつづった本も固まりきった頭をほぐしてくれるのではないだろうか。タイトルには「学生時代にやらなくていい」とあったように、付箋を貼る箇所は1つも無かった。それでも意味や目的を考えず、自分の興味や気持ちを優先していた作者の体験を読むと無駄なことも大切だなと感じられた。北海道へ思いつきで旅行したり、東京から京都に自転車で移動したりする体験を読むとコロナ禍で遠出が厳しい中一緒に旅をし、思い出を分けてもらえた気分になった。
エッセイは20の話に分かれており、短編なのですぐ読める。20の中から1つでもお気に入りの話を見つけて隙間時間や疲れた時に読んでもらいたい。