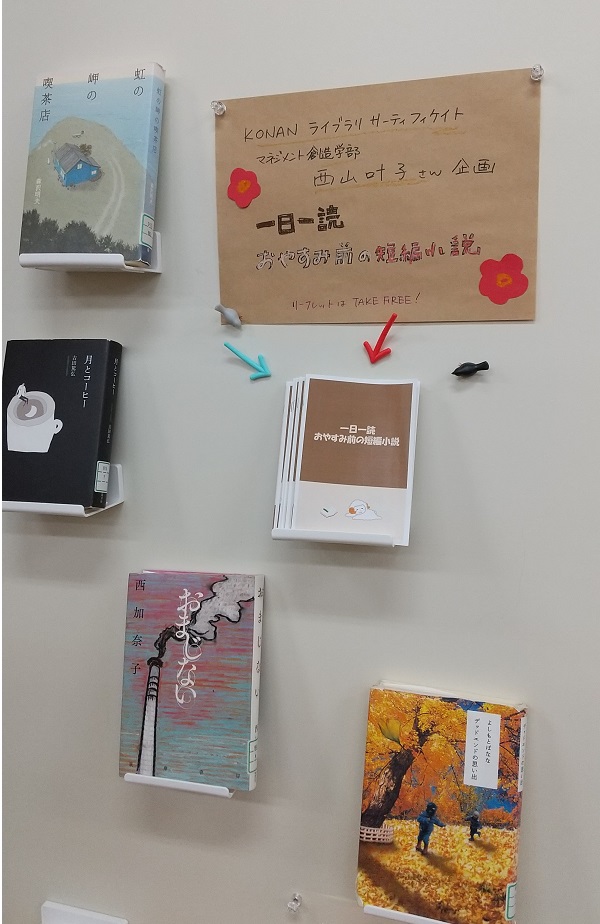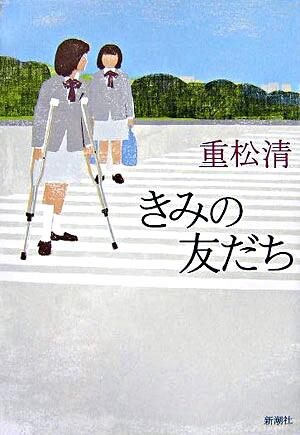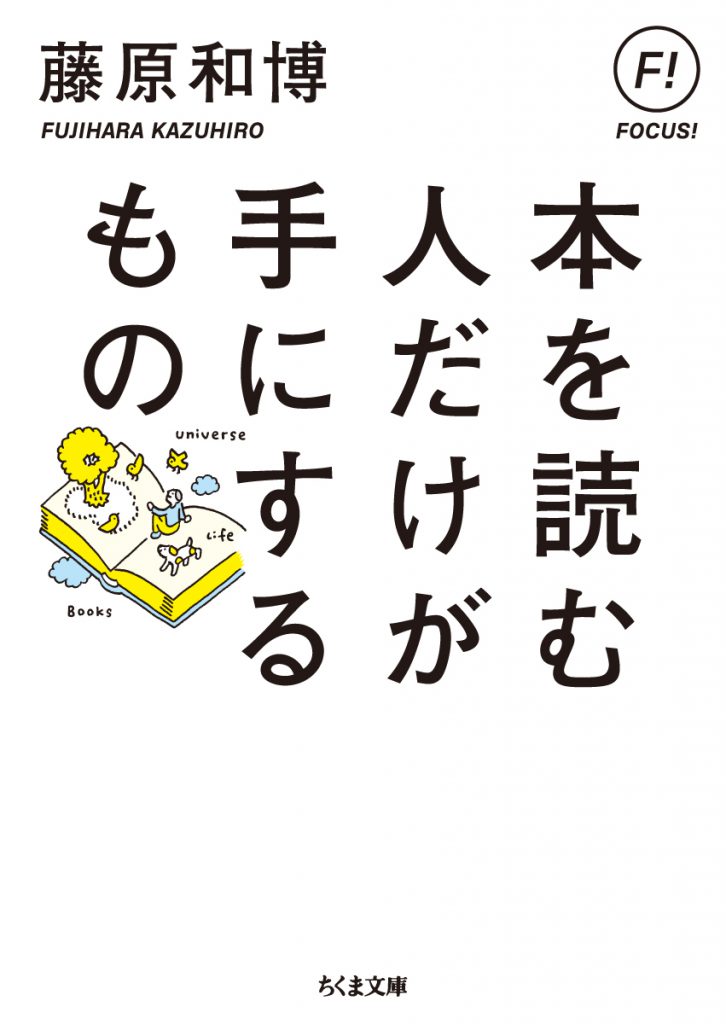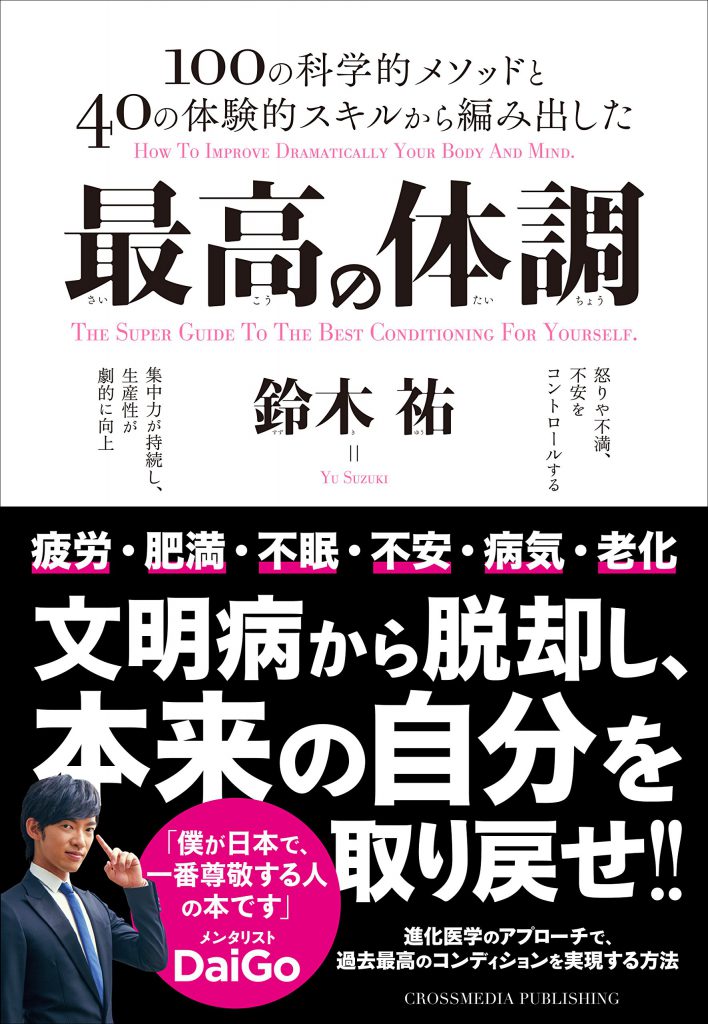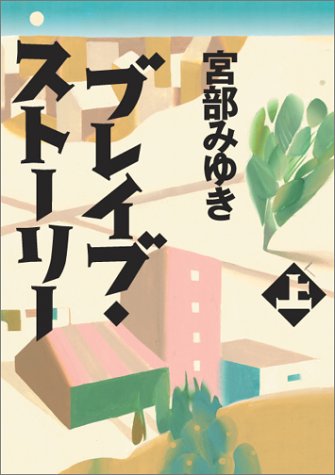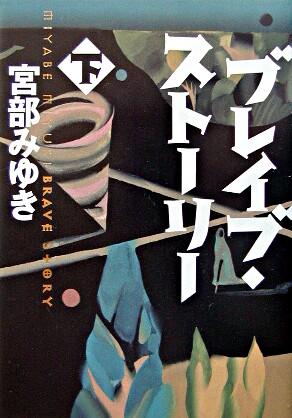知能情報学部 4年生 団野 和貴さんが、文学部 髙石 恭子先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
Q.本に接する機会はありますか?
A.自分の研究や学生相談に必要な文献を探すのは,常にありますね.趣味とか仕事や業務に直結しない本を読む機会は,仕事の忙しさと反比例します.そういった本は,余裕のある時(出張で新幹線を使うときなど)を見つけて読むのが,最近では多いです.
若い頃は,仕事に関係なく興味のある本を読んでいました.私の専攻する臨床心理学は「1人1人の人がどのように生きていくか」という人生のことに直結しているので,哲学,小説,児童文学,絵本,海外の小説とか古典文学など,手当たり次第読んでいました.人間は生きていると,簡単に解決できないことがたくさんあります.そういうものを抱えながらどのように考え生きていけばいいのかということを,本から得られると思います.例えば小説を読むと,その主人公の生き様から参考になるものたくさんあります.そこから,相談に来られたときに,自分の経験と本からその人の悩みを引き出して話を聞くことが可能になると思っています.
Q.学生相談の際に本を薦めることはありますか?
A.「こういうことについて悩んでいます.ヒントになる本はありますか」と言われたときは,要望に応じて探すことがあります.相談者の抱えている悩みがとても深くて簡単に解決策が出ないときは,私で答えられることも限りがあるので「この本が参考になるかもしれない」と薦めることがたまにあります.しかし,私がこういう意味だと思って読んだ本を,受け取った方が私と同じように感じられるとは限りません.また,薦めることによって「そのように考えないといけない」と思って,その人の自然な気持ちの方向を変えてしまう危険もあります.お薦めした方に「読んでみてどうだったか」と聞き,紹介して終わりということがないように心がけています.
Q.学生は本を読むべきでしょうか?
A.学びには本が必要であることはこれからも変わらないと思いますが,10年後がどんな時代になっているのかわからないので「近未来の人全てが本に親しまないといけない」と断言はできないと思います.でも,本は今まで人間が,人間の情緒や生き様を表し言葉にして後世に残してきたものです.日々生きていく上で上手く言葉にできないことを,どのように言語化したらいいか,自己理解したらいいか,人に伝えたらいいか,そういう手がかりを本が教えてくれると思います.例えば,自分の気持ちを相手と共有するときに,すぐに「私の気持ちはこのようになっています」と喋ったり書いたりできるケースは少ないでしょう.苦労して言葉にして,どんな風に嬉しいのか悲しいのかということを言葉で表すほかないと思います.人間はいきなり進化するわけではないので,若いときに「言葉」に触れられる本に出会うことがとても大事ではないかと私は思います.
ただ,時代によってやるべきことが異なり,今の人は昔にはなかったものを取り込まないといけないので,そのエネルギーと時間を考えるとなかなか「言葉」に触れることは難しくなっていると感じます.例えば,SNSなどで短い言葉をやり取りする機会が最近多いですが,長い文章で自分を表現することが今の日常ではなかなかありません.でも,時代が流れても人間の根幹は変わらないと思うので,少しでも「言葉」に触れ自分自身のことを「言葉」にする機会を作ってほしいです.
感想 :今回の髙石先生とのインタビュー,キーワードは「言葉」ですね.髙石先生の研究テーマでもある「人がどのように生きていくか」という視点で,読書を考えることができました.人間が急に変化しないことを考えると,これからも「言葉」を介したコミュニケーションは続いていくと思います.誰もが知っている共通の「言葉」で自分をどう表現できるか,ということはこれからも重要になります.社会人になっても読書を継続したいと強く感じました.
非常に楽しい時間でした.髙石先生,改めましてお時間をいただき,ありがとうございました.
(インタビュアー:知能情報学部 4年 団野 和貴 )