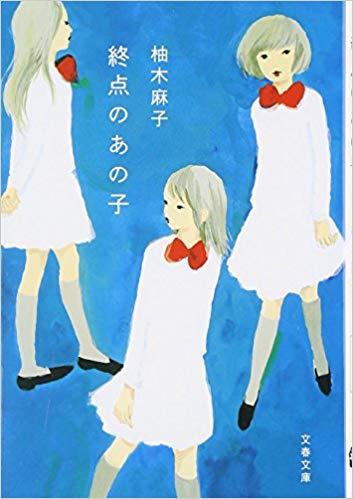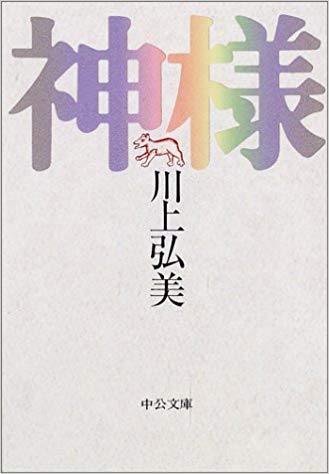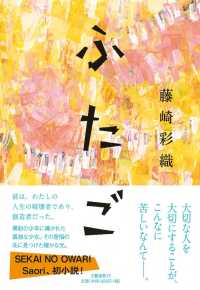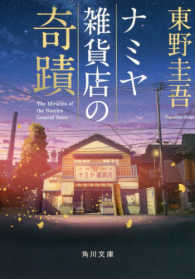法学部 1年生 匿名さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名:戦国日本と大航海時代
著者:平川 新
出版社:中公新書
出版年:2018年
私が今回おすすめする理由は、戦国時代の武将たちが、当時ヨーロッパ諸国で盛んに行われていた新大陸発見と布教をどのようにして切り抜けていったかということが丁寧に書かれているからである。
今まで日本史か世界史どちらかの事しか書かれていない本ばかりであったが、本書は日本の戦国武将の視点から海外を見た内容が丁寧に書かれており、高校で日本史・世界史のどちらかだけしか学んでいない人に強く薦めたい。
特に私が興味を惹かれた部分は、伊達政宗が徳川家康の意向に反してキリスト教を広めようとしていたスペインと友好関係を築き、積極的に貿易をしようとしていたという解説である。なぜ、天下統一を成し遂げた強力な武士徳川家康に対して政宗はこのような大胆な政策を進めることができたのか、また、家康はどうしてここまでキリスト教を弾圧しようとしていたのかといったような鎖国に関するたくさんの疑問を丁寧に解説してあるので、今まで歴史を縄文時代から最後まで学んだけれどももう少し歴史を詳しく学びたいと思った人に特に薦めたい1冊である。
しかし、本書の最大の欠点は作者が日本史の専門家であるために、世界史の内容があまり盛り込まれていないというところである。本書の構成は、第1章でヨーロッパの大航海時代の大まかな解説があり、後の章でそれぞれの戦国武将の行った政策と対外関係について書かれているのだが、物語の中心がほとんど日本から見た視点で書かれているため世界史しか学んでいなかった人が読むとなると少し分かりにくい内容となってしまっている点が少し残念であった。
そのため、歴史の教科書を読みながら本書を読み進めていくと非常に理解しやすくなると思う。私は本を読むときには予備知識などいらないと思っていたのだが、今回の読書を終えて予備知識が必要な本があるということを知ることができた。
また、そうすることによって本の内容が頭に入ってきやすくなるということを実感することができたので、とても有意義な時間を過ごすことができた。