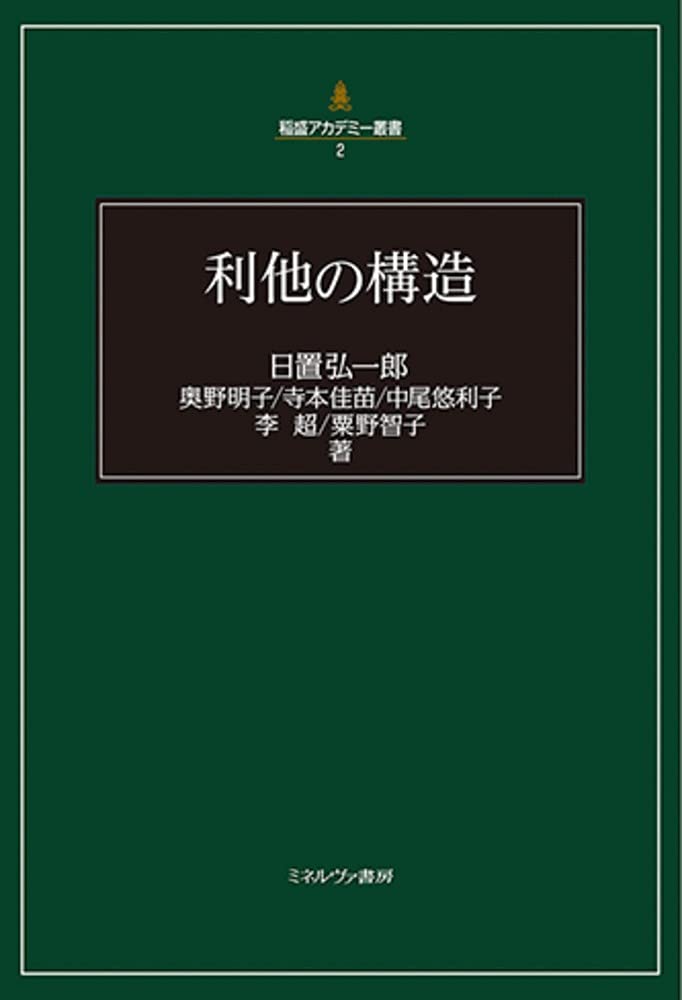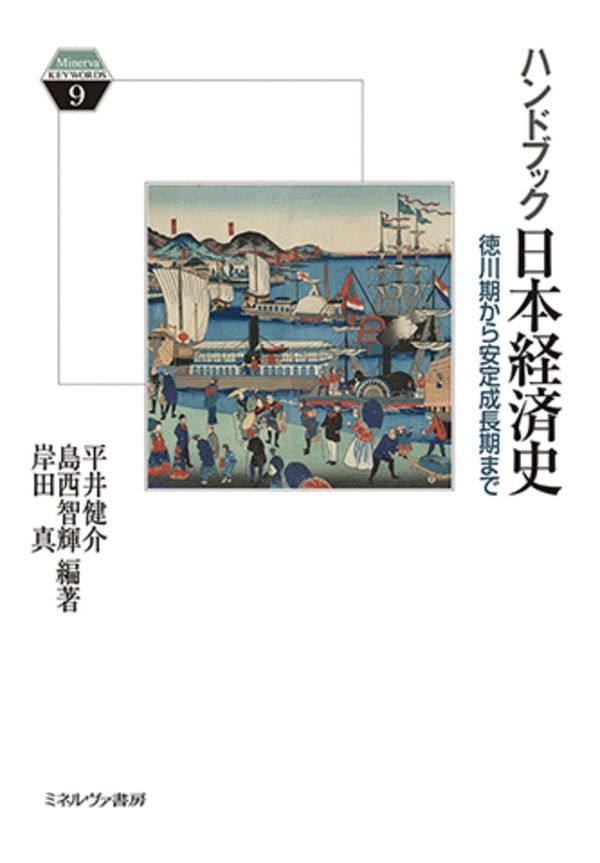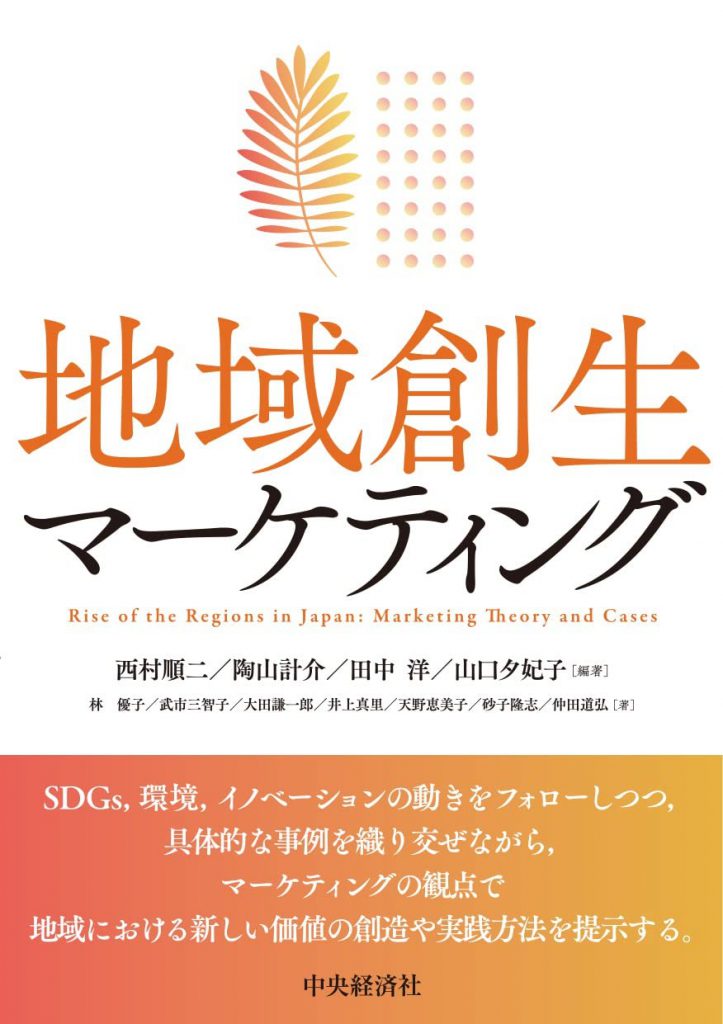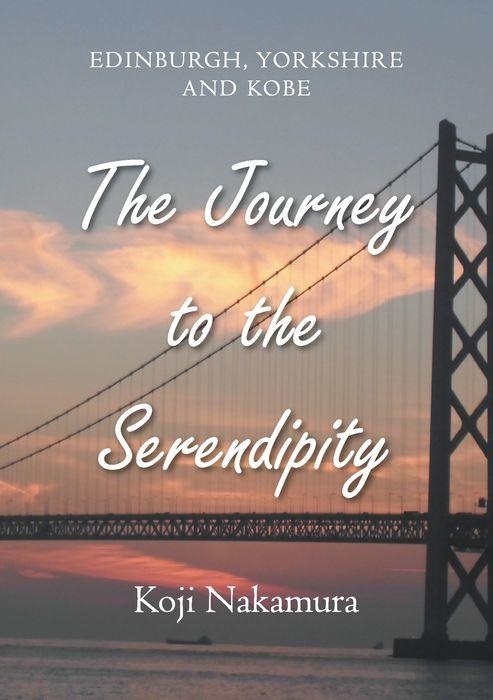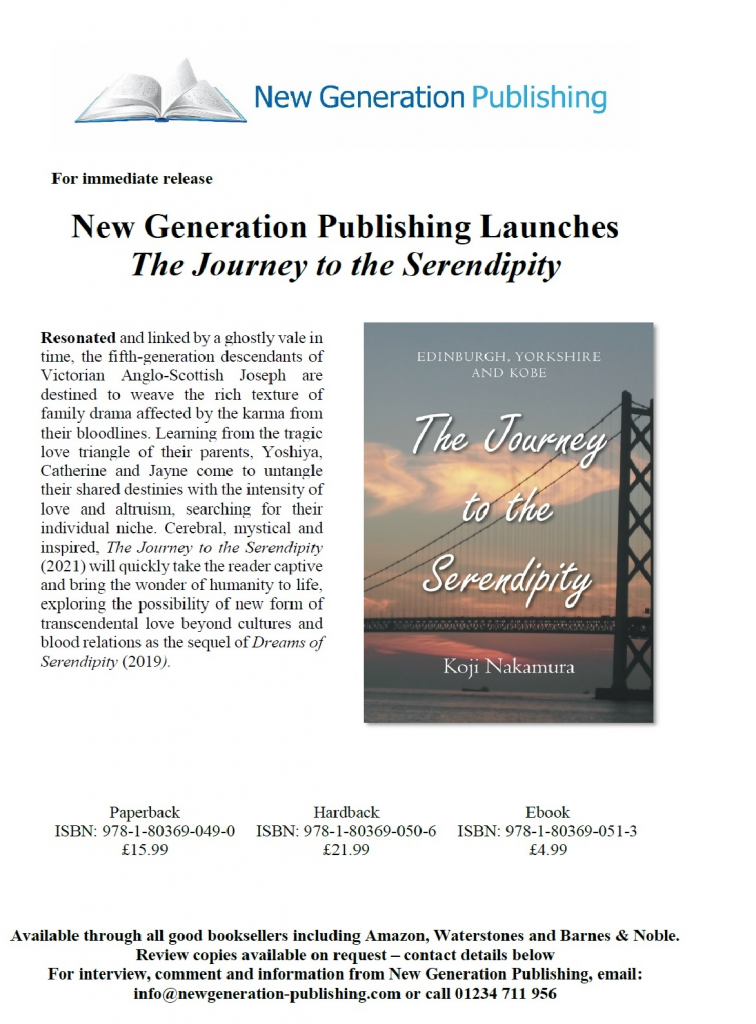マネジメント創造学部 4年生 小栗 珠実さんが、経済学部 ・マネジメント創造学部三上 亮先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
Q.どのくらいの頻度で本を読みますか?
A.参考書や教材は週に2冊。一般的な書籍(小説等)は2か月に1冊です。
Q.普段どのような本を読みますか?
A.大抵は専門書をよく読みます。今抱えて居る問題を解決するための本を結構よく読むことが多いです。例えば、パソコン操作や分析の方法を詳しく知りたい時に、それを知れる本を探して読みます。研究者になってから、専門書を読む時間が多くなり、それ以外の本を読む時間が減ったので、大学生の時に、色々な本を読んだ方がいいと思います。
Q.書店や図書館で本を買う、借りる時、どのように本を探して読んでいますか?
A.現状の問題を解決したい時に買いに行きます。書店や図書館に行くときは、自分の抱えている問題に関する分野に足を運び、本を探します。大学生の時は、ふらっと訪れて当てもなく本を探していました。
Q.大学生にお勧めしたい本は何ですか?お勧めの理由は何ですか?
A.2冊あります。1冊目は、内田樹さんの『寝ながら学べる構造主義』です。構造主義という哲学の考えを、とてもわかりやすく書かれている本です。例えば、経済学の父アダム・スミスについてどのような考え方だったのか、どのような流れでその考えにたどり着いたのかを分かりやすく教えてくれます。昔と今の考え方の違いや、登場人物がなぜ歴史的に重要な人になったのかを、素人にもわかりやすく書かれており、刺激的で好奇心をそそられる内容となっています。
2冊目は、『出社が楽しい経済学(NHK)』です。経済学が何かを全く知らない初学者でも、この本を読めばなんとなく理解ができるようになっています。
Q.最近読んだ本で面白かった本などありますか?
A.福永武彦さんの『古事記物語』です。海外の人と話した時、日本の歴史わかってなかったなぁと思ったのが読むきっかけでした。読んでいくと、日本の地名の由来や風土等、知らなかったことを学べて、楽しんで読んでいます。
Q.どういった時に本を読みますか?
A.小説などは、時間に余裕がある時、心に余裕がある時、アイデアに行き詰った時に、頭をリフレッシュさせるのに、読むことが多いです。
Q.専門書を読むとき、どの部分に注意して読むとかありますか?
A.全部を理解しようとするよりも、大事なところが何かを意識して読むことが重要だと思います。自分が知りたいところは何か、今分からないところがどこかを確認しながら読めば、理解できる部分に対して集中して読むことができるようになります。
感想 :質問に対し丁寧にお答えいただき、またインタビュー内容以外で面白かった本について、本の趣味など楽しいインタビューになり、とても楽しかったです。先生が紹介した本はどれも自分自身とても好奇心を刺激させる内容であり、本を借りて読んでみようと思いました。哲学の本から、経済や古典など幅広く読まれているので、私も様々な分野の本を読んでいこうと思いました。インタビューさせていただき、ありがとうございました。
<三上 亮先生おすすめの本>
内田 樹 著 『寝ながら学べる構造主義』 文藝春秋 , 2002年
吉本 佳生 著, NHK「出社が楽しい経済学」制作班編 『出社が楽しい経済学 』 日本放送出版協会 , 2009年
(インタビュアー:マネジメント創造学部 4年 小栗 珠実 )