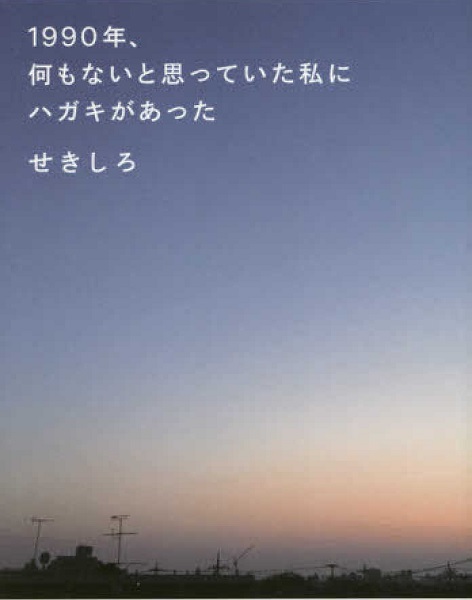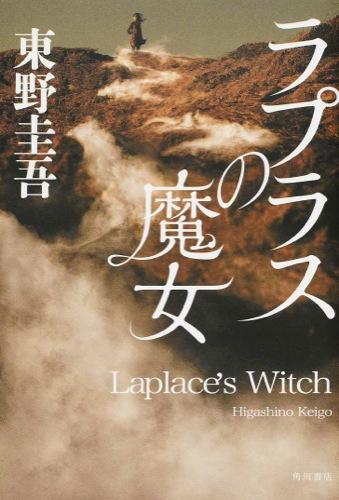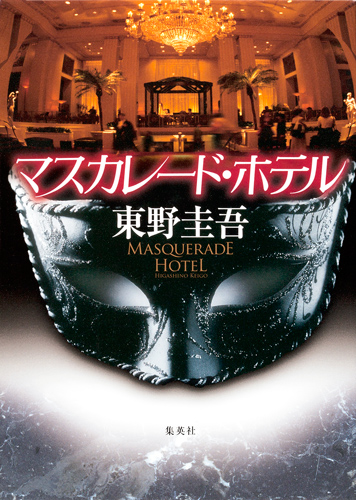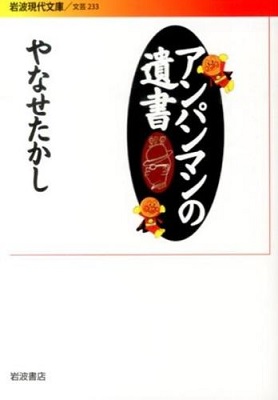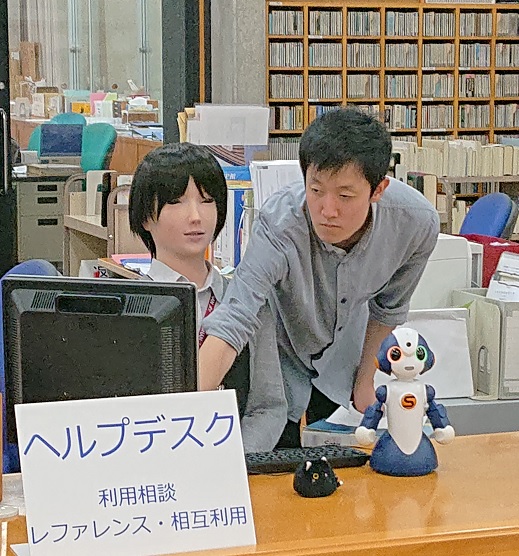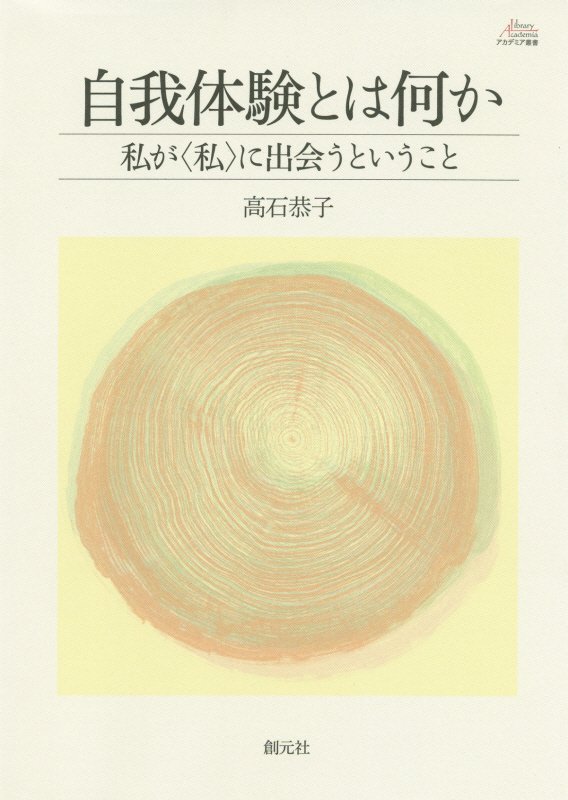法学部1年 長井大和さん(「基礎演習(濱谷)」リサーチペーパーより)
ラジオ職人について説明するとラジオ番組で募集されたお題に対してリスナーがハガキに自分の考えを書きそれを投稿する人たちのことです。
まずラジオそのものの情報を確認していきたいと思います。私が持つラジオの歴史で最も古いイメージは昭和天皇による玉音放送だと思います。実際にラジオが日本に渡ったのは1925年のことで、1923年に発生した関東大震災で情報伝達のメディアとして必要性が認識されたからです。こう考えてみるとラジオというものは現在生きている日本人全員がラジオに触れる機会があったと言えます。しかし人々は時代が進むにつれてより多くの情報をより簡単に収集することができるテレビや携帯電話に頼るようになっていきました。そうするとラジオは日常生活に必要不可欠なものではなく、一種の娯楽という面が大きくなったと考えられます。ニュースを聞くため経済状況を知るためなどではなく、音楽を聴いたり面白い話を聞いたりしたいという思いが強くなりその延長でラジオ投稿が流行ったと私は考えるます。
ラジオはメディアの一つとしてはどのような存在なのか?これを調べるために私は実際にラジオを聞いてみました。ラジオを聞いて一番感じたことはラジオの面白さは聞き手の知識によるものが大きいということです。このことはラジオを聴くには多少頭を使わなければならないということです。例えばパーソナリティが何かを話すとそれを頭でイメージしなければならないというわけではないけれどイメージしたほうが面白いと感じます。このことはラジオではどのような情報に対しても自分の感情考えなど私情が入ってしまうということを意味しています。これは正確な情報を伝えなければいけないという面ではメディアとしてはふさわしくないと考えられます。しかし読書などと同じで娯楽としてみれば何ら問題はないと考えられます。そうした背景が影響し情報収集のためのメディアではなくハガキ投稿を行う娯楽としての面が大きくなったと思いました。
ハガキ投稿が流行った原因としてラジオ出演者との距離が近いということが挙げられると思います。これは現代でもTwitterなどで有名人と交流できることが人気なように当時はテレビよりもより距離が近かったのでラジオは人気があったと考えます。
またラジオを聞くことは人間が成長していくうえでメリットデメリットを持っていると思います。メリットは文章の理解力が上がるということです。また自由で面白い発想もできるようになると思います。理由はラジオを聞くには音声だけなので頭を使う必要があるので文章の理解力が上がると思い、ハガキ投稿などを行うことでお題に対する答えを探すことが発想力を鍛えると思うからです。デメリットとしては音声だけの情報ということで視覚から得る情報を得ることができないので完璧な情報を得ることができないという点です。
ではこのように直接対面方式ではなく何かメディアを一つ挟んだうえで交流していくことの意義や価値について考えてみると、情報の一部が欠けた状態でコミュニケーションをとることでその人の本当の姿を知ることができないと考えられます。実際に私たちが現在行っているオンライン上の授業でも同じことが感じられると思いますメリットとしてはより多くの人と交流することができるということです。
以上のことをまとめると、ラジオは時代と共に情報源から娯楽の一部へと変化していきそれがさらに進化した姿が現在のインタネット社会を作り上げたと考えられます。またそれらの社会にはメリットデメリットが存在するが、それらとは上手に共存していくことが必要であると思う。
またこの本の著者はこの本に出て来る主人公なのだが、この本を書いた理由は単にラジオを知ってほしいという考であると書かれていました。
ラジオが現代にまた私たちに与えてくれるこは、娯楽としての楽しさと端的に発信される正確な情報だと思います。