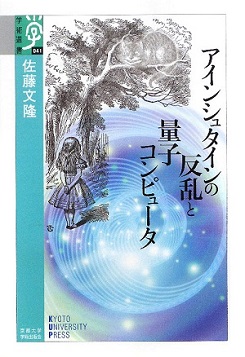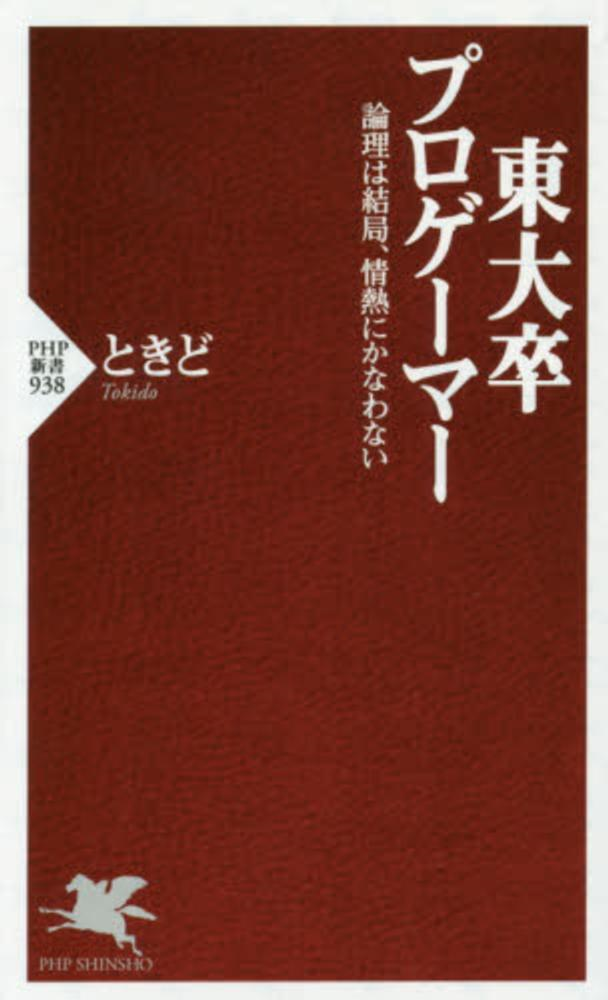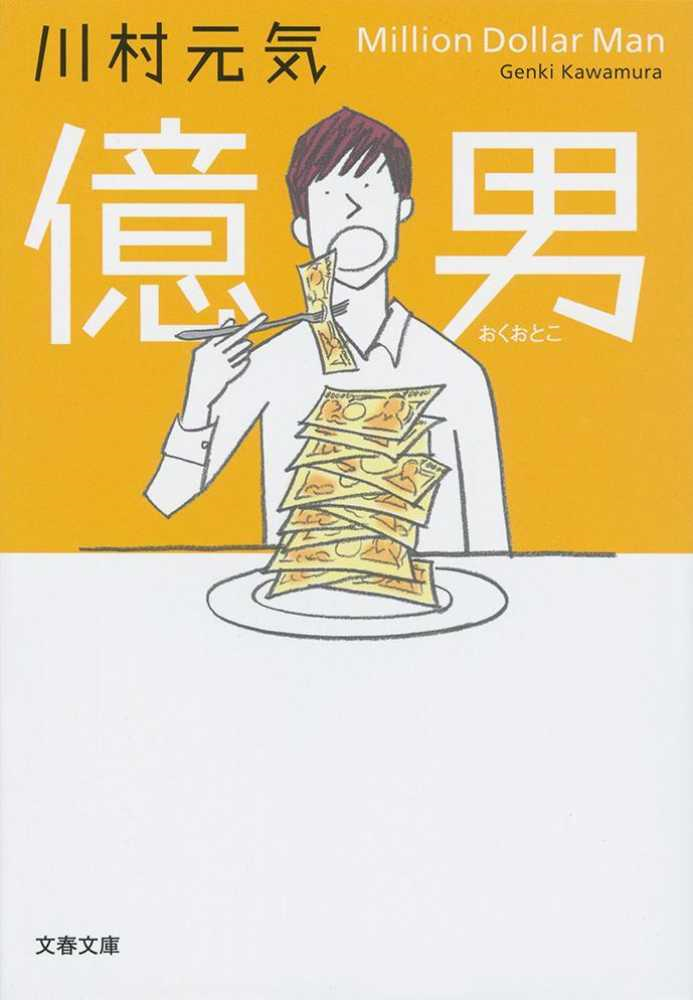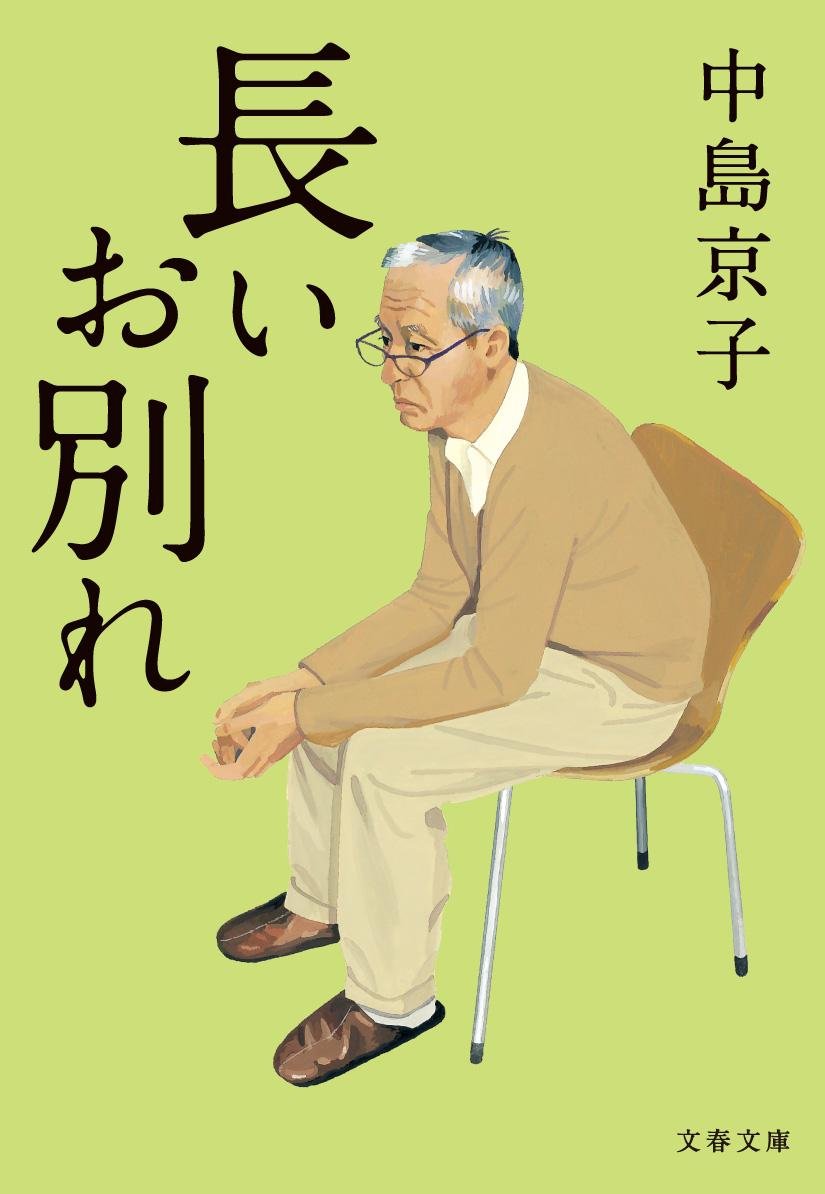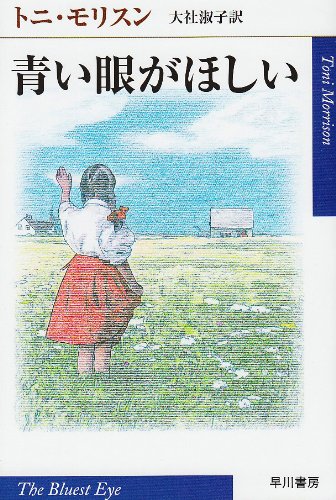図書館報『藤棚ONLINE』
鳩貝耕一先生(共通教育センター) 推薦
東京2020オリンピック・パラリンピックの直前6月には日食があり、新型コロナウイルスの脅威が去っていれば、梅雨時期の日本を離れ、北回帰線まで金環日食を見に行くクルーズ船ツアーに参加したい天文ファンも多いと思います。さて回帰というと、地球面上ではなく時間軸上での過去のふりかえりと考える人も多いと思います。以下は、いろいろと回帰するお話です。
まず、私が甲南大学4年生の時(天文同好会発足当時の1978年)に回帰すると、テニスコート、バスケットコートや藤棚のあったところに現在の図書館が竣工しました。図書館HPには、「憩いの場の思い出を大切にと、館報名を『藤棚』としました」とあります。その後、原子核理論物理学研究者のほんの端くれだった大学院生の時に、人文・社会系院生から「大学院生協議会」を立ち上げないかとの話がもちかけられ、理系院生のまとめ役として応じました。その組織活動の一環として、開館時間延長について大学執行部にお願いしにあがりました。
以下に紹介する書籍のテーマは、院生時代に「だまって、計算」していた原子核物理学の根幹をなす「量子力学」と現在の私の研究分野である「情報科学」の両方にまたがる話題です。
昨年末の10月に回帰すると、グーグルは開発中の量子コンピュータを用いた「量子超越(quantum supremacy)」の成功を発表しました。これは、スパコン「富岳」などでも計算には多大な時間(発表では約1万年)のかかるような問題を、極めて短時間(同3分20秒)で解けることを示したことになります。研究成果は、査読付きのれっきとした英科学誌「ネイチャー」に論文として掲載されました(ただし、IBMの量子コンピュータ研究陣からは異論が出ています)。
量子コンピュータの話題は、実は目新しいことではなく、ほぼ十年前の2011年に回帰すればカナダのD-Wave社が製品としての商用量子コンピュータの提供を開始しました。今回のグーグルの発表よりもこちらのほうがよほどショックで、「えっ、こんなの出していいの?!」と心の中でつぶやいたのを思い出します。1996年、甲南に教員として戻って以来、量子コンピュータの研究は全く行っていませんが、情報収集はしていました。まだまだ研究の域を出ないだろうと、たかをくくっていたわけです。
さて、この「えっ!」の背景や意味するところをまとめると本1冊ぐらいは書けるだろうなということが分かっていたので、最近になってググらずに(笑)Amazon.co.jpで検索してみました。
京都大学名誉教授で、2001年から2014年春まで本学にも教授として在籍されていた佐藤文隆先生の『アインシュタインの反乱と量子コンピュータ』が見事ヒットしました(ここでも甲南に回帰!)。研究者の端くれの私が、碩学大儒(せきがくたいじゅ)である佐藤先生の書評を書くなどはもってのほかなので、このような回帰大作戦とあいなった次第です。
この本のスゴイところは、D-Waveマシン以前、本学におられた2009年に出版されているところです。量子情報に関する研究が活発になっていることをリサーチした上での出版ではないでしょうか?
本当は、近著でほぼ人文・社会科学系の言葉で書かれている『量子力学が描く希望の世界』を紹介したかったのですが、読者はあらかじめ20世紀初頭に回帰して量子力学近代史を調べておかないと、チンプンカンプンだと思います。その点、こちらの書籍では、理系の言葉とはいえ内容を理解するための説明が簡単に添えられているので、理系学部のみなさんにはオススメです。より実験志向な方には、『佐藤文隆先生の量子論』がオススメです。
えっ、「なぜ、アインシュタインなの?」かって・・・。アルベルト・アインシュタインは、相対性理論ではなく「光量子仮説に基づく光電効果の理論的解明」によって1921年にノーベル物理学賞を受賞しています。量子の世界について最も深く考察した人だと言われています。ただし、最近のミクロな技術の進展により、量子への理解がこのころよりはより深まっています。
五里霧中ならぬ五「黍」霧中に杖を差し込んで探るような量子の世界にミーハーな私は、「だまって、計算しろ!」TシャツをAmazon.comより購入してしまいました(笑)。学生のみなさんの中から、回帰大作戦→開基大作戦→怪奇大作戦と進まれる方の出ることを期待しています。
●書誌情報(書籍は全て1F開架に揃っています)
・『アインシュタインの反乱と量子コンピュータ』,京都大学学術出版会,2009
・『佐藤文隆先生の量子論:干渉実験・量子もつれ・解釈問題』,講談社ブルーバックス,2017
・『量子力学が描く希望の世界』,青土社,2018
・「アインシュタインと量子」,日本経済新聞,2020年2月16日朝刊,p.32